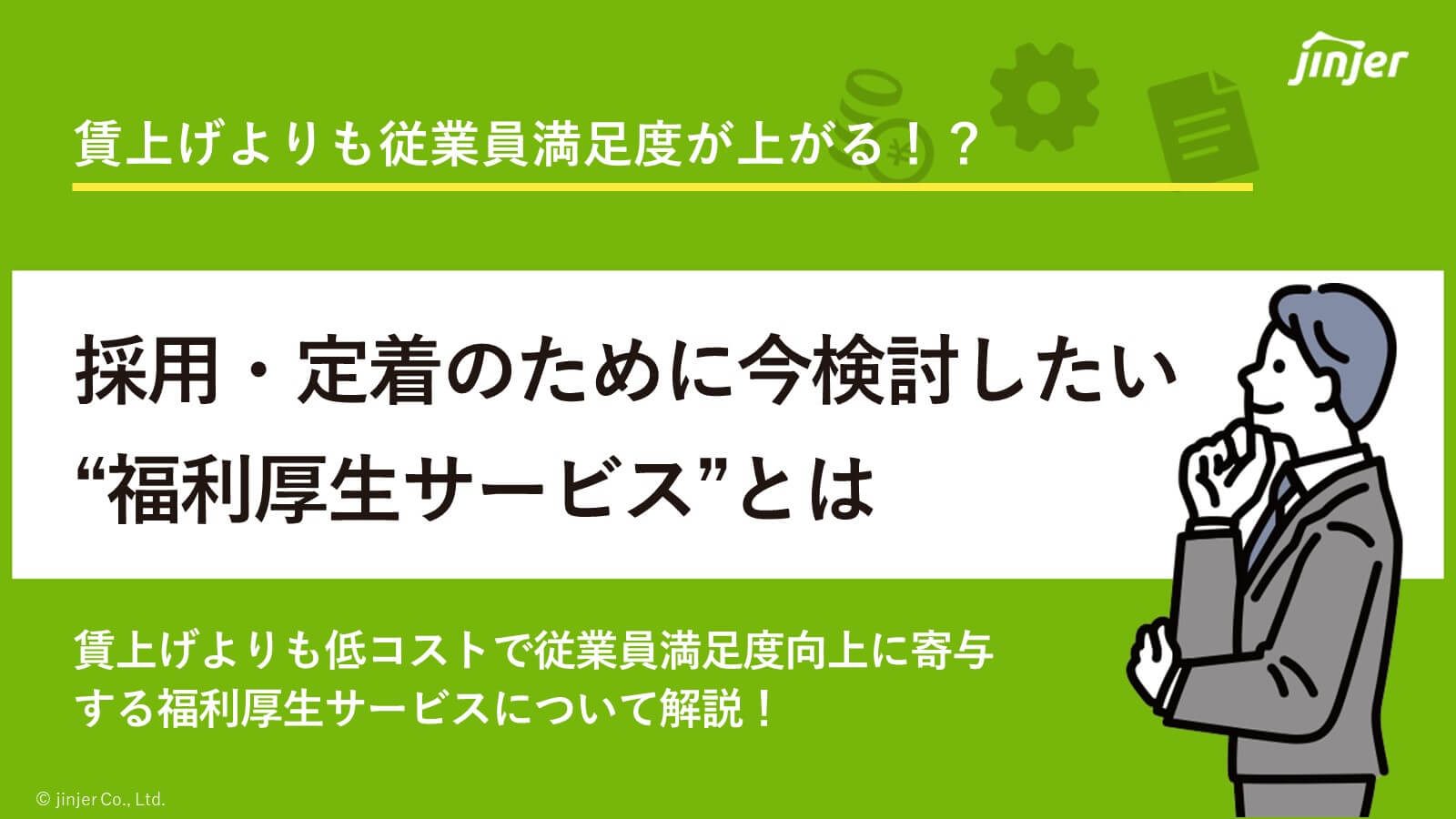「賃上げとは?」
「賃上げが増加している背景は?」
「賃上げを検討するにあたって、メリットを知りたい」
上記のような疑問を持っている労務担当者は多いでしょう。賃上げとは、企業が従業員の賃金を引き上げることです。物価の上昇が急速に進むなか、従業員の生活を守るため、賃上げをする企業は増加傾向にあります。
本記事では、賃上げの概要や賃上げが増加している背景を詳しく解説します。賃上げするメリットについても紹介するので、賃上げを検討している場合は参考にしてください。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 賃上げとは

賃上げとは、企業が従業員の賃金を引き上げることです。賃上げは、以下の2種類に大きく分けられます。
- 定期昇給
- ベースアップ
それぞれの特徴について、詳しく解説していきましょう。
1-1. 定期昇給
定期昇給は、企業が定めたタイミングで定期的に従業員の賃金を引き上げる制度です。昇給のタイミングは企業によってさまざまですが、年1~2回で設定している企業が多い傾向にあります。
企業の規程により異なりますが、基本的には年齢・勤続年数・成果に応じておこなわれます。ただし、企業が必ず昇給を実施するとは限りません。
1-2. ベースアップ
ベースアップは、従業員の賃金水準を一律で引き上げることです。略して「ベア」とよばれることもあります。ベースアップを実施するかどうかは、労働組合が毎年春におこなう春季闘争を経て決定します。
定期昇給とは異なり、従業員の年齢・勤続年数・成果には影響されません。また、ベースアップするタイミングに決まりはなく、企業の業績を考慮しておこなわれます。従業員全員の賃金が一律でアップするため、新入社員や中途採用者も賃上げの対象です。
2. 賃上げする企業が増加している3つの背景

賃上げする企業が増加している背景として、以下の3つが挙げられます。
- 物価が上昇している
- 人材確保が厳しくなっている
- 賃上げ促進税制が導入された
それぞれ、具体的に解説します。
2-1. 物価が上昇している
賃上げする企業が増加する背景として、物価上昇が急速に進んでいることが挙げられます。賃金を引き上げることで従業員の生活を守る必要があるためです。
ロシアのウクライナ侵攻で原材料費が高騰したことで、物価は上昇傾向にあります。2024年6月に総務省が発表した、2020年を基準とする2024年5月分の消費者物価指数は以下の通りです。
|
名目 |
指数(2020年を100とする) |
上昇率 |
|
総合指数 |
108.1 |
2.8% |
|
生鮮食品を除く総合指数 |
107.5 |
2.5% |
|
生鮮食品およびエネルギーを除く総合指数 |
106.6 |
2.1% |
参考:2020年基準 消費者物価指数 全国2024年(令和6年)5月分|総務省
物価が上昇すると、お金の価値は下がります。同じ金額で購入できるモノやサービスの量や質が下がるためです。
物価上昇時に賃上げをおこなわないと、賃金の高い企業へ転職する従業員が増える恐れがあります。人材の流出を防ぐためにも、賃上げに踏み込む企業が増加しているのです。
2-2. 人材確保が厳しくなっている
企業が賃上げをおこなう背景には、人材確保が厳しくなっていることも挙げられます。高い賃金を支払うことで、優秀な人材に選ばれる企業にならなくてはいけません。
少子高齢化が進み、労働人口が不足することは企業にとって深刻な問題です。実際、倒産件数全体に占める人手不足関連倒産の割合は上昇傾向にあります。
厚生労働省が公表したデータによると、15~64歳の人口は以下のように減少すると想定されています。
|
年代 |
15~64歳の人口(想定) |
|
2020年 |
7,509万人 |
|
2040年 |
6,213万人 |
|
2070年 |
4,535万人 |
参考:人口減少社会への対応と 人手不足の下での企業の人材確保に向けて|厚生労働省
今後ますます労働人口が減少していくなかで、他社より賃金を上げることが人材確保にもつながります。
2-3. 賃上げ促進税制が導入された
賃上げ促進税制が導入されたことも、賃上げする企業が増えた理由のひとつです。賃上げ促進税制は2022年から導入されている制度で、一定の要件を満たすと、給与の増額分の一部を法人税から控除することができます。
この制度をうまく利用して、賃上げを実施する企業も増えてきました。制度の詳細は次の項目で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
3. 政府による賃上げ促進税制とは

政府は2022年4月に「賃上げ促進税制」を導入しました。物価上昇に対して賃上げする企業を支援するためです。
賃上げ促進税制の概要を以下にまとめました。
|
対象 |
継続雇用者の給与等支給額(前年度比) |
税額控除率 |
上乗せ要件1:教育訓練費 |
上乗せ要件2:子育てとの両立・女性活躍支援 |
|
大企業向け |
+3~7% |
+3%:10% +4%:15% +5%:20% +7%:25% |
前年度比+10%で税額控除率5%上乗せ |
プラチナくるみんまたはプラチナえるぼしの認定で税額控除率5%上乗せ |
|
中堅企業向け |
+3~4% |
+3%:10% +4%:25% |
前年度比+10%で税額控除率5%上乗せ |
プラチナくるみんまたはえるぼし三段階目以上で税額控除率5%上乗せ |
|
中小企業向け |
+1.5~2.5% |
+1.5%:15% +2.5%:30% |
前年度比+5%で税額控除率10%上乗せ |
くるみん以上またはえるぼしに二段階目以上で税額控除率を5%上乗せ |
賃上げ促進税制を利用すると、大・中堅企業は最大35%、中小企業は最大45%を税額控除できます。また、中小企業は賃上げをおこなった年度に控除しきれなかった金額を5年間繰り越すことも可能です。
賃上げ促進税制のメリットを上手に活用し、賃上げをおこないましょう。
4. 企業が賃上げする2つのメリット

企業が賃上げするメリットは以下の2つです。
- 従業員のモチベーションが上がる
- 優秀な人材を確保しやすくなる
それぞれのメリットについて、詳しく解説します。
4-1. 従業員のモチベーションが上がる
企業が賃上げするメリットのひとつは、従業員のモチベーションが上がることです。賃金が上がれば、企業や仕事に対する愛着が強くなり、生産性の向上も期待できます。
条件がよくなることで離職を考える従業員も減少するため、離職防止効果も期待できるでしょう。
4-2. 優秀な人材を確保しやすくなる
企業が賃上げするメリットとして、優秀な人材を確保しやすくなることも挙げられます。職種や勤務形態などの条件が同等であれば、賃金が決め手となる可能性が高いためです。
他社より高い賃金を支払うことで、人材獲得競争において有利になると考えられます。
5. 企業が賃上げするデメリット
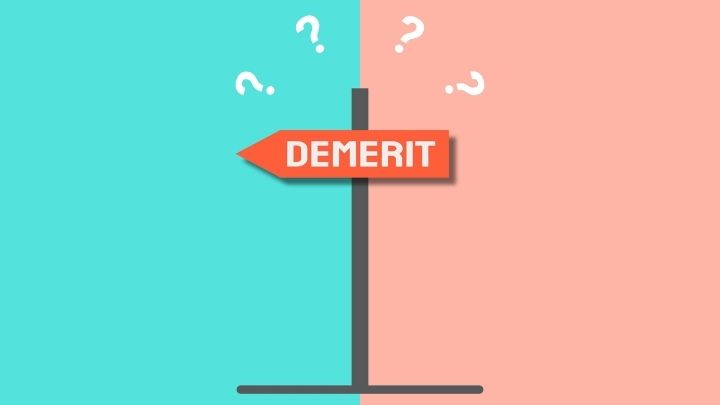
さまざまなメリットがある一方、賃上げには以下のようなデメリットもあります。
- 人件費が増加する
- 下げるのが難しい
各デメリットについて簡単に確認しておきましょう。
5-1. 人件費が増加する
人件費が増加することは、賃上げをおこなうデメリットのひとつです。定期昇給やベースアップを実施すると基本給がアップするため、従業員数が多いほど、企業の負担は大きくなります。
業績が悪いときに無理に賃上げをおこなうと、経営が苦しくなるケースもあるため注意しましょう。従業員の待遇を改善することは大切ですが、事業が継続できなくなっては意味がありません。賃上げをおこなうかどうかは、慎重に判断しましょう。
5-2. 下げるのが難しい
賃上げの手続きは比較的簡単ですが、一度上げた賃金を引き下げることは簡単ではありません。賃金の引き下げは不利益変更と見なされるため、従業員の同意を得てから実施する必要があります。基本的には会社の都合で一方的に引き下げることはできないため注意しましょう。
6. 賃上げの方法

賃上げする方法として、月例給与を引き上げる方法と一時的な手当を支給する方法があります。月例給与を引き上げる方法は定期昇給とベースアップに分けられますが、特性は大きく異なるので注意が必要です。
定期昇給・ベースアップ・一時的な手当について以下にまとめました。
|
特徴 |
メリット |
デメリット |
|
|
定期昇給 |
企業が定めたタイミングで、年齢・勤続年数・成果を考慮し、賃金を引き上げる |
長期で働く意欲を向上させるため、人材を定着させやすい |
実力のある若手の従業員にとっては、不満となる恐れがある |
|
ベースアップ |
従業員の賃金を一律で引き上げる |
初任給も引き上げとなるため、人材獲得競争において有利 |
一度賃金を引き上げると引き下げるのは難しい |
|
一時的な手当 |
通常の賃金とは別に支給する |
支給意図が明確でわかりやすい |
一過性の施策のため、固定給が重視される採用活動においては有利になりにくい |
それぞれの特徴を理解したうえで、賃上げの方法を検討するようにしましょう。
7. 賃上げを検討する際のポイント

賃上げを検討する際は、以下のようなポイントを意識しましょう。
7-1. 以前の賃上げの効果を確認する
過去に賃上げをおこなっている場合は、その効果を確認しましょう。賃上げをしたことにより従業員満足度は向上したのか、モチベーションは高まったか、定着率は向上したかなど、効果を把握しておくことが大切です。
仮に大きな効果がなかった場合は、賃上げをする意味はないかもしれません。賃上げは従業員の待遇を改善するひとつの方法ですが、他にもさまざまな方法が存在します。長時間労働の削減や福利厚生の充実など、従業員のニーズに合った改善策を講じることが重要です。
7-2. 売り上げを伸ばす
賃上げを検討する際は、原資の確保ができるか否かを見極めなくてはいけません。とくに、ベースアップをおこなう場合は注意しましょう。従業員全員の賃金水準を上げる必要があるので、継続的な原資確保が必要となるためです。
売り上げを伸ばす、新規顧客の獲得を目指すなど、原資を確保できるような対策を検討しましょう。
7-3. 無駄なコストを削減する
賃上げをおこなうなら、その分、無駄なコストを削減して原資を確保することも必要です。従業員の能力を最大限に生かせる環境を整え、生産性アップと業務効率化を図ることが賃上げにかかる原資確保につながります。また、政府が掲げる支援制度の活用も有効な手段の一つです。
8. 賃上げが困難なケースの施策

賃上げが困難な場合は、以下のような手段により待遇を改善することを検討してみましょう。
8-1. 福利厚生を充実させる
賃上げすることが困難な場合は、福利厚生を充実させることを検討してみましょう。労働者のなかには、福利厚生の充実を望む人が多いためです。株式会社エデンレッドジャパンが2020年に公表した、待遇・働き方について望むことのアンケート結果を以下にまとめました。対象者は全国の中小企業に勤務する30~50代の正社員600名です。
|
基本給のアップ |
1500ポイント |
|
賞与額のアップ |
877ポイント |
|
手当の充実 |
329ポイント |
|
福利厚生の充実 |
291ポイント |
基本給・賞与・手当など金銭的なものに次いで、福利厚生の充実を望んでいることがわかります。
福利厚生にかかる費用は経費に計上でき、企業にとっては節税対策にも有効です。ただし、福利厚生費として計上するには条件があるため、注意しましょう
参考:ビジネスパーソンと企業を比較した「働き方・待遇に関する意識調査」|株式会社エデンレッドジャパン
8-2. 多様な働き方を認める
多様な働き方を認めることも従業員の満足度を高める方法のひとつです。リモートワークや時短勤務、フレックスタイム制などを導入すれば、従業員ごとの事情に合わせて働けます。家事や育児と仕事を両立しやすくなるため、従業員が働きやすい環境だと感じ、会社に対する満足度やエンゲージメントが高まるでしょう。
8-3. コミュニケーションを活性化させる
コミュニケーションを活性化させる取り組みも重要です。コミュニケーションを活性化させると、仕事の相談をしやすくなったり、協力体制が構築されたりするため、働きやすい環境になるでしょう。
また、新しいアイデアが生まれやすくなる、組織全体の生産性が向上するなどのメリットもあります。従業員と会社の双方にとってメリットがある施策であるため、賃上げの代わりに検討するよいでしょう。
9. 賃上げにより優秀な人材を確保しよう!

今回は、賃上げの意味や注目されている理由、メリット・デメリットなどを紹介しました。賃上げによって従業員の基本給をアップさせることで、モチベーションや生産性が高まることを期待できます。また、採用活動がスムーズに進んだり、優秀な人材を確保できたりするケースもあるでしょう。
ただし、賃上げをおこなうと人件費が増加するため、注意しなければなりません。また、一度上げた賃金を引き下げることは難しいため、賃上げするかどうかは慎重に検討しましょう。従業員の待遇を改善することは大切ですが、事業が継続できるよう、原資を確保したうえで進めることが重要です。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。