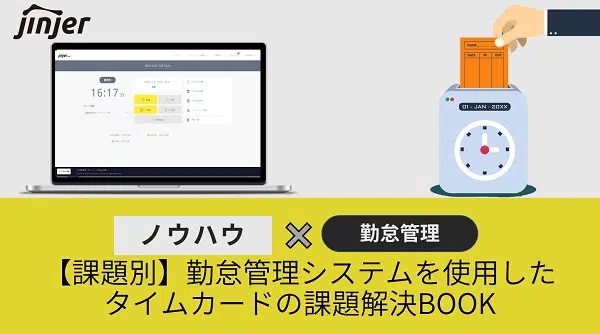紙のタイムカードを使用して勤怠管理をおこなっている企業は、まだ多く存在しているでしょう。近年では、さまざまな打刻方法のあるタイムカードが登場しています。
当記事では、タイムカードの仕組みや使い方・操作について解説します。また、ICカードや生体認証を用いたタイムカードの使用方法についても紹介します。タイムカードの基本的な操作方法について知りたい人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしている場合、以下のような課題はないでしょうか。
・タイムカードの収集や打刻漏れ、ミスの確認に時間がかかる
・労働時間の集計に時間がかかる/ミスが発生しやすい
・労働時間をリアルタイムで把握できず、月末に集計するまで残業時間がわからない/気づいたら上限を超過していた
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムです。システムであれば工数・ミスを削減して労働時間の集計ができるほか、リアルタイムで労働時間が把握できるため、残業の上限規制など法律に則った管理を実現できます。
勤怠管理システムについて気になる方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. タイムカードとは

タイムカードとは、始業時間や終業時間、残業時間などを書き込むためのツールのことです。なお、紙のタイムカードとタイムレコーダーをあわせて、「タイムカード」とよぶこともあります。
職場の出入口付近にタイムレコーダーを設置しておき、出勤・退勤時刻に従業員に打刻してもらえば、簡単に勤怠管理をおこなうことが可能です。
1-1. タイムカードを使うメリット
タイムカードを使うメリットは以下の通りです。
- 導入コストを抑えられる
- 簡単に運用できる
従業員の少ない企業であれば、タイムカードを使用する場合、勤怠管理システムを用いる場合と比べて、導入や運用のコストが低く済むというメリットがあります。また、運用方法がシンプルであるため、教育にかかるコストも軽減できるでしょう。
1-2. タイムカードを使うデメリット
手軽に使えるタイムカードですが、以下のようなデメリットもあります。
- 集計の手間がかかる
- 打刻ミスや集計ミスが発生しやすい
紙のタイムカードで勤怠管理をおこなう場合、手作業で集計する必要があるため、作業に時間がかかってしまいます。打刻ミスや集計ミスが生じる恐れもあるので注意が必要です。また、打刻ミスが発生したときの対応ルールを設定しておく必要もあります。
1-3. タイムカードの種類
タイムカードと聞くと紙のツールをイメージするかもしれませんが、実は他にも種類があります。タイムカードの代表的な形式は、以下の4つです。
- 紙のタイムカード形式
- ICカード形式
- 生体認証形式
- QRコード形式
社員証や交通系のICカードを使って打刻できるシステムや、指紋・顔を認証して打刻できるシステムなども登場してきました。紙のタイムカードと比較すると導入コストはかかりますが、打刻の手間を省きつつ、不正打刻を防止することが可能です。それぞれの使い方は後の章で詳しく解説しているので、参考にしてください。
2. タイムカードの仕組み
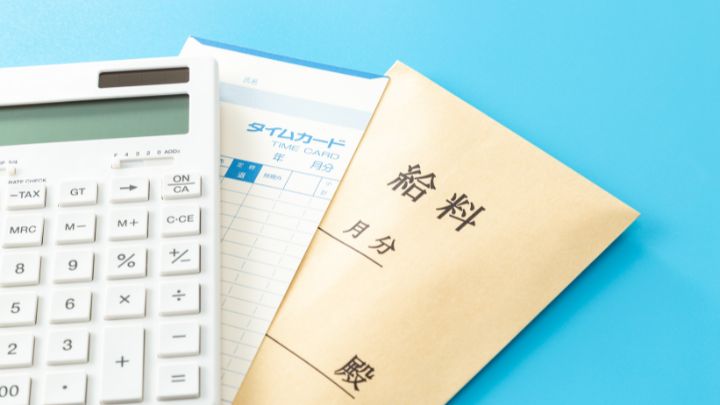
一般的なタイムレコーダーの場合、紙のタイムカードを挿入して時刻を打刻することで、労働時間を客観的に証明し、勤怠管理をおこなうことが可能です。
タイムレコーダーのなかには、打刻情報をデータとして保管できる機能が搭載されているものもあります。たとえば、紙のタイムカードは、紛失や盗難などが生じる恐れもあります。タイムカードがなくなってしまうと、従業員の勤務状況を把握できないため、従業員に対して適切な賃金を支払えない可能性もあります。データが残るタイムレコーダーであれば、バックアップをおこなうことも可能です。
そして、タイムカードに印字された記録は、労働時間を集計するために使用されます。管理者は、タイムカードに記載された労働時間をもとに、従業員に支払う賃金を計算します。タイムカードには、始業時間と終業時間を打刻するのが一般的です。また、備考欄などに、休憩時間や中抜け時間を記載することで、適切な労働時間を算出することができます。なお、タイムカードには、保管期間が定められているため、労働基準法にもとづき、適切に管理することが大切です。
関連記事:タイムカードの保存期間は5年!知っておきたいタイムカード保管方法
3. タイムカードの使い方・操作|従業員編

ここでは、紙のタイムカードの使い方や操作方法について詳しく紹介します。
3-1. 押したい打刻(出勤・退勤)のボタンを選択する
タイムカードの使い方はシンプルです。基本的に、タイムレコーダーにタイムカードを差し込むだけで打刻が完了します。タイムレコーダーによっては、出勤や退勤などのボタンが用意されていることもあります。タイムカードに記載したい打刻のボタンを選択しましょう。
なお、ボタンを押す必要がないタイムレコーダーもあったり、休憩時間や中抜け時間のボタンが用意されていたりすることもあるため、会社の指示に従って利用することが大切です。
3-2. タイムカードの裏表を確認する
打刻する前に、タイムカードの裏表を確認することが大切です。たとえば、月の前半日(1日から15日まで)は表、後半日(16日以降)は裏で打刻するようなタイムカードがあります。また、タイムカードの向きにも注意が必要です。
タイムカードの裏表や向きが異なると、正しく時刻が打刻されなかったり、エラーが発生したりする可能性もあります。場合によっては、間違った日のところに印字されてしまい、適切な勤怠管理ができない恐れもあります。そのため、タイムレコーダーに挿入する前に、タイムカードの裏表や向きが正しいか確認しましょう。
3-3. タイムレコーダーにカードを差し込み、印字する
タイムカードの裏表や向きが正確であることを確認できたら、実際にタイムレコーダーに挿入しましょう。タイムレコーダーによっては、打刻が完了したときに音が鳴ります。音が鳴らないうちに引き抜いたり、音が鳴っているのにもかかわらず複数回挿入したりしないように注意することが大切です。
紙のタイムカードには、タイムレコーダーに挿入したときの時刻が印字されます。打刻が完了したら、タイムカードに印字されている時刻や位置が正しいか確認することが大切です。
3-4. ミスした場合は手書きで修正して管理者の承認を得る
紙のタイムカードを使用する場合、手作業で運用することが多いため、打刻漏れなどの打刻ミスが生じることは少なくありません。打刻ミスがあると、従業員の労働時間を適切に把握できず、給与の支払いなどでトラブルが発生することもあります。また、タイムカードの集計担当者の業務負担の増加につながる恐れもあります。
そのため、ミスが発覚したときには、素早く管理者に伝えることが大切です。その後の対応については、企業の運用方法によって異なることが多いでしょう。
なお、手書きで修正する場合には、ボールペンなどを使用して、後から改ざんできないようにしましょう。そして、修正後には、管理者の承認を得るというフローを用意すると、適切な勤怠管理につながります。
4. 打刻方法に応じたタイムカードの使い方

ここでは、打刻方法に応じたタイムカードの使い方について詳しく紹介します。
4-1. ICカードを使う場合
ICカードを使用する場合、タイムレコーダーなどの機器にICチップが内蔵されたカードを近づけることで、始業時間や終業時間の打刻をおこないます。ICカードで勤怠管理を実施する場合には、社員証や交通系ICカードなど、従業員の保有しているカードを使用するため、なりすましなどの不正打刻を防止することが可能です。
また、紙代やインク代などのコストを削減することもできます。さらに、電子データとして管理できるため、集計業務の効率化を図ることが可能です。ただし、ICカードの紛失・盗難が発生する可能性もあるので、対応策を事前に把握しておくことが重要といえます。
4-2. 生体認証を使う場合
生体認証機能の搭載されたタイムカードを使用する場合、従業員の顔や指紋などの生体情報を利用して、打刻をおこないます。紙のタイムカードやICカードを使用する場合と比べて、紛失や盗難のリスクを防げるというメリットがあります。また、なりすましなどの不正打刻を防ぐことも可能です。
ただし、生体認証の機器によっては、反応が悪く、打刻に時間がかかることもあります。また、顔や指をケガしたときには、生体認証をおこなえない恐れもあります。そのため、生体認証を使用できないときの対応策を事前に考えておくことが大切です。
4-3. QRコードを使う場合
QRコード形式の場合、従業員ごとに固有のQRコードが発行されます。QRコードは、スマートフォンで表示できるようにデータとして配布したり、名刺のような紙に印刷して渡したりすることが一般的です。
打刻時は、QRコードを端末のカメラで読み取ってもらいます。従業員ごとにQRコードを発行するため、ICカードや生体認証と同様、不正打刻を防止しやすいでしょう。QRコードを紛失した場合は、端末から再発行をおこなうことも可能です。
5. タイムカードの見方

ここまで紹介した通り、タイムカードにはさまざまな種類のものがあります。タイムカードには、所属部署や氏名などを記入する欄が設けられており、きちんと記載しておくことで誰のものかを素早く把握できます。また、打刻をおこなった日付の出勤・退勤の時間を把握することが可能です。
タイムカードによっては、残業時間や休憩時間・中抜け時間を管理できるものもあります。備考欄が用意されているものもあり、修正をおこなった場合や早退・遅刻をした場合など、会社が記載するように指示したその他の事項が書かれます。
このように、タイムカードによって、管理項目が異なるため、自社のニーズに合ったタイムカードを採用するのがおすすめです。
6. タイムカードの使い方に関するよくある疑問

ここでは、タイムカードの使い方におけるよくある質問に対する回答を紹介します。
6-1. タイムカードは何分単位で押す?
労働時間は、実際に業務をおこなった時間に基づき、原則として1分単位で管理されなければなりません。
タイムカードで勤怠管理をおこなっている企業は、タイムカードの打刻時間をもとに、労働時間を算出しているでしょう。そのため、タイムカードについても、1分単位で記録する必要があります。
15分単位・30分単位などで記録時間をまとめるといった打刻時間の設定行為は違法とされます。たとえば、9時5分に出社してタイムカードを切ると、9時15分や9時30分として打刻されてしまうケースは違法です。
このように、原則として、企業が働いていなかったことを証明できない限り、タイムカードの記録をもとに、労働時間は管理されなければならないため、1分単位でタイムカードを押すのが適切です。
6-2. タイムカードはどこにある?
タイムカードの設置場所は、企業によってさまざまです。タイムカードがどこにあるのかわからない場合には、管理者に聞いてみる必要があります。打刻漏れを防ぐために、タイムカードは事業所の出入口など、目につきやすい箇所に設置されていることが多いでしょう。
また、業務場所とタイムカードの設置場所に距離があると、タイムカードに打刻された時間と実際の労働時間に誤差が生まれてしまう可能性もあります。そのため、タイムカードは業務場所の近くに設置されていることが多いでしょう。
このように、タイムカードの設置場所は業務をおこなう場所に近く、目につきやすいところに設置されている可能性が高いです。ただし、セキュリティ上の問題などで、タイムカードがわかりづらいところに設置されていることもあるため、管理者に確認してみるのがおすすめといえます。
6-3. 休憩の打刻はどうする?
休憩時間を管理するために、必ずしも打刻する必要はありません。なお、労働基準法34条には、休憩時間の付与について定められています。使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に付与しなければなりません。
休憩時間を把握しなくても、始業時間と終業時間から勤務時間を算出して、会社で規定されている休憩時間を差し引けば、労働時間を計算することができます。ただし、使用者は、従業員がきちんと休憩を取れているのか確認することが大切です。また、休憩時間の打刻管理も実施すれば、より正確な勤怠管理をおこなうことができます。
このように、基本的に休憩時間の打刻は必要ありませんが、会社によって運用方法は異なるためルールを確認しましょう。
7. タイムカードを使うときの注意点

ここでは、タイムカードの使用するときの注意点について詳しく紹介します。
7-1. ボタンの押し間違いに注意する
タイムレコーダーのボタンの押し間違いは、打刻漏れや打刻ミスにつながるため、注意しなければなりません。たとえば、退勤するときに、「出勤」のボタンを押してしまうと、出勤時間を記録するところに打刻されてしまったり、エラーにより打刻されなかったりする恐れがあります。
ボタンの押し間違いによって正しく打刻ができない場合、タイムカードの集計担当者が正確な労働時間を把握できず、賃金の支払いなどにトラブルが生じることもあります。ボタンの押し間違いは人的ミスであるため、すべてを防ぐことはできないかもしれません。ただし、打刻が完了した後、タイムカードの正しい箇所に印字されているかを確認するなど、自分なりのルールを決めておくことが大切です。
7-2. 打刻ミスした場合はすぐに修正・報告する
タイムカードの運用は手作業でおこなうことが多いので、打刻ミスをすべて防ぐことは難しいです。そのため、打刻ミスがわかったら、すぐに管理者に報告して修正をおこないましょう。打刻ミスを放置してしまうと、正しい労働時間を把握できず、給与の支払いなどでトラブルが生じることもあります。
管理者に報告すると、打刻ミスの事実確認がおこなわれる場合もあります。また、企業によっては、タイムカードを修正したというエビデンスを残すために始末書を提出する必要がある場合もあります。
このように、勤怠管理や給与計算におけるトラブルを起こさないためにも、打刻ミスを見つけたらすぐに修正と報告をおこないましょう。
7-3. 不正打刻が発生しないようにする
労働時間を正確に把握するためには、不正打刻が発生しないよう注意しなければなりません。不正打刻の例としては、遅刻しそうなときに同僚に頼んで打刻してもらったり、退勤時刻を手書きすることで残業を多く見せかけたりすることが挙げられます。
不正打刻が発生すると、正確な労働時間を把握できないだけではなく、労働していない時間分の賃金を支給することになってしまいます。とくに紙のタイムカードでは不正打刻が起きやすいので、不正を防止するための対策を講じることが重要です。
8. タイムカードが使いにくい場合は勤怠管理システムがおすすめ

タイムカードによる勤怠管理に限界を感じた場合は、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。勤怠管理システムには、以下のようなメリットがあります。
8-1. 集計業務を効率化できる
勤怠管理システムを導入すれば、労働時間の集計業務を効率化できます。紙のタイムカードを使っている場合、全従業員のタイムカードを回収して、打刻された労働時間を集計しなければなりません。時間がかかるだけではなく、エクセルの表に転記するときなどにミスが起こる可能性もあるでしょう。
勤怠管理システムであれば、日々の労働時間が自動的に集計されるため、担当者の負担はありません。また、残業時間の上限規制を超えそうなときにアラートで知らせてくれるシステムもあります。
8-2. 不正打刻を防止できる
不正打刻を防止できることも勤怠管理システムのメリットです。基本的には、従業員ごとのIDとパスワードを入力してログインするケースをはじめとして、社員証・ICカードを利用したり、生体認証をおこなう必要があるので、タイムカードのような代理打刻を防止できます。
また、システムへのアクセス権限を設定できるため、データを不正に書き換えるような行為も防止可能です。
8-3. リモートワークに対応できる
紙のタイムカードによる勤怠管理は出社することが前提となっているため、リモートワークに対応させることは困難です。また、直行直帰する場合にも打刻できないので、後日申請書を出したり、会社へ連絡して出退勤時刻を報告したりする必要があります。
一方の勤怠管理システムであれば、パソコンやスマートフォンからログインできるため、通信環境さえあればどこにいても打刻可能です。多様な働き方を取り入れている場合は、ぜひ勤怠管理システムを活用しましょう。
9. タイムカードの使い方を理解して正しく打刻しよう!

今回は、タイムカードの使い方や種類、タイムカードによる勤怠管理の注意点などを解説しました。紙のタイムカードを使用する場合には、タイムレコーダーに挿入することで打刻をおこないます。タイムカードの使い方や操作方法は、機器や会社によって異なります。
そのため、会社の制度を正しく把握して、適切な方法でタイムカードの運用をおこなうことが大切です。また、打刻ミスがあったときは、トラブルを防ぐためにすぐに管理者に報告してもらいましょう。
タイムカードによる勤怠管理に限界を感じている場合、便利なシステムを導入することがおすすめです。リモートワークなどにも対応できるため、ぜひ導入を検討してみてください。
タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしている場合、以下のような課題はないでしょうか。
・タイムカードの収集や打刻漏れ、ミスの確認に時間がかかる
・労働時間の集計に時間がかかる/ミスが発生しやすい
・労働時間をリアルタイムで把握できず、月末に集計するまで残業時間がわからない/気づいたら上限を超過していた
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムです。システムであれば工数・ミスを削減して労働時間の集計ができるほか、リアルタイムで労働時間が把握できるため、残業の上限規制など法律に則った管理を実現できます。
勤怠管理システムについて気になる方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。