
社会保険の扶養に入ることで、社会保険料の負担を減らし、家計の負担を軽減させることができます。しかし、扶養に入るための条件は複雑であるため、間違った手続きをしないためにも、正しく仕組みを理解しておくことが大切です。本記事では、社会保険の扶養について、税金の扶養との違いも踏まえながらわかりやすく解説します。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 社会保険料の扶養とは?

社会保険料の扶養とは、社会保険の被保険者の配偶者や子、親族などが、社会保険料を支払わなくとも社会保険に加入できる制度のことです。ここでは、社会保険料と扶養それぞれの定義を説明したうえで、社会保険料の扶養とはどのような意味なのか詳しく紹介します。
1-1. そもそも社会保険料とは
社会保険料とは、社会保険に対してかかる保険料のことです。社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の5つから構成されます。
なお、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3つを狭義の社会保険として定義することがあります。また、「労災保険」と「雇用保険」をまとめて「労働保険」と呼ぶケースもあるため覚えておきましょう。この記事では、狭義の社会保険を「社会保険」とみなして解説します。
関連記事:社会保険の種類ごとの特徴や加入条件をわかりやすく解説
1-2. そもそも扶養とは
扶養とは、自分一人の稼ぎで生計を立てられない家族や親族に対して経済的な援助をおこなう仕組みのことです。援助する人を「扶養者」、援助を受ける人を「被扶養者」といいます。たとえば、本業で生計を立てている人の配偶者や子、親などが被扶養者に該当します。
1-3. 社会保険料における扶養の意味
社会保険料における扶養とは、社会保険の被保険者の配偶者や子、親族などが、社会保険料を支払うことなく社会保険に加入できる仕組みのことです。収入のない専業主婦や専業主夫のほか、パートやアルバイトで短時間労働をしている家族であっても、一定の条件を満たせば扶養に入ることができます。
社会保険料の扶養に入る場合は、配偶者や親・子の健康保険に加入することになります。被扶養者本人は社会保険料を支払う必要がなく、金銭的な負担を減らして病院などを受診することが可能です。
2. 社会保険料の扶養範囲
 社会保険の扶養には一定の範囲が定められています。税金の扶養と範囲が異なるので注意が必要です。ここでは、社会保険料の扶養範囲について詳しく紹介します。
社会保険の扶養には一定の範囲が定められています。税金の扶養と範囲が異なるので注意が必要です。ここでは、社会保険料の扶養範囲について詳しく紹介します。
2-1. 親族の範囲
社会保険の扶養の対象となるのは、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、三親等内の親族のみです。配偶者には、事実上婚姻関係と同様の人を含みます。
2-2. 生計をともにしていること
生計をともにしていることも社会保険における扶養の判断材料となるため、亡くなった内縁関係の配偶者の父母や子どもであっても扶養の対象として認められます。扶養の条件はかなり広い範囲に適用されるので、手続きの際には詳しい条件を確認しましょう。
2-3. 同居の有無
扶養に入れるかを判断する際には、家族や親族の同居の有無が確認されます。直系尊属や配偶者、子、孫、兄弟姉妹については、同居していない場合でも扶養に入ることが可能です。それ以外の三親等以内の親族については、同一世帯に居住していることが扶養に入るための条件となります。
2-4. 日本国内に住民票を有する
社会保険の扶養に入れるのは、原則として日本国内に住民票を有する人です。一定期間海外で生活する場合でも、日本に住民票があれば問題ありません。なお、短期間の出張や留学で住民票を移動させる場合、生活の基礎が日本国内にあると認められれば扶養に入ることができます。
2-5. 【ポイント】年金の扶養対象となる家族は配偶者のみ
健康保険の被扶養者になった場合、配偶者(20歳以上60歳未満)に限り、第3号被保険者として国民年金保険料の支払いが免除されます。保険料を納付しなくとも、扶養に入っている間は保険料を納付したとされ、年金額に反映されます。
たとえば、大学生の子(22歳)を健康保険の扶養に入れたとしても、その者の国民年金保険料の支払いは免除されないので注意が必要です。この場合、第1号被保険者として、自分で国民年金保険料を納めなければなりません。
3. 社会保険料の扶養に入るための年収・年齢条件
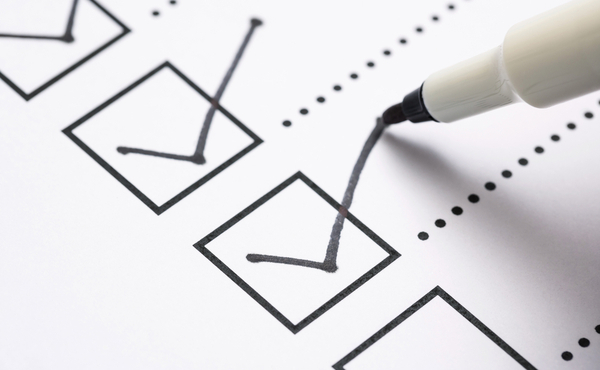
社会保険の扶養に入るためには一定の条件を満たす必要があります。ここでは、収入や年齢など、社会保険の扶養に入るための細かな条件について詳しく紹介します。
3-1. 生計維持関係にあるか否か
被保険者が生活費を負担するなど、生計を維持されている人のみが社会保険料の扶養に入ることができます。年収などの条件を満たしているときでも、生計維持関係になければ扶養に入ることはできません。
生計維持関係は、同居の場合であれば扶養家族の年収が被保険者の年収の2分の1未満のときに認められます。別居のときには、扶養家族の年収が被保険者からの仕送り額よりも低い場合に生計維持関係があると判断されます。
3-2. 扶養に入る人の年収条件(130万円)
被保険者の扶養に入るためには、年収が一定額未満でなければなりません。原則として、年収130万円(月収108,334円)未満であれば扶養に入ることが可能です。ただし、60歳以上または障害者については、基準額が年収180万円(月収150,000円)に設定されています。
社会保険料の扶養に関する収入を計算する場合、所得税の収入計算とは異なります。次のように、所得税の計算では非課税に該当するものが、社会保険の計算では収入に含まれるので注意が必要です。
- 障害年金
- 遺族年金
- 雇用保険の基本手当
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 傷病補償給付 など
年収130万円を超える場合は扶養に入れないので、勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入するかを検討する必要があります。なお、年収106万円以上(月収8.8万円以上)になる見込みの人は、社会保険適用事業所で働いている場合、社会保険の加入対象者に当てはまる可能性があります。その場合は、社会保険に入れるか勤務先に相談してみましょう。
3-3. 扶養の対象となる年齢条件
社会保険の扶養の対象となる年齢に条件はありません。しかし、社会保険の被保険者が65歳になり、老齢基礎年金などの受給権を有している場合、第2号被保険者ではなくなります。この場合、当該第2号被保険者に扶養されていた60歳未満の配偶者は、第3号被保険者から第1号被保険者に切り替えて、自ら保険料を納める必要があります。
また、被扶養者が75歳以上になると、後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。この場合は、健康保険の扶養から外れ、自ら保険料を支払う必要があるので注意しましょう。
3-4. 社会保険料は扶養人数で変わる?
社会保険料は扶養人数によって変わることはありません。社会保険料は、被保険者の標準報酬月額によって決まるからです。ただし、国民健康保険に加入している会社員などの場合、社会保険料が扶養人数などによって変わる可能性があるので注意しましょう。
4. 社会保険適用拡大で扶養はどう変わった?

働き方改革の影響もあり、多様な働き方が推進されています。しかし、非正規雇用者が正規雇用者と同様の社会保障を受けられないことが問題視され、社会保険適用拡大が進められています。ここでは、2024年10月の社会保険適用拡大によって、社会保険料の扶養に関してどのような変化があったのか詳しく紹介します。
4-1. 2024年10月から社会保険の適用範囲拡大
令和2(2020)年5月に年金制度改正法が成立し、社会保険の適用範囲が拡大されることとなりました。社会保険料適用拡大は段階的に進められ、2024年10月からは従業員数51人以上100人以下の組織で働くパート・アルバイトなどの短時間労働者も、社会保険の適用対象となっています。
これまで扶養に入れていた人でも、次のすべての要件を満たした場合には、原則として、扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければならなくなります。
- 従業員数50人を超える事業所で働く
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
これによって、手取り額が減少し、生活に支障が出る恐れがあります。一方、厚生年金保険にも入れるため、将来の年金を増やせる可能性もあります。
社会保険適用拡大へ正しく対応するために、企業は社会保険の対象者が増えた場合の対応方法を確認しておかなければなりません。しかし、何をすればよいのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて、当サイトでは、社会保険適用拡大をうけて企業がすべき対応をまとめた資料を無料で配布しています。社会保険適用拡大への対応準備がまだできていない方や正しく対応できているか確認したい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご活用ください。
5. 社会保険の扶養に入るメリット

社会保険の扶養に入ると、どのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは、社会保険の扶養に入るメリットについて詳しく紹介します。
5-1. 家計の負担を軽減できる
家族を社会保険の扶養に入れたとしても、原則として、社会保険料の負担額は変わりません。一方、配偶者や子どもなどは、扶養に入ることで、自身で社会保険料を負担せず、社会保険に加入できます。そのため、免除された社会保険料の分、家計の負担を軽減することが可能です。
5-2. 健康保険に加入できる
公的医療保険への加入は強制であるため、働いていない人でも、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険料の支払いにより生活への負担が大きくなってしまいがちですが、扶養に入れば自分で保険料を納める必要はなくなります。また、健康保険に加入することで、国民健康保険よりも手厚い保障を受けられる可能性があります。
5-3. 扶養手当が支給される
会社によっては、扶養手当が支給されるケースもあります。家族の人数や年収などの条件は会社によって異なりますが、扶養に入ることで手当が増えることは大きなメリットといえるでしょう。
6. 社会保険の扶養に入るデメリット

社会保険の扶養に入る場合、メリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、社会保険の扶養に入るデメリットについて詳しく紹介します。
6-1. 収入を調整する必要がある
社会保険の扶養に入る場合、収入の調整など、管理の手間がかかります。扶養に入ったまま働く場合は、収入を一定の金額以下に抑えなければなりません。やりがいを得るためにもっと働きたいと思っても、勤務時間を増やせないケースもあるでしょう。
また、その時点の契約などに基づき収入条件は判断されます。たとえば、今後退職する予定があっても、雇用契約書に「月収12万円」と記載があれば、収入条件を満たさなくなるため、扶養から外れなければならないので注意が必要です。
6-2. 年金の受給額が減る
年金の受給額が減ることも、扶養に入るデメリットの一つです。被扶養者である配偶者は国民年金に加入できますが、厚生年金保険には加入できません。厚生年金保険に加入しないことで受け取れる年金額が少なくなるため、生活資金の不安を感じることもあるでしょう。自分で働いて勤務先の社会保険に加入すれば、厚生年金保険に加入できるので、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
6-3. 傷病手当金がもらえない
健康保険に加入する場合、病気やケガをしたときに一定期間傷病手当金を受け取れます。国民健康保険に傷病手当金制度はないため、手厚い保障が受けられると考えられます。
しかし、傷病手当金とは、被保険者が病気やケガで仕事を休んだときに支給されるものです。そのため、被扶養者の場合、被保険者の健康保険に加入できても、傷病手当金を受給することはできないので注意しましょう。
7. 社会保険の被扶養者になる手続き方法

社会保険の被扶養者になるには、いくつかの手続きが必要になります。被保険者は「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」を作成して、事業主を経由して日本年金機構に提出しなければなりません。また、状況に応じて、下記のような書類を添付する必要があります。
- 続柄確認のための書類
- 収入要件確認のための書類
- 仕送りの事実と仕送り額の確認のための書類
- 内縁関係の確認のための書類 など
提出期限は「扶養の事実発生から5日以内」とされています。提出方法は「窓口持参」「郵送」「電子申請」から選ぶことが可能です。提出先は、事務センターもしくは、所轄の年金事務所となります。
なお、協会けんぽ以外の健康保険組合などに所属している場合、「国民年金第3号被保険者関係届」は日本年金機構に、「健康保険被扶養者(異動)届」は健康保険組合に提出することになるので注意しましょう
参考:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
8. 社会保険料と税金「扶養」の違いとは?

扶養は「社会保険料の扶養」と「税法上の扶養」の2種類に分けることが可能です。税法上の扶養とは、所得税・住民税を計算する際に扶養控除(配偶者控除)の対象になることです。納税者に控除対象となる扶養親族・配偶者がいる場合、納税者の所得から一定の金額を控除することができます。このように、「社会保険料の扶養」と「税法上の扶養」は異なる意味を持ちます。
また、扶養に入れるかの条件も異なるので注意が必要です。ここでは、扶養控除と配偶者控除を適用するための条件について詳しく紹介します。
8-1. 扶養控除の条件とは?
扶養控除とは、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除を指します。扶養親族とは、原則として、その年の12月31日時点で、次のいずれもの要件を満たす人のことです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)や里子、養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)
- 青色申告者や白色申告者の事業専従者として給与などを受け取っていない
なお、控除対象扶養親族の対象になるのは、16歳(その年12月31日現在の年齢)以上の扶養親族です。また、年齢や同居の有無などによって控除額も変わるので注意しましょう。
8-2. 配偶者控除の条件とは?
配偶者は扶養控除の対象外です。しかし、配偶者がいる場合、配偶者控除を適用できる可能性があります。配偶者控除とは、控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除です。控除対象配偶者とは、原則として、その年の12月31日時点で、次のいずれもの要件を満たす人のことです。
- 民法上の配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)
- 青色申告者や白色申告者の事業専従者として給与などを受け取っていない
配偶者控除を適用する場合、配偶者だけでなく、納税者自身にも条件があります。納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が下がり、1,000万円を超えると配偶者控除を適用できないので注意が必要です。
なお、配偶者の年間の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除を適用できませんが、配偶者特別控除を適用できる可能性もあるので、正しく制度の理解を深めておきましょう。
9. 社会保険の手続きの際は扶養の範囲・条件をしっかり確認しよう!

社会保険の扶養に入るには、収入や同居の有無など、さまざまな条件を満たす必要があります。また、社会保険適用拡大により、自ら社会保険に加入しなければならない労働者は増えています。従業員それぞれの状況をきちんとチェックし、正しく扶養の手続きをしましょう。









