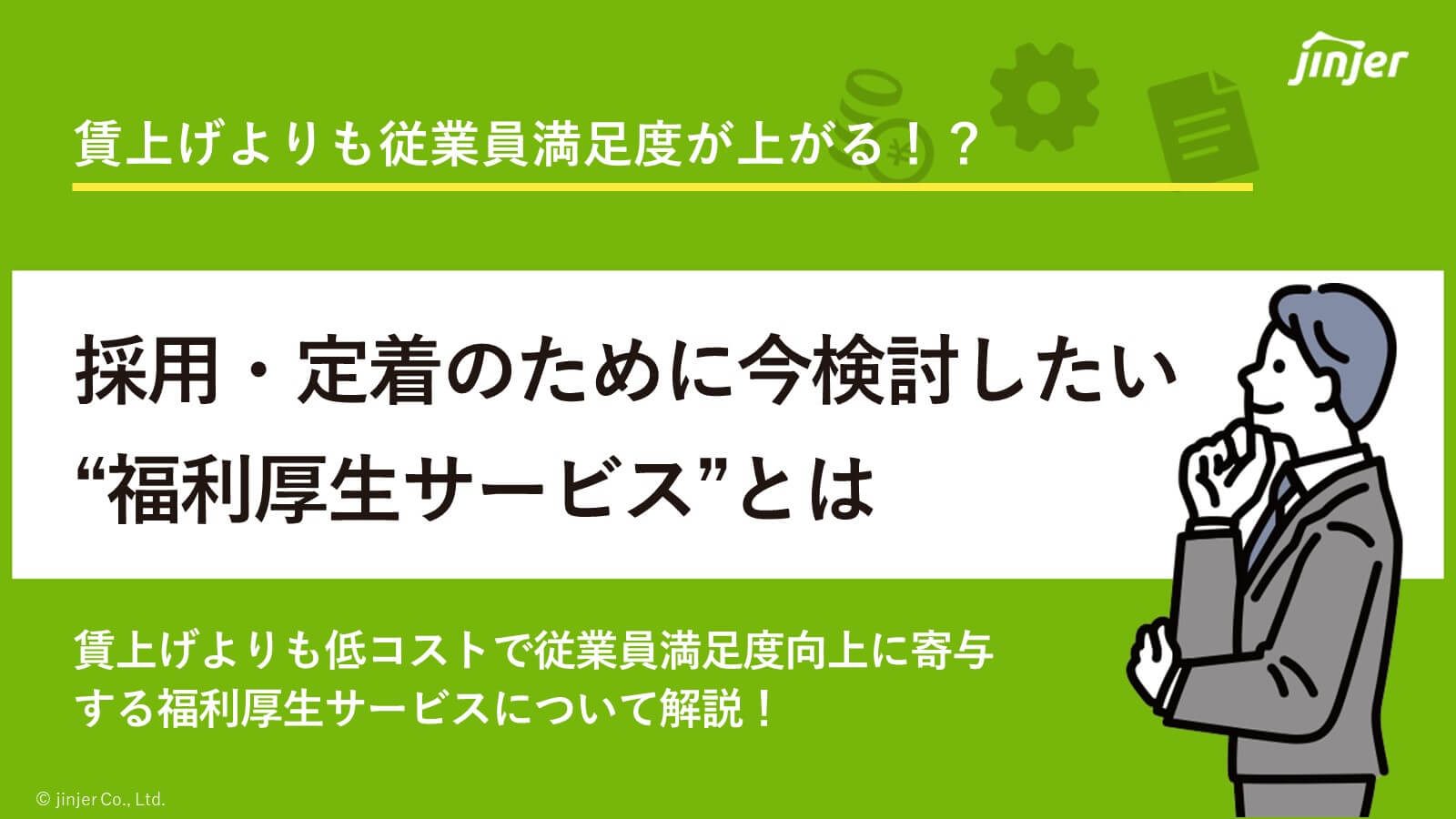「退職金制度の種類とは?」
「退職金制度を導入するメリット・デメリットとは?」
「退職金制度を導入すると税金の計算方法はどう変わる?」
上記のような疑問を持っている人も多いでしょう。
企業の経営者や労務担当者のなかには、退職金制度を導入したい一方で、知識がほとんどない人が多いでしょう。退職金制度は大きく分けて3種類あり、導入することで税金の計算が複雑になります。
本記事では、退職金制度の種類や特徴について解説します。また、退職金制度を導入するメリット・デメリットや退職金の相場、導入する手順も紹介するため、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 退職金制度とは

退職金制度とは、従業員が企業に長年勤続したときに、企業から従業員に送られる一時金や年金のことを指します。従業員の老後の生活を支えるために導入された制度です。
昔の企業独自の退職金の支給開始時期は、全面的に企業側に委ねられており、明確な基準はありません。日本では、退職金制度が従業員への福利厚生の一環として、長年にわたり重要な役割を果たしてきました。
しかし、近年は退職金制度の見直しや廃止を検討する企業も増えています。一方で、優秀な人材の確保や従業員の労をねぎらうことを目的として、退職金制度を活用することも可能です。
退職金制度は、従業員の一斉退職などがあると大きな金額が動くため、長期的な計画性を持ったうえで、導入を検討しましょう。
1-1. 退職金制度なしは違法?
退職金制度を導入することは、法律上の義務ではありません。退職金制度を導入するかどうか、どのような基準で支払うか、といったことは企業が自由に決定できます。ただし、退職金について就業規則や雇用契約書などに記載している場合は、ルールに従って支払わなければなりません。
1-2. 退職金と傷病手当金の違い
退職金と傷病手当金の違いですが、退職金は、退職を理由として支給されるものですが、傷病手当金は、業務外で病気やケガなどにより働けなくなって休職する場合に従業員とその家族の生活を支えるために支給される手当金です。傷病手当金は、各種の健康保険組合や協会けんぽから給付されるものであり、企業が支給するわけではありません。退職したときに支給される退職金とは異なり、基本的には在職中に支給されます。ただし、休職した後、職場復帰できず退職した場合にも継続給付できる場合があります。
1-3. 退職金制度の対象者
退職金制度の対象者は、企業によって異なります。前述の通り、退職金制度を導入する義務はなく、内容も自由に決定できるため、誰を対象とするのかも企業によって異なるのです。一般的には正社員を対象として支給するケースが多いのですが、契約社員なども含め、幅広く支給している企業もあります。
2. 退職金制度の種類

退職金制度には、大きく分けて3つの種類があります。
- 自社準備型の退職一時金制度
- 企業年金型の退職金制度
- 退職金共済型の退職金制度
2-1. 自社準備型の退職一時金制度
自社準備型の退職一時金とは、従業員が退職するときに企業から一括で支給される退職金です。「退職金制度」と聞いて、真っ先にイメージするのは、この自社準備型の退職一時金でしょう。
退職一時金の原資は、企業の内部保留や保険商品などです。支給条件や運用ルールは、企業が独自で決められます。財務状況に応じて柔軟に退職金を準備できることがメリットです。一方で、企業の運転資金と混同する可能性があるため、積立金に対して課税が発生するデメリットがあります。
自社準備型の退職一時金制度を導入すると、将来的に業績が悪化した場合、資金繰りに苦労することもあるでしょう。財務が安定していない企業や比較的規模が小さい企業では、導入の難易度が高いといえます。
2-2. 企業年金型の退職金制度
企業年金型の退職金制度は、企業が年金基金を設立して、従業員が退職したときに、年金形式で退職金を支給する制度です。企業年金型の退職金制度の種類は3つあります。
|
確定給付企業年金(DC)制度 |
・従業員が受け取る年金額が事前に確定している企業年金制度 ・予定利率に基づいて運用し、成果が不足した場合は企業が補填する ・従業員は安定した年金型の退職金を受け取れることがメリット |
|
企業型確定拠出年金(企業型DC)制度 |
・企業と従業員の両方が拠出金を出して、運用は従業員自身でする年金制度 ・運用リスクは従業員が追うため、企業は財務の負担が軽減できる場合がある |
|
iDeCo+(イデコプラス)制度 |
・中小企業が従業員の個人型確定拠出年金(iDeCo)に追加掛金を拠出する制度 ・企業が拠出する分は全額損金算入されるため、企業には節税効果がある ・従業員は個人型DCに加入し、iDeCo口座を開設していることが前提 |
企業年金型の退職金制度は、拠出金を出す対象と運用の責任を負う対象によって違いがあるため、状況に応じて選ぶことが大切です。
2-3. 退職金共済型の退職金制度
退職金共済型の退職金制度は、中小企業や個人事業主(フリーランス)が多く利用する制度です。現役時代は共済組織に加入して、退職後はそこから退職金を受け取ります。
退職金共済型の退職金制度の種類は3つです。
|
中小企業退職金共済制度 |
・中小企業が共済組織に加入して毎月積み立て、従業員が退職したときに共済組織から直接退職金が支払われる制度 ・企業の掛金は全額損金計上されるため、税制上のメリットがある |
|
小規模企業共済制度 |
・小規模企業の経営者や個人事業主が退職後の生活資金を準備するための制度 ・毎月積み立て、退職または廃業のときに支払われる ・掛け金は税控除の対象となり、非課税で運用できるメリットがある |
|
特定退職金共済制度 |
・業界団体や地域団体が運営する共済制度 ・業種や業界の特徴に合わせて、柔軟な資産運用ができる ・企業の掛金は全額損金計上されるのがメリット |
退職金共済型の退職金制度は、共済組織の違いにより差異があります。それぞれの理解を深めたうえで選びましょう。
3. 企業が退職金制度を導入する5つのメリット

企業が退職金制度を導入する主なメリットは、以下の5つです。
- 優秀な人材を採用できる
- 従業員の勤続年数を引き上げられる
- 企業が負担する掛金は全額損金になる
- 早期退職を進めやすい
- 従業員の不正防止につながる
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
3-1. 優秀な人材を採用できる
退職金制度を導入することで、優秀な人材を採用できるチャンスが広がります。退職金制度は、従業員にとって重要な福利厚生の一つであるためです。
退職するときに将来受け取れる退職金が用意されている安心感は、企業への信頼感につながります。退職金制度を充実させることで、他社との差別化を図ることが可能です。優秀な人材から選ばれやすくなり、採用につながります。
3-2. 従業員の勤続年数を引き上げられる
退職金制度は、従業員の勤続年数を引き上げる効果があります。退職金の額は、勤続年数に比例して増加する傾向があるため、従業員が長く働くためのインセンティブです。
また、長期に渡り勤続する従業員が増えることで、企業の生産性が向上します。さらに、従業員の定着率が高まることで、採用や教育にかかるコストの削減が可能です。
3-3. 企業が負担する掛金は全額損金になる
退職金制度において、企業が負担する掛金は全額損金として計上可能です。そのため、企業が支払う法人税を抑えられます。
退職金制度を活用すれば、企業の利益のうち、退職金の積立金が経費として認められる仕組みです。節税効果を高めたい企業は、退職金制度を導入することも一つの方法といえます。
3-4. 早期退職を進めやすい
早期退職を進めやすいことも退職金制度を導入するメリットのひとつです。どのような企業であっても、急な業績悪化などにより、早期退職を進めなければならない状況に陥る可能性があります。退職金制度があれば、従業員はしばらくの間は生活できるため、早期退職をスムーズに進められるでしょう。
3-5. 従業員の不正防止につながる
退職金制度をうまく活用することで、従業員の不正を防止することも可能です。たとえば、従業員が犯罪に関わったり、重大な規律違反をしたりした場合は、退職金を減額や不支給にするようなルールを設定しておくと、不正防止につながるでしょう。
4. 企業が退職金制度を導入する3つのデメリット
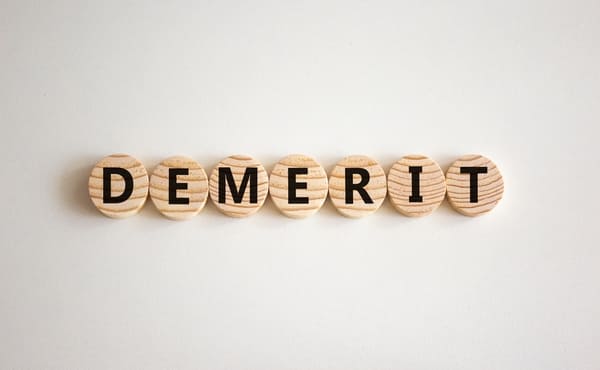
企業が退職金制度を導入するデメリットは3つです。
- 退職金制度を導入したら簡単には廃止できない
- 退職金の原資を準備する負担がある
- 退職金の運用にランニングコストがかかる
各デメリットの詳細は以下の通りです。
4-1. 退職金制度を導入したら簡単には廃止できない
一度導入した退職金制度は、簡単には廃止できません。退職金制度は、企業のリクルート戦略であると同時に、従業員の権利であるためです。
退職金制度の廃止や積み立てる金額の見直しは、従業員のモチベーションが低下する可能性があります。退職金制度を導入するときには、長期的な視点の計画を持つことが重要です。
4-2. 退職金の原資を準備する負担がある
退職金制度を維持するためには、積立金の原資を確保する必要があります。とくに従業員数が多い企業では、退職金の積み立ても高額です。
たとえば、景気が悪化して企業の業績が低迷すると、退職金の原資を準備する負担が大きくなります。また、退職金の支払い時期が重なると、企業のキャッシュフローが悪化することがあるでしょう。
4-3. 退職金の運用にランニングコストがかかる
退職金の積立金を運用するためには、手数料や管理費用などのランニングコストがかかります。かかるランニングコストは会社によるため、事前に試算することが大切です。
また、企業自ら運用する場合、専門知識がある人材を確保する必要があります。退職金制度を導入するときには、積立金の拠出だけではなく、ランニングコストに目を向けることが重要です。
5. 退職金の相場

令和4年度の政府統計によれば、会社都合の退職金の平均支給額は約1,399万円、自己都合の場合は約487万円です。
退職金の金額は、退職理由や勤続年数、退職時の給与所得額などを踏まえて、総合的に決定します。企業の規模や業種によっても、退職金の相場は大きく異なることが一般的です。
会社都合の退職は、従業員の退職後の生活を支援するために、自己都合の退職よりも高額な退職金が支給されることもあるでしょう。
参考:賃金事情等総合調査 / 令和5年賃金事情等総合調査 令和5年退職金、年金及び定年制事情調査|e-stat政府統計の総合窓口
5-1. 退職金の金額は自社の状況に合わせて設定すべき
退職金の相場を把握することも大切ですが、実際に金額を決定するときは自社の状況に合わせましょう。そもそも、退職金制度を導入することは義務ではありません。本当に退職金制度を導入すべきなのか、どのくらいの金額が妥当なのか、さまざまな視点から慎重に検討することが重要です。
6. 退職金と税金の計算方法

退職金にかかる税金を計算するには、4つのステップが必要です。
- 退職所得控除の金額を求める
- 課税退職所得の金額を求める
- 課税退職所得から所得税を求める
- 課税退職所得から住民税を求める
それぞれのステップについて簡単に確認しておきましょう。
6-1. 退職所得控除の金額を求める
退職所得控除の金額は、勤続年数によって変わります。
|
勤続年数 |
退職所得控除 |
|
20年以下 |
勤続年数 × 40万円(最低80万円) |
|
20年超 |
800万円 + (勤続年数 – 20年)× 70万円 |
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
6-2. 課税退職所得の金額を求める
退職金には、「退職所得」として特別な計算方法で課税されます。給与所得とは計算方法が異なるため注意が必要です。
課税退職所得 = (退職金の総額 – 退職所得控除額)× 1/2
6-3. 課税退職所得から所得税を求める
課税退職所得を通常の所得税率に基づいて算出します。所得税は累進課税方式です。
|
課税所得 |
税率 |
|
195万円以下 |
5% |
|
195万円を超え329.9万円以下 |
10% |
|
330万円を超え694.9万円以下 |
20% |
|
695万円を超え899.9万円以下 |
23% |
|
900万円を超え1,799.9万円以下 |
33% |
|
1800万円を超え3,999.9万円以下 |
40% |
|
4,000万円を超える部分 |
45% |
6-4.課税退職所得から住民税を求める
退職金には住民税も課税されるため、計算して金額を求めましょう。
なお、住民税は一律で10%の税率が適用されます。
住民税 = 課税退職所得 × 10%
7. 退職金制度を導入する手順

退職金制度を導入する手順はこちらです。
- 退職金制度の種類を決める
- 労働者の代表者に合意を取る
- 退職金規定を作成して説明会を開く
- 所轄の労働基準監督署へ届け出る
各手順の詳細は以下の通りです。
7-1. 退職金制度の種類を決める
まず、退職金制度の種類を決めます。
自社準備型の退職一時金制度、企業年金型の退職金制度、退職金共済型の退職金制度から、企業の特徴にマッチした制度を選択しましょう。
7-2. 労働者の代表者に合意を取る
退職金制度を導入するためには、労働者の代表者との協議と合意が必要です。
労働者の代表者とは、労働組合の代表者や従業員の代表者のことを指します。導入前に従業員から同意を得ておくことで、後々のトラブルを回避することが可能です。
7-3. 退職金規定を作成して説明会を開く
労働者の代表者との協議が終わると、退職金規定を作成してから、従業員説明会を開きます。退職金規定には、支給対象となる従業員の範囲、支給条件、計算方法、支給時期などを明記しましょう。
説明会では、質疑応答の時間を設けるなどして、従業員の納得感を得ておくことが重要です。
7-4. 所轄の労働基準監督署へ届け出る
退職金制度を正式に導入するためには、就業規則を変更することが必要となるため、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。提出書類は、退職金規定の写しや労働者の代表者との協議記録などを含むことが一般的です。
8. 既存の退職金制度を変更・廃止することは可能?

既に導入している退職金制度を変更したり、廃止したりすることも可能です。ただし、金額を下げることや廃止することは、従業員にとって不利益な変更となるため、適切な手順で進めなければなりません。
具体的には、制度を変更・廃止する必要性や理由、不利益の内容などを従業員に対して説明することが必要です。また、打切り支給を検討するなど、退職金の減額や廃止による不利益に対して、緩和措置を講じる必要があります。そして従業員の同意を得られれば、退職金制度の変更や廃止をおこなうことが可能です。
ただし、変更・廃止の内容を従業員に周知したうえで、変更・廃止が合理的であると認められた場合は、従業員の合意は必要ありません。
9. 退職金制度の導入に関する助成金

退職金制度の導入に関する助成金として、以下のようなものがあります。
- キャリアアップ助成金
- 中小企業退職金共済制度への助成金
それぞれの助成金の詳細は以下の通りです。
9-1. キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者・派遣労働者・短時間労働者などのキャリアアップを促進するための助成金です。上記のような労働者の正社員化や、処遇改善の取り組みをおこなった場合に支給を受けられます。
退職金制度を導入した場合も支給の対象となり、大企業には30万円、中小企業には40万円支給されるため、うまく活用しましょう。
9-2. 中小企業退職金共済制度への助成金
中小企業退職金共済制度に新規加入する場合、掛金月額の半額を1年間助成してもらえます。ただし、加入後4カ月目からの支給となります。また、従業員ごとに5,000円が上限です。
短時間労働者の特例掛金月額加入者については、さらに助成金が上乗せされるので確認しておきましょう。
参照:中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成|厚生労働省
10. 退職金制度のメリット・デメリットを理解して導入を検討しよう!

今回は、退職金制度の意味や導入するメリット・デメリットなどを解説しました。退職金制度を導入することは法律上の義務ではありませんが、優秀な人材を採用したり、定着率を高めたりするために導入している企業も多いでしょう。退職金制度の内容は企業が自由に設定できるため、大きな負担にならないよう、金額や支給対象などは慎重に検討することが重要です。
また、退職金制度を導入すると、簡単に廃止することはできません。従業員にとって不利益な変更となるため、緩和措置を講じるなど、従業員に対する配慮が必要です。長期的に運用していけるか、予算はどのように確保するのか、さまざまな視点から検討したうえで退職金制度を導入しましょう。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。