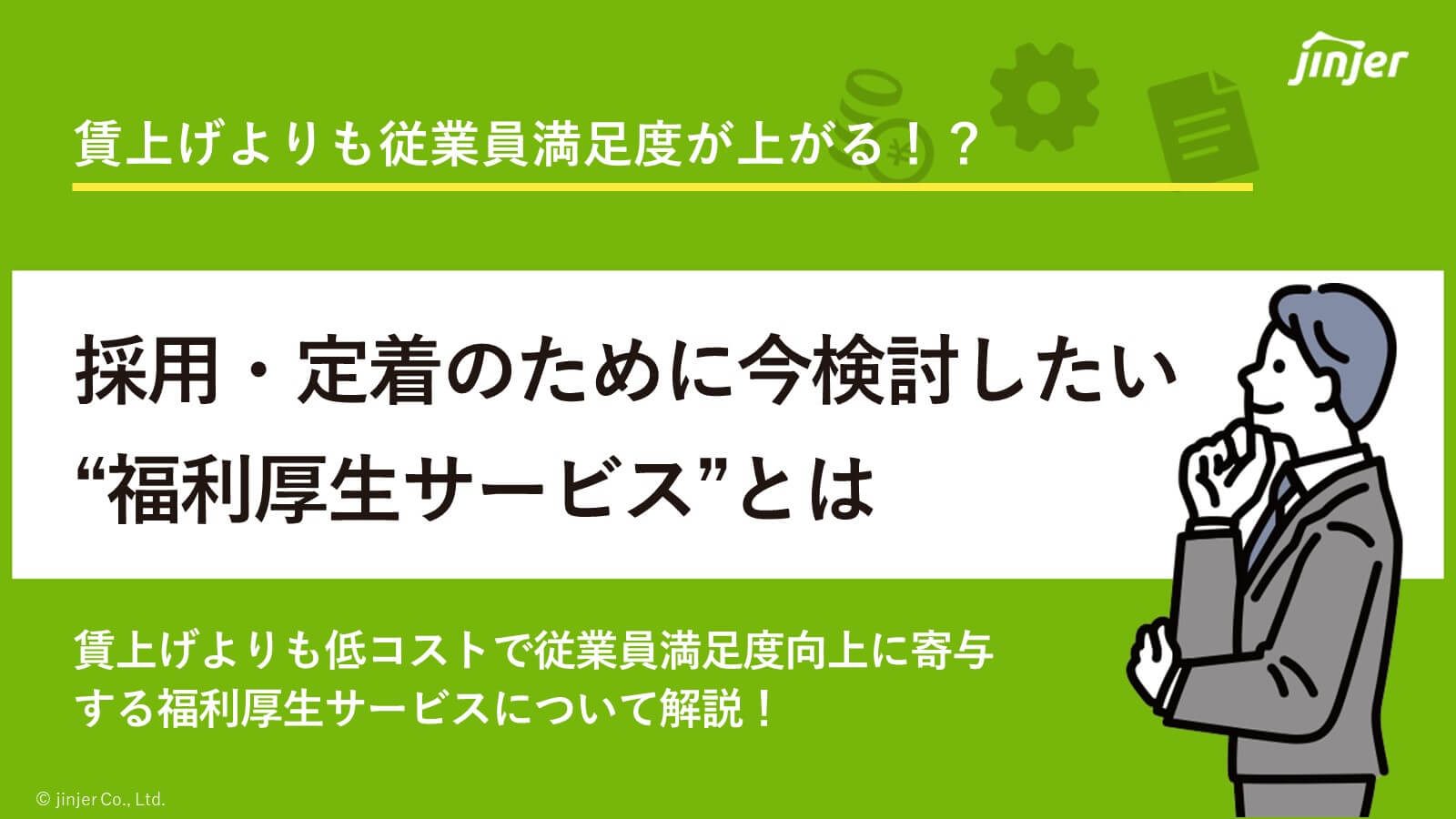「資格手当って何?」
「資格手当はどれくらい支給するべき?」
上記のように悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
資格取得に必要な資金を援助したり、特定の資格を保有している従業員に支給したりする資格手当ですが、法律などで明確に金額が決められているわけではありません。相場を把握して、適切な金額を設定することが大切です。
そこで本記事では、資格手当の概要や相場を解説します。資格手当を導入することで得られるメリットや、導入の際の注意点も説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 資格手当とは

資格手当は、従業員が業務に関連する資格を取得した際、または保有している場合に、企業が支給する手当のことです。従業員のスキルアップを奨励し、企業の競争力を高めることを目的としています。
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、資格手当を支給している企業の割合は50.8%です。人材不足対策やリスキリング対策として、資格手当を導入している企業もあります。
1-1. 資格手当については就業規則に記載するのが基本
資格手当を支給することは法律的な義務ではないため、有無や支給条件、支給金額などは企業によって異なります。資格手当を導入する場合は、支給に関するルールを就業規則に記載しておきましょう。また、資格手当があることを従業員に周知しておくことも大切です。
1-2. 資格手当を廃止する企業も増えている?
新たに資格手当を導入する企業がある一方で、廃止する企業も存在します。業績が悪化したことや従業員のニーズが変化したことを受け、資格手当を廃止したり、別の手当を支給したりする企業も多いでしょう。
前述の通り、資格手当を支給するかどうかは企業の自由です。経営状況や従業員のニーズに合わせて、導入するかどうかを検討しましょう。
2. 資格手当の種類

資格手当には、以下の2種類が存在します。
- 毎月支給される「資格手当」
- 取得時に支払われる「合格報奨金」
それぞれ具体的に解説します。
2-1. 毎月支給される「資格手当」
資格手当とは、従業員が特定の資格を保有していることに対して、企業が継続的に支給する手当のことです。基本給に上乗せされ、給与明細に「資格手当」や「技能手当」などの名目で記載されます。
資格手当の額は資格の種類・企業の規模・業界によって異なりますが、1カ月あたり1,000〜5万円が一般的です。
資格手当の支給期間は、企業によって異なります。無期限で支給される場合もあれば、資格取得から数年間のみ支給される場合も珍しくありません。
一定期間収入が増加することで従業員のモチベーションを高められる一方で、手当を支給することで人件費が増加する点はデメリットです。従業員が手当に見合う成果を上げられない場合はコストだけがかかるため、費用対効果を十分に考慮する必要があるでしょう。
2-2. 取得時に支払われる「合格報奨金」
合格報奨金とは、従業員が資格試験に合格し、資格を取得できた際に一時的に支給される手当のことです。資格取得の努力を評価し、従業員のスキルアップを奨励する目的で支給されます。
合格報奨金の額は企業の方針や資格の難易度によって異なりますが、数千〜数万円程度が支給されることが多いです。資格取得の瞬間に一度だけおこなわれるため、先述した資格手当のように人件費が無駄になるリスクがありません。
ただ、資格取得に対して一時的な報酬を支給するだけでは、長期的なスキル維持やモチベーション向上につながらない可能性があります。合格報奨金と併せて、継続的なスキルアップを支援する仕組みを整えることが重要です。
3. 【国家資格】資格手当の相場一覧

ここからは、国家資格に対する資格手当の相場をいくつか紹介します。
- 中小企業診断士
- 社会保険労務士
- 宅地建物取引士
- 危険物取扱者
それぞれ詳細に解説します。
3-1. 中小企業診断士
中小企業診断士は、企業経営に関する高度な知識と分析力を持つ専門家として認められる国家資格です。資格手当の相場は、月額1〜3万円程度と高い傾向があります。
中小企業診断士の資格手当が高い理由には、資格の取得難易度が高いことが挙げられるでしょう。2023年の合格率をみると、1次試験が29.6%・2次試験が18.9%と、難関であることがわかります。
また、資格の需要が高い点も資格手当が高い理由の一つです。中小企業診断士は経営コンサルタントとしての業務に直結する知識を証明できます。
そのため、コンサルティング業界や金融業界を中心に、多くの企業で重宝されている点が特徴です。さらに、難関資格であることから、合格報奨金を支給する企業も少なくありません。
参考:令和5年度 中小企業診断士第1次試験に関する統計資料| 中小企業診断協会
参考:令和5年度 第2 次試験に関する統計資料|中小企業診断協会
3-2. 社会保険労務士
社会保険労務士は、労働・社会保険関連の法律に精通した専門家として認められる国家資格です。国家資格のなかでも難易度はトップクラスに高く、令和6年度 社会保険労務士試験の合格率は6.9%となっています。
資格手当の相場は、月額5,000円〜5万円程度と幅広く設定されている点が特徴です。
格手当の相場が広範囲に及ぶ理由は、資格保有者が携わる企業規模・業種・担当業務の範囲が広いことが挙げられます。従業員の働き方や部署に合わせて手当の額が異なるケースも珍しくありません。
人事部や総務部など、社労士の資格が効果的に働く分野では高めに設定すると、より従業員のモチベーションを高められるでしょう。
参考:第56回社会保険労務士試験の合格者発表|社会保険労務士試験オフィシャルサイト
3-3. 宅地建物取引士
宅地建物取引士は、不動産取引の専門家として認められる国家資格です。資格手当の相場は、月額5,000円〜3万円程度となっています。
宅建士の資格は、ほかの国家資格と比較すると取得難易度がそれほど高くない一方、資格手当が支給されやすい点が特徴です。
その理由として、不動産業界や金融機関などで需要が高いことが挙げられます。資格の内容をそのまま業務に活かせるため、従業員が取得することで企業の生産性や競争率強化を図れるでしょう。
3-4. 危険物取扱者
危険物取扱者は、消防法で定められた危険物を取り扱うときに求められる国家資格です。具体的には、ガソリンや石油など、火災の危険性の高い燃焼物を扱うときに必要となります。工場やガソリンスタンドなどで働く人に人気の資格といえるでしょう。
危険物取扱者に対する資格手当の相場は、月額3,000円〜1万円です。危険物取扱者は、難易度によって甲種・乙種・丙種の3つに分けられています。甲種を取得すると可能な業務が増えるため、資格手当も高額になるのが一般的です。
4. 【民間資格】資格手当の相場一覧

ここからは、民間資格に対する資格手当の相場をいくつか紹介します。
- 日商簿記
- 秘書検定
- TOEIC
- ファイナンシャルプランナー
- マイクロソフトオフィススペシャリスト
それぞれ具体的に解説します。
4-1. 日商簿記
日商簿記は、企業の経理・財務部門で広く活用される実務的な資格です。1級から3級まであり、資格手当の相場は取得した級に応じて3,000円〜2万円程度と設定されるケースがみられます。
とくに、2級以上の取得者に対して手当を支給する企業は多いです。2級以上の実践的な学習内容は、経理業務や経営分析、財務戦略の立案などさまざまな業務で役立ちます。企業の生産性や競争力の向上が期待できるでしょう。
4-2. 秘書検定
秘書検定は、ビジネスパーソンとしての基本的なスキルや知識を評価する資格です。1級から3級まであり、資格手当の相場は取得した級に応じて5,000円〜1万円程度となっています。
秘書検定は、資格を取得することで以下のスキルを取得可能です。
- 秘書業務スキル
- 一般的なビジネスマナー
- 社会常識
- 文書作成能力
そのため、多くの企業が新入社員教育の一環として秘書検定の取得を奨励しており、資格手当の対象にしています。とくに、より実践的なスキルを獲得できる準1級以上の取得者に対して、高額な手当を支給する企業は多いです。
4-3. TOEIC
TOEICは、ビジネス英語能力を測定する国際的な試験として知られています。資格手当の相場は、スコアに応じて3,000円〜2万円が一般的です。
ただ、なかには高額な報奨金を設定している企業も存在します。たとえば大手電気通信会社では、800点以上で30万円、900点以上で100万円の報奨金制度を導入中です。
グローバル化が求められる現代において、従業員の英語力獲得の重要性が伺えます。海外との取引がある企業は、TOEICの資格手当の導入によって企業の競争力向上が狙えるでしょう。
4-4. ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは、収入や支出を考慮しながら資金計画を立て、目標達成をサポートするための資格です。生命保険・年金・不動産などの分野で役立つ資格であり、資格手当の相場は1〜2万円です。1級と2級に分かれており、1級の難易度はとくに高いため、高額の資格手当を支給する企業もあります。
4-5. マイクロソフトオフィススペシャリスト
マイクロソフトオフィススペシャリストは、WordやExcel、PowerPointなどの操作スキルを証明する資格です。パソコンのスキルとしては役立ちますが、資格手当の相場はそれほど高くなく、1,000〜2,000円程度としている企業が多いでしょう。資格取得の難易度もそれほど高くはありません。
5. 資格手当を導入する3つのメリット

資格手当を導入するメリットは、以下の3つです。
- 従業員のモチベーション向上につながる
- スキルアップによって生産性が向上する
- 企業のイメージアップが期待できる
以下、それぞれ詳しく解説します。
5-1. 従業員のモチベーション向上につながる
資格手当の導入は、従業員のモチベーション向上に大きく影響します。多くの従業員が、自己成長や専門性の向上を望んでいるためです。
企業が資格手当を提供することで資格取得にかかる費用が軽減し、従業員の学習意欲を刺激できます。また、「会社から評価されている」などの感覚が生まれ、従業員の帰属意識や忠誠心の向上も図れます。
長期的な雇用維持にもつながり、企業にとって貴重な人材の流出を防ぐことにもつながるでしょう。
5-2. スキルアップによって生産性が向上する
従業員が業務に関連する資格を取得することで専門知識や技術が向上するため、より効率的かつ高品質な業務遂行が可能です。
とくに業界特有の資格を取得すれば、プロジェクトの成功率が上がり、顧客満足度も向上するでしょう。また、資格取得を通じて得られた新しい知識や技術は、研修などを通じて職場内で共有可能です。
チーム全体のスキルアップにもつながり、企業全体の競争力強化が期待できるでしょう。
5-3. 企業のイメージアップが期待できる
資格手当の導入は、企業のイメージアップにも大きく貢献できます。求職者に対して、「従業員の成長を支援する企業」とポジティブなイメージを与えるためです。
とくに若手人材や成長意欲の高い人材の場合、資格取得支援制度の存在は企業選びにおいて魅力的な要素となります。資格手当を提供することで、人材獲得競争において優位に立てるでしょう。
さらに、資格保有者が多い企業は、顧客からの信頼度も高まります。たとえば、金融機関でファイナンシャルプランナーの資格保有者が多ければ、顧客は安心して利用可能です。
企業の信頼性やブランド価値の向上につながり、長期的な企業成長を期待できるでしょう。
6. 資格手当に税金はかかる?

資格手当が支給された場合、課税の有無は手当の種類や支給方法によって異なります。
毎月の給与に加算される形で継続的に支給される資格手当は給与所得として扱われるため、所得税および住民税の対象です。手当の全額がそのまま振り込まれるわけではなく、源泉徴収された後の金額が支給されます。
また、資格取得後に一度だけ支給される「合格報奨金」も一般的には課税対象です。
ただ、以下の場合は、所得税法に基づき非課税として扱われることがあります。
- 会社の業務に必要な技術や知識を習得するための費用
- 業務に直接関連する資格の取得費用
手当の課税・非課税の条件を正確に把握し、適切な税務処理をおこなうことが大切です。
7. 資格手当を導入する方法

資格手当を導入する際は、資格ごとの支給額や運用方法を検討しなければなりません。具体的には以下のような手順で導入を進めましょう。
7-1. 対象となる資格を検討する
まずは、どのような資格を対象として手当を支給するか検討しましょう。資格を選ぶときは、従業員のニーズや事業計画、業界の動向などに合わせることが大切です。
いくら人気の資格であっても、事業を展開するうえで不要であれば手当を支給する意味はありません。さまざまな視点から慎重に検討するようにしましょう。
7-2. 支給額を決める
対象となる資格が決まったら、支給額を検討します。資格の重要性や取得の難易度などをもとに考えると、決定しやすいでしょう。
また、相場や自社の予算などを参考にすることも大切です。手当によって従業員のモチベーションを高めることは重要ですが、企業の負担が大きくなりすぎないように注意しなければなりません。
7-3. 運用方法を検討する
次に資格手当の運用方法を考えましょう。資格取得後の手続き方法や支給のタイミングなどを決めておく必要があります。取得時に合格報奨金として支給する、毎月の給与に上乗せして支給するなど、自社の状況に合った支給方法を検討することも必要です。
7-4. 就業規則を変更する
資格手当の金額や運用方法が決まったら、就業規則を変更しなければなりません。ここまで検討したような内容を就業規則に明記しておきましょう。また、資格手当が導入されたことを従業員へ周知することも重要です。
8. 資格手当を導入する際の注意点

資格手当を導入する際は、以下の3点に注意しましょう。
- 廃止・減額の際は従業員の同意を得る
- 非正規労働者も資格手当の対象にする
- 不公平感がないようにする
それぞれ詳細に解説します。
8-1. 廃止・減額の際は従業員の同意を得る
資格手当の廃止や減額を検討する際は、従業員の同意を得ることが極めて重要です。資格手当を同意なしに変更すると、労働条件の「不利益変更」とみなされる可能性があります。
廃止や減額の理由を明確に説明し、会社の経営状況や外部環境の変化などの合理的な根拠を示すようにしましょう。また、ほかの福利厚生や給与を見直すなどの代替案を提案したり、手当廃止までの猶予期間を設けたりなどの措置も大切です。
突然の変更は従業員のモチベーション低下や退職につながる可能性があるため、慎重に進めるように心がけましょう。
8-2. 非正規労働者も資格手当の対象にする
2020年(中小企業は2021年4月)に施行された「同一労働同一賃金」によって、以下の非正規労働者も資格手当の対象です。
- パートタイム労働者
- 有期雇用労働者
- 派遣労働者
具体的には、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、それぞれの待遇に不合理な差を設けることが禁止されています。資格手当の支給基準や金額を明確にし、全従業員に公平に適用することが重要です。
8-3. 不公平感がないようにする
資格手当を導入するときは、不公平感が生まれないように注意しましょう。たとえば、特定の部署の従業員しか受験できない場合、他の部署から不満の声が上がる可能性もあります。
従業員の不満が大きくなると、モチベーションの低下や離職の増加につながるため、できる限り公平な仕組みを構築することが重要です。
9. 資格手当を導入して従業員のモチベーションを高めよう!

今回は、資格手当の意味や種類、導入するメリットなどを解説しました。資格手当を導入すれば、従業員のモチベーションアップや定着率の向上を期待できます。スキルアップを支援することで、業務効率や組織全体の生産性が向上することも期待できるでしょう。さらに、資格取得をサポートしている企業として、イメージアップにつながることもあります。
ただし、資格手当を導入する場合は、不公平感が生まれないように注意しなければなりません。公平な制度にしなければ、不満を感じる従業員が増え、モチベーションが低下する可能性もあります。対象となる資格や支給方法をしっかりと検討したうえで、制度を導入するようにしましょう。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。