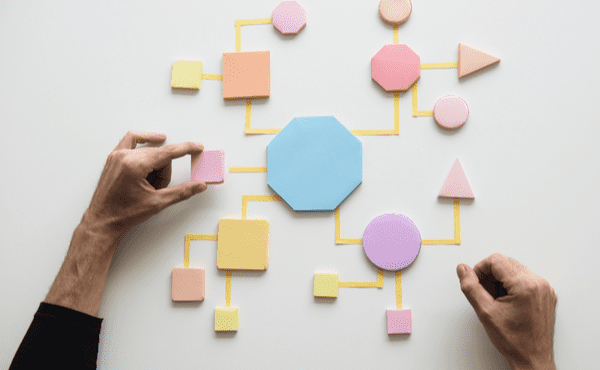 2022年4月の税制改正により、年末調整に関していくつかの変更が加えられました。
2022年4月の税制改正により、年末調整に関していくつかの変更が加えられました。
変更点のひとつは2022年の年末調整で対応が必要になりますので、変更の内容をしっかりチェックしておきましょう。
今回は、年末調整の変更点について解説します。
関連記事:年末調整とは|確定申告との違い、対応方法、注意点など基礎からわかりやすく解説!
関連記事:年末調整のキホン|今さら他人に聞けない担当者必見の内容をご紹介

令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。
- 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」
- 「アルバイトやパート、退職者に年末調整は必要?」
- 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、令和7年分の年末調整に必要な書類から対象者、計算の流れまで、年末調整に関する基本的な業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
業務の進め方に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整の内容は毎年変更される?

年末調整は毎年必ず変更すると決まっているわけではありません。
ただ、2019年の税制改正に伴い、2020年からは毎年のように年末調整に何らかの変更が加えられています。
たとえば、2020年には給与所得控除・基礎控除の額に変更があったほか、ひとり親控除や所得金額調整控除が新設されました。
さらに、2021年には年末関係書類への押印が廃止されたり、年末調整に関する書類を従業員から電磁的方法で受け取る際、税務署長への事前承認が不要になったりする変更も加えられました。
そして2022年、2023年にも年末調整に関する変更が予定されています。
年末調整が行われる時期は、会社そのものも忙しい時期に差し掛かりますので、2022年や2023年の変更点については早い段階から確認しておくことをおすすめします。
関連記事:年末調整の必要書類は?書き方・提出先も一からわかりやすく解説!
2. 年末調整に関する変更点を年度別に解説

2019年の税制改正にともなって生じた年末調整に関する変更点を年度別に解説します。
2-1. 2022年の年末調整に関する変更点
年末調整では各種控除証明書を提出する必要があります。
かつては原本を添付して提出しなければなりませんでしたが、2020年以降は年末調整関係の書類の電子化要件が緩和され、電子データで提出できる書類の範囲が拡大されました。
2020年には生命保険や地震保険、住宅ローンに関する控除証明書を電子データで提出できるようになりました。
そして2022年には、新たに社会保険料控除、小規模企業共済等控除の書類についても電子データでの提出が可能になります。
また、電子データを提出する手段として、電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードの付与された出力書面も対象に加えられました。
その場合、QRコード付証明書等作成システムを使って取得した電子データを読み込み、書面で控除証明書等を出力し、提出することになります。
最終的には書面で提出することになりますので、e-Taxなどの電子申告に比べるとやや手間がかかりますが、従来の紙媒体での提出より手間や時間を省くことができます。
関連記事:年末調整の電子化のやり方は?メリット・デメリットもわかりやすく解説
2-2. 2023年の変更点1:住宅ローン控除の要件変更
2023年の年末調整の変更点は大きく分けて2つあり、そのうちの一つが住宅ローン控除の要件変更です。
通称「住宅ローン減税」と呼ばれる住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅の新築や取得、または増改築等を行った場合に、年末のローン残高に対して一定の控除率を乗じて求めた額を所得税から控除する制度です。(※注1)
住宅ローン控除を受けるためには所定の要件を満たしている必要がありますが、2022年度にはその要件が一部緩和されました。
具体的な変更ポイントは以下の通りです。
①適用期限を2025年(令和7年)まで延長
もともと住宅ローン控除の適用期限は令和3年12月31日まででしたが、今回の変更により4年延長されることになりました。(※注1)
②控除率は0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年に変更
控除率は現行の1%から0.7%に引き下げとなりましたが、そのぶん新築住宅の適用期限が13年に延長されています。(※注1)
③既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
従来の認定住宅に加え、新たにZEH水準省エネ住宅と、省エネ基準適合住宅が住宅ローンの適用対象に加わっています。
既存あるいは新築住宅がいずれかの要件に当てはまった場合、借入限度額が一般住宅に比べて1,500万円(ZEH水準省エネ住宅)または1,000万円(省エネ基準適合住宅)上乗されます。(※注1)
④令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について省エネ基準適合を要件化する
令和5年までに入居した場合は、省エネ基準に適合しない一般住宅も適用対象となりますが、令和6年以降は省エネ基準適合が必須条件となります。(※注1)
⑤新築住宅の床面積要件を、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和
床面積40㎡以上50㎡未満の住宅については、令和3年1月1日~令和4年12月31日までの期間限定で適用される予定でした。
しかし、今回の変更により令和5年12月31日以前に建築確認を受けた住宅の取得においても適用されることになりました。(※注1)
ただし、合計所得金額が1,000万円以下の人に限ります。
⑥適用対象者の所得要件を2,000万円以下に引き下げ
住宅ローン控除の適用を受けられる所得要件が、合計所得金額3,000万円以下から、2,000万円に引き下げられました。(※注1)
2-3. 2023年の変更点2:非居住扶養親族の扶養控除の適用除外
これまで、以下の条件を満たしていれば国内・国外扶養親族ともに扶養控除の適用対象となっていました。
配偶者以外の親族等
納税者と生計を一にしていること
年間の合計所得金額が48万円以下であること
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
しかし、2023年1月1日以後は、以下のいずれにも該当しない年齢30歳以上70歳未満の非居住者は控除対象から除外されます。(※注2)
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
障害者
扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
なお、1と2はその事実を証明するための書類を提出する必要があります。
※注1:住宅ローン減税|国土交通省
3. 年末調整の変更点を無視するとどうなる?

年末調整の変更点を無視すると、適用要件を満たしているのに控除を受けられない、あるいは適用外なのに誤った手続きしてしまったというトラブルが発生するおそれがあります。
特に注意が必要なのは年末調整のやり方を誤って納税額が少なくなってしまった場合です。
会社は従業員に代わって所得税を源泉徴収し、国に納める義務があります。
年末調整の変更点を無視した結果、本来よりも納税額が少なくなってしまった場合、後のトラブルの原因となりますので要注意です。
変更点以外にもそもそも年末調整は手続きや計算が複雑です。変更点とあわせて年末調整に必要な手続き方法をおさらいしておきましょう。当サイトでは、年末調整の手続きの流れが1冊でわかる資料を無料でお配りしています。
図も交えてわかりやすく解説しているので、年末調整で必要な業務についてわかりやすく理解したい方はこちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてご活用ください。
4. 年末調整の変更点をしっかり押さえておこう

2019年の税制改正の影響で、前年までに引き続き、2022年や2023年も年末調整のルールにいくつか変更点があります。
2022年は控除証明書の電子データ化の適用範囲が拡大し、社会保険料控除などの電子データでの提出が新たに認められるようになりました。
そして2023年には住宅ローン控除や非居住者扶養控除などの適用要件やルールが変更されます。
毎年のように変更があると対応しきれず、混乱してしまいがちですが、控除が適用されるか否かは従業員にとって非常に重要なポイントになります。
年末調整が始まる前に変更された部分をよく理解し、適切に手続きを済ませられるようにしましょう。

令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。
- 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」
- 「アルバイトやパート、退職者に年末調整は必要?」
- 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、令和7年分の年末調整に必要な書類から対象者、計算の流れまで、年末調整に関する基本的な業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
業務の進め方に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。







