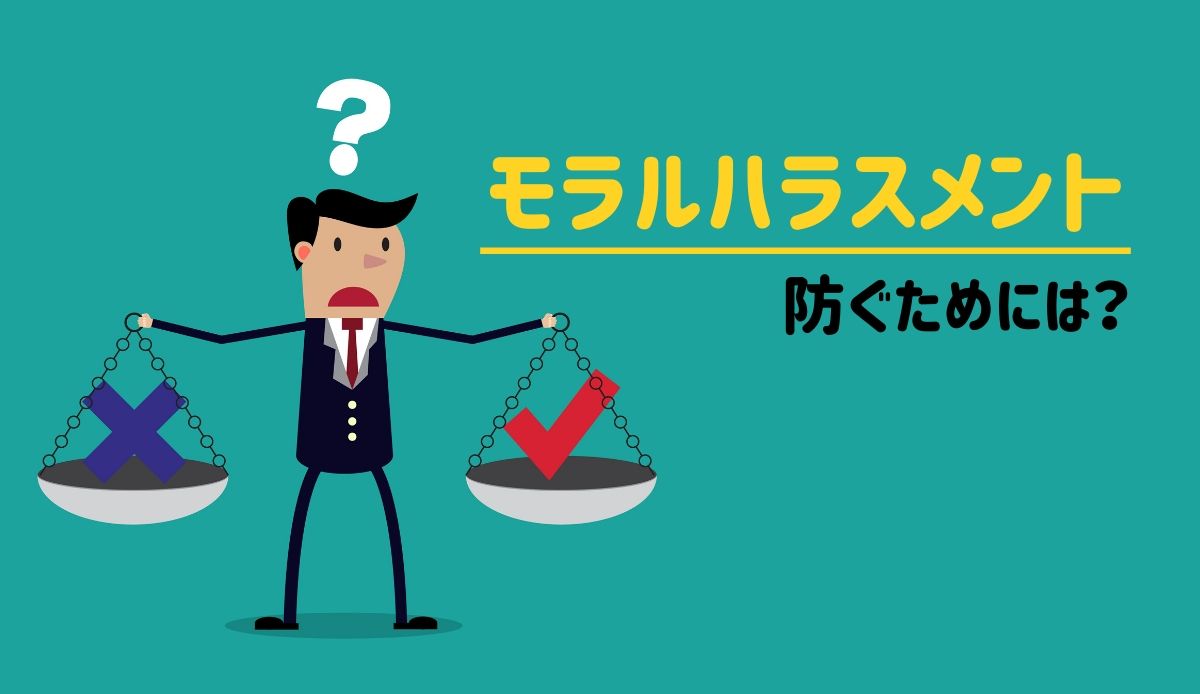
職場内で起こる「モラハラ」は社員を追い込むだけでなく、当事者の周りにいる社員にとっても悩ましい行為です。
最終的には会社のイメージダウンにもつながってしまうため、人事担当者は、モラハラをする人の特徴を把握し、モラハラ発生を未然に防ぐような対策をしなければなりません。
本記事では、職場内で起こりうるモラハラの原因や実態、その対策についてまとめました。
1. そもそも「モラハラ」とはなにか?
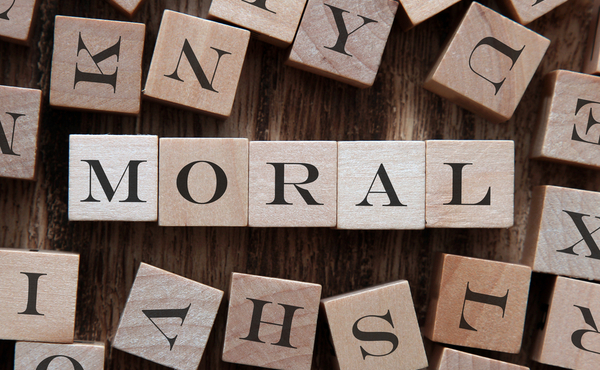
「モラハラ」とは、モラルハラスメントの略語で、倫理や道徳(モラル)に反した、嫌がらせ(ハラスメント)をおこない、相手に精神的苦痛を与えることをいいます。
態度や言動、あるいは文章などにより、相手の人柄やプライドを傷つけ、精神的に追い込む行為を継続しておこなうことがモラハラに該当します。
モラハラは陰湿な行為が多く、周りに気づかれにくいという特徴があるため、人事担当者が未然に防ぐことがとても難しくなっています。
- パワハラ:上司が部下に対しておこなう行為
- モラハラ:上司と部下、同僚同士など、さまざまな関係性の中で起こりうる行為
モラハラと似たような表現に、「パワハラ」があります。パワハラは、置かれている地位や立場を利用して、相手を精神的にも身体的にも追い込むことをいいます。
「モラハラ」チェックリスト
では、職場においてどのようなモラハラが起こっているのか、実際の実例をみていきます。
- 仕事が遅い、使えないなどと言った仕事に対する暴言や嫌みを言う
- 容姿、見た目などの悪口を言う
- バカ・頭が悪いなど人権を否定する内容の発言をする
- ミスしたことを公に発言したり大勢の前で叱責したりする
- 聞こえるように陰口を言ったり、その人を見て笑ったりしてからかう
- 特定の人を無視したり、集団で関わらないようにしたりする
- 仲間はずれにして飲み会など会社の行事に誘わない
- 連絡事項など仕事に関する情報を共有しない
- プライベート(恋人や家族)を必要以上に詮索する
- 趣味などをばかにする
- 膨大な量の仕事や大変な仕事を押しつける
- 仕事を頼まない
- 他の社員との対応に明らかに違いがある
モラハラは、「その行為がどこからモラハラに当たるか」という明確な基準はありません。
加害者側の中には、モラハラをしているつもりがなく、このような行為をしている人もいます。
そのため、まずは社員一人ひとりが「どのような行為がモラハラに当たる可能性があるのか」を知っておくことが大事です。
加害者側にモラハラの意識がなくとも、行為を受けた側が精神的苦痛を感じたのなら、その行為はモラハラに該当する可能性があります。
モラハラが発生することによる影響
モラハラが発生することで、企業にはさまざまな影響が起こりえます。
モラハラは被害者にも多大な損害を与えてしまう行為ですが、企業自体にもさまざまな影響が起こる可能性があることに注意しましょう。
社員(モラハラ被害者)が辞めてしまう
モラハラが発生することで、モラハラの被害者は会社に行くことがつらくなり、仕事に対する意欲が低下してしまいます。
誰にも相談できず抱え込んでしまうこともあり、最悪の場合、休職や退職せざる得ない状況になってしまうこともあります。
モラハラが原因で鬱病を発症してしまい、今後の社会復帰に影響が出ることもあるかもしれません。
企業としての責任を問われる場合がある
モラハラの実態を把握しながら会社が何も対策を取らずに放置した場合、企業としての責任を問われることがあります。
労働安全基準法により、企業は労働者が健康で安全に働くことができるように配慮しなければならない義務があると定められているため、この義務を怠ったと判断されれば、損害賠償を請求されるケースもあるでしょう。
業績に大きな影響が出る可能性がある
モラハラ発生への対応によっては企業に対する評価が下がり、当事者だけでなく他の社員の中にも辞めていく人が増えたり、社員のやる気が低下したりするかもしれません。
そのため、会社の業績にも大きな影響が出る場合も考えられます。
被害を受けた側が労働基準監督署へ相談に行った場合、企業に指導が入ることもありますし、モラハラが原因で事故が起こった場合には、社会全体からのイメージダウンも免れません。
モラハラが起きている事実を把握した場合、「会社が真摯に対応したかどうか」「モラハラを未然に防ぐための活動をしていたか」といいた点は重要なポイントになってきます。
2. 加害者・被害者の性格がモラハラを職場で起こす

それでは、なぜモラハラが起こってしまうのでしょうか。原因は、モラハラの加害者、被害者それぞれの性格が大きく関わってきます。
本章では、モラハラの加害者側、被害者側になりやすい人の性格の特徴について説明します。
モラハラ加害者の特徴
- 勝負にこだわり嫉妬深い
- 自己中心的な目立ちたがり屋
仕事上の勝ち負けにこだわるため、ノルマなど自分よりも成績が良い人がいると気に食わず、それが引き金となりモラハラが起こることがあります。
また自分の成績の悪さをさらに成績の悪い人のせいにすることでいらだちを解消しようとし、それがモラハラへと発展する場合もあります。
自分中心で物事を考える性格の人は、仕事が多く疲れがたまっていることで他人に当たりがちになります。そのいらだちの矛先になった人が被害者となることもあります。
また、仕事が遅い人が気になり、その人が処理できなかった仕事が自分に回されてきたことの不満が原因となり嫌がらせをするきっかけになる場合もあります。
プライベートや家庭環境の充実さなど仕事以外での悩みや不満も合わさって起こっていることもあります。
モラハラ被害者側の特徴
- 自己肯定感が低い
- 自分の意見を主張することがない
加害者側ではなく自分が悪いと思い込んでしまう傾向があり、嫌がらせを我慢してしまうことで、よりモラハラが進んでしまうことになります。
自分がモラハラを受けていることを把握し、助けを求めて事態を改善するよう努めなくてはなりません。
被害者側が退職をすれば事態が収まったようにも思われますが、加害者側が改善しなければ、職場内でのモラハラはなくなりません。
このように加害者も被害者もその性格に当てはまる人は数多くいます。そして、生活している以上不平や不満はだれしもでてくることです。その不満を上手く改善できない限り、モラハラはだれもが加害者にも被害者にもなってしまう可能性がある身近なものだということがわかります。
3. モラハラを起こさない組織を作るために

モラハラは基準がないため判断も難しく、当事者で解決するよう促される場合もあります。
企業側は原因がどこにあるのかをしっかり調査把握し、その原因を少しでも取り除き、モラハラを起こさない体制を整えることが大切です。
モラハラを起こさないための組織にするために会社ができる対策としては、次のようなことが挙げられるでしょう。
- モラハラは犯罪であると認識してもらい、社内で罰則など規定を明記する
- モラハラの加害者や被害者になりやすい傾向のある人を把握する
- 定期的にアンケートや聞き取りを行いモラハラのような行為が起こっていないか確認を取る
- 面談等を行い、社員の不満などを聞く機会を設ける
- 医療関係者と連携したカウンセリングや相談できる窓口を用意しておく
- 研修を行い、モラハラの実態を把握してもらう
- 1人で抱え込んでしまう社員などがいなくなるよう良好な職場環境を作る
このように日頃から、こまめに取り入れることができる内容も多くあります。
モラハラの原因は不満が元になることが多いので、社員一人一人の意識を変えていくよう会社が呼びかけていくことも大切です。
未然に防ぐためにもできる対策はすぐに取りかかるとよいでしょう。
4.まとめ
モラハラは、どの企業でも発生する可能性があります。
嫌がらせの元となる不満を会社の対策で取り除けるものは解消し、モラハラを起こさない、起こさせない体制をとりましょう。
モラハラは被害者にも会社にもダメージが大きいものです。
社員一人ひとりが相手のことを思いやり、モラルを持った行動を心がけることで未然に防ぐことが可能です。
そのためにも会社側は、社員の人柄を把握し、社員の声に耳を傾け、モラハラの起こらない会社作りをしていくことが大切です。







