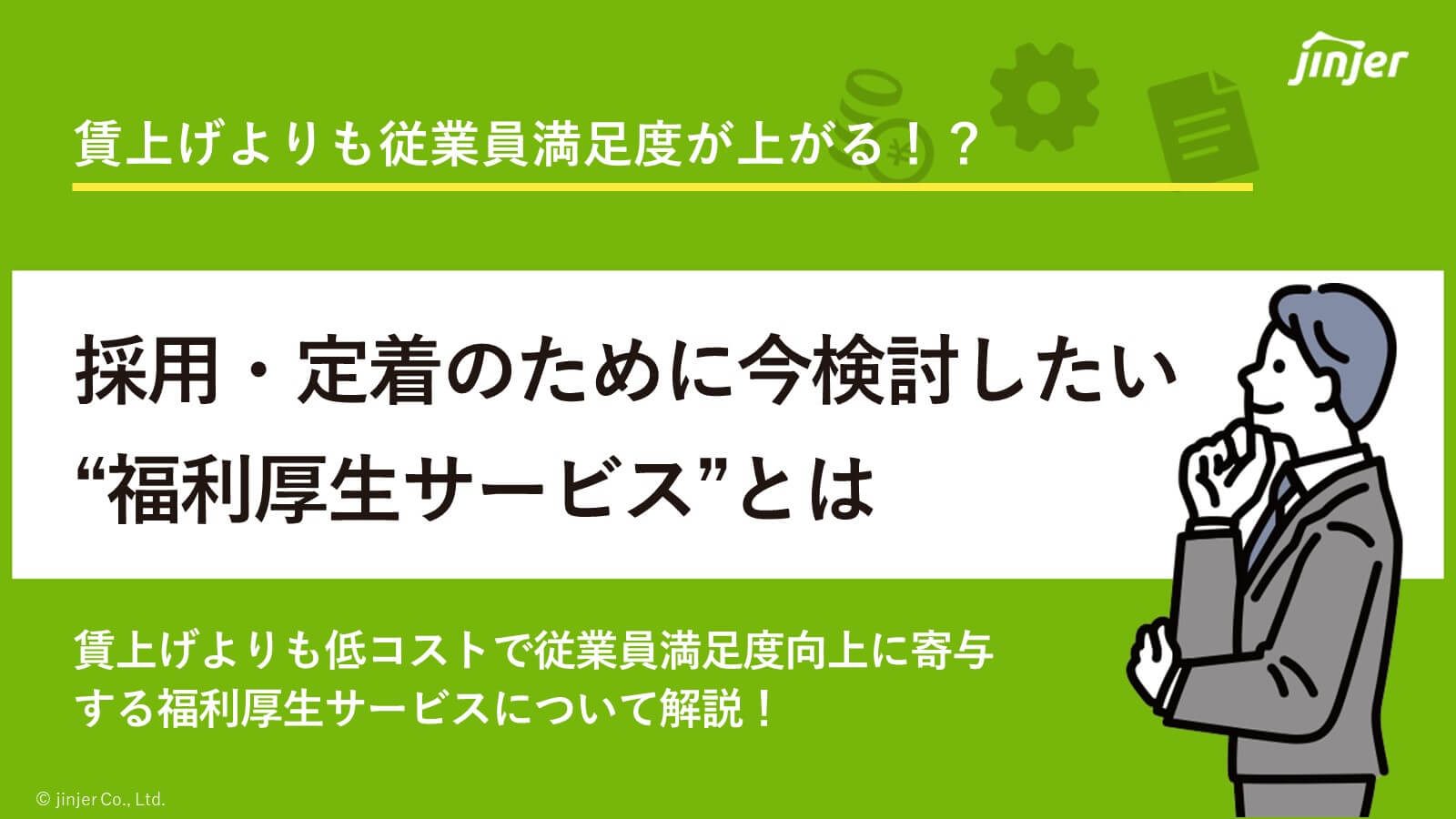「扶養手当はどのような手当で、どのような従業員へ支払われるのか知りたい」
「扶養手当を導入するメリット・デメリットについて知りたい」
上記のような疑問を抱く人も多いでしょう。扶養手当とは、扶養家族をもつ従業員に対して、会社が提供する手当の一つです。
本記事では、一般企業における扶養手当の概要や家族手当との違い、相場や支給条件、導入するメリット・デメリットを紹介しています。扶養手当の導入を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
目次
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 扶養手当とは

一般企業の扶養手当とは、法定外福利厚生の一つとして、会社から従業員へ給与のほかに提供される次のような手当のことです。
|
目的 |
扶養家族をもつ従業員への資金援助 |
|
対象者 |
扶養家族をもつ従業員 |
上記の扶養家族とは、経済的に自立した生活が難しいため、従業員から金銭的援助を受けて生活する親族を指します。具体的な対象者は、以下の通りです。
- 配偶者
- 子ども
- 親
扶養手当の支給によって従業員の生活をサポートすることで、定着率やエンゲージメントの向上を期待できます。
1-1. 扶養手当を支給する法律的な義務はない
扶養手当を含む法定外福利厚生には、法律による企業への導入義務はありません。それぞれの会社が、次のような事柄について、独自に判断して取り決めます。
- 導入の有無
- 導入数
- 内容
- 条件
- 金額
扶養手当を導入することで経営が苦しくならないよう、予算を確認したうえで導入することが大切です。
1-2. 扶養手当以外の代表的な法定外福利厚生
会社の法定外福利厚生において、扶養手当以外の代表的な手当やサービスは以下の通りです。
- 住宅手当
- 交通費
- 家族手当
- 健康診断の受診料
- 退職金
厚生労働省の令和2年就労条件総合調査によると、以下のような手当を導入している企業が多いことがわかりました。
|
手当の種類 |
割合 |
|
通勤など |
92.3% |
|
役付など |
86.9% |
|
扶養・家族・育児支援など |
68.6% |
|
技能・技術など |
50.8% |
|
住宅など |
47.2% |
参考:令和2年就労条件総合調査 結果の概要 2賃金制度|厚生労働省
2. 扶養手当と家族手当の違い

扶養手当と家族手当は、次のように対象者と支給対象が違います。
|
扶養手当 |
家族手当 |
|
|
対象者 |
扶養家族をもつ従業員 |
家族をもつ従業員 |
|
支給対象 |
従業員の扶養家族 |
従業員の家族 |
扶養手当では、企業の定めた条件を満たす、従業員の扶養に入っている親族のみが支給対象となります。たとえば、年収が103万円以下の配偶者や、年齢が18歳未満の子どものみが支給対象として認められるでしょう。
一方、家族手当では企業の定めた条件を満たす家族のすべてが支給対象となるため、扶養の有無は関係ありません。支給対象を子ども・配偶者のみに限定していたり、家族の人数に応じて支給を決めたりする会社もあります。
さらに扶養手当と同様に、支給対象の家族の収入や年齢について条件を定めている企業も多いです。
3. 扶養手当の金額相場

家族一人あたりの扶養手当の金額相場(月額)は、以下の通りです。
|
配偶者 |
10,000~15,000円 |
|
子ども |
3,000~5,000円 |
多くの企業において、一人目の子どもの支給額よりも、二人目以降の子どもの支給額を減らす傾向があります。
厚生労働省の令和2年就労条件総合調査の結果では、次のような手当における従業員一人・一月あたりの平均支給額は17,600円でした。
- 扶養
- 家族
- 育児支援
また、企業規模別の同調査の結果は以下の通りです。
|
企業規模 |
平均支給額(月額) |
|
1,000人以上 |
22,200円 |
|
300~999人 |
16,000円 |
|
100~299人 |
15,300円 |
|
30~99人 |
12,800円 |
上記の結果から、企業規模が大きくなるにつれて、平均支給額も増えていることがわかります。
参考:令和2年就労条件総合調査 結果の概要 2賃金制度|厚生労働省
4. 扶養手当の支給条件

前述の通り、扶養手当を導入する法律的な義務はなく、支給条件も企業が自由に決定できます。一般的な企業における扶養手当の支給条件は、次の通りです。
- 扶養家族がいること
- 扶養家族と同居していること
- 扶養家族との続柄が配偶者・子ども・親であること
- 配偶者の年収が条件の範囲内であること
- 家族の人数が条件の範囲内であること
扶養家族の条件として、「従業員が被保険者の社会保険において被扶養者となっていること」などと定めている会社も多く見られます。加えて、子どもの場合は18歳未満、親の場合は60歳以上など、年齢に条件を設けている企業も多いです。
支給条件は企業が自由に設定できますが、不公平感が生まれないように注意しましょう。
5. 扶養手当を導入する4つのメリット

扶養手当を導入するメリットは、次の通りです。
- 従業員の満足度の向上につながる
- 定着率の向上につながる
- 求職者から選ばれやすくなる
- 子育て・介護を支援する企業としてイメージがアップする
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
5-1. 従業員の満足度の向上を期待できる
扶養手当を導入するメリットの一つは、従業員満足度の向上につながることです。扶養手当により従業員の収入は増えるため、金銭的な負担が減ることにより、会社に対する満足度もアップするでしょう。
従業員の満足度が上向くと仕事に対するモチベーションも上がり、積極的に業務に取り組む結果、生産性の上昇が期待できます。
5-2. 定着率の向上につながる
定着率の向上につながることも、扶養手当を導入するメリットといえるでしょう。会社から扶養手当を提供されることにより、愛社精神が増したり、満足度がアップしたりするためです。
法定外福利厚生が充実している労働条件のよい会社で、長く働きたいと考える従業員は多いでしょう。結果、自己都合による退職が減るため、定着率も上がります。
5-3. 求職者から選ばれやすくなる
扶養手当を導入するメリットとして、求職者から選ばれやすくなることも挙げられます。求職者が同条件の企業を比べる際に、扶養手当を始めとする法定外福利厚生が充実している企業は魅力的に映るためです。
求職者から選ばれやすくなると、求人コストの減少も期待できるでしょう。
5-4. 子育て・介護を支援する企業としてイメージがアップする
扶養手当を導入すれば、子育てや介護を支援する企業としてイメージがアップするでしょう。支給条件にもよりますが、小さな子どもや高齢の親がいる人にとって、扶養手当は嬉しい存在です。
扶養手当を支給していることをアピールすれば、家族がいても働きやすい企業として、印象がよくなることを期待できます。
6. 扶養手当を導入する3つのデメリット
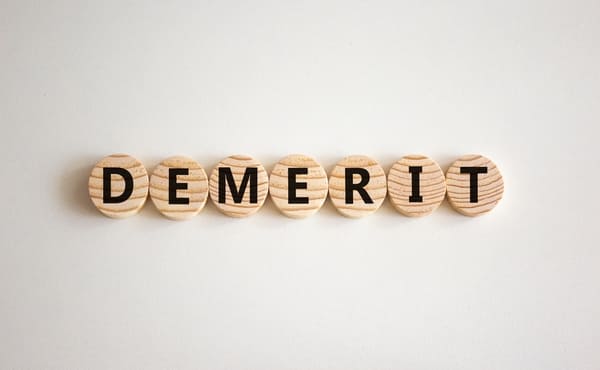
扶養手当を導入するデメリットは、次の通りです。
- 対象者以外のモチベーション低下につながる
- コストが増える
- 不正受給の発生リスクがある
各デメリットについて簡単に確認しておきましょう。
6-1. 対象者以外のモチベーション低下につながる
扶養手当を導入するデメリットの一つは、対象者以外のモチベーション低下につながることです。扶養家族をもたない従業員は支給対象外となるため、能力や成果とは関係のない支給条件について、不公平感を抱く従業員も少なくないでしょう。
支給対象外となる従業員のモチベーションが低下したり、愛社精神が減少したりする結果、離職につながる可能性もあります。
6-2. コストや手間が増える
扶養手当を導入するデメリットとして、コストや手間の増加も挙げられます。扶養手当は給与所得として扱うため、基本的に所得税や住民税の課税対象となるためです。
結果、給与計算の手間が増え、従業員と企業の双方において税金の負担が増えます。
6-3. 不正受給の発生リスクがある
不正受給の発生リスクがあることも、扶養手当を導入するデメリットの一つです。
従業員の申告内容のチェック方法や支給条件の設定が不十分な場合には、不正受給発生の可能性があります。たとえば、従業員の申告内容を厳しくチェックすることなく支給を決めると、条件を満たしていないケースもあるかもしれません。
申告内容のチェック方法や支給条件の細かな設定を検討する際には、不正受給が発生した場合の対策についても検討しておきましょう。
7. 扶養手当はなくなる?支給する企業は減少傾向にある

扶養手当を従業員へ支給する企業は、減少傾向にあります。背景には以下が挙げられるでしょう。
- 共働き世帯が増えた結果、扶養手当において配偶者を扶養する従業員が減少した
- 扶養する親族をもたない従業員との不公平感をなくすために、成果主義を重視する企業が増えた
家族手当も同様の傾向です。新たに設定したスキルや資格などの条件に基づき、廃止や見直しにより浮いた手当分を賃金に組み込む企業も多く見られます。
現在も家族をもつ従業員に何らかの手当を支給する企業は多いです。しかしながら扶養手当の導入前には、風潮や従業員のニーズなども調査しつつ、さまざまな制度と比較検討しましょう。
7-1. 国家公務員の扶養手当も廃止?
国家公務員の扶養手当についても見直しが進められています。人事院の給与勧告によると、配偶者に対する扶養手当は段階的に廃止されることになりました。共働き世帯が増加している状況に合わせ、2025年度から2026年度にかけて段階的に廃止されます。
一方で、子どもに対する扶養手当は増額されることになりました。このような社会の状況も踏まえたうえで、扶養手当を導入するかどうかを慎重に判断しましょう。
8. 扶養手当を廃止するときの注意点

扶養手当を導入した場合、簡単に廃止できるわけではありません。廃止するときは、以下のような点に注意しましょう。
8-1. 不利益変更になるため従業員の同意を得る必要がある
扶養手当の廃止は、労働条件の不利益変更に該当します。不利益変更とは、会社側の都合で、従業員にとってマイナスとなるような変更をおこなうことです。
不利益変更は会社が一方的に実施することはできず、従業員の同意を得なければなりません。従業員の代表者や労働組合と交渉をおこない、同意を得るようにしましょう。納得してもらえるよう、変更の理由や必要性を丁寧に説明することが重要です。
8-2. 基本給のアップなどを検討する
扶養手当を廃止する代わりに、基本給のアップなどを検討することも大切です。扶養手当を廃止すると、従業員の負担が増えてしまいます。
基本給をアップするなどの緩和措置を検討すれば、制度の廃止に納得してもらいやすいでしょう。また、全従業員が公平に恩恵を得られるような緩和措置であれば、より納得感が高まります。
9. 扶養手当のメリット・デメリットを把握して導入を検討しよう!

今回は、扶養手当の意味や導入するメリット・デメリットなどを紹介しました。扶養手当は、法定外福利厚生のひとつであるため、導入していなくても罰則を受けることはありません。また、支給条件や支給対象者なども企業が自由に決定できます。扶養手当を導入することで、家族のいる従業員の生活をサポートでき、定着率やエンゲージメントの向上につながるでしょう。
ただし、扶養手当を導入するには手間とコストがかかります。長期的に運用していく必要があるため、予算をしっかりと確認したうえで導入を決定しましょう。また、事前に従業員のニーズを確認することも大切です。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。