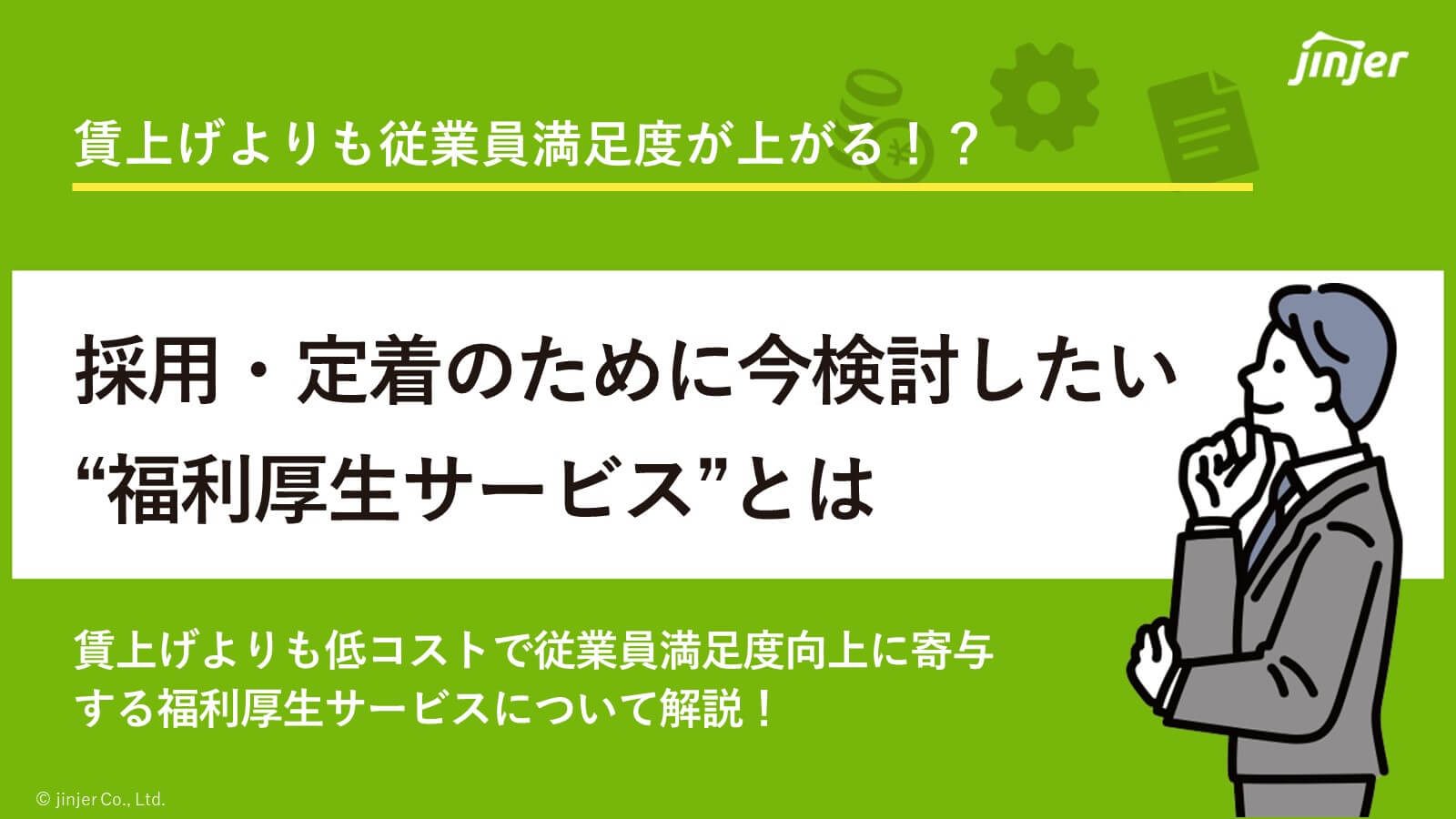「インフレ手当とは?」
「インフレ手当を支給すべき?」
「インフレ手当はいくら支給すればいいの?」
昨今の物価上昇や円安に応じて、従業員にインフレ手当の支給を検討している企業は多いのではないでしょうか。しかし、実際にインフレ手当を支給している企業は多くありません。
インフレ手当を支給することで、従業員のモチベーションが向上したり離職防止につながったりと、メリットは多くあります。一方で、体制をしっかり整えたうえで支給しなければ、従業員の不満の原因になりかねないため、慎重に判断しなければいけません。
本記事ではインフレ手当が注目されている理由や支給方法について解説します。支給するメリットや注意点も紹介するので、経営者や人事担当者はぜひ参考にしてください。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. インフレ手当とは

インフレ手当とは、物価の高騰に伴い、企業が従業員に支給する特別手当のことです。従業員の「生活支援」を目的として支給します。
そもそもインフレ(インフレーション)とは、物価が継続的に上昇し、お金の価値が下がっていく状態のことです。インフレが続くと家計が圧迫され、従業員の生活が苦しくなる可能性が考えられるでしょう。
従業員の負担を軽減するために、インフレ手当への取り組みに注目が集まっています。なお、「インフレ手当」は法令で定められた言葉ではありません。企業によって「インフレ特別手当」や「物価上昇手当」など、名称は異なります。
また、インフレ手当を導入することは企業の義務ではありません。導入するかどうか、どのような基準で支給するかなど、手当の仕組みは企業が自由に決定できます。
2. インフレ手当が注目されている理由

インフレ手当が注目されている理由は「物価の高騰」です。インフレが発生する原因はさまざまですが、近年世界中でインフレが発生しています。
世界規模でインフレが発生している主な原因は以下の通りです。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大
- ロシアのウクライナ侵略
まず、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、需要と供給が不安定になりインフレが発生しました。経済活動が再開し、需要が拡大したことで原価が上昇傾向にあります。
追随するように、ロシアのウクライナ侵略によって小麦や原油の価格が上昇しました。この影響を受け、食料をはじめとするさまざまな分野で国際的に物価が高騰したのです。
日本は、物価高騰に賃金の伸びが追いついていないといえます。実質、賃金が減少しているといっても過言ではありません。円安によって国内では輸入品の値上げも増えました。不安を感じている従業員の生活を支援するため、インフレ手当の支給を検討する企業が増えたといえるでしょう。
2-1. インフレ手当を支給している企業の割合
帝国データバンクが1,248社を対象におこなったアンケートでは、次のような結果が出ています。
|
インフレ手当の有無 |
パーセンテージ |
|
インフレ手当を支給した |
6.6% |
|
支給を予定している |
5.7% |
|
支給を検討中 |
14.1% |
|
支給の予定はない |
63.7% |
|
わからない |
9.9% |
全体の4社に1社が、インフレ手当に前向きに取り組んでいることがわかります。
参考:インフレ手当に関する企業の実態アンケート|帝国データバンク
2-2. インフレ手当の平均支給額
インフレ手当の支給額は、企業によって大きく異なります。インフレ手当を一時金として支給した企業については、金額の内訳は以下の通りです。
|
金額 |
パーセンテージ |
|
1万円~3万円未満 |
27.9% |
|
3万円~5万円未満 |
21.9% |
|
5万円~10万円未満 |
21.9% |
|
10万円~15万円未満 |
9.1% |
|
15万円以上 |
7.3% |
平均支給額は約5万3,700円という結果でした。
一方で、月額手当として支給した企業については、金額の内訳は以下の通りです。
|
金額 |
パーセンテージ |
|
3,000円未満 |
26.9% |
|
3,000円~5,000円未満 |
30.3% |
|
5,000円~1万円未満 |
30.3% |
|
1万円~3万円未満 |
11.8% |
|
3万円以上 |
0.8% |
平均支給額は約6,500円という結果でした。平均支給額を参考にしながら、自社の状況に応じて金額を決定しましょう。
参考:インフレ手当に関する企業の実態アンケート|帝国データバンク
3. インフレ手当の支給方法

インフレ手当の支給方法は以下の3種類に分けられます。
- 一時金
- 月額手当
- 賞与
それぞれの違いやメリット・デメリットを詳しく解説します。
3-1. 一時金
まず、「一時金」として給与にプラスして支給する方法があります。一時金で支給するメリットとデメリットは以下の通りです。
|
メリット |
デメリット |
|
・通常の給与や賞与とあわせて事務処理をおこなえるため事務の負担が増えない ・継続して支給する義務がない |
・短期的に支出が増加してキャッシュフローの悪化になる場合がある ・従業員が賞与と混同しやすいため企業の誠意を感じてもらいにくい |
現状では、インフレ手当を支給している多くの企業が一時金での支給を選んでいます。「インフレが収束したとき元に戻しやすい」「見通しの立たないコストを増やすほどの余裕がない」などの理由が挙げられるでしょう。
3-2. 月額手当
インフレ手当を「月額手当」として毎月の給与にプラスして支給する方法です。基本的に、特別手当としてではなく、ベースアップとして対応します。
インフレ手当を月額手当で支給するメリットとデメリットは以下の通りです。
|
メリット |
デメリット |
|
・まとまった金額を支払うことがないためキャッシュフロー面で負担になりにくい ・従業員が企業の配慮を感じやすい |
・事務負担が増え手間がかかる (例:就業規則を改定、労働基準監督署への書類提出、所得税や雇用保険料の再計算など) |
月額手当として支給する場合は、将来的に基本給に組み込まれることを視野に入れて金額設定をするとよいでしょう。
3-3. 賞与
インフレ手当を「賞与」のような形で支給する方法です。賞与として支給するメリット・デメリットは以下の通りです。
|
メリット |
デメリット |
|
・継続して支給する必要がない ・就業規則の改定が必要ない |
・従業員に企業の誠意を感じてもらいにくい ・賞与規定がない場合は就業規則の改訂が必要となる |
以上のように、さまざまな方法でインフレ手当を支給できるため、企業の状況に合わせて適切な方法を選びましょう。
4. インフレ手当を支給する3つのメリット

インフレ手当を支給するメリットは以下の通りです。
- 従業員のエンゲージメントの向上
- 離職率の軽減
- 企業のイメージアップ
4-1. 従業員のエンゲージメントの向上
インフレ手当を支給することで従業員のエンゲージメントが向上します。物価の上昇が継続すると、収入に不安を覚える従業員が増えてくるでしょう。
インフレ手当を支給することで、収入面での不安を軽減でき、仕事に対するモチベーションが高くなる効果が期待できます。従業員のエンゲージメントが向上することで、より良いパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。
企業が「従業員を守る」姿勢を見せ、実際に支援することで、従業員の企業に対する愛着や貢献意欲も高められます。
4-2. 離職率の軽減
インフレ手当を支給することで離職率の軽減につながります。人材の定着は、多くの企業にとって課題となっているでしょう。
従業員に自社にとどまってもらうためには、待遇面などで他社との差別化が重要です。インフレ手当を支給している企業は少ないため、従業員に対して大きなアピールポイントになる可能性があります。
4-3. 企業のイメージアップ
インフレ手当を支給することで「従業員を大切にしている企業」との印象がつき、企業のイメージアップにつながります。社内だけではなく、取引先や投資先などの社外にも好意的に受け止めてもらえるでしょう。
また、求職者に対しても好印象を与えられるため、人材が集まりやすくなり、採用においても有利になる可能性があります。
5. インフレ手当を支給した企業事例

インフレ手当を支給した企業の事例を紹介します。
- 一時金としてインフレ手当を支給
- 月額手当としてインフレ手当を支給
以下、詳しく解説しますので、インフレ手当を支給するときの参考にしてください。
5-1. 一時金としてインフレ手当を支給
2022年、某ソフトウェア開発の企業は、直接雇用契約を結ぶ従業員を対象にインフレ手当を支給しました。
インフレ手当の支給額は、多様な働き方に伴って手当額の比率を検討し、以下の4段階に設定したようです。
|
就業時間 |
インフレ手当支給額 |
|
128時間超/月 (1日8時間で週4日超勤務) |
15万円 |
|
96時間超128時間以下/月 (1日8時間で週3日超勤務) |
12万円 |
|
64時間超96時間以下/月 (1日8時間で週2日超勤務) |
9万円 |
|
64時間以下/月 (1日8時間で週2日以下勤務) |
6万円 |
この企業は、前年度の給与決定時の給与相場から急激なインフレが起きたため、インフレ手当の支給を決定しました。今後、継続的にインフレ手当を支給する予定はないようです。
それでも従業員から感謝の声が多く、企業全体が業務に集中して取り組める結果になったといいます。
5-2. インフレ手当を月額手当として支給
2022年、某Web制作会社は、雇用形態を問わずグループの全従業員に1カ月あたり一律で1万円を支給しました。
急激な円安と物価の上昇を、インフレ手当支給の理由としています。この企業は、社員が安心・安全に働ける環境づくりに取り組むことで、信頼性の高い情報を広く社会に提供し、豊かな生活の実現と企業の発展に貢献しています。
インフレ手当の終了期間は設定せずに運用していくようです。
6. インフレ手当を支給する際の4つの注意点

インフレ手当を支給する際の注意点は以下の通りです。
- 社会保険料や税金の負担額が増す
- 支給方法によって就業規則を変更しなければいけない
- 同一労働同一賃金の原則に注意する
- しっかりと資金計画を立てる
それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。
6-1. 社会保険料や税金の負担額が増す
インフレ手当を支給する際は、社会保険料や税金の負担額が増すことに注意しましょう。
従業員に支給するインフレ手当は、基本的に「給与所得」として扱われます。つまり、所得税などが課税対象になるので注意しなければいけません。
また、社会保険料の負担額などが変更になるケースもあります。支給額にもよりますが、事務手続きの負担が増えるといえるでしょう。そのため、福利厚生で受けられるサービスを充実させるなど、現金支給以外でインフレ手当を導入している企業もあります。
6-2. 就業規則の変更や月額変更届の手続きが必要になるケースがある
月額手当でインフレ手当を支給する場合、給与改定とみなされるため、場合によっては就業規則の変更や月額変更届の手続きが必要になります。ただし一時金で支給する場合は、必要ないケースがほとんどです。
就業規則を変更した場合は、労働基準監督署長に届出なければいけません。月額手当でインフレ手当を支給する場合は、一時金で支給する場合と比較すると手間がかかります。
1度支給したインフレ手当を取り止めることは、従業員の不満につながりかねません。インフレ手当を支給する際は、自社の基準を明確にして慎重におこないましょう。
6-3. 同一労働同一賃金の原則に注意する
インフレ手当を支給するときは、同一労働同一賃金の原則に配慮しましょう。同一労働同一賃金とは、同じ労働をしているなら、雇用形態に関わらず同じ待遇にするという考え方です。インフレ手当についても、雇用形態による不合理な差をなくし、公平な対応となるよう心がけましょう。
6-4. しっかりと資金計画を立てる
インフレ手当を支給する前に、資金計画をしっかりと立てなければなりません。とくに月額手当として支給する場合、長期的に費用が発生するため、企業側の負担が大きくなってしまいます。途中で支給が難しくなる可能性もあるため、長期的な視点に立って検討することが大切です。
7. インフレ手当によって従業員の生活をサポートしよう!

今回は、インフレ手当の意味や必要性、支給する方法などを紹介しました。インフレ手当を導入することは、企業の義務ではありませんが、インフレ手当を支給することで従業員の生活をサポートできます。その結果、従業員のモチベーションが向上したり、企業への愛着が増したりするでしょう。
また、インフレ手当を支給する方法としては、一時金・月額手当・賞与などが挙げられます。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、支給の目的や企業の予算に合わせて最適な方法を選びましょう。ただし、インフレ手当を支給するときは、同一労働同一賃金の原則に配慮することや、長期的な資金計画を立てることなどに注意が必要です。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。