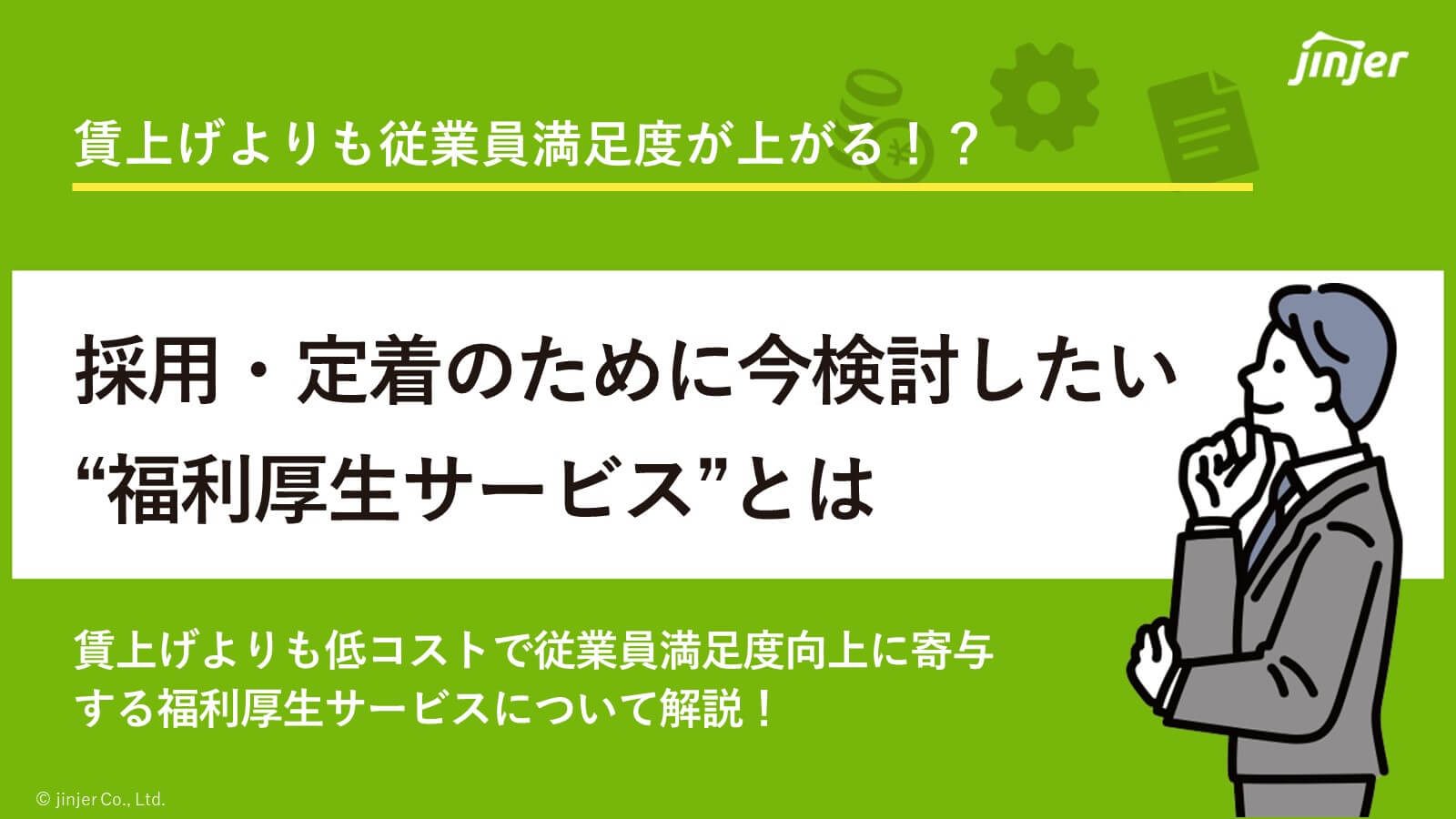「インセンティブ制度の設計方法がわからない」「インセンティブの種類が知りたい」という人も多いでしょう。
インセンティブ制度とは、従業員の働きを評価して報酬を付与する仕組みです。従業員のモチベーションを高め、組織の生産性を向上させるために効果的といわれています。
本記事ではインセンティブ制度の種類や設計方法、具体的な事例などを紹介します。制度のメリット・デメリットや、設計時のポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. インセンティブ制度とは?

インセンティブ制度とは、従業員の成果やスキルに応じて報酬を支給する仕組みのことです。インセンティブ制度をうまく活用すれば、従業員のモチベーションや満足度を高められます。
インセンティブ制度における報酬は、金銭的なものだけではありません。昇進や表彰などを与えることも可能であるため、事業内容や目標に合わせて最適な制度を設計しましょう。
1-1. インセンティブとボーナスの違い
ボーナスとは、会社の業績や目標の達成度合いに応じて、臨時的に支給する賃金のことです。役職や勤続年数によって金額が異なるケースもありますが、全従業員を対象として支給することが多いでしょう。
一方のインセンティブは、個人の成果やスキルに応じて支給するため、全従業員が対象となるわけではありません。それぞれ異なる制度であるため、違いをしっかりと理解しておきましょう。
2. インセンティブ制度を設計する際の5つのステップ

インセンティブ制度を設計する際には、次の5ステップで進めましょう。
- 報酬制度を導入する目的を設定する
- 社内でニーズ・リスクを調査する
- 報酬システムの内容を決める
- 社内に周知して運用する
- 定期的に見直しをおこなう
それぞれのステップにおけるポイントを、以下にて説明します。
2-1. 報酬制度を導入する目的を設定する
報酬制度の内容を考える前に、なぜインセンティブが必要で、何のために導入するのか明確にしましょう。目的を明確にすると、どのような施策を導入するのかの判断基準がブレにくくなるためです。
たとえば営業成績の向上が目的ならば、成績に応じた歩合給が効果的でしょう。従業員のモチベーションアップが目的の場合は、従業員同士で感謝の気持ちを送りあうピアボーナス制度が考えられます。
インセンティブ導入の理由を従業員に説明しやすくするためにも、事前に目的をしっかり議論しておきましょう。
2-2. 社内でニーズ・リスクを調査する
次に、社内でのインセンティブに対するニーズを調査しましょう。従業員が魅力を感じる制度を設計することで、モチベーション向上につながるためです。
同時に、制度を取り入れることで問題が生じることはないか、リスクについても調査しておく必要があります。
調査の際には、従業員満足度調査などを用いた定量的なデータに加え、直接ヒアリングするなど定性的な情報も考慮しましょう。
2-3. 報酬システムの内容を決める
従業員へのヒアリングが終了したら、実際の報酬システムの内容を決めます。具体的には、次のような内容を検討しましょう。
|
項目 |
内容 |
|
対象者 |
全従業員対象か、年次や職位、性別などによる違いはあるか |
|
条件 |
付与されるタイミングはどのような条件を満たした場合か |
|
運用方法 |
報酬はいつ支払うのか、社内表彰を実施する場合、どの時期に実施するのか |
|
計算方法 |
金銭的な報酬の場合、具体的にどのような計算式で付与額を計算するのか |
一例として成績に対応した金銭的インセンティブを付与する場合、目標額を上回った割合を加算する方式があります。たとえば通常の給与が20万円の従業員が目標額を15%上回った場合、報酬は20万円×0.15(15%)で3万円です。従業員の誰が見ても不公平感を感じない、わかりやすい制度設計を心がけましょう。
2-4. 社内に周知して運用する
インセンティブ制度を運用する際には、目的や制度の内容をしっかりと社内に周知しましょう。従業員に周知されていないと、制度が利用されなかったり、間違って利用されて問題を引き起こしたりする可能性があるためです。
具体的には、社内の掲示板やイントラなど、すべての従業員の目にとまる場所に掲示する必要があります。制度の仕組みや内容を詳しく理解してもらいたい場合には、説明会を開くことも検討しましょう。
2-5. 定期的に見直しをおこなう
インセンティブ制度を導入したら、定期的に見直しをおこなうことが重要です。インセンティブ制度を導入したのに、従業員のモチベーションや成果が上がっていなければ意味がありません。
支給条件や運用方法に問題がある可能性もあるため、従業員の意見を聞きながら制度を改善していきましょう。とくに従業員から不満の声が出ている場合は、早急な対応が必要です。
3. 制度を設計する際に押さえておくべきインセンティブの5つの種類

インセンティブの主な種類としては、次の5つが挙げられます。
- お金やモノ|物質的インセンティブ
- 昇進や表彰|評価的インセンティブ
- 夢や達成感|自己実現的インセンティブ
- 人間関係|人的インセンティブ
- 価値観の共有|理念的インセンティブ
導入する目的に応じて、適切な種類のインセンティブを選択しましょう。
3-1. お金やモノ|物質的インセンティブ
物質的インセンティブとは、経済的な報酬を与える方式です。真っ先にイメージされる種類のインセンティブといえるでしょう。成果を上げたこと、会社に貢献したことが従業員にもわかりやすく、モチベーションが上がりやすいといわれています。
具体的には、昇給や賞与を付与したり、特別休暇を与えたり、社員旅行を実施したりするなどの施策が挙げられるでしょう。社内ポイントを付与して、商品やサービスと交換する制度も考えられます。
3-2. 昇進や表彰|評価的インセンティブ
従業員の働きをさまざま方法で評価することで、承認欲求を満たすインセンティブです。従業員が会社への帰属感を得やすいため、離職率の低下につながりやすいでしょう。
具体的には業績に応じて昇進・昇格させる、大勢の従業員の前で表彰するなどが挙げられます。上司が日常的に部下を褒めることも評価的インセンティブであり、費用をかけずに実行しやすい施策です。
3-3. 夢や達成感|自己実現的インセンティブ
従業員の夢、やりたいことを実現させることで、モチベーション向上につなげるインセンティブです。内発的動機にもとづいているため、物質的な報酬よりもモチベーションが持続しやすいとされています。
たとえば、従業員が希望する部署へ異動や、仕事がしやすくなる権限を付与するなどの施策が具体例です。評価的・理念的インセンティブと組み合わせて実施することも考えましょう。
3-4. 人間関係|人的インセンティブ
上司や同僚など、一緒に働く従業員の人間関係によってモチベーションを維持するインセンティブです。従業員の組織への愛着が強まり、離職しにくくなる、会社に貢献するようになるなどの効果が見込めます。
人間関係の強まりは抽象的なものであり、制度化は難しいでしょう。しかし人事・労務部門、会社のトップが人的インセンティブを活用する意識を持って働きかけることが重要です。
3-5. 価値観の共有|理念的インセンティブ
企業理念や経営者の価値観を示し、従業員に共感してもらうことでモチベーションを高めるインセンティブです。仕事にやりがいや社会貢献性を求める人材には効果的とされています。
人的インセンティブと同じく抽象的なため、社内制度として設計することは困難です。しかし、自分の仕事がどのように役に立っているのか、従業員に実感してもらうために、事業の意義や理念などを積極的に発信しましょう。
4. インセンティブ制度の導入に成功した企業の具体例3選

次に、インセンティブ制度の導入に成功した企業の具体例を3つ紹介します。
- A社|従業員のパフォーマンスが把握できる社内通貨を導入
- B社|感謝の気持ちを伝え合うピアボーナスを導入
- C社|人の評価を気にする必要のない「サイコロ給」
それぞれの制度が重視しているポイントをおさえて、ぜひ自社の施策を考えるうえでの参考にしてください。
4-1. A社|従業員のパフォーマンスが把握できる社内通貨を導入
シリコンウェハー加工装置・ツールを製造するA社では、従業員の働きを管理する社内通貨を導入しています。
従業員は社内通貨によって、業務のパフォーマンスや売り上げへの貢献度を客観的に把握可能です。貯まった通貨は賞与に反映されたり、仕事や働き方を選べるオークションで利用したりできます。
社内通貨は物質的インセンティブでありながら、従業員が自己実現を果たす手段としても効果的な施策です。施策の結果、同社は「働きがいのある会社」ランキングでも16年連続で選出されています。
4-2. B社|感謝の気持ちを伝え合うピアボーナスを導入
B社は、従業員同士が感謝の気持ちに添えて一定の金額を送り合えるチップ制度が整備されています。
もともと同社には感謝を伝えるためのサンクスカードがありましたが、日々発生するさりげない感謝を伝えるための施策としてチップを導入しました。社内コミュニケーションツールを活用して、リアルタイムで感謝が表明できる仕組みになっています。
2020年にはメッセージ数が100万を突破し、流通したポイントは3,000万にのぼっています。具体的に制度化しにくい人的インセンティブを、物質的インセンティブと組み合わせてうまく制度化した事例といえるでしょう。
4-3. C社|人の評価を気にする必要のない「サイコロ給」
Web広告事業やゲームアプリ開発などを手がけるC社では、従業員の給与の一部をサイコロで決める給与制度を導入しています。
具体的には「月給に(サイコロの目)%をかけた金額」が給与に上乗せされて支給されるシステムです。この制度には、人の評価にとらわれずに楽しく働いてほしいという企業の思いが込められています。
サイコロ給は、会社や経営陣の理念を物質的インセンティブの形でうまく制度化した事例といえるでしょう。同社は給与制度のほかにも、独創的な社内制度・行事で企業理念を反映しています。
5. インセンティブ制度の5つのメリット

インセンティブ制度のメリットとしては、次の5つが挙げられます。
- 短期間でのモチベーション向上につながる
- 優秀な人材を確保できる
- 競争によって従業員や企業が成長する
- 人件費をコントロールしやすい
- 企業の理念を浸透させられる
以下において、それぞれのメリットを解説します。
5-1. 短期間でのモチベーション向上につながる
インセンティブは、短期間における従業員のモチベーション向上につながります。目標達成に応じた物質的な報酬が設定されていると、仕事を頑張る直接的な動機付けになるためです。
金銭的な報酬でなく評価的インセンティブであっても、大勢の前で賞賛される経験は従業員の自信になります。会社への愛着が芽生えることで、離職率を下げることにもつながるでしょう。
5-2. 優秀な人材を確保できる
インセンティブ制度を整えることで、優秀な人材が確保しやすくなることもメリットといえます。自分の働きを正当に評価してもらい、見合った報酬をもらいたい人には魅力的な制度であるためです。
仕事でいくら成果を上げても、ほかの従業員と給与が変わらないと不満を覚える人は多いでしょう。
インセンティブを設定すると、従業員の働きを公平に評価することにつながります。人材獲得だけでなく、定着率の向上も期待できるでしょう。
5-3. 競争によって従業員や企業が成長する
適切なインセンティブを設定することは、従業員個人や企業の成長につながるメリットもあります。働きが給与に反映されることで、健全な競争が生まれるきっかけになるためです。
報酬をもらうためには、ほかの従業員よりもよい成績をあげなくてはなりません。結果として「もっと成長したい」と業務改善に取り組むようになります。
従業員一人ひとりの生産性が向上すれば会社全体の生産性も高まり、ひいては組織の成長につながるでしょう。
5-4. 人件費をコントロールしやすい
インセンティブ制度のメリットとして、人件費がコントロールしやすくなることも挙げられます。固定給と異なり、インセンティブは変動可能な給与であるためです。
固定給は一度上げると下げにくく、業績が下降した際に負担となります。インセンティブで給与を変動させることで、時期によっては人件費を削減可能です。
もちろん固定給が少ないために、従業員の生活が不安定になっては元も子もありません。生活を保証できる給与が支給されるよう、設計時には入念にシミュレーションしておきましょう。
5-5. 企業の理念を浸透させられる
企業の理念を浸透させられることもインセンティブ制度のメリットです。企業の目標やビジョンに関連したインセンティブを設定しておけば、企業が従業員に求めていることが明確になります。
たとえば、新規サービスのアイデアを提案したときに表彰する、新規顧客を獲得したときに報酬を支給するなど、企業の目標を反映した制度設計にするとよいでしょう。
6. インセンティブ制度の5つのデメリット

インセンティブ制度には、次のようなデメリットがあることにも注意しましょう。
- 長期的な目線が持ちにくくなる
- 安定志向の人材が集まりにくくなる
- 従業員同士の人間関係が悪化する可能性がある
- 制度に関係ない業務が疎かになる
- 仕事にやりがいを感じられなくなる
以下にて、それぞれのデメリットについて解説します。
6-1. 長期的な目線が持ちにくくなる
従業員がインセンティブを意識しすぎると、長期的な目線が持ちにくくなることがデメリットといえます。目先の目標を重要視し、先につながる取り組みが実行に移されにくくなるためです。
企業が安定的に成長してゆくためには、長い目での事業計画が欠かせません。制度を設計する際には、従業員に長期的なビジョンを意識させることも重視しましょう。
6-2. 安定志向の人材が集まりにくくなる
インセンティブ制度は、安定志向の人材が集まりにくくなることもデメリットといえます。収入が大きく変わると、計画的な人生設計が難しく感じられるためです。
たとえば家庭を持っている従業員の場合、住宅ローンの返済や養育費の捻出などを考えなくてはなりません。インセンティブをネガティブに感じる従業員がいないか、事前に社内で調査しておきましょう。
6-3. 従業員同士の人間関係が悪化する可能性がある
適切な評価制度を設定しないと、競争によって従業員同士の人間関係が悪化する可能性があることもデメリットです。
他人に負けたくない、抜きん出たい思いが強すぎると個人主義が広がりかねません。結果的にノウハウが共有されなかったり、従業員が協力しなかったりと、悪い影響を及ぼします。
このため人的・理念的インセンティブなども活用して、会社のビジョンを実現するために協力しあう体制を作りましょう。
6-4. 制度に関係ない業務が疎かになる
インセンティブ制度に関係ない業務が疎かになることもデメリットのひとつです。インセンティブを獲得したいと考え、評価とは無関係の業務を適当にこなす従業員も出てくるかもしれません。
事業を継続していくためには、評価に直結しないような細かい作業もしっかりとこなす必要があります。インセンティブ制度を導入する場合は、すべての作業がうまく進むような設計にすることが重要です。
6-5. 仕事にやりがいを感じられなくなる
インセンティブ制度を導入することで、仕事にやりがいを感じられなくなる可能性もあります。報酬を受け取ることや、表彰されること自体が目的となってしまうからです。
本来はやりがいを感じながら仕事をしていた従業員も、インセンティブが目的となってしまい、熱意を失ってしまうかもしれません。やりがいの喪失につながりやすい物質的インセンティブだけではなく、評価的インセンティブや人的インセンティブを組み合わせるとよいでしょう。
7. インセンティブ制度を設計する際の4つのポイント

インセンティブ制度を設計する際のポイントは次の4つです。
- 物質的・評価的インセンティブに偏らないようにする
- 結果だけでなくプロセスも評価する
- 現実的で公平な評価基準を設ける
- 段階的な基準を設ける
これらのポイントについて、以下にて解説します。
7-1. 物質的・評価的インセンティブに偏らないようにする
制度を設計する際には、物質的・評価的な報酬に偏らないようにしましょう。従業員の内発的な動機づけが育たないためです。
金銭や他者評価などによって得られる外発的動機づけは、短期的な成果は期待できます。しかし収入がよくても会社の理念に共感できない、やりがいを感じられないと人材は定着しません。
自己実現的・人的報酬なども意識して、従業員がやりたいことにのびのびとチャレンジできる制度や環境を整備しましょう。
7-2. 結果だけでなくプロセスも評価する
インセンティブの付与条件を検討する際には、結果だけでなくプロセスも評価できるようにしましょう。数字では業務の成果がわかりにくく、インセンティブが受け取れない人が出てくるためです。
たとえば、人事部や経理部、総務部などは、業務の性質的に前年度比以上の成績を出すことは容易ではありません。開発部門でも、短期間では成果が上がりにくい長期のプロジェクトに携わる人はたくさんいます。
インセンティブによって全社的にモチベーションを向上させるためには、各部門にあった評価基準を用意することがかかせません。
7-3. 現実的で達成可能な評価基準を設ける
報酬制度を設計するうえでは、現実的な評価基準を設けることもポイントとして挙げられます。設定する目標が高すぎても低すぎても、従業員のモチベーション向上につながらないためです。
たとえば目標が低すぎる場合、従業員は目標以上の働きをしなくなります。逆に目標が高すぎて達成不可能な場合、インセンティブを追わなくなって生産性の向上につながりません。
会社が期待する働きと従業員のレベルを擦り合わせ、適切な評価基準を設定しましょう。
7-4. 段階的な基準を設ける
インセンティブ制度を導入するときは、段階的な基準を設けることも大切です。インセンティブを獲得するまでのハードルが高すぎると、従業員のモチベーションが低下してしまう可能性もあります。
スモールステップのようなイメージで、小さな目標を達成するごとにインセンティブを支給するような方法にすれば、誰もが挑戦しやすくなり、組織全体のモチベーションが向上するでしょう。
8. 効果的なインセンティブ制度を設計して組織の成長につなげよう

本記事では、インセンティブの種類や制度の設計方法、具体的な企業の成功事例などを紹介しました。インセンティブ制度をうまく活用することで、従業員のモチベーションや定着率を高めることが可能です。
インセンティブ制度を設計するうえでは、導入の目的を設定したうえで、事前にニーズやリスクを調査することが欠かせません。システムの内容を決めたら、すべての従業員に確実に周知したうえで運用することも重要です。
内容を決める際には、インセンティブの種類を理解し、物質・評価だけに偏らない評価基準を設けましょう。本記事で解説しているメリット・デメリットを理解し、自社に合った制度を設計してください。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。