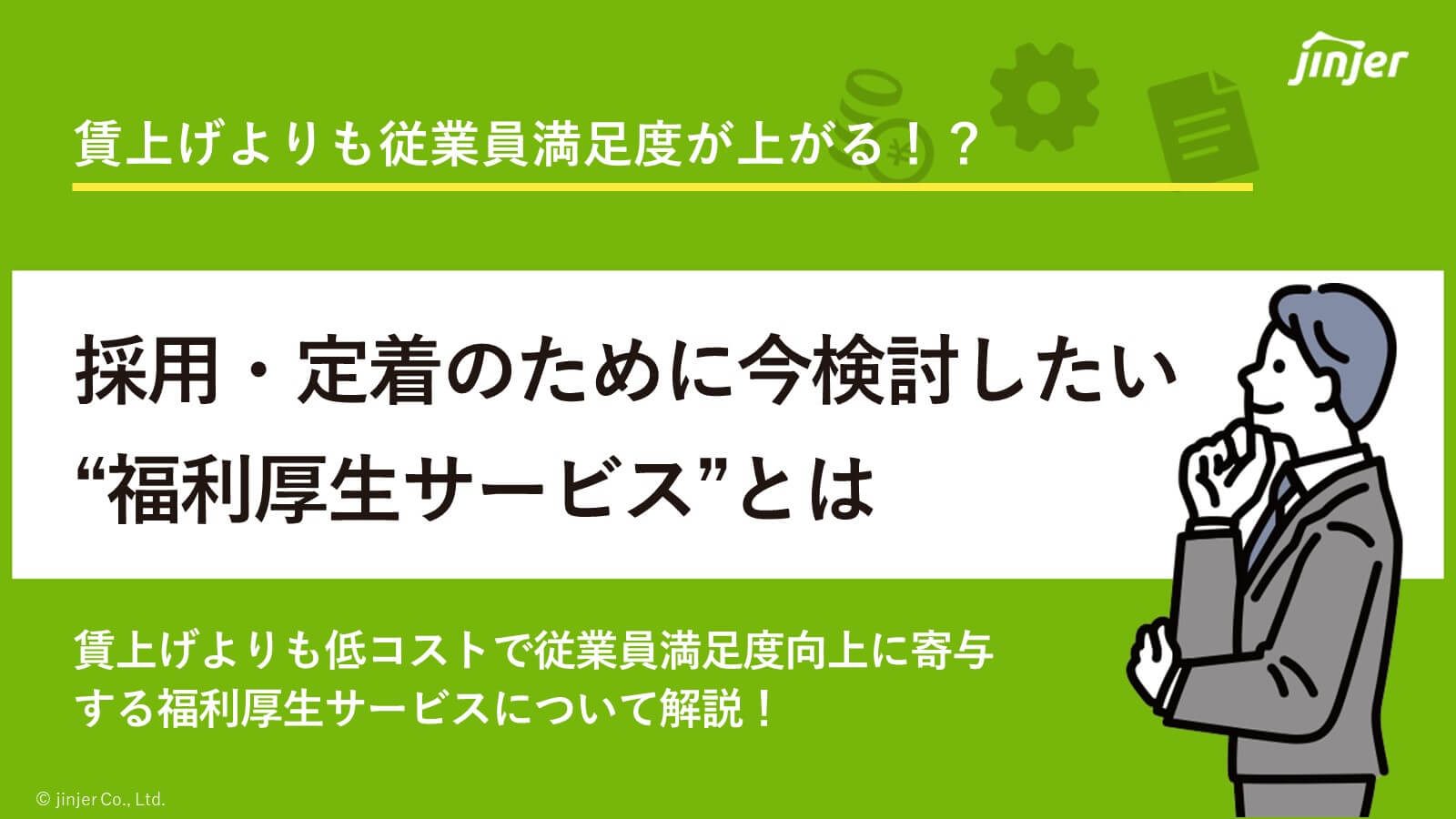「会社からの結婚祝いは福利厚生にできるのか?」
「具体的な内容や導入方法は?」
上記の疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
企業が瞬間を祝う方法として、結婚祝い金や結婚休暇を福利厚生として提供することが増えてきています。しかし、導入する際、どのような内容を盛り込むべきか、また導入の方法や注意点について悩む企業も多いでしょう。
本記事では、会社からの結婚祝いを福利厚生として導入する方法やメリット・デメリットを紹介します。結婚祝いを福利厚生として取り入れたいと考えている方は、ぜひご一読ください。
目次
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 会社からの結婚祝いは福利厚生にできる

会社からの結婚祝いを福利厚生にすることは可能です。具体的には下記の福利厚生が該当します。
- 結婚休暇
- 結婚祝い金
それぞれ詳しく紹介します。
1-1. 結婚休暇
結婚休暇とは、社員が結婚を機に新生活を開始するための準備期間や、新婚旅行に充てるために利用できる休暇制度です。
この休暇は法定外休暇(特別休暇)に分類され、法律で義務づけられているものではありません。そのため、下記の点を企業ごとに自由に設定できます。
- 結婚休暇を取り入れるか
- 何日間取得可能にするか
- 有給にするか無給にするか
結婚休暇の導入は、従業員にとって大きなメリットとなるでしょう。特に、人生の大切な節目である結婚を支える制度は、社員のやる気向上や会社への帰属意識を高める効果が期待できます。
すべての社員が安心して利用できるよう、周知を徹底し、取得しやすい環境を整えることが企業の信頼向上につながるでしょう。
1-2. 結婚祝い金
結婚祝い金は、従業員が結婚した際に会社から支給されるお祝い金の一種です。多くの場合、従業員本人に支給されますが、企業によっては従業員の家族、例えば従業員の子どもが結婚した場合にも支給されることがあります。
結婚祝い金に関しても、法的な義務ではなく、企業ごとに導入するかどうかを自由に決定可能です。結婚祝い金の額は、企業ごとに異なります。全員に一律の金額を支給する場合や、勤続年数や役職に応じて支給額を変えるなど、さまざまです。
2. 結婚祝い金の相場と結婚休暇の日数

結婚祝い金の相場と結婚休暇の日数は下記のとおりです。
|
結婚祝い金の相場 |
2〜3万円 |
|
結婚休暇の日数 |
5日 |
結婚祝い金の相場は、全従業員に一律で支給する場合、2〜3万円程度が一般的です。勤続年数に応じて金額を変動させる企業では、最大5万円程度まで支給するケースもみられます。
また、従業員本人ではなく、その子どもが結婚した場合に支給される金額は1万円程度が相場です。
結婚休暇の日数は、従業員自身が結婚する際に5日程度を特別休暇として付与する企業が多い傾向があります。雇用形態によって取得可能な日数を調整する企業もあるでしょう。
例えば、正社員には5日間、契約社員やパート・アルバイトには2〜3日間付与するなど、柔軟な運用がおこなわれることもあります。
3. 会社からの結婚祝いを福利厚生にするメリット

会社からの結婚祝いを福利厚生にするメリットは、主に下記の4つです。
- 従業員の意欲向上につながる
- 採用活動にプラスの影響を与える
- 助成金を受け取れる可能性がある
- 節税効果を得られる場合がある
それぞれ詳しく解説します。
3-1. 従業員の意欲向上につながる
福利厚生が整備されていると、従業員の満足度が向上し、結果として仕事への意欲が高まるでしょう。
結婚を迎える従業員は、結婚式や新婚旅行などで多くの時間や費用が必要です。会社から結婚休暇が提供されると、休暇の取得に伴う負担が軽減され、安心して人生の節目を迎えられます。
このような環境は従業員の定着率向上につながり、結果的に職場全体の生産性にも良い影響を与えるでしょう。
一方で、結婚休暇がない場合は、有給休暇を消化するしか選択肢がなく、従業員にストレスを与える可能性があります。こうした点を考慮すると、結婚休暇の導入は従業員の負担軽減に大きくかかわってくるでしょう。
3-2. 採用活動にプラスの影響を与える
結婚休暇や結婚祝い金を福利厚生として導入すると、採用活動にプラスの影響を与えます。
結婚休暇や結婚祝い金は法定外福利厚生に分類され、企業に義務づけられているものではありません。しかし、制度が整っている企業は「従業員を大切にする会社」と評価されやすく、求職者にとって魅力となります。
福利厚生の内容は、求職者が企業を選ぶ際に非常に重要な判断基準の一つです。人生の一大イベントを支援する制度が整っていると、働きやすく配慮の行き届いた企業である印象を与えられます。
その結果、他社との差別化を図りやすくなり、優秀な人材の採用にもつながるでしょう。
3-3. 助成金を受け取れる可能性がある
結婚休暇や結婚祝い金を導入すると、企業は助成金を受け取れる場合があります。働き方改革が注目される中、中小企業が特別休暇制度を整備することを奨励する制度が設けられているのです。
結婚休暇の導入は、「働き方改革推進支援助成金」を受給できる可能性があるでしょう。労働環境の改善や柔軟な働き方の実現を目指す企業を支援するものです。
結婚休暇などの制度を通じて従業員の生活を支援する企業には大きな助けとなります。福利厚生にかかる費用を軽減できるため、企業にとって経済的なメリットも大きいでしょう。
参考:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|厚生労働省
3-4. 節税効果を得られる場合がある
福利厚生費は税制上、非課税の対象となるため、企業にとって節税効果をもたらす点が魅力です。結婚祝い金を支給する際、従業員福利に関する費用として扱える場合があります。従業員をサポートしつつ、企業の経費負担が軽減可能です。
ただし、相場を大幅に超えるような高額な結婚祝い金を支給した場合、従業員福利に関する費用として認められない可能性もあるでしょう。課税対象となる経費として扱われるため、結果的に節税効果が失われることになります。
適切な金額での支給が前提となりますが、ルールを守った運用を行えば福利厚生費として計上し、節税が実現できます。
4. 会社からの結婚祝いを福利厚生にするデメリット
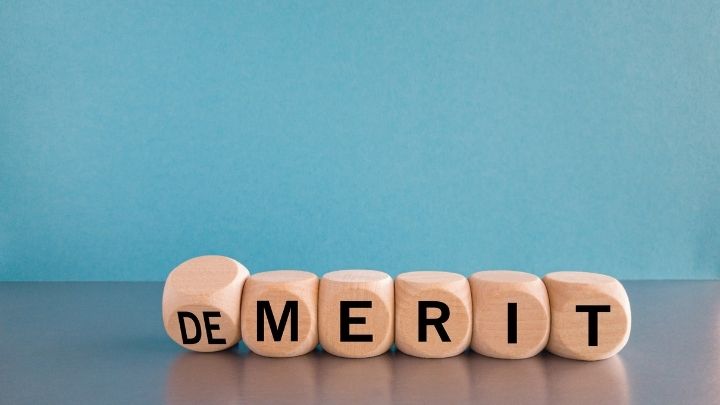
会社からの結婚祝いを福利厚生にするデメリットは下記のとおりです。
- 結婚休暇の取得による人手不足
- 担当者の業務増加
会社からの結婚祝いを福利厚生にするデメリットとして、結婚休暇の取得による人手不足のリスクが挙げられます。休暇を利用した社員の業務をほかのメンバーがカバーする必要があるため、一時的に業務負担が増加するでしょう。
また、結婚祝い金の支給や休暇申請に伴う事務手続きも課題です。申請書の確認や承認作業など、福利厚生制度を管理する担当者の業務が増加します。
手続きが滞ると従業員や担当者双方にストレスが生じるでしょう。デメリットを軽減するためには、事前の準備が重要です。
制度導入に伴う問題点を事前に理解し、適切に対処することで、運用上のトラブルを回避できます。
5. 会社からの結婚祝いを福利厚生にする方法

会社からの結婚祝いを福利厚生にする方法を下記の2つ紹介します。
- 結婚休暇を導入する方法
- 結婚祝い金を導入する方法
それぞれ詳しくみていきましょう。
5-1 結婚休暇を導入する方法
結婚休暇を導入する方法は、下記のとおりです。
- 有給・無給を選択する
- 再婚を対象にするかを決定する
- 取得日数や条件を設定する
- 申請方法と期限を決定する
- 就業規則に反映して全社員へ周知する
結婚休暇を有給にすると従業員のやる気が向上し、会社への満足度も高まる傾向があります。一方で、無給の場合はコストを抑えられるものの、取得率が低下する可能性があるでしょう。
再婚を対象とすると公平性を保てますが、制度の濫用を防ぐために一定の基準を設けることも重要です。
結婚休暇の日数は一般的に5〜7日程度が多く、企業の規模や業務量に応じて適切な期間を設定しましょう。
結婚休暇を取得するための手続きがスムーズにおこなわれるよう、申請方法や期限を明確にしておくことも大切です。
5-2. 結婚祝い金を導入する方法
結婚祝い金を導入する方法は下記のとおりです。
- 支給対象者・条件の設定
- 相場を参考に金額を設定する
- 就業規則の作成と周知
結婚祝い金は、正社員だけでなく、契約社員やパートタイム、アルバイトにも支給するのか明確にしましょう。企業の規模や方針によって範囲を設定することが重要です。
結婚祝い金の金額を決定する際、相場を参考にすると、会社の予算に見合った額を設定できます。就業規則には、支給対象者、支給額、申請手続きなどを具体的に記載し、従業員が誤解なく利用できるようにしましょう。
6. 会社からの結婚祝いとして福利厚生を導入しよう

結婚祝い金や結婚休暇を福利厚生に取り入れることは、従業員のやる気を高めるための有効な手段です。
制度を整備することで、従業員に対する思いやりや支援の姿勢を示せるため、企業の魅力向上にもつながります。
導入にあたっては、支給対象者や条件、金額設定、申請方法などを決定し、社内の理解を得るために周知を徹底することが重要です。
従業員が制度を適切に利用できるよう、透明性のある運用が求められます。
結婚祝いを福利厚生にすれば、企業と従業員との信頼関係を深め、長期的な企業成長も期待できるでしょう。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。