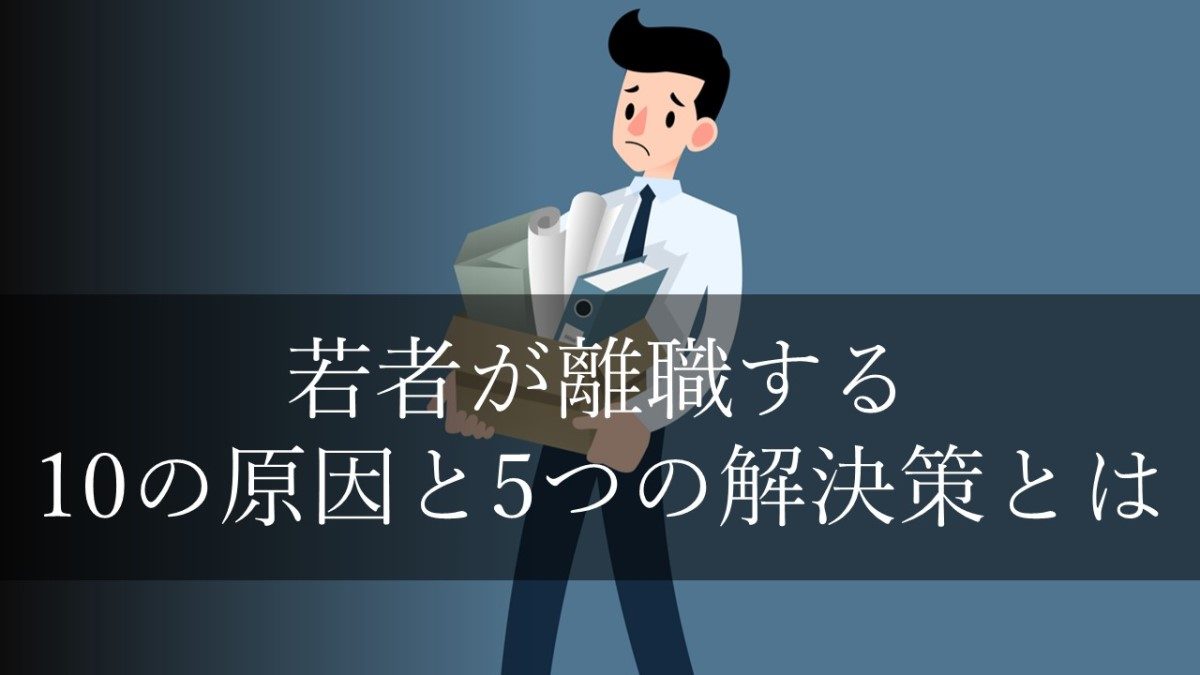
就職活動という厳しい戦いの中で勝ち取った内定。
将来への期待に胸を膨らませて入社したにもかかわらず、新入社員の3人に1人は3年以内に離職しているのが現状です。なぜ若者たちは、そんなに早く仕事に見切りをつけて離職してしまうのでしょうか?
早期離職者が出ると、会社としては大きな痛手となってしまいます。本記事では、「若者が早期離職する原因」と「早期離職を減らすための方法」についてご紹介します。
目次
1. 離職率とは

離職率とは、ある時点で仕事に就いていた労働者に対して、一定期間のうちに仕事を辞めた人の比率を示す数値です。
離職率が極端に高ければ、労働者がその仕事に定着しにくく、入れ替わっていくことが常態化していることを意味します。
反対に、低ければ労働者がその仕事に定着し、転職や産業間の労働力移動がおこなわれにくくなっていることがわかります。
1-1. 厚生労働省による離職率の定義と計算方法
厚生労働省による離職率の定義は「常用労働者数に対する離職者の割合」です。1月1日時点の常用労働者数と離職者の数を用いて、以下の計算式によって求めます。
|
離職率=離職者数÷1月1日時点の常用労働者数×100% |
常用労働者の定義は、「期間を定めずに、または1カ月を超える期間を定めて雇われている者」あるいは、「日々または1カ月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前2カ月にそれぞれ18日以上雇われている者」です。
上記の計算式に基づき、1月1日時点の常用労働者数が1,000人で離職した人が8名だった場合の離職率を求めると0.8%となります。
一般的に、離職率は期初から期末までの1年で計算するのが一般的です。しかし、入社後3年、5年などの期間で求めることもあり、離職率の算出期間は目的によって異なります。
1-2. 離職率が高いことで生じるデメリット
離職率が高い企業は「ブラック企業」と揶揄されることがありますが、離職率が高いことは企業にとって多くのデメリットをもたらします。
採用コストが無駄になる
企業は、将来利益を生んでくれることを見越して、人材の採用に多大な費用をかけています。最近は採用代行サービスも増えており、人材採用にかかる費用も見えやすくなりました。
早期離職されると、採用活動にかけたお金と採用担当者の工数が無駄になってしまいます。また、入社予定者1人当たりの平均採用費は約45.0万円となっています。
また、将来の戦力と見込んでいた人が離職するとなると、再度採用活動をおこなわなければなりません。そこでもまた、追加の採用活動費用が余分に必要となってしまいます。
参考:新卒採用の予算について|HUMAN CAPITAL サポネット
教育コストが無駄になる
新入社員たちが会社の利益に貢献してくれると信じて、業務工数を割きながら教育したにもかかわらず、早期離職されると、教育にかけたお金と上司の時間が無駄になってしまいます。
新入社員の教育は、入社後の研修だけでなく、実際の配属後もOJTの形をとっている企業は多いのではないでしょうか。
OJT期間の生産性は大幅に下がってしまうので、せっかく新入社員に費やした工数が無駄になってしまうのは、企業としてもなんとか避けたいところです。
新たな人材確保が難しい
早期離職者が出て人材不足になった場合は、新たに人材を採用しなければなりません。しかし、今は売り手市場であり、求職者が仕事や企業を選べる時代なので、早々に新たな人材を確保できるとは限りません。
2. 離職率の平均と業界別の傾向

自社の離職率が高いか低いか、気になる人も少なくないでしょう。ここからは、日本企業の離職率について具体的な数値を示しながら解説します。
2-1. 日本企業における離職率の平均
令和以降、日本企業における離職率の平均は以下のように推移しています。
| 年度 | 離職率 |
| 令和元年 | 15.6% |
| 令和2年 | 14.2% |
| 令和3年 | 13.9% |
| 令和4年 | 15.0% |
参照:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」
この離職率は、年度開始時に常用労働者となっていた人が、年度内に退職した割合です。
令和以前の離職率も14~16%程度の範囲内で推移しています。
2-2. 大卒の3年以内の離職率は約30%
日本では特に「新卒」の早期離職に悩む企業が多い傾向にあります。
早期離職率は毎年の入社総数に対して、1年間で入社3年以内に離職した人の割合を表します。
若者の離職率の高さは、厚生労働省が発表している「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者の状況)」にて確認することができます。
高卒と大卒に分類されており、大卒であっても約30%の人が早期離職していることがわかります。なお、()内は前年比の増減を示すものです。
|
[ 事業所規模 ] |
【大学】 |
【高校】 |
|
1,000 人以上 |
26.1% (+0.8P) |
26.6% (+0.2P) |
|
500 ~999人 |
30.7% (+1.1P) |
31.8% (+1.7P) |
|
100 ~499人 |
32.9% (+1.1P) |
36.7% (+1.6P) |
|
30 ~99人 |
40.6% (+1.2P) |
43.6% (+0.2P) |
|
5~29人 |
49.6% (+0.8P) |
51.3% (▲0.4P) |
|
5人未満 |
51.4% (+1.8P) |
60.7% (+0.2P) |
表:新規学卒就職者の事業所規模別就職後3年以内離職率
2-3. 【業界別】離職率ランキングが高いのは?ワーストはサービス業?
業種別に見ると、サービス業に属する企業の離職率が高くなっており、特に「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連サービス業・娯楽業」「教育・学習支援業」に関しては40%以上と非常に高い離職率となっています。
|
■ 大学 |
■ 高校 |
||
|
宿泊業・飲食サービス業 |
51.4% (+1.7P) |
宿泊業・飲食サービス業 |
62.6% (+2.0P) |
|
生活関連サービス業・娯楽業 |
48.0% (+0.6P) |
生活関連サービス業・娯楽業 |
57.0% (▲0.2P) |
|
教育・学習支援業 |
46.0% (+.05P) |
小売業 |
48.3% (+0.7P) |
|
医療、福祉 |
38.8% (+0.2P) |
教育・学習支援業 |
48.1% (▲5.4P) |
|
小売業 |
38.5% (+2.4P) |
医療、福祉 |
46.4% (+1.2P) |
表:新規学卒就職者の産業別就職後3年以内離職率のうち離職率の高い上位5産業
企業規模が大きくなればなるほど離職率が下がる傾向がありますが、これは、福利厚生や給与面での不満が少なくないことが理由として考えられます。
3. 離職率が高い企業に共通する10の要因

企業にとって若者の早期離職は、デメリットだけではなく、メリットもあることがわかりました。
それでも将来のことを考えると、デメリットの方がはるかに大きいといえます。若者の早期離職を防ぐためには、企業として、離職に至った理由や原因をしっかりと把握するようにしましょう。
①給与に不満がある
「もっと給与が良いと思っていた」「辛い思いをして働いた割に、給与があまり良くない」という若者の声は少なくありません。最初の数年はほとんどが勉強期間なので、給与がもらえるだけでありがたいという考えはもう通用しないと考えましょう。
給与の比較は同世代で会話のネタにあがりやすく、就業状態はさておき、給与が負けていると働く意欲を失う若者が多いのも事実です。給与が適正か、定期的に見直して改善することが大切です。
②仕事上のストレスが大きい
新入社員の中には、これまでとは異なる環境で「社会人」として給与をもらいながら働くことで、ストレスを抱える若者が多くいます。何事にも納期がある中で、プレッシャーを感じたり、納期が遅れると怒られたりすることがストレスの原因となるでしょう。
また、大学ではトップクラスだった新入社員も、会社に入るとその道のスペシャリストには勝てないことも多々あるので、それがストレスと感じてしまう人も多くいます。
③会社の将来性・安定性に期待が持てない
就職活動時に企業の情報を十分に集めることなく就職先を決める新入社員もいます。
仮に情報収集を十分にしている社員を採用したとしても、実際に働いてみるまでは、現場の雰囲気や経営方針など詳しい部分を理解することはできないでしょう。
新入社員が、特定部署でしばらく働いただけで会社の将来を不安に思うのは、いささか早すぎるとは思いますが、最近の若者は会社の将来性を不安視しているかもしれません。
④労働時間が長い
入社して実際に配属されるまでは、労働時間の長さを意識することはほとんどありません。新入社員の中には、思っていたより労働時間が長く、自分のプライベートな時間を優先できないことに不満を感じる人もいます。
給与が増えるわけでもなく、ただ労働時間が長くなるという働き方ではモチベーションを維持するのが難しいかもしれません。
⑤求められるノルマ・成果が厳しい
入社して間もない頃は、求められるノルマが厳しいと、ストレスを感じてしまう新入社員もいるかもしれません。
学生時代の研究や論文とは異なる厳しさがあるので、気持ちが折れてしまうと、仕事のやる気が低下してしまう新入社員もいます。
⑥仕事が面白くない
「入社したときは、目をキラキラさせて頑張ろうと思っていたけど、実際に働いてみると全然面白くない」という声も少なくありません。最近の若者は、仕事に面白さを求める人が多く、面白くなかった場合に、そのことを理由に早期離職をしてしまうケースもあります。
⑦職場の人間関係が上手くいっていない
若者に限らず、人間関係が上手くいっていない職場環境で仕事を継続するのは難しいでしょう。何かあった時に相談できる上司がいなければ若手社員が孤立してしまうので、精神的に参ってしまう可能性があります。
⑧キャリアアップするため
「部署に配属され、まわりの状況をみると、キャリアが長いのにまだ平社員という人が多い」ということでは、自分の将来に不安を感じても不思議ではありません。新入社員は自分をそういった先輩に重ね、昇進の希望がなくなり、自分のキャリアビジョンを見つめ直すこともあります。
たかが3年、されど3年。仕事に見切りをつけてキャリアアップを目指してポジティブな離職をする若者は今後より増えていくと考えられます。
⑨会社の経営者や経営理念・社風があわない
会社の経営者や経営理念・社風が自分の性格に合う、合わないは必ずあります。合わなくても、合わせてみようと思えるほど、会社に対して強い愛着心がなければそのまま退職してしまうかもしれません。
⑩相談できる上司・同僚がいない
人間関係とも重なりますが、相談できる上司や同僚がいないと、辛い日々を送ることになります。特に入社したばかりの時はできないことの方が多く、上司への相談はかかせません。
コミュニケーションがとれず、孤立してしまうと会社に居場所がなくなり、出勤することがどんどん辛くなっていきます。新入社員の心のケアは、離職率を下げる上で大きなポイントと言えるでしょう。
4. 離職率を下げる5つの方法

ここでは、離職率、特に早期退職率を減らす方法についてご紹介していきます。
①社内のコミュニケーションを活発にする
人間関係や職場の雰囲気、先輩や上司に相談できずに退職する人が多いため、意見をいいやすい職場の雰囲気をつくることが大切です。何をいっても聞き入れられない雰囲気や、相談しにくい雰囲気を作っていると、新入社員から何も相談を受けないまま、ある日突然の「退職」となってしまいます。
またノルマが厳しい場合も、新入社員から手を挙げるのはなかなか難しいかもしれません。先輩や上司が話しやすい雰囲気をつくったり、常に新入社員を気にかけたりするなどの配慮が必要です。
新入社員にも同じチームの一員であることを認識させるためにも、社内におけるコミュニケーションが活発におこなえる環境づくりをしましょう。
②採用段階でのミスマッチをなくす
給与が少ない、労働時間が長いことが原因で早期離職する人も少なくありません。しかし、これらの早期離職は、就職セミナーや選考の段階で、就業条件についてしっかりと説明をおこなうことで防止することができます。
面接ではいいにくいことも多いと思いますが、そこはあえて隠そうとせず、相互理解を深めるよう心がけましょう。
③やりがいを見出させる
入社直後は新人研修など、学ぶことがほとんどで、なかなか会社の利益のために働いているという感覚を得られない新入社員が多くいます。そうなると、新入社員は何を目標に頑張ればいいかがわからなくなります。
そこで、小さいことからでも構わないので、達成できそうな目標を設定させるなど工夫しましょう。目標の大小はあっても、みんなで同じように目標に向かって仕事をすることで、仲間意識が高まります。
④会社施設を有効利用する
他部署の人とも交流できる機会を作りましょう。職場での人間関係がうまくいくと、仕事もどんどん楽しくなっていきます。
会社施設を使ってスポーツをするなど仕事以外での交流が、若者の心をひきつけたり、仕事のモチベーションを向上させることにもつながるかもしれません。
⑤褒める
上司に褒められて嫌な気持ちになる人はいません。小さいことでもしっかり褒めるようにしましょう。
文章が読みやすい、理解が速い、気遣いができるなどなんでもかまいません。いつも先輩社員の顔色をうかがって働いている新入社員たちにも、気持ちよく働いてもらう工夫が大切です。
5. 離職率が高い・低いの基準は?離職率の正しい見方
自社の離職率が高いか低いか、気になる企業は少なくありません。しかし、そもそも離職率には基準や絶対値は存在しないのです。というのも、離職率は対象の母体や算出期間、求める目的などによって大きな違いが出てしまうためです。
そのため、先ほど紹介した厚生労働省の離職率の平均も、あくまで参考に過ぎません。平均よりも離職率が低いから大丈夫と安易に考えるのは危険です。
例えば、離職率が低くても、管理職やプロジェクトの中心となる人材が会社に対する不満を理由に退職する場合は注意しましょう。これは、企業が必要とする優秀な人材が会社から離脱していることを示すものであり、このような状況が続けば企業の成長や存続が危ぶまれます。
離職率を下げることだけに注力することにはリスクがあることを覚えておきましょう。
6. 離職率を参考に、自社の待遇や従業員の働き方を見直そう!
3人に1人は入社してから3年以内に離職しています。早期離職は企業にとってデメリットが多いため、企業としては早期離職を減らすための施策が必要です。
おそらく最も重要なのは新入社員との「コミュニケーション」です。相談されるのを待つばかりではなく、自ら聞きに行くなどして、上司はなるべく新入社員に寄り添い、新入社員ものびのびとリラックスして働ける職場の雰囲気をつくりましょう。
離職率は低いに越したことはありませんが、低いからといって安堵しているのは危険です。離職を検討する従業員が出ないよう、待遇の見直しや職場・働き方の改善を進めていきましょう。
今回は若者の定着率が低い原因をご紹介しましたが、アルバイトの定着率が悪い原因について知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。







