
働き方改革がさけばれる今日、従業員の満足度を向上させるためにEX(Employee Experience/従業員体験)という考え方が注目を集めています。
FORRESTER社は、来年度はより多くの企業がEXに注目するだろうと予測しており、EXは今後さらに重要な概念となるのではないでしょうか。
本記事では、EXに関する取り組みが進んでいる海外の事例やケースを参考に、きたる2019年に向けておさえておくべきEXという概念について解説します。
関連記事:従業員満足度とは?役立つシステム紹介や取り組み事例をご紹介
目次
EX(Employee Experience)とは何か?
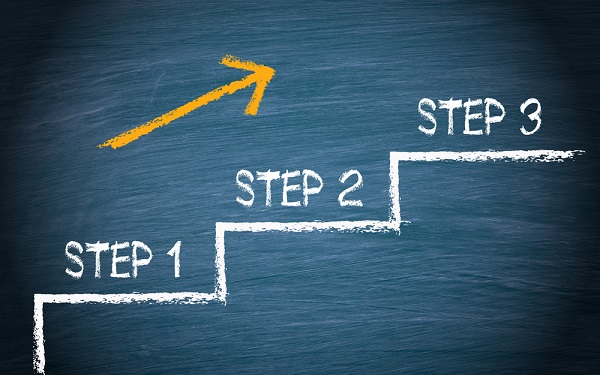
そもそもEX(Employee Experience)とは何のことなのでしょうか。ここでは、EXとはどういう概念なのか紹介します。
EX(Employee Experience)は企業成長に欠かせない
EX(Employee Experience)は日本では「従業員体験」と訳されます。従業員が働くことで得られる、あらゆる体験のことを指します。
これは、働くことで得られるスキルや経験のみならず、福利厚生や報酬制度など、組織内のさまざまな要素から構成されています。
EXを向上させている企業は、S&P500(アメリカの代表的な株価指数)が122%も向上したというデータ(※1)もあり、企業の収益増加を図るためにはEXの向上は必要不可欠になっているといえるでしょう。
(※1)EMPLOYEE EXPERIENCE REIMAGINED|accenture strategy
「顧客体験」と同様に「従業員体験」も考えるべきである
EXという概念がある一方、顧客満足度をはかるための概念としてUXやCXという言葉があります。
UXはUser experience、CXはCustomer experienceの略であり、双方とも「顧客体験」を意味する用語です。顧客がその商品やサービスを通じてどのような体験をすることができるのかを示す概念です。
そして基本的には、EXはUXやCXと同様の文脈で使われています。主語を顧客から自社の従業員に変えただけのものです。
基本的にこのEXには、「自社の従業員に働きやすい環境を整備できない企業が、より多くのお客様に満足していただく商品やサービスを作ることができるはずがない」という考え方(※2)が根底にあります。
モノやサービスや飽和する今日、他社と自社の商品の差別化を図って収益を増大させるために、まず自社の働く環境を見直している企業も増えてきています。
よりよい商品やサービスを提供するためには、まずEXを見直す必要があるのではないでしょうか。
(※2)CX and EX: Improve your Customer Experience by Listening to Your Employee Experience|Linkedin
EXが注目を集めている3つの背景

ではそもそもなぜ、EX(Employee Experience)が注目を集めているのでしょうか。ここではEXが注目を集めている背景を解説します。
1.雇用の流動化
「ひとつの企業に勤めあげる」という旧来の働き方が崩壊しつつある今日、多くの社会人は新たなスキルの獲得に向けて、転職を視野に入れながら日々の仕事をこなしています。
実際、転職する人の割合も増加しており、近年の雇用はかなり流動的になっています。ただ一方で、企業側からすると自社から他社へ転職してほしくないという気持ちもあるでしょう。
そういったなかで、EXに注目し働きやすい環境を整備することが、自社に従業員をとどめておくための必要条件であると認識され始めています。
2.人材不足
サービス業や運送業を筆頭に人材不足がますます進む今日、企業側にとっては一人でも多くの従業員が少しでも長く自社で働いてほしいと同時に、新たな従業員を獲得する必要があるでしょう。
リクルートキャリア社の「第32回転職世論調査」によると、転職の際に福利厚生や転職先の雰囲気を重視する転職者は多くの割合を占めており、転職者の多くは働く環境が良いのか悪いのか、という点に注目しています。
したがってEXを向上させることで、離職率の低下につながるとともに、この人手不足の労働市場でも、より多くの転職者を囲い込むことができる可能性をはらんでいる点で注目を集めているのでしょう。
3.働き方改革/生産性向上
働き方改革が叫ばれる今日、多くの企業が生産性を向上させる必要に迫られています。
従業員一人ひとりの生産性を向上させるためには、それぞれの従業員が生き生きと働くことができる環境を整備する必要があるでしょう。
全従業員が各々の個性を発揮し、組織に貢献したいと思ってもらうためには、EXの向上に注目してみるのもひとつの手であるのではないでしょうか。
EXとウェルビーイング

ウェルビーイング(well-being)とは、心と体だけでなく社会的にも健康な状態のことです。ウェルビーイングが整っていれば、社会のなかで充足した生活を送ることができます。
企業ができるウェルビーイングの種類はさまざまです。労働法を遵守し適切な労働時間を定めることや潤沢な福利厚生を提供することは、ウェルビーイングの向上につながります。また、ストレスチェックを通じて従業員の心身の状態を把握することも大切なポイントです。
近年では、新たなEXやウェルビーイングを重視する企業が増加傾向にあります。ポジティブなEXやウェルビーイングを提供することで、従業員のモチベーションやパフォーマンスはアップしやすくなります。
EXとワークエンゲージメント
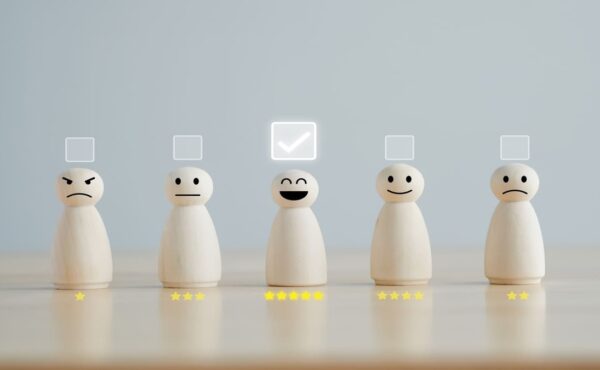
EXにはワークエンゲージメントが高まりやすいという良さがあります。
ワークエンゲージメントとは、従業員が仕事に対して熱心に取り組める心理状態を示す概念です。従業員が仕事から活力を得て熱意・やりがいを感じたり、仕事に没頭したりすることで、ワークエンゲージメントは高まっていきます。
EXは従業員のワークエンゲージメントに大きな影響を及ぼします。EXが充分でない場合、従業員のワークエンゲージメントも比例するように低下します。すると、生産性が下がったり人材の流出が起こったりといったリスクが高まってしまいます。
従業員が組織のなかで体験するあらゆる経験がワークエンゲージメントにつながるという点を意識し、適切な施策を打ち出すことが大切です。
EXを向上させるための6つの原則

EXを向上させるためには、おさえておくべきポイントがあります。
ここでは、インディアナ大学のJosh Plaskoffが提唱する(※3)、EX向上のための6つの原則を参考にしながら紹介します。
(※3)「Employee experience: the new human resource management approach」|Josh Plaskoff
1|従業員のことを深く理解する
Josh氏はまず従業員のことを深く理解することから始めるべきだといいます。
近年、従業員満足度調査やアンケートをおこなって、従業員の不満や不平をくみ取ろうとしている企業は多くありますが、それだけでは相手のことを表面的にしか理解できません。
相手のことを真に理解し組織や企業のビジョン、ミッションに共感して一緒に走ってくれるようにするには、対話や面談を通して相手のこと自体を理解することが必要であるようです。
2|視野を広く持って、全体を捉えながら考える
EXとは、そもそも従業員が経験するものすべてを捉えて考えるべきであるとJosh氏はいいます。
つまり、仕事上の業務やコミュニケーションに関してはもちろん、仕事外の家族関係やこれまでの生い立ちなど、一見プライベートな内容で敬遠されがちなものも含めて従業員一人ひとりを理解する必要があります。
EX向上を図って組織の課題を解決するためには、組織全体を俯瞰的に捉えるデザイン思考で取り組む必要があります。
3|可視化できるものに落とし込む
上で挙げた1,2のポイントを意識して行動したとしても、結局目に見える形として可視化しておかないとEXは向上しにくくなるとJosh氏はいいます。
誰がどんなことを考えていて、何をしたいと思っているのかなど、組織の全員がお互いを理解できるようにするためには、それらを可視化できるものに落とし込む必要があります。
例えば、エンプロイージャーニーマップを作ったり、組織の仕組みとして組み込んだりするなど、各従業員が1,2のポイントを可視化できるような形で制度を整える必要があるでしょう。
エンプロイージャーニーマップとは、従業員が今の組織に所属し、その組織を抜けるまでの間に何を経験し、そこからどのような成長を得ることができるのかを整理した図のことを指します。
4|「Radical Participation」を意識する
Radical Participationとは、従業員全体が組織に貢献するために、積極的に組織作りに参加することです。
一部の人が組織作りに携わるのではなく、さまざまな業種、さまざまな役職の人が組織作りに関与することで、偏りのない組織づくりが推進されるだろうとJosh氏はいいます。
さまざまな従業員の視点を組織作りに組み込むことで、各従業員のエンゲージメントや当事者意識がより育まれ、ひいてはEXの向上につながるのではないでしょうか。
5|少しずつ施策実験を繰り返す
組織をよりよくするための施策を打ち出す際、多くの企業では施策を完全に練り上げてから一気に組織全体にアプローチするでしょう。
しかし施策を打ち出した後に、大きな問題が露呈したり組織構造が変わったりと、後戻りせざるを得ない状況が発生する場合もあります。
したがって、新たにEX向上のための施策を打ち出す際は、一部の組織やコミュニティにのみアプローチし、かつ何度も実験を繰り返してブラッシュアップする必要があります。
そうすることで、柔軟性が高く組織や企業のニーズに合った施策を生み出すことができるでしょう。
6|プロセスを重視する
各従業員のリーダーシップを高めるためには、デザイン思考を取り入れてEX向上施策の設計をする必要があるとJosh氏はいいます。
従業員がどのような体験をして、そこからどのように成長するのか、といった成長プロセスを重視し、改めて再構築する必要があります。
そもそもEXを向上させるということは、従業員にとって働きやすい環境を整えることと同義であり、その点で従業員の立場に立って彼らがどのような経験を経てどのように成長するのかを考えることは当然であるともいえるでしょう。
EXを向上させるのであれば、第一に「従業員視点」を心掛けるべきではないでしょうか。
EXに注目している海外の企業
ここでは、EX(Employee Experience)に注目し、組織作りをおこなっている海外の有名企業を3社ほどご紹介します。
Airbnb
民泊サイトを運営するAirbnbは、EXに注目した組織作りを徹底しています。
従業員が働きやすいオフィス環境を整え、従業員の自己学習をサポートする制度を導入するなど、従業員がさまざまな体験を通じて成長し、結果として仕事に還元できるような仕組みを整えています。
Netflix
「TeamBlind.com」のリサーチによると、ストレスを感じにくい会社ランキングでNetflixは1位になっています。
Netflixでは、有給休暇や経費規定などの制度が存在せず、各々の従業員がいつ休むべきか、経費を使うべきかどうかといったことまで自分で判断して考える裁量が与えられており、各従業員はさまざまなタッチポイントでEXを向上させることができます。
この理念は「従業員を大人として扱う」という企業文化にも表れています。
シスコシステムズ
2018年の「働きがいのある会社ランキング:大規模部門」において1位を獲得したシスコシステムズは、働き方改革の一環としてEX向上のための施策を多く打ち出しています。
多様なワークスタイルの推進や女性社員の獲得、育成などを掲げており、働きやすい環境を整備しています。
さらにシスコシステムズはそういった制度設計にとどまらず、従業員視点を取り入れるための企業文化や土壌作成にまで力を入れており、結果として多くの従業員がシスコシステムズで働くことに誇りを持っているというデータが出ています。
さいごに
いかがでしたか。
まだまだ日本には浸透しきっていないEXという概念は、今後さらに注目を浴びていくでしょう。
従業員1人1人のEXを向上させることで、それぞれが個性を最大限発揮して働くことができ、結果として会社への貢献という形で還元されるのではないでしょうか。
働き方改革がさけばれる今日、より多くの社会人が楽しく働くようになるための鍵がこのEXにあるのかもしれません。










