
社会保険は、従業員の生活を守るための重要な制度です。従業員を雇用して事業を展開する場合は、社会保険に関する必要な手続きを進める必要があります。
実は、社会保険には強制適用と任意適用の2種類があります。該当する条件や加入手続きの方法は、それぞれ異なるためしっかりと把握しておきましょう。今回は、強制適用と任意適用の違いについて詳しく解説します。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 社会保険は強制加入?

社会保険は従業員の生活を守るための重要な制度ですが、すべての事業所に加入義務があるわけではありません。社会保険の適用事業所は、強制適用事業所と任意適用事業所に分けられます。
強制適用事業所に該当する場合は、必ず社会保険に加入しなければなりません。一方、任意適用事業所に該当する場合は、社会保険に加入するかどうかを自由に選択できます。メリット・デメリットや従業員の希望を考慮したうえで、加入の是非を検討することが可能です。
強制適用事業所と任意適用事業所の違いについては、次の項目で詳しく解説します。
2. 社会保険の強制適用事業所と任意適用事業所の違い
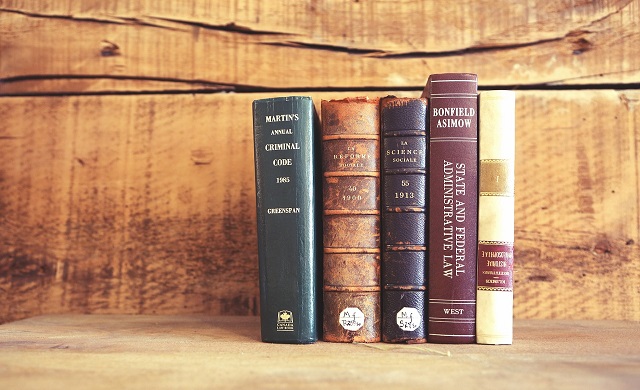
前述の通り、社会保険の適用事業所は、加入が義務付けられている強制適用事業所と、任意で加入ができる任意適用事業所の2種類に分けられます。以下、それぞれの事業所について解説しますので、どちらに該当するか確認しておきましょう。
2-1. 強制適用事業所とは
強制適用事業所とは、法律によって社会保険への加入が義務付けられている事業所のことです。法人の事業所は事業の種類を問わず、強制適用事業所となります。また、法人以外の場合でも一部の業種を除き、常時5人以上の従業員がいれば強制適用事業所となるため注意が必要です。
強制適用事業所に該当する場合、会社の経営状況に関わらず社会保険へ加入し続ける必要があり、特別な法的措置以外では加入しない選択はできません。
強制適用事業所で次のような従業員を雇用する場合は、社会保険への加入手続きをおこないましょう。
- フルタイムで働く従業員
- 週所定労働時間・月所定労働日数がフルタイムで働く人の4分の3以上の従業員
パート・アルバイトの社会保険については、後ほど詳しく解説します。
2-2. 任意適用事業所とは
任意適用事業所とは、任意で社会保険へ加入できる事業所のことです。従業員が5人未満の個人事業主や、飲食業・美容院などの適用外となる業種の個人事業主は、任意適用事業所に該当します。
任意適用事業所の場合、無理に社会保険へ加入する必要はありません。ただし、従業員の半数以上の同意があるときは、社会保険に加入することも可能です。
加入する場合は、事業所を管轄している年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」を提出しましょう。
関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介
3. パート・アルバイトも社会保険に強制加入?
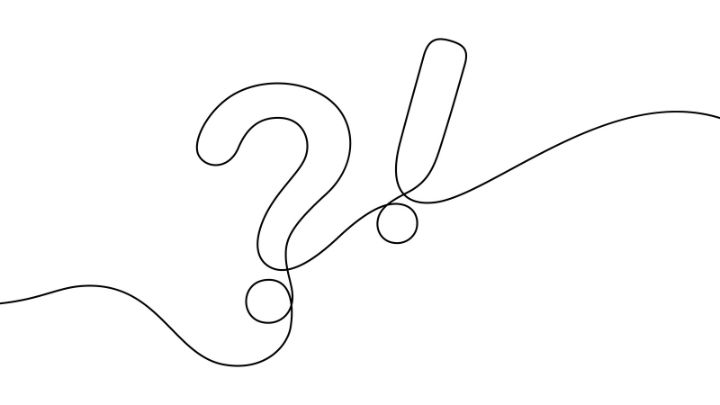
正社員などのフルタイムで働く従業員だけではなく、パートやアルバイトについても一定の要件を満たす場合は社会保険へ加入させる必要があります。週所定労働時間・月所定労働日数がフルタイムで働く人の4分の3以上の場合は、パートやアルバイトであっても社会保険に加入させなければなりません。
また、4分の3未満であっても以下の要件に該当する場合は、社会保険への加入手続きが必要です。
- 従業員数101人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
3-1. 2024年10月からは適用範囲が拡大される
社会保険の適用範囲は、少しずつ拡大されています。上記の従業員数に関する要件は、以前は501人以上でしたが、2022年10月から101人以上に変更されました。
さらに2024年10月には、従業員数51人以上の企業にまで適用範囲が拡大されます。小規模な事業所も適用の対象となるため、必要な手続きを進めましょう。
4. 社会保険の任意継続とは?

事業主と従業員ともに知っておきたいのが社会保険の任意継続です。任意継続とは、社会保険に加入している事業所に2カ月以上所属していた状況で退職した場合に、手続きをすることで2年間だけ社会保険への加入を継続できる制度です。
任意継続を希望する場合は、退職後20日以内に最寄りの役所で手続きをしなければなりません。万が一、20日間を過ぎてしまうと、病院での医療費負担が10割となる可能性があります。
任意継続に関して、以下の収入要件などを把握しておきましょう。
4-1. 被保険者(加入者)の収入要件と範囲
収入要件には、所得証明や直近の源泉領収票の写し、その他資産の証明、会社退職者(離職票、雇用保険受給資格者証)年金受給者(年金の通知書等)が証明書類として必要になります。
4-2. その他の手続きは?
資格取得ができ、手続きが完了した場合、早ければ2、3日程度で指定の住所に健康保険証が郵送されます。もし、健康保険証が届くまでに病院に通う場合では、一時的に医療負担をした後、療養費支給申請書で手続きすれば7割分が返ってくるので心配ありません。
国民保険と任意継続のどちらかを選択するかは、負担となる保険料で比較するとよいでしょう。
当サイトでは、本記事の内容を把握するうえでも重要な社会保険手続きの内容や、そもそもとなる社会保険料とはといった基礎知識をまとめた資料を無料で配布しております。
社会保険に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
5. 社会保険への加入条件を理解しておこう!

今回は、社会保険における強制適用と任意適用、任意継続について解説しました。強制適用事業所に該当する場合は、従業員を社会保険へ加入させなければなりません。手続きを忘れると労使間のトラブルに発展する可能性もあるため注意しましょう。
また、社会保険の適用範囲は順次拡大されています。法改正の内容や自社の状況を把握したうえで、社会保険への加入が必要な場合は速やかに手続きを進めましょう。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









