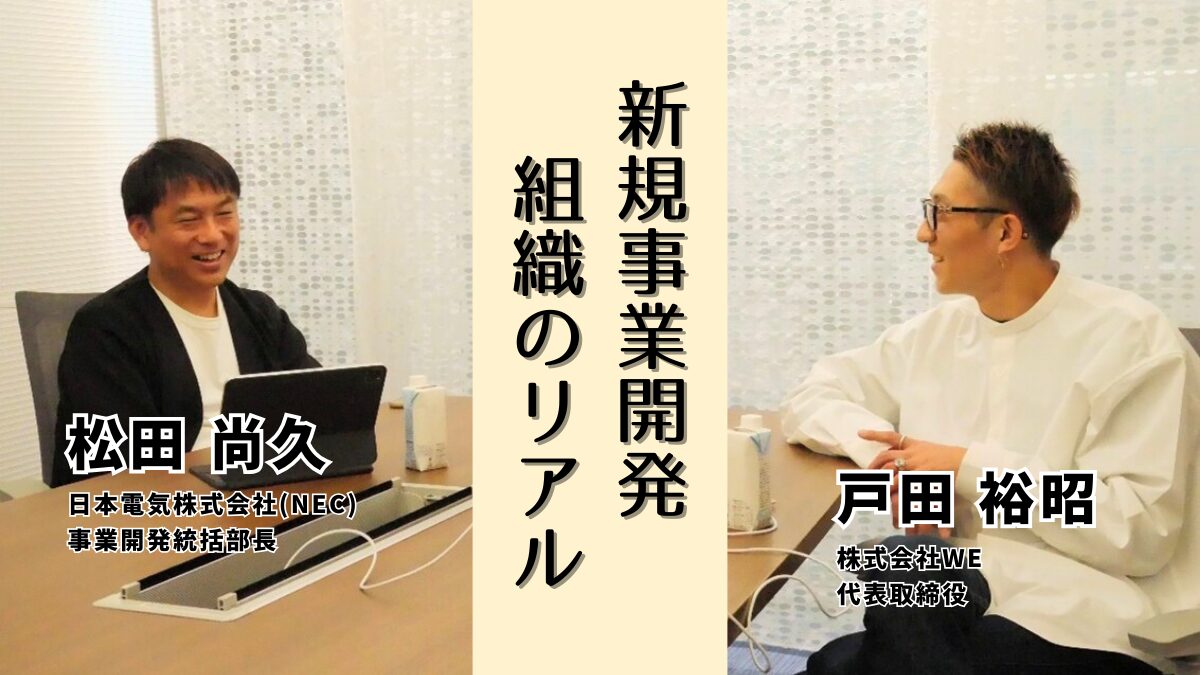
人事の皆さんへ、新シリーズがスタート!第一回目のゲストは、NEC事業開発統括部長の松田尚久さん。
「仕掛けよう、未来。」を掲げ、新規事業開発に挑戦するNEC。その最前線に立つ事業開発統括部は、約80名のうち半数がキャリア採用という、多様性あふれる組織です。異なるバックグラウンドを持つメンバーがそれぞれの強みを活かしながら新たな事業を仕掛けていく。 その力の源は、一人ひとりの成長を徹底的に支える組織づくりにあります。
「自律的に動くメンバーが新たな事業を生みだす。それが、日本企業が海外市場へ挑む力となる。」そんな松田さんの組織づくりへの想い、ぜひご覧ください!

登場人物松田 尚久氏日本電気株式会社(NEC) 事業開発統括部長
2000年NECに入社し、SEとして通信事業者向けビジネスを担当。2008年にはNECが買収した米国Netcracker社でPMIやシナジー創出に従事。帰国後10年以上にわたりIoTやID経済圏生成、5Gのグローバル展開など数々の通信系新規事業を推進。2023年グローバルイノベーションユニットで全社の技術戦略策定等に携わり、2024年より現職。

登場人物戸田 裕昭氏株式会社WE 代表取締役 / 総務省地域力創造アドバイザー
大学卒業後、オフィス家具メーカーにて新規事業創出・地域活性化に携わる。総務省地域力創造アドバイザーや国土交通省スマートアイランド推進実証事業コーディネーターなどを担い、全国各地の地域における事業振興のアドバイスを行なっている。 また、個々人のやりたいことが起点となる事業創出を目的とした伴走型教育プログラムを開発・構築。小学校から大学までの教育機関や自治体、民間企業と連携し、人材育成を軸とした「組織変革」「事業創造」「地方創生」を行う。
目次
自己紹介
– まずは自己紹介をお願いします!

松田さん:NECに新卒で入社して、SEとして通信業界のお客さまを担当していました。その後、NECが買収した米国Netcracker社への2年間の出向を経て、通信分野での新規事業を推進。2年前からは全社の技術戦略策定等に携わり、現在はNECの次の成長の柱となる新規事業の創出に取り組んでいます。
– これまでの経験は、新規事業開発にどう役立っていますか?
松田さん:やはり「現場を知らずに新規事業は生まれない」と思っています。お客さまと直接向き合い、現場で試行錯誤してきた経験こそが、今の新規事業開発の基礎になっています。
そして今は、メンバーが自分の力を発揮できる「働きやすい環境」をどう作るか?を常に考えています。
– 働きやすい環境というのは、オフィス設備などのハード面?それとも雰囲気づくりなどのソフト面でしょうか?
松田さん:どちらも大切ですが、特に重視しているのはソフト面です。特に「途中の過程を評価すること」は欠かせません。新規事業は成果が出るまでに時間がかかる。その途中の過程をしっかり評価しないと、モチベーションが続かないんですよね。
新規事業を生み出す組織づくり
新規事業における評価とは?

– 途中の過程を評価、という点をもう少し掘り下げて教えてください。
松田さん:企業である以上、もちろん財務的な成果は求められますから「P/Lを意識すること」はメンバーに明確に伝えています。ただし新規事業開発においてはなかなかすぐに財務的な成果が出るとは限らないので、「パフォーマンスと行動」もしっかり見ています。
例えば「PoCを実施してプレスリリースをする」「社外の場に出て新たな人脈を作る」「積極的に情報を集める」こういった行動も新規事業の大切なプロセスとして評価しています。
– 「ゼロから立ち上げる」のが新規事業というイメージがありますが、松田さんはどう考えていますか?
松田さん:「ゼロから」だけでなく、既存事業の中にも新規事業の芽はたくさんあるんです。
例えば、既存顧客とのビジネスのモデルを変えて収益を上げたり、現在の投資を元に将来の成長の可能性を提案したり。「新しい価値を生み出し形にすること」こそが、新規事業の本質だと考えています。
‐「自分で考えて動くのは苦手」という人が多いという話もよく聞きますが、松田さんの組織ではどうですか?
松田さん:もちろん、そういう人もいます。でも大切なのは「考えて動く力」を育てるためのトレーニングを提供する環境を作ることです。今の時代、言われたことをこなすだけでは評価されにくいですよね。
でもそれは本人だけではなく、評価する側も変わらないといけない。こうあるべきと決めつけず、柔軟に変化に対応する姿勢をお互いがもつ必要があります。
新規事業に必要なマインドの「トレーニング」
– 確かに「トレーニング」は大切ですね。松田さんにとって「トレーニング」としてどのようなことを行うとマインドが変わることに繋がるでしょうか。
松田さん:理論やフレームワークはある程度整備されていますが「実際にやってみる」経験が一番大事。まずは「新規事業のプロセスに沿って、一周回してみる」ことです。
私たちもサポートしますが、自分で考え、試行錯誤しながら実践することが成長につながります。
– これは大きなヒントですね。自分のやり方を見直し「もっと良くするには?」を考えることが大切。そうすれば、誰でも新しい方法を考えることができる。
松田さん:そうですね。何かを考えるには、その土台となる経験が必要です。
経験が多いほど引き出しも増えます。スタートアップは若い起業家が多い印象がありますが、実は年齢を重ねてからの方が成功しやすいというデータもあります。
「新しいことを創り出すのは苦手」「言われたことはできるけど・・・」と感じている人でも、さまざまな分野で「やり遂げる」経験を積んでいくことで、自分の強みになっていくのではないでしょうか。年齢に関係なく、多様な経験を積み、泥臭く取り組むことが大事だと思います。
「泥臭く」動く経験を積み重ねる
– AIやテクノロジーの進化で、場所を選ばず働けるし、LINEですぐに連絡も取れる。なんでもスマートにこなせる時代になりましたよね。その分「泥臭さ」が薄れてきているように感じますが、この変化についてどう思われますか?
松田さん:「泥臭さ」は、ツールを使ってスマートにこなせるかどうかとは別だと思います。優秀なコンサルタントも、事業会社や現場での経験が豊富だったりしますよね。
戦略を大上段から考えるだけでなく、現場の泥臭さを理解し、どれだけ事業の再生や成長に貢献できるかが大切です。どんなにテクノロジーが進んでも、生き残るために必要な力や泥臭い努力の重要性は変わらないと思います。
– そうですね。一般論やデータだけでは心に刺さらない。自分の経験をもとに語ると心に響いていく。それも、その人自身がどれだけ現場で経験を積んできたかが大事なのだろうと思います。
AI・テクノロジーと組織のあり方
– AIは本当に便利ですが「人の仕事がなくなるのでは?」とよく言われますよね。実際に、その影響は感じていますか?
松田さん:AIによって仕事のやり方や質は変わりますし、一部の仕事はAIに置き換わることもあるでしょう。
でも、AIはあくまで人間を支援するツール。効率化によって今までの仕事が減ったとしても、新たな領域で人間の役割が生まれてくると考えています。
AI・テクノロジーの進化で生まれる機会
– DeNAではAI活用により従業員の半分を新規事業に特化させる、という話もありますよね。AIが進化するからこそ、新規事業は生まれやすくなるのでは?
松田さん:そうですね。私たちの業界でいうと、インパクトが大きいのはプログラム開発の自動化です。開発には非常にコストがかかりますが、AIで自動生成できるようになればすぐ形にできる。そうすると「作る」ことではなく「作ったうえで何をするか」が重要になる。業界構造も変わるでしょうし、新しい価値を生み出すには、面白い時代になるのではないでしょうか。
– AIやテクノロジーの進化で、コストは下がりスピードも上がる。提供されるものが変わると世の中が変わるスピードも速まっていく。誰でもスタートラインに立って挑戦できる時代になりますね。
挑戦しやすくなった環境で何をする?
– ポジティブに「これがやりたい!」と思う人が増えていくと、挑戦しやすい環境がどんどん広がりますよね。

松田さん:環境的にはどんどん挑戦しやすくなっています。でも、実際に挑戦するかどうかはその人次第ですね。
– 松田さんは組織のなかでメンバーに挑戦してもらう立場ですが「メンバーが挑戦しやすい環境づくりの工夫」はしていますか?
松田さん:「頭から否定しない」ことを心がけています。メンバーから提案を受け「それ、前にやったけど失敗したよね」なんて全否定すると、せっかくの可能性が閉ざされてしまう。だから、柔軟にピボットできるようなフィードバックを意識しています。
そして、提案する側も柔軟であることが大事です。フィードバックする側は「次の可能性」を示し、提案する側は「絶対にこれじゃなきゃだめ」と固執しすぎない姿勢が必要です。お互いに建設的に話せる環境がなければイノベーションは生まれません。
– アドバイスやフィードバックを通して、世界を広げていくことが大事ですね。そして、新規事業においては意思決定も重要ですよね?
新規事業における意思決定・決断
松田さん:多くの企業で新規事業が失敗する要因の大半は、リソースの分散ではないでしょうか。限られたリソースのなかでは「やめる決断」をすることも大切です。
– 「やめる」という意思決定にはどういう工夫がありますか?
松田さん:まず意思決定のプロセスは決めています。でも、例外は出てくるので、最後は誰かが決めなければいけない。実はこれが最も難しい部分です。
物事がうまくいかないとき、短期的にみると「上の人が決めていない」ことが多いんですよね。「やめますか?」ときくとずるずると「もう少し様子をみよう」となってしまう。
明確に「やめる」と決断することが必要で、それが次の選択肢を広げることにつながります。
組織メンバーとのコミュニケーション
プロパーかキャリア採用か
– プロパーとキャリア採用の融合が求められる中、組織運営でどのような工夫をされていますか?
松田さん:プロパーかキャリア採用かはあまり意識していません。以前はキャリア採用が少なく、力を発揮する前にだんだんとNECに染まっていくことが多かった。でも、半数近くがキャリア採用になると、逆にプロパー側がNEC文化を疑うようになる。例えば、社内の用語や会議が多い、承認プロセスが長い、など「自分たちのやり方って本当に正しい?」と問い直し、組織が進化する原動力になっています。
– 松田さんと若手社員との距離が近い印象ですが、意識していることはありますか?
松田さん:若手社員が納得していないのに、私の言う事に無意識にYESと言ってしまうケースはまだまだあったりするなど、課題は多いと思います。本当の意味で役職を超えたフラットな環境になり、みんなが自律的にアウトプットを出せるように、毎年少しずつ自分のスタイルも進歩していきたいです。
組織の長として意識していること
松田さん:キャリア採用が増えることで多様性が生まれ、とても良いことだとお話ししましたが、キャリア採用の方たちが苦労することもあります。なんだと思いますか?
– 仕組みでしょうか?
松田さん:「社内の誰に相談すればいいか分からない」というのが大きなハードルです。それを聞いてから、組織長として他部門や社内キーマンとメンバーとの「つなぎ役」を意識するようになりました。そうすると、偶発的に新しいものが生まれたり、つながりが生まれたりするんですよね。
長く会社にいるからこそできることでもあるし、プロパーとキャリア採用のメンバーが互いに補完しあう関係を築くには、こうした役割が重要なのかなと思っています。
– 自分の組織としての仕事もありつつ、繋ぐ役割もする。だんだん組織の在り方が見えてきたような気がします。「そういう」組織ができたらいいですね。
メッセージ(企業人事の方へ)

松田さん:NECの新規事業開発はまだまだ挑戦の最中です。でも私たちは本気で「日本企業が世界で挑戦する力」を高めたいと考えています。
日本企業同士がオープンイノベーションを進め、スタートアップとも連携し、世界に挑む。NECのノウハウもどんどん使ってもらい、日本全体を強くしたい。
「日本発」にこだわり、未来を一緒に仕掛けていきましょう!この分野に興味がある方、一緒に挑戦したい方、ぜひお気軽にNECにお声がけください。
NEC Open Innovation について
https://jpn.nec.com/innovation/index.html








