
近年、新型コロナウイルスの流行やAI技術の急激な進化により世の中の変化を予測しにくくなっています。
このような先行きが不透明な時代であるからこそ、人材育成の重要性が高まってきました。
本記事では、人材育成領域でとくに注目されている「アンラーニング」という手法について、リスキングとの違いやメリット・デメリットをわかりやすく紹介します。
目次
1.アンラーニングとは
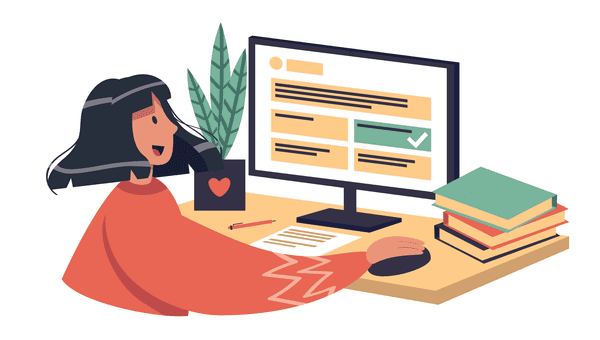
まずは、アンラーニングの意味やリスキリングなどとの違いについて確認しておきましょう。
1-1.アンラーニングの意味
アンラーニングとは「学習棄却」「学びほぐし」と呼ばれ、これまで培ってきた価値観を取捨選択し、新しい価値観・知識を身に付けることを指します。
アンラーニングは英語で「unlearning」と表記されるように、新しい知識を身に付けるだけでなく、従来の価値観を捨てることも重要であるとする考え方です。
人は誰しも今までに身に付けてきた価値観に固執しがちです。しかし、従来の価値観に固執していると、時代の変化を捉えることができず、新しい知識を吸収することが難しくなるケースもあるでしょう。
そのため、新しい知識を身に付けるためには、「まず従来の価値観を取捨選択する」ことが重要になってきます。
1-2.アンラーニングが注目されている理由
昨今のビジネス業界でアンラーニングが注目されている理由としては、VUCA時代が到来したことが挙げられます。
なお、VUCAとは、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を取った造語です。
変化が激しい現代において、既存の考え方に依拠した価値観では競争社会を生き残るのが難しくなっています。そのような状況のなかで、「アンラーニング」に注目が集まるようになりました。アンラーニングにより、常に新しい価値観や知識を活用することができるようになります。
さらに常に危機意識を持ち時代の流れを先読みすることで、必要とされるものをいち早く習得できるようになるでしょう。
1-3.アンラーニングと経験学習の関係
アンラーニングは、経験学習と深い関係性があります。経験学習は「具体的経験」「内省的反省」「概念化・抽象化」「能動的実験」の4サイクルを繰り返す学習モデルで、デービッド・コルブ氏により提唱されました。
経験学習では、自らの経験によって何らかの気づきを得て内省したうえで、教訓を概念化し、次の機会で実験的に活かしていきます。
そのプロセスにおいて、過去の教訓にいつまでも縛られていては、新しい学びを得ることができません。アンラーニングは、執着を手放しゼロベースで成長していくために不可欠な考え方だといえます。
2.アンラーニングと「リスキリング」「アップスキリング」の違い

アンラーニングと似た用語に、リスキリングやアップスキリングがあります。ここでは、リスキリングとアップスキリングの意味を説明したうえで、アンラーニングとリスキリング、アンラーニングとアップスキリングの違いをわかりやすく解説します。
リスキリングとは、英語では「Reskilling」と呼び、経済産業省では下記のように定義しています。
2-1.リスキリングとは
新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること
近年では、IT技術の発展の影響からデジタル化が進んでおり、技術革新やビジネスモデルの変化に対応し、価値を創造し続けるために、新たに知識やスキルを習得することが必要とされています。
このように、リスキリングとは新しい職業に就くために、保有していない新しい知識やスキルを習得する取り組みを指します。
一方、アンラーニングは知識やスキルを取捨選択して、バージョンアップしていく取り組みを指します。以上から、アンラーニングでは「捨て去る」の意味合いが強く、リスキリングでは「獲得する」の意味合いが強いという違いがあります。
2-2.アップスキリングとは?
アップスキリング(Upskilling)とは現在の職業で、新しい知識・技術を取り入れてスキルを向上させる取り組みを指します。アップスキリングは、アンラーニングよりもリスキリングと似た意味をもちます。
しかし、リスキリングとアップスキリングでは、新しい知識・技術を取り入れる目的としていますが、現在の職業でスキルアップするためなのか、別の職業に就くためなのかという違いがあります。
3.アンラーニングをおこなうメリット
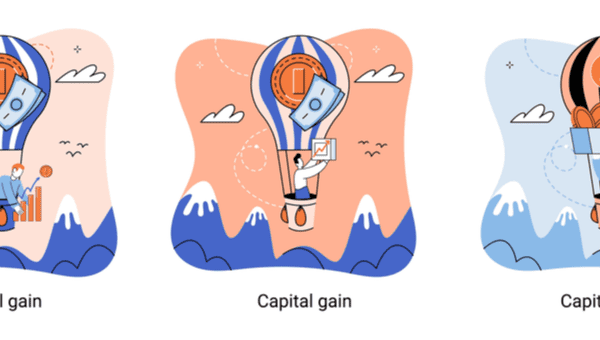
ここでは、アンラーニングをおこなうことで得られる効果を4点紹介します。
3-1.従業員のパフォーマンス向上
経験値が高い従業員が陥りやすいのが、過去の経験に執着し、新しいやり方、視点を考えなくなってしまうことです。
とくにベテラン従業員の場合、これまでの上手くいった経験に固執してしまい、新しい知識やスキルを取り入れることを疎かにしていることもあるかもしれません。
アンラーニングに取り組むことで、従来の価値観に変化をもたらすことができます。
新しい価値観のなかで今までの経験を活かすことができれば、従来にはなかったアイデアや課題解決へのアプローチなどを生み出す足掛かりになり、今までにないサービスや商品を提供することができるでしょう。
3-2.業務の効率化
アンラーニングを推進することで、既存の社内ルールや業務フローなどを見直すことができます。業務における新たな気づきや無駄を発見し、改善をおこなえば業務の効率化につなげることが可能です。
ただし、社内ルールや業務フローなどを変更すると、従業員がその環境に慣れるまでに時間がかかることもあり、最初は業務効率が下がったと感じる場合もあるかもしれません。
短期的な成果で判断せず、中長期的な効果を見据えて取り組むことが大切です。
3-3.マネジメント力強化による収益性の向上
現代ではさまざまな人材が多様な雇用形態で働いています。そのような環境に変化しているのにマネジメント方法は変わらないままだと、軋轢が起きる可能性もあるでしょう。
そこで経営層を含めアンラーニングをおこなうことによって、新しいマネジメント方法や制度を作成することができます。マネジメント力の強化は組織力向上の重要な要素であるため、企業成長のためにも取り入れる必要があります。
3-4.社会の変化に対応しやすい組織になる
現代のような変化が激しい時代では、柔軟に情報を取捨選択する必要があります。たとえ経験が豊富な従業員でも、過去の経験だけにとらわれていると、成果が出ないなど、伸び悩みを感じてしまうかもしれません。
アンラーニングにより、これまでの考え方や価値観などを見直し、新しい知識やスキルを吸収できる基盤を整備することで、変化が激しい時代でも従業員の継続的な成長が期待できます。
また、従業員一人ひとりがアンラーニングへの意識を持ち、継続的な学習習慣を推進することで、ビジネス環境の変化にあわせて、スピーディーかつ柔軟に対応できる組織を作り出すことができます。
4.アンラーニングのデメリットは?導入する際の注意点
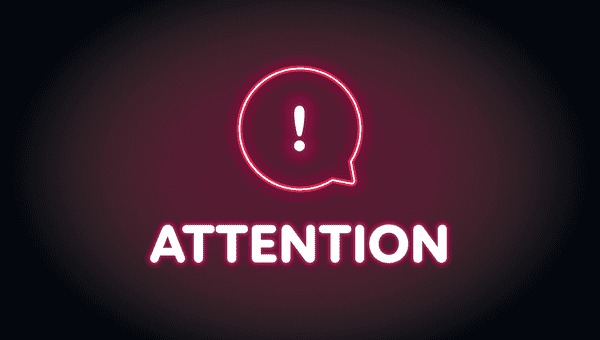
ここでは、アンラーニングのデメリットや、おこなう際の注意点について解説します。
4-1.モチベーションの低下
アンラーニングをおこなう過程で、モチベーションの低下に注意する必要があります。なぜなら、今まで学んできた経験や知識を疑ったり棄却したりすることで、今まで学んできたことを否定されたと考える人がいるからです。
否定されることは大幅なモチベーション低下につながります。また従来のやり方を変えることで、一時的にパフォーマンスが低下する可能性もあるでしょう。
モチベーションの低下を防ぐために、アンラーニングは今までの知識や経験、自分自身を否定する行為ではなく、自己成長のためにおこなうことだと事前に理解してもらう必要があります。
4-2.組織全体でおこなう必要がある
アンラーニングを実施する際には、組織全体が重要性を理解し、一体感を持って取り組むことが不可欠です。従業員が孤立して取り組むのではなく、組織としての文化や価値観が変化するよう努めることで、アンラーニングの成果を最大限に引き出すことができます。
組織全体が共通の目標に向かって進むことで、従業員はアンラーニングに対してより前向きに捉えることができ、モチベーションが向上します。
4-3.保守的な組織では実施しにくい
アンラーニングを実施するにあたって、組織においても個人においても、変化を受け入れる柔軟性が大切であることは言うまでもありません。組織が既存の文化や慣習に縛られてしまうと、アンラーニングを成功させることは難しいでしょう。
そのため、アンラーニングを導入する際は、組織の意識改革が不可欠です。まずは従業員が新しい考え方やスキルを受け入れやすい環境が整えられているかどうか、組織全体で見直す必要があります。
4-4.ラーニングを否定しない
アンラーニングの導入において、従業員が過去の学びや経験を否定されることなく、新たな学びとつなげることが必要です。ラーニング(従来の学び)を断ち切るのではなく、さらなる成長のためにアンラーニングをおこなうといった目的を理解してもらうことが、成功の鍵となります。
具体的には、アンラーニングを通してスキルの見直しをおこなった後に、従業員それぞれのラーニングと結びつけて学びを加速させる流れが望ましいです。
5.アンラーニングをおこなう方法・やり方
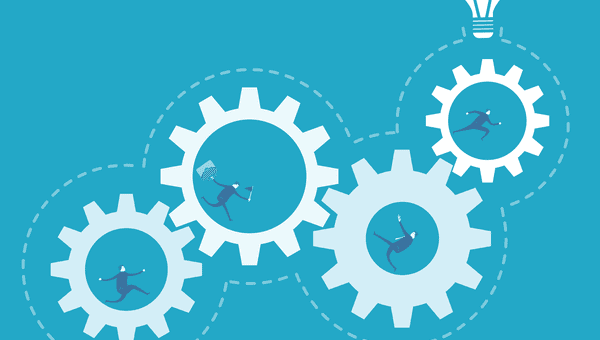
ここでは、アンラーニングをおこなう一連の過程について解説します。
5-1.個人単位での内省を実施する
アンラーニングを始める場合、まず従業員一人ひとりが自己内省や振り返りをおこない、考え方や価値観などを整理します。
日々の成功・失敗などの体験を記録することで、時代にあわない思い込みや、譲れないこだわりなどに気づくことができるかもしれません。 自己内省や振り返りをおこない整理ができたら、今後の業務で必要かどうかを見直しましょう。
アンラーニングを実施する場合、自分を客観視したり、新しい価値観に触れたりするために、チームメンバーや他部署、外部など幅広い方と交流するのがおすすめです。
5-2.クリティカルシンキングをおこなう
クリティカルシンキングとは、論理的・構造的に物事を考えることを指します。自分の無意識的な行動や考え方を客観的に振り返るという意味で使われます。
内省のあとは自分自身の考え方を整理することが重要です。クリティカルシンキングを通して、自分自身の思考や行為をさまざまな視点から見直してみましょう。
5-3.気付きの場を提供し参加する
自分一人だけでアンラーニングをおこない続けることはとても困難です。そこで外部機関などを利用し、新しい意見や知識を得られる場に参加します。そのような場に参加することで、新しい知識を習得することができるでしょう。さらに現在の業務を新しい視点で見直すことが可能です。
このように周囲の意見を聞くことで、自分のアンラーニングをより促進することが可能になります。
5-4.効果を測定する
新しい技術や知識は常に更新され続けるため、アンラーニングは一度で終了することはありません。継続的に内省をおこなうことが重要となります。
そのため、定期的な効果測定を実施し、改善することで次につなげるPDCAサイクルを回すことが必要です。アンラーニングの効果は、新しい技術や知識の習得度合い、活用度合いで測定します。
学習者自身だけでなく、上司との面談の機会を設置すると、客観的な評価を得ることができます。
6.アンラーニングを活用する際の人材育成方法

アンラーニングを活用した人材育成方法について解説します。
6-1.評価制度への反映による成長度合い測定
評価制度を見直すことでアンラーニングによる成長度合い、対応度合いを測定します。アンラーニングを実施しても実際に実務で利用できなければアンラーニングをおこなった意味がありません。
そこでアンラーニングと実践をセットで評価制度に組み込むことで、実践前提で学びがおこなえるようになります。
6-2.新しい知識を得るための学習機会の提供
アンラーニングでは新しい学びを得ることが目的であるため、学習機会の提供とセットであると考えましょう。また、アンラーニングは一度限りの研修ではなく、継続的に学べる環境を整えることが重要です。
環境を整えることによって、経験学習における「具体的経験」「内省的反省」「概念化・抽象化」「能動的実験」のステップを繰り返すことができ、従業員の成長を期待できます。
7.アンラーニングを実施して新しい価値観を取り入れよう!

本記事では、アンラーニングの意味やメリット、類義語との違いや注意点などを解説してきました。アンラーニングをおこなうことで、従来の価値観や確立されてきたルーティンワークを変えることになります。
このように大がかりなものなので、短期的に効果が現れるものではありません。しかし、アンラーニングに取り組み続けることによって、新しい発想を持つ人材の育成や、普段の仕事に新しい価値観を取り入ること、業務を効率化することなどを期待できます。
会社の継続的な発展のためにもアンラーニングを取り入れてみてください。







