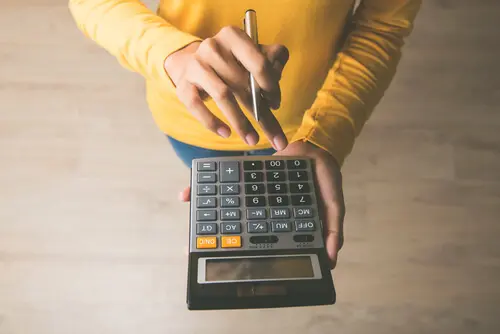
テレワークを導入するにあたって、交通費や通信費、光熱費などの費用負担をどのようにするかという悩みを抱えている方は多いのではないのでしょうか。なお、従業員に費用負担させる代わりに、テレワーク手当を支給している企業もあります。 当記事では、テレワーク手当の相場や必要性、注意点、支給方法について解説します。テレワーク手当のルール作りに関する知識を深めたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
目次
テレワークとは
テレワークとは、情報通信技術(ICT技術)を活用した、時間や場所を選ばないフレキシブルな働き方を指します。テレワークには、在宅勤務やモバイル勤務、サテライトオフィス勤務、ワーケーションなど、さまざまな形態があります。そのため、自社の規模や業務内容にあわせて、適したテレワーク形態を取り入れることが大切です。
テレワークを導入すれば、コストの削減や業務生産性の向上、BCP対策など、さまざまなメリットがあります。ただし、従業員と企業側でトラブルが生じないように、あらかじめ交通費や通信費、光熱費などの費用負担を明確にする必要があります。
テレワーク手当(在宅勤務手当)とは
テレワーク手当(在宅勤務手当)とは、テレワークを実施する従業員に対して支給される手当を指します。近年では、通勤手当の代わりに、テレワーク手当を支給する企業も増えています。
テレワークを実施するには、通信環境を整備するために光回線を契約したり、業務に集中できる環境を用意するためにデスクチェアやパソコンデスクを用意したりする必要があります。また、テレワークにより、冷房・暖房器具を使用したり、電気を使用したりする機会も増加するでしょう。
そのため、テレワークを実施できる環境を整えるには、通信費や光熱費、消耗品費などの費用が発生します。このように、テレワーク手当(在宅勤務手当)は、テレワークを導入したことにより生じた従業員の費用を企業側で負担するためにあります。
テレワーク手当(在宅勤務手当)は必要?
テレワーク手当(在宅勤務手当)の支給は、労働基準法の観点からも義務ではありません。そのため、テレワークを導入していても、手当を支給していない企業もあります。ただし、テレワークでも、働きやすい環境を従業員に準備してもらうためには、手当を支給するのがおすすめです。
在宅で業務をおこなうには、PCやネット環境が必須です。また、快適かつ安心なテレワークを実施するには、モニター・イヤホン・Webカメラなどの周辺機器やセキュリティ対策ソフトを用意する必要があります。また、業務に集中しやすい環境を整備するには、冷房・暖房器具やテレワーク用のパソコンデスク・チェアを準備することも大切です。
このように、テレワーク手当(在宅勤務手当)を支給することにより、従業員はテレワークでも働きやすい環境を整備できるため、結果として業務生産性の向上にもつながります。
テレワークの費用負担の相場は?
PLAN-B社の運営する「カジナビ」の調査によると、テレワーク手当(在宅勤務手当)は「1,000円~5,000円未満」の支給が44%と最も多く、「5,000~10,000円未満」の支給が19%であり、平均支給額は3,683円という結果が出ています。また、10,000円以上支給している企業もあります。
この結果から、会社の負担するテレワーク費用の相場は、3,000円~5,000円程度であると捉えることができるでしょう。
なお、さまざまな企業のテレワーク手当(在宅勤務手当)を支給している事例を参考に、自社に適した支給額を決定するのがおすすめです。
テレワーク手当(在宅勤務手当)のメリット
ここでは、テレワーク手当(在宅勤務手当)のメリットについて詳しく紹介します。
多様な働き方を実現できる
テレワーク手当(在宅勤務手当)を支給すると、テレワークでも働きやすい環境を整備できるため、多様な働き方を実現することができます。
たとえば、テレワーク手当を支給しない場合、費用負担の観点から、テレワークよりオフィスに出社したほうが、メリットを感じる従業員もいるかもしれません。そのため、テレワークを上手く社内に浸透させることができない可能性もあります。このような場合、手当を支給することでテレワークのハードルを下げることができるため、テレワークの促進につながります。
また、テレワーク手当(在宅勤務手当)を支給すれば、テレワークでも働きやすい環境を構築することが可能です。自宅とオフィスのどちらでも業務を実施できる環境を整備できれば、従業員の多様な働き方を推進することができます。結果として、人材の流出を防止や、優秀な人材の確保にもつながります。
コスト削減につながる
通勤手当の代わりに、テレワーク手当(在宅勤務手当)を支給することで、コストを削減できる可能性があります。交通費は従業員によって支給額は異なるため、遠方から通う従業員が多い企業などは、費用負担が大きい傾向にあります。
一方、テレワーク手当であれば、テレワークをおこなう従業員に一律で同額の手当を支給することができます。そのため、交通費の負担が大きいほど、コストの削減が期待できます。また、テレワークを推進できれば、オフィススペースの縮小にもつながるため、賃料やオフィスを維持するためのコストを削減することも可能です。
社員のモチベーション向上につながる
テレワーク手当(在宅勤務手当)を支給すれば、従業員満足度の向上が期待でき、会社への貢献意識や仕事のモチベーションの上昇にもつながります。
テレワークでストレスなく働ける環境を整備するには、さまざまな備品や機器を用意する必要があるため、従業員の費用負担が大きくなる可能性もあります。そのため、費用負担の観点から、会社に対する不満を覚える従業員もいるかもしれません。
また、テレワークでは、直接対面で会話できないため、孤独感や不安感を抱く方も少なくありません。そのため、従業員によっては、仕事へのモチベーションが下がってしまう可能性もあります。
そこで、会社側はテレワーク手当を支給することで、テレワークにおける従業員の負担を理解して、サポートする姿勢を示すことが大切です。このように、テレワーク手当(在宅勤務手当)を支給すれば、従業員の不満を解消し、仕事のモチベーションの向上につなげることができます。
テレワーク手当(在宅勤務手当)は課税?非課税?
テレワーク手当(在宅勤務手当)は、業務で必要な費用については、支給方法によって課税・非課税は異なります。テレワークに必要な費用を精算する方法の場合、一定の支給額については、課税する必要がありません。たとえば、従業員に支給した金銭のうち、業務に必要であった部分については課税が不要ですが、超過した部分(業務で使用していない部分)については、給与として課税する必要があります。
一方、テレワーク手当(在宅勤務手当)として、決まった金銭を支給する方法の場合は、給与と同等に扱われるため、課税の対象となります。課税される理由として、従業員によって手当の使い道は異なり、課税対象分が減収につながるとは言い切れないということが挙げられます。
このように、テレワーク手当は課税対象となることもあるため、支給方法について、自社できちんと明確にすることが大切です。
テレワーク手当(在宅勤務手当)の支給方法
ここでは、テレワーク手当(在宅勤務手当)の支給方法について詳しく紹介します。
現金支給
テレワーク手当(在宅勤務手当)の一般的な支給方法として、給与へ上乗せして現金支給する方法が挙げられます。現金支給の場合、手当の使い方の自由度の高さが特徴です。ただし、テレワークを推進するための手当であるのに、従業員によっては、プライベートなどほかのことに使用してしまう可能性もあります。
そのため、適切に手当を使用してもらうために、テレワーク手当に関する目的や意味について従業員にきちんと周知することが大切です。また、業務のために使用された分のみを精算する形態などを取ることで、使い道を制限する方法もあります。
現物支給
テレワークでもオフィスと同等の業務パフォーマンスを発揮できるような環境を提供するために、テレワーク手当(在宅勤務手当)を支給する場合には、現物支給が向いている可能性もあります。
現物支給であれば、PCやネット機器など、テレワークに必要な備品や機器のみを支給するため、必要以上の手当の支給を防止できるというメリットがあります。ただし、申請方法や管理方法などの取り決めが必要なため、申請に手間がかかったり、購入できる金額が決まっていたりするなど、従業員に不満が生じることもあります。
テレワーク手当(在宅勤務手当)を導入する際の注意点
ここでは、テレワーク手当(在宅勤務手当)を導入するときの注意点について詳しく紹介します。
テレワーク手当に関するルールを定める
テレワークを導入する目的にあわせて、テレワーク手当(在宅勤務手当)に関するルールを適切に定めることが大切です。たとえば、支給方法によっては、手当が課税対象となることもあります。また、自社の規模や業務環境によって、現金支給と現物支給のどちらが適しているかは異なります。
また、テレワーク手当(在宅勤務手当)を導入する場合には、就業規則を変更する必要があります。現物支給の場合は、申請手順を明示しておくと、従業員はスムーズに申請をおこなうことが可能です。そして、従業員と企業の間でトラブルが発生しないように、テレワーク手当における費用負担の範囲を明確にする必要があります。
なお、就業規則を変更する場合には、従業員代表の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署に届け出をおこわなければならない点に注意しましょう。
ルールを周知する
テレワーク手当(在宅勤務手当)では、とくに現金支給の場合、実費補填である通勤手当とは異なり、使い道が限定されていません。そのため、テレワーク手当の意図や使い方のルールを従業員にきちんと周知することが大切です。
また、テレワーク手当の対象者や支給額、申請方法などについて、従業員に正しく伝わっていない場合、クレームにつながる恐れがあります。そのため、すべての従業員に対して、テレワーク手当のルールを説明する機会を設けるのがおすすめです。
手当の導入でテレワークを推進しよう!
テレワーク手当(在宅勤務手当)とは、テレワークを実施する従業員に対して支給する手当のことであり、通勤手当の代わりに支給する企業も増えています。テレワーク手当を導入すれば、多様な働き方の推進やコストの削減、従業員のモチベーションアップなどの効果が期待できます。
テレワーク手当を導入するにあたって、トラブルを生まないようにルールを明確化し、きちんと周知することが大切です。テレワークをスムーズに推進できるように、手当を上手く活用するのがおすすめといえます。







