
近年、新型コロナウイルスの影響により、働き方が大きく変化しています。
出社して対面での勤務をおこなう場合とリモートワークの場合とでは、コミュニケーションの取り方に明確な違いがあります。
今回は、このような状況においてコミュニケーション不足に陥り、チーム力の欠如を実感している方に向けて、「チーミング」を紹介します。
この記事が、改めてチームの在り方を見直すきっかけになれば幸いです。
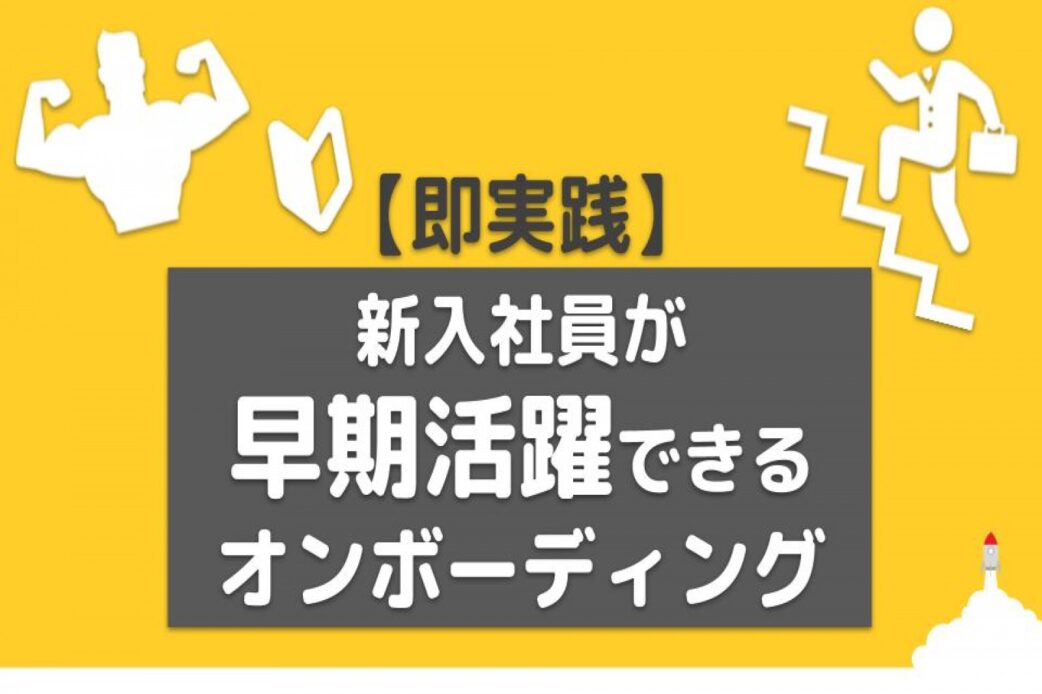
目次
1. チーミングとは

そもそも「チーミング」とは何なのでしょうか。ゲームをよくするという方には聞き慣れた言葉かもしれませんが、最近になって企業におけるチーム作りにもチーミングという言葉が使われるようになってきたため、その意味を知らないという方も多いことでしょう。
チーミングとは、英語でteamと進行形のingが組み合わさった言葉で、「チームを組む」という意味の英単語です。チームワークの構築と最適化を絶え間なく模索し、実践しつづけることを指します。
チーミングによりフラットな組織が構築され、新たなアイデアが生まれ、答えを探し、問題を解決するために人々を団結させる動的な活動が可能となります。
ちなみに、ゲームで使用されるチーミングの意味は、「ルールに逆らってチームを組む」です。しかし、企業での「チーミング」は、ポジティブな意味でのチーム作りを指してるため、少し意味が異なります。
また、この他にもネットワーク分野で「チーミング」という言葉が専門的用語として使われる事もありますが、今回は、企業における「チーミング」について解説していきます。
1-1. チーミングが注目されている理由
近年、チーミングが新たな概念として企業から注目されている理由は、新型コロナウイルスによる影響が大きいと考えられます。
予測不能な現代社会においてチームの在り方は常に変化し続けており、日々の業務や研修をリモートワークでおこなう企業も増加しています。リモートワークの導入後に「以前よりもチームとして仕事を進める意識が低下している」という声もよく耳にします。
しかし、チーム力の低下は企業の業績や人材育成において大きな影響を及ぼします。
そのため、対面でなくてもチーム意識をもって仕事を進めるためのさまざまなツールや手法が生まれ、今後も予測不能な時代に対応するためにチームのあり方が変化していく中で、チームワークを絶え間なく模索するチーミングが重要視されているのです。
1-2. リモートワークにおけるチームのあり方とは
最近では、「テクノロジーの進歩が早すぎて議論についていけない」「部署をまたがるビジネスにうまく対応ができない」「業務が複雑化する中、どこで誰が意思決定すべきかが曖昧になってしまう」といった悩みを抱える会社も少なくありません。
こうした悩みを解決すべく、各分野に専門的な人を集め、プロジェクトごとにチームをつくったり、必要なスキルを持つ人をその都度メンバーに加えたりしてプロジェクトを進めるケースが増えてきています。
部や課、チームといった固定化されたメンバーで構成する従来型の職場でも、コロナ禍によってリモートワークや交代制が定着し、メンバーが物理的に離れた状態で業務をおこなうことも珍しくないでしょう。
このように、メンバーが物理的に離れたりプロジェクトごとにメンバーが入れ替わったりする「流動的なチーム」が増えており、その際にチーミングという考え方が役に立ちます。
1-3. 新しいリーダーシップの必要性
チームワークを模索・構築しつづけるチーミングは、メンバーと対話を続け相互理解を大切にする新たなリーダーシップの形です。
チーミングでは、リーダー1人が意見を取りまとめてチームを主導するのではなく、チームメンバー全員に意見や主張を求めます。
リーダーは、これまでの常識や前提条件を当たり前と捉えず、チームメンバーと話し合いを重ねることで、チームとしてより良いパフォーマンスを発揮することが求められます。
2. 理想のチームを作るために知っておくべき2つのこと
チーミングによって理想のチームを作るためには、優れたチームの条件やチームの成長の流れを知っておくことが大切です。
2-1. 優れたチームの3つの条件
優れたチームには以下の3つの条件が必要です。
| 対話的である |
|
| 生成的である |
|
| 発達的である |
|
2-2. 理想のチームを作るための4つのステップ
理想のチームは、何か1つの施策を講じるだけで作り上げることはできません。チームは4つの段階によって発達していくと考えられています。
| チームの発達段階 | 概要、次のステージに移行するためのポイントなど |
|
フォーミング (同調期) |
|
|
ストーミング (混沌期) |
|
|
ノーミング (調和期) |
|
|
トランスフォーミング (変態期) |
|
3. チーミングの進め方

ここからチーミングによるチームの作り方について解説します。
チームとは、ただ人が集まれば出来上がるわけではありません。チームとは、その中で共通の目的を達成するための組織のことを指します。
ただ優秀な人材を集めるのではなく、異なった個性や経験を活かしチーム力を高め合っていきます。そしてチームの生産性が向上することが理想の状態です。
本章では、チーム作りのポイントについて、4つ解説していきます。
3-1. 心理的安全性を高める
心理的安全性とは、チームメンバーそれぞれが恐怖や不安を感じることなく発言・行動することができる状態を指す言葉です。
チームメンバーがお互いを尊重し高め合っていくには、皆が信頼し合える関係性を構築する事が大切です。お互いが意見を交わし合える環境は心理的安全性を高め、失敗を恐れずに発言し新しいことに挑戦できる環境が作れます。
心理的安全性は、米Google社のリサーチチームが、自社の生産性を向上するために実施した「Project Aristotle」というプロジェクトの研究結果として生産性の高いチームをつくるために心理的安全性が最も重要であると発表して以来、世界中で注目されるキーワードとなりました。
https://hrnote.jp/contents/psychological-safety-20210514/
3-2. 失敗を改善して学習する
現状の方法をより効率的かつ効果的なものへと改善するためには、失敗から学ぶことが求められます。
そのため、失敗したときこそ、次に同じ過ちを繰り返さないために、失敗の要因や改善点を洗い出すことが重要です。またそれをチームで共有し理解する必要があります。
心理的安全性が確保されているチームであれば、臆せずに自分の失敗をチームに共有でき、それを財産として学習することも可能になっていることでしょう。
3-3. フレーミングとリーダーのあり方を認識する
フレーミングとは、その言葉通り世の中を見るフレームを変えることです。
各個人には、各個人の状況に応じたそれぞれの意見があります。そして、世の中に起こる事は、その人なりのフレームの中で解釈されているため、人によって見方は全く異なることでしょう。
チーミングの際には、「自分の見方の方が、他人の見方より正しい」と感じる認知バイアスがかかるケースも多くあることをリーダーが認識している必要があります。
- 登録
- 準備
- 試行
- 省察
詳しく知りたい方はこちらからフレーミングを学んでください。(参考資料:学習する組織をつくる:フレーミングの力│ナカシマガジン)
3-4. 職業や文化的な価値観の違いによりできる境界をつなぐ
職業や文化的な価値観の違いなどによる境界線はどこにでもあります。しかし、意識しないと見えなくなってしまいます。
境界は、アイデンティティを同じくするグループ同士の間の区切りであり、そうしたグループは、ジェンダー、職業、国籍など、人間が属するあらゆるカテゴリーに存在します。
また境界には目に見えるものと見えないものがあり、今回紹介した職業や国籍などは目に見えやすい境界に位置付けされます。
見えない境界としては、様々なグループの中で当たり前になっている思い込みや考え方が当てはまります。「自分の意見こそが常識的なものであり、他人も道理をわきまえていたら自分と同じように考えるはず」という考え方のことです。
チームでも境界が出来てしまうことは当然の事です。しかし、リーダーはそれらも取りまとめる必要性があります。
「3-3. フレーミングとリーダーのあり方を認識する」にもつながりますが、リーダーとメンバーの双方向のコミュニケーションがバランスよく混ざっている組織が力を発揮しますので、それぞれの意見を元に話し合い、継続的な対話と内省こそが、リーダーシップによる一体感を支えると共に、つくり出すものでもあります。
3-5. チームを横断した文化的つながりをもつ
チームの知識や技術を高めるため、積極的に他チームと情報交換をすることも求められます。
チームの方針や進捗状況について他チームから客観的な意見をもらうことで、チーム内だけでは気づくことができなかった視点に気がつくことができ、新たな発展へとつながります。
4. チーミングで学習する組織を作るために

冒頭で話したように近年は時代の変化が激しいです。そんな時代に柔軟なチームであるために、最適なチームワークを絶え間なく模索する必要があります。
そのようなチームワークを模索しつづける組織は、学習する組織として定義されています。ここでは、学習する組織を作るためにやるべきことにを解説していきます。
4-1. 学習する組織の意味
学習する組織とは、従業員一人ひとりが個人やチームとして、効果的に変化をつくり続ける組織のことを指しています。
環境に迅速に適応する適応性、そして自ら学び、創造し、デザインし、進化する自己組織化することが大切になってきます。
こうした能力を組織が身につけることによって、長期にわたって持続的にパフォーマンスを出しつづけることができます。
4-2. 学習する組織の目的
学習する組織の目的は、チームのパフォーマンス向上です。個々が学習するだけではなく、その学習の成果をチームに反映することが求められます。
インターネットの普及により情報の拡散や上書きのスピードが速まったため、既存のやり方やチームの方針に固執せずに、新たな方法を模索しつづけることでチームのパフォーマンスを向上させることが可能になってきます。
4-3. 組織として学習するべき領域
組織が学ぶべき領域を5つに分類したものを「ディシプリン」といいます。
ディシプリンは直訳すると「規律」という意味に訳されますが、組織が学習する領域としては、「学習して実践されるべき理論や技術」という意味として使われています。
ここでは5つのディシプリンについて詳しく解説します。
①システム思考
システム思考とは、解決するべき課題をシステムと見なし、多角的な見方で原因特定やその解決を目指すことです。
複雑な物事を構造的に理解しようとするもので、ほかの4つの要素を統合する役割をもつ基礎的な能力です。システム思考では、目の前の課題だけではなく、全体を俯瞰して各要素のつながりにも着目します。
そのため、1つの視点からだけでは読み解くことができない複雑な課題に対する対応力の向上が期待できます。システム思考によって客観的な視点で柔軟な考え方ができるようになるため、異なる考え方や意見をもった人とも互いの意見を尊重しながらつき合えるようになります。
②自己実現
自己実現とは、各従業員が自分の業務や役割を望ましい方向へ広げていくことです。 自分で理想を思想し、現状の自分の知識や立ち位置を理解し、その差を埋めるための必要な要素を見つけていく必要があります。
チームメンバーが自己実現を重要視するようになると、それぞれが内発的な動機で主体的に業務に取り組むようになります。 現在の自分と理想の自分を比較し、今の自分に必要な要素を身につけるために学び続けるようにもなるため、個人の成長が期待されます。
結果的にチーム全体のモチベーションが向上し、高いパフォーマンスが発揮できるようになります。 また、チームメンバーがチーム内でなりたい自分に近づけるような役割分担やチーム編成がされていることも重要になります。
③メンタルモデル
メンタルモデルとは、個人の心の根底にぶれずに固定化されたイメージや考え方のことです。心の奥深くにあるため、周囲からも捉えにくいだけでなく本人でさえも認識できないものがほとんどです。
メンタルモデルは思考のもっとも核となる部分で、個々の行動特性や発言の傾向を生み出しています。メンタルモデルはいわば個人を形作る肝となるため、変えることは困難になります。
そのため、チームメンバーのメンタルモデルを認識した上で、組織の方向性や成長を決定づける必要があるでしょう。
④ビジョン
チームとして共有されたビジョンが明確であり、そのビジョンにチームメンバーが賛同できているかどうかはチームの方向性を決定づける上で非常に重要です。
組織には、異なる考え方や価値観をもった人が集まっています。 そのため、皆が自分の考えのみに基づいて行動するようになってしまうと、物事における優先順位や業務への取り組み姿勢がバラバラになってしまい、組織としての1つの目標に向かっていくことが難しくなります。
なので全体として共通の明確なビジョンがあり、個々がそのビジョンに従って行動することで、根本的な考え方のすれ違いを防ぐことが可能になります。
組織のビジョン達成の先で、自分の掲げるビジョンも達成できると感じられると、個々の内発的動機づけが促されるので、個々のビジョンについても目を向けることが大切です。
➄チーム学習
学習する組織では、最終的に個人の成長でなくチームとしての成長を目指します。 個人だけでは解決が難しい課題でも、チームが一丸となって取り組むことで、個人での限界を超えて問題解決に近づくことができるようになるのです。
そのため、学習する組織ではチームとして学び合う姿勢は必要不可欠になってきます。チームで対話をし、それぞれの知識や課題に対して意見を交わし合うことによって、より強いチームへ成長することができます。
5. チーミングを実践してチームのパフォーマンス力を高めよう

チーミングについての理解は深まったでしょうか。テレワークにより出社をしないと、チームの目標や個人の目標などが感じられなかったり、共通認識が持てなかったりする可能性があります。
そんな時はリーダーがコミュニケーションを取りやすい環境を作り、チーム内での交流を深めていきましょう。
チーム力の向上は、企業の業績に直結します。チームの在り方に課題を抱えている場合は、チーミングによるチーム構築に取り組んでみてください。







