
MBOとOKRは、目標管理に携わったことがある人は一度は耳にする言葉です。どちらも目標を立ててその達成を目指すことは変わりませんが、実際にどのような違いがあるかとなると理解しきれていない人も多いでしょう。
本記事では、MBOとOKRの違いやそれぞれの特徴、メリット・デメリットなどを詳しく解説していきます。
目次
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. MBOとOKRの違い
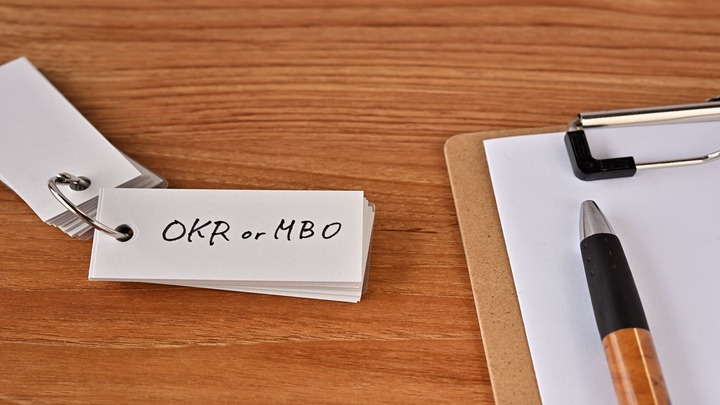
MBOとOKRの目的は、組織・企業の目標と従業員の目標を共通化させることです。
MBOにおいては、組織内での従業員の役割をはっきりさせて自主性を引き出し、貢献度を元に人事評価に反映させます。
一方でOKRでは、難易度の高い目標設定をすることで、従業員個人だけでなく組織全体の飛躍的な向上を図り、結果として目標に対する達成率を人事評価に反映させません。そのため、OKRとMBOの両方を実施している会社もあります。
MBOとOKRは、以下の点で大きく異なります。
- 目標の共有範囲
- 目標の達成状況に対する評価・目標の立て直しの頻度
- 評価の基準と計測方法
MBOは、あくまで上司と部下である従業員との間で個人目標を共有します。共有された目標は人事評価のほか、人材育成の指標として使われることもあります。
一方のOKRは、組織や企業全体で個人目標を共有するのが一般的です。組織や企業、各従業員の目標や成果指標を共有するため、企業全体のコミュニケーションが活性化しやすいでしょう。
また、MBOでは半年もしくは1年ほどの周期で評価をおこないます。OKRでは企業によって異なるものの、長くても3カ月(四半期)ごとに評価と目標の再立案を実施するのが一般的です。OKRは、目まぐるしく状況が変化する事業で多く取り入れられています。
MBOは企業ごとに基準が異なり、OKRは定数化された目標で客観的に測定できます。また、MBOの場合、理想的な達成率は100%です。一方、OKRの目標設定は難易度が高い傾向にあり、達成率は60~70%が理想とされます。
1-1. MBOとは目標管理制度のこと
MBOは「Management By Objectives(目標による管理)」を略したものです。MBOは「個人もしくはチーム自ら目標を設定して申告してもらい、目標の進捗を管理しつつ生産性を高めること」を意味します。つまり、あくまでも従業員が自主的に業務に取り組むよう促す仕組みです。
従業員は会社全体の成績向上を目指し、貢献できることを目標として設定します。従業員はどれだけ目標を達成できたかで評価されるため、モチベーションアップや生産性の向上など、さまざまな効果を期待できる点が特徴です。
MBOは「組織活性型」「人事評価型」「課題達成型」に大別されます。どのタイプを選んで取り入れるかは、組織や企業で異なります。
1-2. OKRとは目標管理手法のひとつ
OKRは「Objectives and Key Results(目的と主要な結果)」を略したものです。
企業やチーム、従業員などの方向性をまとめて、一丸となって目標達成を目指します。全体のモチベーションを上げるような目標を設定し、加えて進捗を図るための具体的な数値を設定します。
さらに、目標設定と進捗確認、評価という一連の流れを高頻度でおこなうことでスピード感のある対応が可能となるところが特徴です。
OKRを運用する場合、まずはシンプルでわかりやすく定性的な目標を立てます。組織や企業の目標をもとにチーム・従業員の目標を設定していき、組織や企業全体の業務効率や生産性のアップを目指します。
OKRでは、目標の進捗を測る指標として2〜5個のKey Results(主要な結果)を設定するのも特徴です。困難だが不可能ではないレベルの「ストレッチゴール」と呼ばれる目標を設定し、60~70%の達成率で成功と見なします。
2. MBOのメリット・デメリット

MBOは確かに優れた目標管理手法です。しかし、メリットがあればデメリットもあります。ここでは、MBOのメリットとデメリットを確認してみましょう。
2-1. MBOのメリット
MBOのメリットは、以下の通りです。
- 従業員の自己管理能力が向上する
- 従業員の育成につながる
- 従業員のモチベーションが向上する
従業員の自己管理能力が向上する
MBOの目標は、あくまで従業員自ら立てることが基本となっています。上司がサポートするケースもありますが、目標を達成するまでの手順や達成期限も従業員が自分で考えます。
結果として自己目標の達成のために必要なものを考え、自ら行動を起こす自己管理能力が自然と身につくのです。
従業員の育成につながる
従業員を効率よく育成できることもMBOのメリットです。MBOでは従業員一人ひとりが個人目標を達成し、課題を分析したりスキルを身に着けたりすることから、従業員の人材育成につながります。
従業員のモチベーションが向上する
自己目標の達成を目指すために、それぞれの従業員が自主性を発揮することで、モチベーションが向上する点もMBOのメリットです。
とくに人事評価型の場合は、目標の達成度やそれまでのプロセスをもとに評価を下します。基本的に目標は客観的なものに定められるため、評価基準も明確です。
2-2. MBOのデメリット
一方、MBOには以下のようなデメリットもあります。
- 職種によっては客観性のある目標を設定できるとは限らない
- 従業員のモチベーション低下を招くことがある
- 簡単な目標ばかりになってしまうことがある
職種によっては客観性のある目標を設定できるとは限らない
人事や総務のように成果を数値化しにくい職種の場合、MBOのなかで必ずしも客観性のある目標を設定できるとは限りません。従業員と評価する上司との間で基準に対する認識の乖離があると、信頼関係やモチベーションにも影響します。
従業員のモチベーション低下を招くことがある
企業のビジョンやMBOに関しての従業員の理解が低い場合などは、目標をうまく設定できないことでモチベーション低下を招く恐れがあります。組織と従業員が共通する目標を持つことが重要なため、新入社員などにはMBOをしっかり理解してもらうことが欠かせません。面談を実施して、上司が目標設定をサポートするなどの対応も必要です。
簡単な目標ばかりになってしまうことがある
従業員を評価しやすい人事評価型のMBOを取り入れている場合、目標達成を意識しすぎて簡単に達成できる低レベルな目標を設定しがちです。
逆に、身にあまる高い目標を設定して失敗し、上司から低評価を受けて給与が下がり、結果モチベーションまで下がってしまうこともあります。個人の成果ばかりを追求して協調性が失われる恐れもあります。
適切なレベルの目標を設定できるよう、上司がしっかりと管理することが重要です。
3. OKRのメリット・デメリット
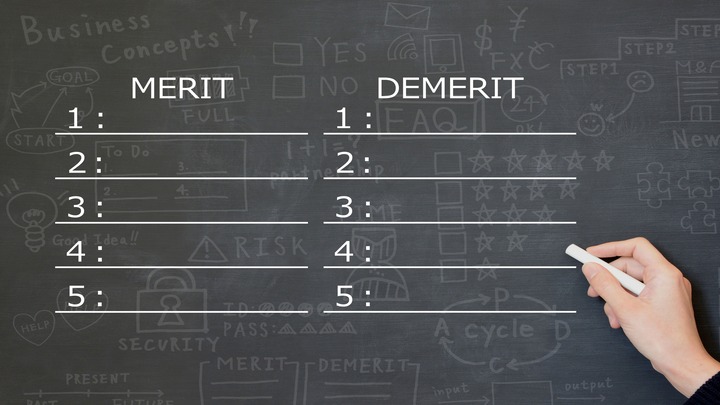
MBOにメリット・デメリットがあるように、OKRにもメリット・デメリットがあります。内容を確認してみましょう。
3-1. OKRのメリット
OKRのメリットは以下の通りです。
- 会社の目標と各従業員の目標を共有できる
- 従業員のモチベーション向上につながる
- 会社全体がまとまりやすくなる
会社の目標と各従業員の目標を共有できる
OKRでは、組織や企業の目標と各従業員の目標を共有できます。こまめに現状を評価する過程で全体を把握できるため、組織や企業と各従業員とがすれ違うことなく、同じ目標に向かいやすいです。
従業員のモチベーション向上につながる
OKRを用いた評価制度は透明性が高いことから、各従業員のモチベーション向上にもつながります。各自の業務がどれだけ目標達成に向けて貢献しているかが見えやすいため、やりがいへとつながるためです。目標を明確化できて業務の優先順位がわかりやすいため、各従業員が行動を組み立てやすくなる点も無視できません。
会社全体がまとまりやすくなる
目標達成のために部署を超えたコミュニケーションが活発になると、組織や企業全体がまとまりやすくなります。
また、OKRならではのルーティーンの短さによって、状況の変化に素早く対応しやすいこともメリットのひとつです。
3-2. OKRのデメリット
OKRのデメリットは、以下の通りです。
- 目標が共有できずかえって効率が悪くなることがある
- 従業員によってはモチベーションが低下する恐れがある
- OKRの回転スピードが合わないケースもある
目標が共有できずかえって効率が悪くなることがある
OKRは、目標達成のために組織や企業で一丸となることが大切です。それだけに組織や企業と部署やチーム、各従業員との間で目標が共有できていないと、効率の悪化を生じかねません。最終的に達成すべき組織や企業の目標と、部署やチーム、各従業員の目標が同じ方向を向いていることを確認することが大切です。
従業員によってはモチベーションが低下する恐れがある
例え目標が一致していても、従業員のモチベーションが下がることもあります。とくに従業員がMBOに慣れている場合などは、目標達成率は100%を目指すことが当たり前です。そのため、ストレスによってモチベーションが下がる危険があります。
OKRの回転スピードが合わないケースもある
業種によっては、OKRの回転スピードが早すぎる場合もあります。導入前に、組織や企業に適したシステム化を検討することなどが重要です。
ここまでMBOやOKRのメリット・デメリットを紹介しましたが、自社適しているかどうか、他の評価指標と比べて考えたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて当サイトでは「人事評価の手引き」という資料を無料配布しており、MBO以外の評価指標の種類や各評価指標のメリット・デメリット、また各評価指標を採用した際の起こりやすいトラブルも紹介しています。自社の企業理念や経営戦略をふまえた上での、自社の企業理念や経営戦略に基づいて、人事評価を選定する際の参考になる内容で、人事評価を導入する際の手引きとしても役立ちます。資料はこちらから無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。
4. MBOとOKRのどちらを採用すべき?

MBOとOKRには、それぞれメリット・デメリットがあるため、どちらを採用すべきかは目的によって異なります。ここでは選び方のポイントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
4-1. チャレンジを促したいならOKR
従業員のチャレンジを促したいなら、OKRを採用すべきでしょう。OKRでは達成するのが難しい目標を設定するため、従業員は目標を達成するための方法を考えながら、試行錯誤しなければなりません。難易度の高い課題に取り組む必要があるため、従業員の新しい挑戦や成長を期待できるでしょう。
ただし、安定志向の企業やチャレンジしにくい業種の場合、OKRがうまく機能しない可能性もあります。適切な目標を設定できなかったり、従業員が不満や戸惑いを感じたりするケースもあるため注意が必要です。
4-2. モチベーションを向上させたいならMBO
従業員のモチベーションを向上させたいなら、MBOのほうが適しているでしょう。OKRとは異なり、MBOでは頑張れば達成できるレベルの目標を設定するため、従業員の努力を促し、仕事への意欲を高めることが可能です。また、人事評価と連動させやすいため、目標管理と人事評価を効率よく運用したい場合はMBOの導入が適しています。
ただし、新入社員が多い場合など、MBOの意味や目的が浸透していないと適切なレベルの目標を設定できないため、必要に応じて面談などを実施してサポートしましょう。
4-3. MBOとOKRを併用することも可能
MBOとOKRのどちらかを導入することも可能ですが、2つの制度を併用するケースもあります。たとえば、MBOによって目標管理と人事評価、待遇の決定をおこない、OKRによって新しいチャレンジを促すといった方法も可能です。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、うまく組み合わせることで自社に合った運用が可能となるでしょう。まずは抱えている課題や今後の展望を明確にして、自社に合った方法で制度を導入することが重要です。
5. MBOとOKRの違いやメリット・デメリットを理解しておこう!

今回は、MBOとOKRの違いや、それぞれの特徴を紹介しました。MBOとOKRのどちらにもメリット・デメリットがあります。企業の目的や業種によって、合う・合わないもあることから、どちらが優れていると一概には言えません。
また、どちらかを導入することも可能ですが、併用するとうまく運用できるケースもあります。MBOやOKRを導入する際は、双方の違いやメリット・デメリットをよく理解し、自社に合った方法で運用していきましょう。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。









