 人事評価がいらない新しい方法として、ノーレイティングが注目を集めています。とはいえ、人事評価が全く不要なわけではありません。
人事評価がいらない新しい方法として、ノーレイティングが注目を集めています。とはいえ、人事評価が全く不要なわけではありません。
ノーレイティングは社員へのランク付けや総合評価を廃止し、頻繁な1on1面談により仕事を評価する方法です。また、目標も1度立てて終わりではなく、状況に則して柔軟に変更します。
本記事では、ノーレイティングとはどのような人事評価方法か、メリット・デメリット、導入の手順やポイント、日本企業の導入事例を解説します。
目次
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. ノーレイティングとは?

まだあまり馴染みのないノーレイティングですが、一体どのような制度なのでしょうか。
1-1. ノーレイティングはランク付けしない新しい人事評価
ノーレイティングとは、社員の業績を採点したりランク付けしたりしない新しい人事評価方法です。年次目標を立てさせて管理することもないため、総合評価もおこないません。
「Rating(レイティング)」には、評価・格付け・採点の意味がありますが、それらをおこなわないのでノーレイティングと呼ばれています。
とはいえ、人事評価が全くいらない制度とは異なります。あくまでも廃止するのは社員へのランク付けだけです。そのため、社員は都度、状況に応じて目標を設定し、上司との頻繁な1on1面談の中で評価が決定されます。
1-2. ノーレイティングが注目される背景
ノーレイティングが注目される理由は、アメリカの大手企業で採用が進んでいるためです。アメリカで導入が進んだ背景には、社員を格付けする従来型の人事評価制度では業績の向上が難しくなっていることが挙げられます。
特に、現代のように市場変化の激しい環境の中では、ランクの降下を恐れて挑戦しない社員が増え、組織全体の停滞を招く可能性があります。そのため、社会の変化にも柔軟に対応でき、評価の透明性も高く、社員それぞれの強みを活かせるノーレイティングが注目を集めているのです。
2. ノーレイティングのメリット

ノーレイティングには、人事評価の納得感が得やすい、上司とのコミュニケーションが深まり、内的動機付けに役立つなどのメリットがあります。それぞれを詳しく見ていきましょう。
2-1. 評価への納得感が得やすい
従来型の人事評価では、評価基準が不明確であったりフィードバックを得られなかったりと不透明な部分が多く、社員の不満の原因になっていました。
しかし、ノーレイティングでは1on1面談をおこない、評価上不明な点があればすぐに確認できます。また、常に目標達成の進捗を上司と共有できるため、評価の理由にも納得感を得やすくなります。
2-2. モチベーションの向上
社員のモチベーションは給与だけでなく、仕事のやりがいや人間関係など、さまざまな要素が関係します。1on1面談を頻繁におこえば上司との信頼関係を構築しやすく、すぐに相談もできます。
また、目標や課題を常に最新の状態に保てるため、自身の成長を実感しやすく、企業への貢献度も分かりやすいのが特徴です。
良好な人間関係や成長の実感などは高いモチベーションを維持するうえで大切な要素となるため、評価方法を変えることで従業員の働き方が変わる可能性もあります。
2-3. 優秀な人材の確保
従来型の人事評価では、成果評価などの一部がよくても総合評価が低ければ成績は上がりません。しかし、企業の問題解決や業績向上に貢献できる可能性のある人材の中には、一部の能力のみが秀でる場合もあります。
ノーレイティングでは社員の能力を型にはめて評価しないため、それぞれの長所を活かした働き方が可能です。そのため、優秀な人材の確保にもつながりやすいでしょう。
3. ノーレイティングのデメリット
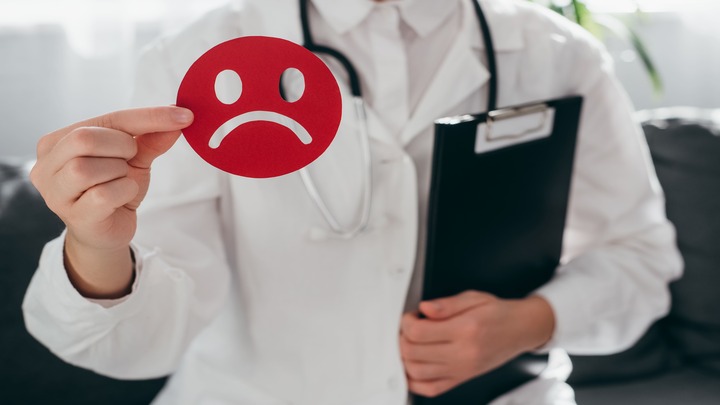
ノーレイティングはモチベーションの向上や人材確保などさまざまなメリットがありますが、デメリットも存在します。ここでは3つのデメリットを紹介します。
3-1. 従来型の評価方法よりも時間や手間がかかる
従来型の評価方法であれば、目標設定・フィードバック・総合評価は年に数回で済みます。しかし、ノーレイティングは月に数回など、頻繁な1on1面談が必要です。さらに、部下の目標も都度確認し、適切なものに変更しなければいけないため、従業員・上司双方にかなりの労力が必要になることは確かです。
3-2. 上司に高い能力が求められる
ノーレイティングの場合、上司には従来型の人事評価以上に高い能力が必要です。社員一人ひとりの目標を把握して達成に導くマネジメント能力、話し合いにより理解を深められるコミュニケーション能力などが求められます。
他にも、好き嫌いで部下を判断しない人間性や論理性などさまざまな能力が備わっていなければ、1on1面談で評価しても部下の納得感は得られず、ノーレイティングが失敗に終わる可能性もあります。
3-3. 上司の裁量が非常に大きい
企業にとってノーレイティングを導入する最大の懸念は、上司の裁量が非常に大きい点です。特に、給与決定権も譲渡するため、中にはプレッシャーを感じる管理職も出てくるでしょう。
また、決定権を不当に利用し、お気に入りの部下に高給を約束するなどの不正に発展する可能性も否めません。
ここまで読んでやはり人事評価を策定する方針で進めたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向け当サイトでは「人事評価の手引き」という資料を無料配布しております。人事評価の種類と各評価指標のメリット・デメリット、また実際に導入する際の評価点数の例なども紹介しており、人事評価を導入する際に、必要な情報をこの資料一つでまとめて確認できます。自社に最適な人事評価を選定するのに大変参考になる資料となっておりますので、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
4. ノーレイティングの導入手順や評価方法、給与との関係性について

ここからは、ノーレイティングの進め方や評価方法を紹介します。
また、ノーレイティングは従来の評価方法と異なるため、給与額の決定にも大きな影響があることを知っておきましょう。
4-1. ノーレイティングの導入手順
ノーレイティングはいつでも気軽に始められる評価制度ではありません。導入には事前の準備が必要になるので、以下の表を参考にしながら段階的に導入しましょう。
| 導入手順 | 具体的な方法や注意点など |
| 課題の分析 |
|
| 信頼関係の構築 |
|
| 評価する(上司)側の意識変革 |
|
| 実施内容の検討 |
|
| 表彰制度の見直し |
|
| 従業員への周知 |
|
| 制度の導入・運用 |
|
| 決定権の譲渡 |
|
4-2. ノーレイティングの評価方法
ノーレイティングでは、年次で目標を設定するのではなく、状況に応じ都度、目標を設定します。また、設定した目標は固定されるわけではなく、臨機応変に変更や再設定も行われます。
また、フィードバックも月に数回、1on1面談で実施します。面談も部下とコミュニケーションを深め、目標の達成状況の確認や相談などが目的です。
評価の際も部下の働きは面談を通して理解できるため、点数を付ける必要はありません。
4-3. ノーレイティングと給与との関係性
従来型の人事評価制度は上司がA~Eなどの評価を行い、ランクに応じた給与が支給される仕組みです。あらかじめランクごとの昇給目安などが定められています。
一方、ノーレイティングでは、給与の決定権限を上司に一任します。上司は人件費予算の中で、それぞれの部下の働きに応じ給与を分配します。
5. ノーレイティングを成功に導くためのポイント

日本企業でノーレイティングを導入するとなれば、既存の人事評価システムを大きく変更し、管理職の育成も必要です。
そのため、まずは1on1面談が所定の回数実行できるかなどを確認し、試験的に小規模で導入したほうがよいでしょう。
5-1. 1on1面談を増やす
ノーレイティングの基本は頻繁な1on1面談です。そのため、まずは、1on1面談を月4回に増やすなど、導入できそうな部分から真似してみましょう。
5-2. 管理職の対応方法を検討する
1on1面談を増やした結果、日常業務が回らないなど多くの問題が生じるでしょう。また、短期目標の設定や改善など、対応課題も明らかとなります。
これらの問題にどのように対処するか、改善方法を蓄積しましょう。
5-3. 一部門など試験的に導入する
ノーレイティングが自社に適しており、管理職の研修や制度の変更など、ある程度展望が見えたら、一部門や子会社など、狭い範囲で試験的に導入します。また、試験導入の際も、賞与は全社統一の指標を使うなど、他の社員と極端な差が生まれないように調整が必要です。
試験工程を経て、業績の向上や社員のモチベーション向上などの効果がみられれば、徐々に導入範囲を広げるとよいでしょう。
6. 日本企業でもノーレイティングは普及するか

現在、ノーレイティングを導入する日本企業は外資系などの一部に限られています。アメリカのように、将来的に普及する可能性はあるものの、現状では年功序列型賃金の名残など、課題も多くあります。
また、管理職に求められる役割が大きく変わる点も課題です。管理職のマネジメントスキルが不足している場合、評価にばらつきが出てしまう可能性もあります。そうなると社員のモチベーション低下も考えられるため、管理職への十分な研修なども必要になってくるでしょう。
7. ノーレイティングを導入している日本企業の事例
お菓子や食品の製造・販売で知られるカルビー株式会社では、すでにノーレイティングを導入しています。具体的には、全従業員が上司・部下のC&A(Commitment & Accountability)を結んでいます。C&Aは日本語で約束と結果責任を意味するもので、企業に対して成果を収め、成果の達成具合によって賞与が決定される仕組みです。
ノーレイティングを導入することで上司と部下の対話や従業員同士の協力が増え、業績アップにつながっているとされています。
8. ノーレイティングによる人事評価は管理職のスキルも重要

ノーレイティングとは、社員をランク付けせず、頻繁な1on1面談を通して仕事を評価していく方法です。また、状況に合わせて目標を柔軟に変更していく点も特徴的です。
日本企業ですぐにノーレイティングを導入するのは難しい部分もありますが、人事評価方法を適宜変更することは評価の公平性を保つためにも大切です。人事評価を効率化して柔軟に運用したい場合は、人事評価が可能な専用システムを活用してもよいでしょう。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。









