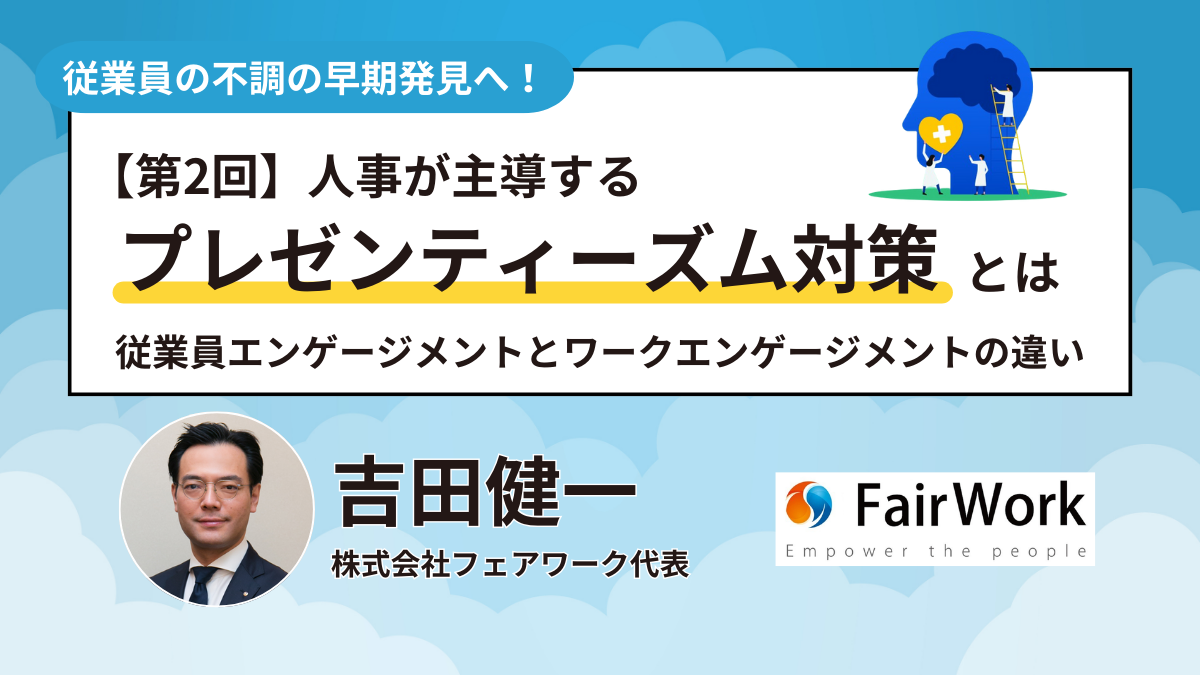 前稿では、「会社に出社しているものの、調子が悪い」という状態である「プレゼンティーイズム」について解説しました。
前稿では、「会社に出社しているものの、調子が悪い」という状態である「プレゼンティーイズム」について解説しました。
さらに、プレゼンティーイズムを可視化するツールとして従業員サーベイがあり、プレゼンティーイズム・アブセンティーイズムやワークエンゲージメント、ヘルスリテラシーなどの項目が測れるものがよいという点をあげました。
本稿では、この「従業員サーベイ」で測定できる数値のうち「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」について解説します。

吉田 健一 | 株式会社フェアワーク代表
株式会社フェアワーク代表。日本医師会認定産業医・精神科専門医・精神保健指定医。1999年千葉大学医学部卒業。千葉県がんセンターと千葉県精神科医療センターの医長を経て医療法人社団惟心会理事長。参議院・国土交通省ほか上場起業など50以上の団体で産業医を経験後、衆参両院や中央省庁にて法定ストレスチェックを受託。2019年株式会社フェアワークを起業。健康経営にフォーカスした組織サーベイ「FairWork survey」を開発し、2021年に経産省後援の「HRテクノロジー大賞」にて注目スタートアップ賞を受賞した。現在はオンライン社内診療所サービスに注力している。
・医療法人社団 惟心会:https://ishinkai.org/
・株式会社フェアワーク:https://fairwork.jp/
目次
1. ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメントの違いを知っていますか?
 皆様は「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」との違いをご存じでしょうか?人事担当になってまだ日が浅い方にとっては、なかなか馴染みのない概念かもしれませんね。
皆様は「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」との違いをご存じでしょうか?人事担当になってまだ日が浅い方にとっては、なかなか馴染みのない概念かもしれませんね。
まず「ワークエンゲージメント」とは、一言でいうと「仕事内容に対してポジティブな感情を持ち、充実した状態」であるかどうかを意味し、「活力」「熱意」「没頭」の3つの側面から構成されます。
たとえば人事の仕事をしている人の場合、「人事という仕事」に対してやりがいや誇りをもって、没頭するように業務に当たる社員のことを「ワークエンゲージメントが高い社員」と定義できます。
一方「従業員エンゲージメント」とは、会社を構成する一人のメンバーとしての愛着心や内発的な貢献欲求を指します。従業員が会社の向かっている方向性や企業理念に共感し、自発的に「会社に貢献したい」と思う意欲のことで、「従業員の企業に対する信頼の度合い」や「従業員と企業との結びつきの強さ」ともいうことができます。
この「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」をどちらを重視するかは、その会社の職場環境や経営方針によって異なる、と言えるでしょう。
2. ワークエンゲージメントが高いはずの保育士のメンタル不調や離職が増えている

私はいくつかの保育園で、顧問医として従業員のみなさんの健康管理に携わっています。
保育士という仕事は国家資格試験に合格しないと従事できない仕事です。したがって、保育士さんたちは学校で専門的な勉強をして、保育士試験を受験して合格しているプロフェッショナルたちであり、職務内容に誇りを持っていることが前提です。
保育士の仕事にやりがいと誇りを持っている、つまりワークエンゲージメントは高い傾向にあるでしょう。
しかし、近年、保育業界においてメンタルに不調を抱える職員が増えているといわれています。私が顧問医を務める保育園を運営する法人でも、ここ10~15年くらいで、働く上で不調を訴える人や、実は不調を抱えながら入職した人が後になって判明するといったケースが見受けられるようになりました。
保育士の仕事に誇りを持っている、つまりワークエンゲージメントが高い状態なのに、なぜメンタル不調や離職につながってしまうのでしょうか。この要因は「従業員エンゲージメント」の側面から分析する必要があります。
ここでは、従業員のみなさんが、勤務先の保育園の経営方針や企業理念に共感しているかどうか、自発的に「会社に貢献したい」と思う意欲を従業員のみなさんがどれくらいもっているのかどうかが論点になります。
従業員エンゲージメントが低い、つまり「この園の運営に貢献したい」とか「もっとこの保育園をよくしていきたい」といった思いが弱いと、別の保育園に転職してしまうかもしれませんね。
したがって、職場環境をよくしていくためには「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」の違いを理解したうえで、みなさんの職場や会社ではどちらのほうをどのように見ていけばよいのか、職場や会社の特徴にあわせて考える必要があるのです。
3. 従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントを従業員サーベイで測定する
 「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」は目に見えるものではありません。そのため、見える化をするためには「従業員サーベイ」を用いて従業員へアンケートをとることが有効な施策の一つです。
「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」は目に見えるものではありません。そのため、見える化をするためには「従業員サーベイ」を用いて従業員へアンケートをとることが有効な施策の一つです。
現在は様々なサービスが提供されていますが、選定基準のひとつとして、経済産業省の定める「健康投資管理会計ガイドライン」に準拠した項目が測定できるものがよいでしょう。
実は「健康投資管理会計」には「ワークエンゲージメント」に関する観点は含まれているのですが、一方「従業員エンゲージメント」に関する観点が入っていません。ガイドライン策定時の委員会に、従業員エンゲージメントの専門家が含まれていなかったことが原因と考えられますが、ともあれ、従業員エンゲージメントも測定できるサーベイを選定すると、上記の実例からしても、より良い結果を得ることができると考えられます。
今後ますます、一つの企業に長年勤め上げるのではなく、転職が当たり前になっていくことを考えると、「ワークエンゲージメント」だけでなく組織への帰属意識をみる「従業員エンゲージメント」も、従業員の定着や働きがい向上を図るうえで重要になってくると予想されるからです。
私が代表を務める株式会社フェアワークの従業員サーベイ「FairWork survey」では、両方のエンゲージメントを測定できる質問から構成しており、「従業員エンゲージメント」は3つ、「ワークエンゲージメント」2つと、計5項目から構成しています。
たとえば「従業員エンゲージメント」を図る質問例としては「組織の目指す方向性を理解し、納得し、賛同できている」というものがあり、これらの質問に「全くそう思わない」から「強くそう思う」の5段階で従業員の方にチェックしてもらいます。
次に、「ワークエンゲージメント」を図る質問例としては「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」というものがあり、これらの質問にも、「全くそう思わない」から「強くそう思う」の5段階で従業員の方にチェックしてもらいます。
他の質問が気になる方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
4. まとめ
 いかがでしょうか。「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」それぞれどういった状態を指しているのかご理解いただけたのではないかと思います。
いかがでしょうか。「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」それぞれどういった状態を指しているのかご理解いただけたのではないかと思います。
これらの質問を活用して数ヶ月に一度の定点観測をすることで、従業員のみなさんの「ワークエンゲージメント」や「従業員エンゲージメント」がどのように変化しているのかを見える化することができます。どちらがどのように変化しているのか、また人事担当者のみなさんが属する企業の特徴によって、結果を踏まえてどのような改善施策を取るのかも異なってくるでしょう。
最後に、従業員サーベイの結果はやりっぱなしにするのではなく、結果を踏まえて組織改善のためのPDCAを回すことが必要です。サーベイの結果から考察を得て、新たな施策を打ち出し実行する、その効果測定としてまたサーベイを参照する。このようなPDCAをしっかり回すことで、社員がよりいきいきと働ける組織につながり、ワークエンゲージメントや従業員エンゲージメントの向上にもつながるのです。







