
「クラッシャー上司はクビにできる?」
「クラッシャー上司はクビ以外にどのような対応ができる?」
クラッシャー上司の対応に悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
クラッシャー上司は、部下に対して過度なプレッシャーをかけたり、ハラスメントをおこなったりして、職場環境を悪化させる上司です。
クラッシャー上司の存在は、従業員のメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、最悪の場合は退職者の増加や企業の低評価につながる可能性があります。企業はクラッシャー上司に対して、適切な対応をおこなわなければなりません。
本記事では、クラッシャー上司をクビにできるかどうか、できる要件や流れを解説します。企業は適切な対応をおこない、段階的に処分を検討しましょう。
従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
目次
1. クラッシャー上司をクビにできるかどうかは状況による

クラッシャー上司をクビ(懲戒解雇)にできるかどうかは、状況によります。従業員を懲戒解雇できる条件は厳格に制限されており、必要な要件を満たしていなければならないためです。
そのため、クラッシャー上司に問題があったとしても、企業側が適切な手続きを踏まなければ不当解雇とみなされる可能性があります。
懲戒解雇は、従業員にとって最も重い処分です。企業が一方的に解雇するもので、退職金が不支給になるケースも珍しくありません。
解雇した従業員の再就職にも大きな影響を与えるため、企業は慎重に対応する必要があります。
2. クラッシャー上司をクビ(懲戒解雇)にできる要件

クラッシャー上司を懲戒解雇にできる要件は、以下のとおりです。
- 就業規則に懲戒解雇の規定がある
- 問題行動の事実と証拠がある
- 適切な手続きを踏んでいる
- 権利濫用ではなく合理的な判断である
2-1. 就業規則に懲戒解雇の規定がある
就業規則に懲戒解雇の規定があることが、条件の一つです。また、就業規則はすべての従業員に周知しておく必要があります。
懲戒解雇に関する事由を就業規則に明記していなかった場合、懲戒解雇ができない可能性が高くなるため注意が必要です。そのため、自社の就業規則を見直し、必要に応じて改訂しなければなりません。
就業規則に明記していなかった場合、普通解雇はできますが、退職金の支払い義務が発生します。
2-2. 問題行動の事実と証拠がある
パワハラやセクハラなど、クラッシャー上司の問題行動の事実と証拠がなければ解雇できません。第三者がみてもわかりやすい、以下のような事実が必要です。
- 被害者の証言
- 録音や録画データ
- メールやチャットの履歴
- 第三者の証言
事実を確認する際は、中立な立場で慎重に判断しなければなりません。
厳しい指導であっても、正当性が認められればハラスメントに該当しないことを留意しておくことが大切です。従業員によっては、厳しい指導をパワハラと捉えることもあるでしょう。
詳しく調査をせずにハラスメントと認識して懲戒解雇すると、不当解雇とみなされる可能性があります。
2-3. 適切な手続きを踏んでいる
懲戒解雇をおこなう際は、適切な手続きを踏んでいなければなりません。再発防止の指導や注意喚起、降格処分、弁解機会を付与しているかなどが挙げられます。
とくに重要視されるのは、クラッシャー上司に弁解の機会を与えているかどうかです。クラッシャー上司の話を聞かずに懲戒解雇をすると、無効となる場合があります。
2-4. 権利濫用ではなく合理的な判断である
権利濫用ではなく、合理的な判断のもと懲戒解雇の判断をしなければなりません。客観的にみて合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合は無効になります。
社内の過去の事例や、同業他社の扱いと比較してバランスが取れているかどうか確認しておくことも大切です。
3. クラッシャー上司をクビ(懲戒解雇)にするまでの流れ
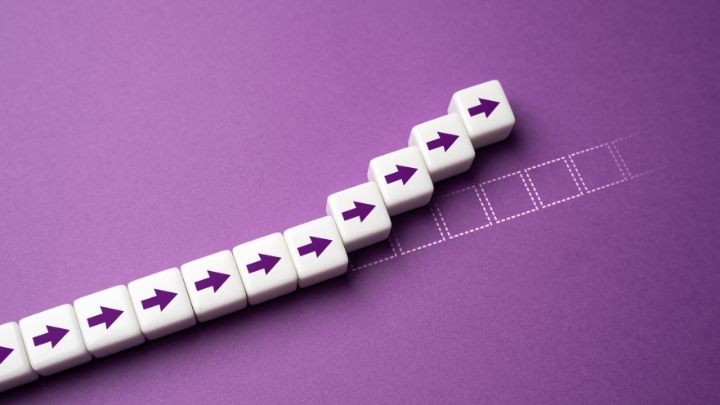
クラッシャー上司を懲戒解雇にするまでの流れは、以下のとおりです。
- 事実関係の調査
- 弁解機会の付与
- 処分内容の検討と決定
- 解雇予告
3-1. 事実関係の調査
被害者から相談を受けたら、事実関係を調査します。被害者とクラッシャー上司の双方からヒアリングをおこない、問題行動が本当にあったかどうかを確認しましょう。
当事者だけでなく、関係者からの客観的な状況証拠の確認も必要です。事実を整理し、記録を残しておきましょう。
調査結果をもとにクラッシャー上司の処分が決まるため、第三者の立場から公正かつ慎重な判断をしなければなりません。
3-2. 弁解機会の付与
処分に先立ち、クラッシャー上司に弁解の機会を付与します。とくに、就業規則に弁解の機会を付与することを明記している場合は、必ずおこなわなければなりません。
弁解の機会を与えない場合、懲戒解雇が無効になる可能性が高くなります。就業規則に明記していない場合でも、労使間トラブルを避けるために、弁解の機会を与えるとよいでしょう。
書面で弁解の機会を与えることもありますが、面談をおこなうのが一般的です。面談をおこなう場合は、面談内容を正確に記録しておきましょう。
クラッシャー上司の反省の弁があるなど、場合によっては処分が軽くなるケースもあります。
3-3. 処分内容の検討と決定
調査結果や、クラッシャー上司の弁解内容をもとに、就業規則に明示された懲戒事由に合致するかどうか検討し、処分を決定します。処分内容が妥当であるか、情状酌量の余地はあるかなど、慎重に判断しましょう。
状況に応じて、専門家の意見を取り入れながら処分を検討することもあります。最終的な判断は、複数人で協議のうえ決定することが一般的です。
3-4. 解雇予告
懲戒解雇が決定した場合は、クラッシャー上司本人に解雇通知をおこないます。懲戒処分の事由や就業規則の根拠、処分の内容などについて明記した書面の作成が必要です。
解雇する際は、少なくとも30日前に予告しなければならないと、労働基準法第20条で定められています。予告せずに解雇する場合、30日以上の平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、重大な問題行動であり、合理的な理由と社会通念上の相当性がある場合は、労働基準監督署に申請することで解雇予告除外認定を受けられます。解雇予告除外認定の許可を受ければ、予告なしで解雇可能です。
4. クラッシャー上司をクビにする以外に企業ができる対応

クラッシャー上司をクビにする以外に企業ができる対応は、以下のとおりです。
|
処分 |
内容 |
|
戒告・けん責 |
・口頭や文書での厳重注意 ・始末書を提出させ問題行動を繰り返さないことを誓約させる |
|
減給 |
・従業員の給与から一定額を差し引く ・平均賃金の1日分の5割を超えない範囲 |
|
出勤停止 |
・従業員の出勤を一定期間停止する ・出勤禁止期間は無給 |
|
降格 |
・従業員の役職などを引き下げる処分 ・降格に伴い、手当が減額される |
|
論旨退職(論旨解雇) |
・退職届を提出させて解雇する処分 ・退職届の提出がない場合は懲戒解雇 |
|
懲戒解雇 |
・企業が一方的に従業員を解雇する ・最も重い処分 |
上記の処分以外の対応として、配置転換をして被害者と引き離す方法もあります。物理的な距離を置くことで、被害の拡大を防げるでしょう。
ただし、ターゲットが変わるだけで根本的な解決には至らない可能性も考えられます。そのためクラッシャー上司に対して、相応の処分を検討した方がよいでしょう。
5. クラッシャー上司を雇用し続けるリスク

クラッシャー上司を雇用し続けるリスクは、以下のとおりです。
- 退職者の増加
- 生産性の低下
- 企業イメージの低下
5-1. 退職者の増加
クラッシャー上司を雇用し続けると、退職者が増加するリスクがあります。従業員が、心身の体調を崩さないよう転職を検討するためです。
そのため、問題を放置していると優秀な従業員が次々と退職するリスクが考えられます。クラッシャー上司の問題行動が社外に漏れると、企業イメージが悪化するため、採用活動にも悪影響を与えるでしょう。
5-2. 生産性の低下
クラッシャー上司を雇用し続けると、企業全体の生産性が低下するリスクがあります。クラッシャー上司は自分が正しいと考えており、他人の意見や価値観を否定する傾向にあるためです。
部下はクラッシャー上司に従うだけになり、仕事がしづらくなるでしょう。高圧的な態度は部下を萎縮させるだけではなく、新たなアイディアも生まれにくくなります。
また、自分が標的にされていなくても、周りの従業員は不快に思うでしょう。クラッシャー上司の存在は職場全体の雰囲気を悪化させ、周りの従業員のモチベーションも下げます。
さらに、問題を放置し続ける企業に不信感が生まれ、仕事への意欲を失う従業員も出てくる可能性もあるでしょう。
5-3. 企業イメージの低下
クラッシャー上司を雇用し続けていると、企業イメージが低下するリスクがあります。SNSや口コミなどを通じて、情報が外部に漏れる可能性があるためです。
従業員の不満や退職者が多い企業は、いわゆる「ブラック企業」のイメージがつきます。さらに、クラッシャー上司の問題が訴訟トラブルに発展した場合、ネガティブなイメージがつくことは避けられません。
6. クラッシャー上司は段階を踏んでクビを検討しよう

クラッシャー上司を雇用し続けると、生産性の低下や退職者の増加、さらには企業イメージが悪化するリスクがあります。とはいえ、無作為に懲戒解雇にすると不当解雇とみなされる場合があるため、企業は適切な手続きを踏まなければなりません。
まずは、注意喚起や配置転換などの対応をおこない、改善されない場合は最終手段として解雇を検討することが重要です。
職場環境の改善を最優先に考え、適切なプロセスを踏んで対応しましょう。
従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。








