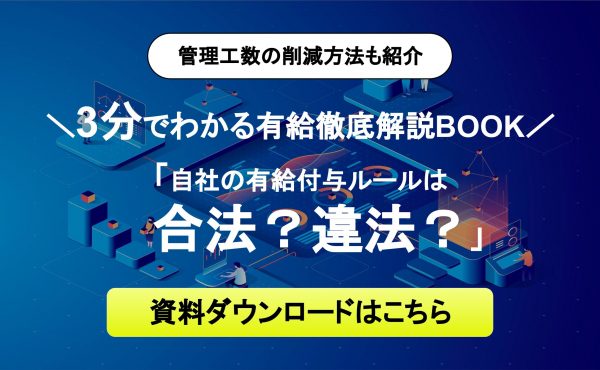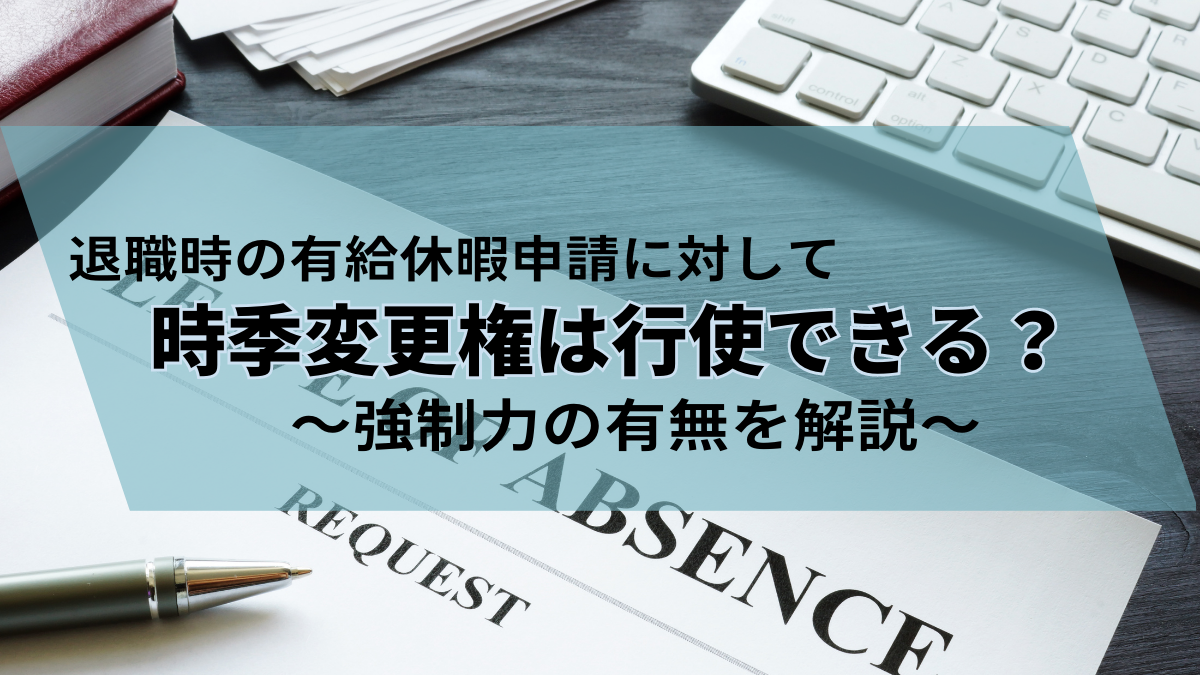
従業員が退職することとなった時には消化していない有給休暇をまとめて最後に消化して退職するケースが多々あります。退職時までにコンスタントに消化していなければ、1ヵ月近く有給が残っていることもあるでしょう。退職時にまとめて消化する場合、業務の引き継ぎなどにも大きな支障を及ぼすことがあるでしょう。
事業の正常な運営に支障をきたすとして、時季変更権を行使する方法もありますが、退職が決まっている従業員に行使することはできるのでしょうか。
本記事では、退職者に対する時季変更権行使の可否やトラブル防止法について詳しく解説します。
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 退職日までに全ての有給休暇を取得させるのが原則

有給休暇とは、条件を満たした労働者全員に認められている権利です。労働基準法第39条第1項、第5項により、使用者は労働者が請求する時期に有給休暇を与えなければならないとされています。
これは、退職日が決まっている従業員に対しても同様です。退職者が有給休暇の取得を申請してきた場合、会社側は申請に応じて取得させるのが原則です。
しかしながら、有給休暇を退職前に長期間取られると、業務の引き継ぎなどに支障が出ることも考えられます。会社側には有給休暇の取得時季を変更できる「時季変更権」があるのですが、退職時に行使することは可能なのでしょうか?
1-1. 退職時の有給休暇申請に対して時季変更権は行使できる?
仮に、退職者が退職の申し出をした日から有給休暇を40日間連続で取得すると、業務に大きな支障が出てしまう恐れもあります。
このような場合、業務の引き継ぎなどをおこなうために取得時季を変更してもらいたいと考えるかもしれませんが、時季変更を申し出ても退職日が迫っているため、変更日を確保できません。
退職者の場合、退職日までの勤務日が限られているため、時季変更権を行使するのは実際のところ難しいでしょう。従業員には、退職する時には、業務の引継ぎなども発生することが必要であることを普段の社員教育で認識してもらうことや退職直前に大量の有給が残ってしまっているという状況にならないようできる限り計画的に有給休暇を取得してもらうことも大切でしょう。
2. そもそも年次有給休暇の時季変更権とは?

時季変更権とは、企業が従業員の有給休暇取得時季を変更できる権利です。ただ、原則として有給休暇を希望の時季に取得することは従業員の権利であるため、事業の正常な運営を妨げない場合、従業員が有給休暇を取得することに対して、会社側はこれを拒否することができません。
しかし、事業の正常な運営に支障が出るとみなされる場合に限り、従業員の有給休暇の時季を変更することができます。これを時季変更権といいます。
3. 有給休暇の時季変更をしなければならなくなる理由

本来であれば、従業員に有給休暇を消化させ、円満に退職してもらいたいところです。しかし、場合によっては会社側にも退職者に対して時季変更権を行使せざるを得ない事情があります。次に、会社側が時季変更権を行使しなければならなくなる理由についてみていきましょう。
3-1. 繁忙期で業務に支障をきたす可能性がある
繁忙期に従業員から退職の申し出があった場合、代わりの要員がすぐに見つかれば良いですが、業務内容によっては急に退職されると非常に困るケースもあるでしょう。
しかし、このケースでは、退職者が退職日までに残っている有給休暇を消化したいと申出があると、会社側は時季変更権を行使することが難しいでしょう。
時季変更権の行使に当たっては、事業の正常な運営に支障をきたすとみなされる事由が必要で、繁忙期だけを理由に行使するのは不当とされる可能性があります。権利を行使する前に、代替人員を確保するなどの努力をしたという事実も必要ですが、何より退職予定者に対しては、時季変更権を行使した場合の変更できる日がない可能性があります。そのため退職が決まっている従業員への時季変更権の行使は通常の従業員に対して行う時季変更権よりもさらに難しくなります。
また、前述のように、時季変更権は有給休暇の取得日を変更するという趣旨の権利ですので、代わりに有給休暇を取得できる日がほとんどないようであれば、行使することができない可能性が高いでしょう。
3-2. 業務の引き継ぎが終わっていない
従業員が急に退職することが決まった場合、業務の引き継ぎがすぐにはできないケースがあります。業務を引き継ぎしないまま退職されてしまっては、後任者や部署、また会社にとっても大きな痛手となります。これにより、業務が遂行できず、顧客対応などに影響を及ぼす可能性があります。
この場合、時季変更権を行使するケースもありますが、前述の繁忙期のケースと同様、有給休暇の取得日を変更できる日がないようであれば難しいでしょう。
退職者に業務の引継ぎの必要を理解してもらい、有給休暇を分割で取得してもらったり、退職日を調整してもらったりすることを検討してみる必要があります。
また、企業側はあらかじめ退職者との引き継ぎのスケジュールを明確にし、就業規則に引き継ぎに関する方針を盛り込むことで、事前にこうした問題を回避することが重要です。 このような取り組みが、円滑な業務運営に寄与し、自社の信頼性を高めることになります。
3-3. 後任者が決まっていない
退職者が特別な役割や仕事に従事していた場合、後任者を探すのが難しいケースもあるでしょう。急に退職が決まった場合は、なおさらです。
後任者が決まるまで退職日を引き延ばしてもらうのがベターですが、会社側でそれを強制することはできません。また、退職者に対して時季変更権を行使するのも難しいため、有給休暇の取得を拒否することもできないでしょう。
この場合には、退職者に業務フローがわかるマニュアルを作成してもらうなど、後任者が決まってからスムーズに移行できるような準備をしておくのが良いでしょう。
4. 退職時の有給休暇申請でのトラブル防止法

時季変更権が使えない場合、業務に支障が出ないようトラブル回避するために、他にどのような方法があるでしょうか。ここでは、退職時の有給休暇申請でのトラブル防止法について紹介します。
4-1. 有給休暇の計画的付与を活用する
有給休暇の計画的付与とは、前もって有給休暇の取得日を決めておき、計画的に取得させる制度です。有給休暇の付与日数から5日を除いた日数が対象となります。
この制度をうまく活用することで、退職時にまとめて有給休暇を取得されるリスクをなくすことができます。
有給休暇の計画的付与を導入するにあたっては、労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定(労使協定のこと)を結びましょう。労使協定で計画年休についての取り決めをしたことについて就業規則へ明記し、運用していきましょう。
休暇の設定方法には、全社で一斉に休暇を取得する「一斉付与方式」、班やチーム別に交替で休暇を取得する「交替制付与方式」、取得計画に基づき個人ごとに取得する「個人別付与方式」の3方式があります。
計画的付与を利用することで、年5日の取得義務にも対応できるため、有給休暇の取得率が低い場合は導入を検討してみるとよいでしょう。
4-2. 就業規則に退職時の引き継ぎについて明記しておく
有給休暇を取得することは従業員の権利ではあるものの、業務の引き継ぎがなされないまま有給休暇を消化して退職されてしまっては、会社としても業務に大きな支障が出てしまいます。
これを回避するための手段として、あらかじめ就業規則に明記しておく方法があります。
「退職の日までに業務の引き継ぎを完了させ支障がないようにする」といったように、退職事項に業務の引き継ぎについて記載しておくことで、従業員の意識付けにも効果が期待できるでしょう。
4-3. 普段から有給休暇を取りやすい環境を整えておく
退職者が長期的に有給休暇をまとめて取得する要因のひとつとして、有給が取得しづらい職場環境であることが考えられます。このため、普段取得できなかった有給休暇を、やむを得ず退職時に取らざるを得ない状況になっている可能性もあります。
退職時に長期間まとめて取得されるのを防止するという観点からも、普段から有給休暇を取りやすい職場環境に整備しておくことが重要です。
たとえば、業務の役割分担を見直しする、1人が休んでも他の従業員でカバーできる体制を整えるなど、有給休暇を取りやすい環境を作ることが必要でしょう。
5. 退職時以外で有給休暇の時季変更権の行使が認められないケース

退職時以外にも、時季変更権を行使できないケースはあります。以下、具体例を紹介しますので、トラブルを防止するためにも理解を深めておきましょう。
5-1. 解雇直前に有給休暇を取得するケース
解雇予定日が決まっている場合、解雇予定日を過ぎた日を有給の変更日として指定すること(時季変更)はできません。普通解雇や整理解雇、会社の倒産が決まっている場合でも、有給休暇は予定日までに消化しなければなりません。
また、懲戒解雇で即時解雇の場合は、解雇が通知された瞬間に有給休暇を取得する権利が消滅します。解雇日以降に有給休暇の消化はできませんし、買い取りの義務もありません。そのため、時季指定権の行使も不可能です。
5-2. 有給休暇の計画的付与をおこなっているケース
前述の通り、有給休暇の消化を促進するため、取得日を労使間で事前に決めておくことも可能です。ただし、計画的付与によって事前に取得時季を決めている場合は、時季変更権を行使できません。会社側から変更を申し出ることはもちろん、基本的には従業員側から変更の申請をおこなうこともできないため注意しましょう。
計画的付与において取得日の変更を可能とするためには、「やむを得ない事情がある場合に限り、計画年休取得日を変更できる」といった労使協定を結んでおく必要があります。
5-3. 育児休業・産後休業期間内の日へ変更するケース
有給休暇を取得できるのは、労働の義務がある日のみです。つまり、時季変更により代わりの日を指定する際は、労働の義務がある日を選ばなければなりません。
たとえば育児休業や産後休業の期間中は労働の義務がないため、代わりに取得する日として指定しないようにしましょう。
6. 有給休暇の時季変更権は退職者に対して基本的には行使できない

時季変更権は、事業の正常な運営に支障が出る場合に行使できる権利ではありますが、退職者のように、有給休暇の取得日が限られているような場合は、時季変更権を事実上行使できないケースもあります。
繁忙期や業務の引き継ぎなど業務に支障が及ぶ場合、会社としても退職者に有給休暇を取得されると困るケースもあります。
そのようなことにならないためにも、企業は有給休暇の計画的付与や退職時の業務引き継ぎについて就業規則に定めるなどの方法によって、あらかじめトラブルを回避する対策を講じることが重要です。
改めて、有給休暇が計画的に取得できている状況であるかどうか、就業規則に問題がないかどうかなどを確認してみましょう。
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。