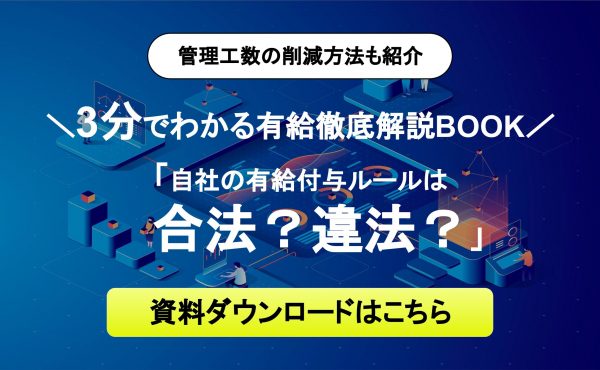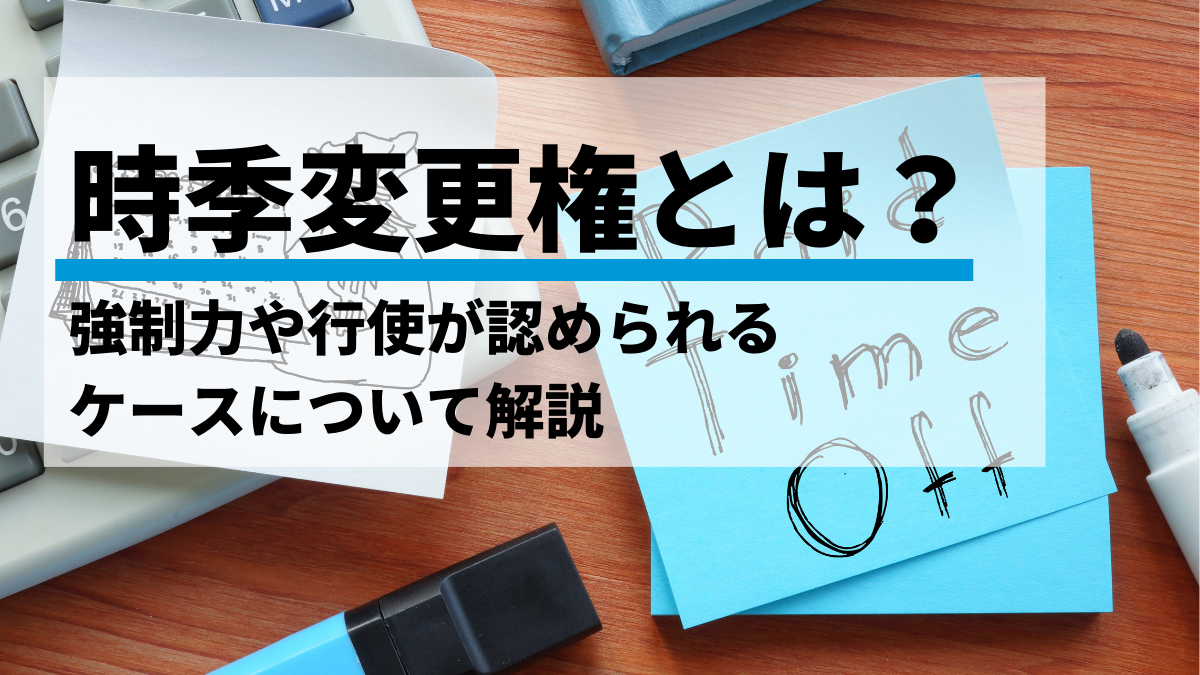
有給休暇の取得は労働者の権利であるため、申請を拒否することは原則できません。
しかし、会社としては繁忙期などに有給休暇を取得されると、正常な事業の運営に支障が及ぶ場合もあるでしょう。そのようなときに行使できるのが時季変更権です。ただし、時季変更権を行使するには一定の条件を満たす必要があります。
本記事では、時季変更権の強制力や行使が認められるケースについて詳しく解説します。
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 有給休暇の時季変更権とは
 時季変更権とは、従業員が希望する日に有給休暇を取得されると、事業の正常な運営に支障をきたすと判断される場合に、有給休暇の取得日を変更することができる権利です。従業員の有給休暇取得について「拒否」するのでなく、「時季を変更させること」ができる権利なので、正しく意味を理解することが大切です。
時季変更権とは、従業員が希望する日に有給休暇を取得されると、事業の正常な運営に支障をきたすと判断される場合に、有給休暇の取得日を変更することができる権利です。従業員の有給休暇取得について「拒否」するのでなく、「時季を変更させること」ができる権利なので、正しく意味を理解することが大切です。
1-1. 時季変更権を行使できるタイミングは限られている
そもそも有給休暇とは、労働者が心身のリフレッシュを図り健康を維持するための休暇で、労働基準法第39条でも取得する権利が認められています。また、労働基準法第39条第5項により、有給休暇は使用者の指定によるものではなく、労働者が希望する日に与えなければなりません。
しかし、多くの従業員が繁忙期に集中して有給休暇を取得してしまうと、営業が危ぶまれることも想定されます。このため、事業を正常に運営するためにも、使用者に時季変更権が認められているのです。
1-2. 時季変更権を行使するためには客観的な理由が必要
使用者が時季変更権を行使するには、事業の正常な運営に支障をきたすと客観的に認められるだけの事由が必要です。
さらに、時季変更権を行使する前に、使用者は従業員が希望した日に有給休暇を取得できるよう勤務計画表を作成したり、代替人員を確保したりといった努力も求められます。
安易に「事業の正常な運営」だけを理由として、従業員へ無制限に行使して良い権利ではないのです。場合によっては、罰則を科せられることもあるので注意しましょう。
時季変更権を行使するにあたっては、あらかじめルールをきちんと把握したうえで、慎重に判断しなければなりません。
1-3. 時季変更権と時季指定権の違い
時季変更権と似た用語に、時季指定権があります。2つの言葉は似ていますが、別物です。
時季指定権とは、従業員が有給休暇の取得日を指定できる権利のことです。「時季指定権」により、使用者は「時季変更権」を行使しない限り、従業員が指定した日に有給休暇を付与しなければなりません。
このように、時季変更権と時季指定権の意味は異なります。時季変更権は「使用者」、時季指定権は「従業員」にあると考えれば理解しやすいかもしれません。
年次有給休暇の時季指定義務
年次有給休暇の時季指定義務について説明します。使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、毎年5日分の有給休暇について時季を指定して与える必要があります。
ただし、労働者が希望する取得時季や、計画的に付与された年休の日数については、この指定義務は適用されません。要は、労働者が年5日の有給休暇を取得出来ていない場合に、使用者が労働者と相談したうえ、有給を取得させるため時季を指定して休んでもらうために行うものです。
また、年次有給休暇の管理に際しては、時季や日数、基準日を労働者ごとに明確に記録した年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。これにより、使用者は適切な管理が義務付けられ、労働者側も自分の権利を把握しやすくなります。
1-4. 時季変更権は労働基準法第39条5項に定められている
時季変更権は、労働基準法第39条5項に定められています。
⑤使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
引用:労働基準法第39条5項|e-Gov法令検索
公務員の時季変更権
国家公務員一般職では、時季変更の制度はありません。これに対し、地方公務員一般職には労働基準法第39条が適用されるため、有給休暇の取得日を指定して申請することが可能です。この場合、使用者は事業のために必要があると認められた場合に限り、時季変更権を行使することができます。
参考:一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律|e-Gov法令検索
2. 有給休暇申請に対する時季変更権の強制力
 前述の通り、使用者は事業の正常な運営に支障をきたすとみなされる相当な事由以外で、時季変更権を行使することができません。そのため、時季変更権自体の強制力は非常に限られています。
前述の通り、使用者は事業の正常な運営に支障をきたすとみなされる相当な事由以外で、時季変更権を行使することができません。そのため、時季変更権自体の強制力は非常に限られています。
たとえば、従業員が繁忙期に「旅行に行くので有給休暇を取得したい」と申し出てきたとします。それに対し、使用者は「旅行に行くのは繁忙期じゃなくてもいいだろう」と従業員の有給取得の目的を理由に、時季変更権を行使することはできません。そもそも、有給休暇を取得する目的を伝えることまでは労働基準法でも求めておらず、労働者の自由とされています。
また、人手不足で代替要員の確保が難しい場合でも、適切に人員配置をおこなっていなかったために時期変更権の行使が違法とされた判例もあります。[注1]
このように、事業の正常な運営に支障をきたす事由があっても、使用者が時季変更権を行使できないケースもあります。そのため、実際に行使するにあたっては慎重に判断しなければなりません。
[注1]労働事件 裁判例集 西日本ジェイアールバス年休権侵害損害賠償|裁判所
3. 有給休暇に対する時季変更権の行使が認められる具体例

時季変更権を行使するために必要な「事業の正常な運営に支障をきたす事由」に該当するかどうかは、次に挙げる要素を考慮して判断しなくてはいけません。
- 事業所の規模
- 業務の内容
- 当従業員が担当する職務内容や性質
- 職務の繁閑
- 代替要員確保の難度
- 該当時季に年次有給休暇を指定した従業員数
- これまでの労働慣行
以上をふまえて、時季変更権の行使が認められるケースを紹介します。
3-1. 代替要員を確保できなかったケース
時季変更権を行使して、従業員からの有給休暇の申請を取り下げる場合、前提として代替要員を確保しようと努力したができなかったという事実がなくてはなりません。
たとえば、申請をしてきた従業員にしかできない業務であって、期日が迫っているような場合は、代替要員を確保するのは困難と判断できるでしょう。
ただし過去の判例で、常に人員が不足しているような場合や、代替要員の確保が可能であったにもかかわらず努力を怠ってしまったような場合は、時季変更権の行使が不当とされているので注意が必要です。
3-2. 繁忙期に有給取得希望者が重なったケース
単に繁忙期であることを理由に、時季変更権を行使することは一般的に認められていません。しかし、繁忙期の同時季に有給取得を希望する従業員が重なり、代替人員をもってしても営業が困難な場合であれば、過去にも時季変更権の行使が認められた例もあるようです。
この場合も、前提として代替人員を確保する努力をしたという事実がなくてはいけません。
3-3. 社内研修の予定日と有給申請日が重なったケース
社内研修や訓練といったものは、先述の事由と異なり、他の人が代理でできる性質のものではありません。スキルアップのために知識や技能を身につけるためのものであるため、本人が参加しないと意味がないでしょう。この場合も、時季変更権の行使は認められやすくなります。実際に、研修期間における有給休暇取得に対して時季変更権の行使が認められた判例もあります。[注2]
[注2]NTT年休権事件最高裁判所判決平成12年3月31日|裁判所
3-4. 長期間連続して有給休暇を取得するケース
有給休暇を長期間連続して取得するような場合も、代替人員の確保が困難であるため、使用者の時季変更権の行使は認められる傾向があります。従業員が約1カ月の有給休暇を取得しようとし、使用者が1カ月の後半部分に対し時季変更権を行使した過去の判例がありますが、正当として認められています。[注3]
[注3]時事通信社事件最高裁判所判決平成4年6月23日|裁判所
4. 時季変更権が行使できないケース

時季変更権を明らかに誤った手段で労働者の不利になるように行使した場合、違法となり罰則を科される恐れもあるため注意が必要です。ここでは、有給休暇の時季変更権を行使できない具体的なケースについて紹介します。
4-1. 急な時季変更をした場合
時季変更権をいつまでに行使すべきかは判例や通達には記載されておらず、一般的には有給休暇取得予定日の前日勤務終了時刻までと解釈されています。
しかし、実際には前から有給休暇を申請している場合、従業員がすでに予定を入れてしまっていて、時季変更ができないといったこともあるかもしれません。時季変更の通達期限に関して規定されていないものの、直前の急な時季変更は、従業員から変更可能と言われない限り難しいでしょう。
有給休暇の時季変更が必要な場合、わかった時点で早めに従業員に対して相談することが重要です。
4-2. 繁忙期のみを理由としている場合
繁忙期であることだけを理由として、時季変更権を行使することは基本的に認められません。繁忙期に人手不足が予想される場合、事前に人員を確保したり、それ以外の時季に計画的な取得を促したりする努力が求められます。
何の対策もおこなわずに、繁忙期における有給休暇申請を却下すると、違法と見される可能性もあるため注意しましょう。
4-3. 有給休暇取得理由による時季変更
そもそも有給休暇の取得理由は労働者の自由とされていて、取得理由を問わないものとなっています。そのため、有給休暇取得理由によって有給休暇の時季変更権を行使することはできません。
過去には、有給休暇取得理由による時季変更に応じなかった従業員の無断欠勤を理由とする懲戒処分を違法とした判例もあります。
道立夕張南高校事件では、職員が春闘の一環の集会に参加するために時季指定した有給休暇に対して、「有給休暇の名を借りておこなうストライキだから」という理由で当時の校長が時季変更権を行使しました。それに対して、職員側は拒否し、出勤しなかったところ、無断欠勤したとして下した懲戒処分を違法としました。[注4]
このように、取得理由による時季変更は法律に則っておらず、それに伴って下した処分は無効と判断されたケースもあります。そのため、時季変更権を行使する際には注意が必要です。
4-4. 年次有給休暇の計画年休制度を導入している場合
計画年休制度は、労使協定を締結することにより、労働者の有する年次有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ計画をした時季に取得させることを可能とする制度です(労働基準法39条6項)。
行政通達により、計画年休については、労使協定が結ばれたことにより、その協定で決めた有給休暇(計画年休)は、労働者側にとっても時季指定権を行使できなくなり、使用者側にとっても時季変更権の行使ができなくなることを意味します。
しかし、どうしても業務の必要性から「計画年休の時季を変更しなければならない」という事態の可能性に備えて、就業規則にその旨を記載しておくということも考えてもいいかもしれません。
その場合、変更した計画年休についても労使協定が必要となります。
4-5. 退職時に時季変更ができるほど日数に余裕がない場合
退職まで日数がない場合、時季変更権を行使しても、時季を変更する日がありません。この場合、時季変更権を行使すると、有給休暇を取得させないことになってしまいます。時季変更権を行使することで有給休暇を取得させない場合、労働基準法違反となり罰則を受ける可能性もあります。
この他にも以下の事由に該当する従業員に対しては行使ができないので注意が必要です。
- 有給休暇が時効により消失する合
- 産後休業・育児休業の期間に重なる場合
- 倒産など、時季変更権を行使により年次有給休暇が消化できないとき
このように、事業の正常な運営に支障をきたす事由があっても、上述の通り、使用者が時季変更権を行使できないケースもあるので、実際に行使するにあたっては慎重に判断する必要があります。
5. 従業員が時季変更を拒否した場合の罰則

事業の正常な運営に支障をきたすとみなされる相当な事由がある場合、使用者は時季変更権を行使することができます。
それに対し、従業員が指示に従わず出勤しなかった場合、有給休暇を取得したとせず、欠勤とし無給扱いにすることがあります。また、就業規則などに基づき、無断欠勤扱いして懲戒処分の対象とすることもあります。
ただし、時季変更に従わなかったことを理由に、懲戒処分をおこなう場合には次に挙げる点を考慮して慎重に判断しなくてはなりません。
- 従業員が欠勤したことで受けた損害の程度
- 実際の欠勤日数
- 従業員の日頃の勤務態度や過去の懲戒処分の有無
- 同時案に対する過去の判例など
数日程度の欠勤で重い処分を科した場合、裁判にまで発展したケースもあります。また、懲戒処分を無効とされる可能性もあるので注意が必要です。
5-1. 時季変更権を濫用すると使用者が罰則を受ける可能性あり
使用者が時季変更権を濫用した場合、労働基準法に基づき6カ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金を科される可能性があります。トラブルを未然に防ぐために、就業規則に時季変更権について記載し、あらかじめ従業員に周知しておくことが大切です。
5-2. 時季変更の理由を明示することが大切
時季変更権を行使するときは、従業員に対して理由を明示することが大切です。口頭で説明する、理由を記載した書面を交付するなど、どのような方法でも問題ありませんが、従業員が納得できるよう丁寧に説明しましょう。また、普段から従業員とコミュニケーションを円滑にし事業の正常な運営に協力してもらえるような関係を築いておくことが大事です。
希望したタイミングで有給休暇を取得することは従業員の権利であるため、不当な理由で時季を変更すると、会社への不満がたまったりモチベーションが低下したりします。理由を明確に伝えたうえで、従業員からの質問などにも丁寧に回答しましょう。
6. 有給休暇の時季変更権の拒否に関するトラブル

前述の通り、従業員が有給休暇の時季変更を拒否して出勤しなかった場合、無給扱いにしたり懲戒処分を与えたりすることもあるかもしれません。。ただし、以下のようなトラブルが発生する可能性もあるため注意しましょう。
6-1. 無給扱いにしたことに関するトラブル
従業員が無給扱いにされたことに納得できず、労働基準監督署に相談したり、訴訟を起こしたりする可能性もあります。裁判を通して、無給扱いにしたことが認められるケースもありますが、時季変更権の行使が不当であると判断され、敗訴してしまうケースもあるでしょう。
トラブルを防止するためにも、本当に時季変更権の行使が認められるケースに該当するのか、しっかりと確認しておくことが重要です。
6-2. 懲戒処分を与えたことに関するトラブル
懲戒処分を与えたことに対して、従業員が訴訟を起こす可能性もあります。懲戒処分とは、会社のルールに違反した従業員に対して与える罰則のことです。具体的には、始末書の提出や減給、出勤停止といった種類の処分があります。
懲戒処分をおこなう場合は、どのような行為に対してどのような処分が与えられるのかを就業規則に明記しておかなければなりません。就業規則を確認せずに処分を下すと、トラブルに発展しやすいため注意しましょう。
7. 有給休暇の時季変更権は正しく行使しよう!

時季変更権は、事業の正常な運営に支障をきたす場合に限り、使用者が従業員に唯一の特例的に行使できる、有給休暇の時季を変更できる権利です。そのため、強制力も非常に狭い範囲に限られています
時季変更権を使用するには、人員確保ができないなど、相応と認められる事由が必要で、簡単に行使できるわけではありません。
時季変更権の概要について正しく理解し、事業の安定した運営のために、適切に行使することに努めましょう。
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。