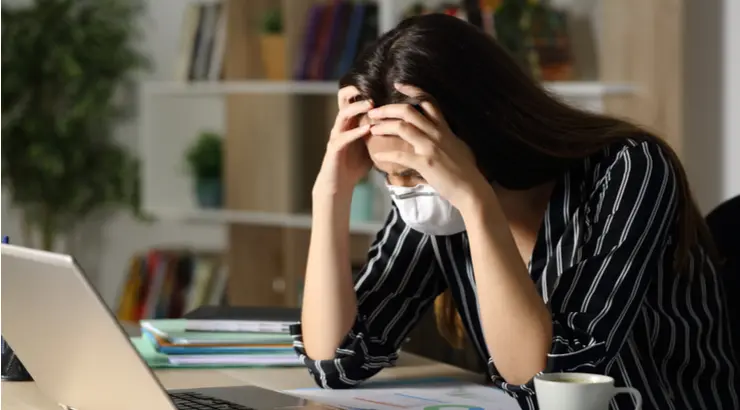
テレワークが一般化している昨今、業務の見直しを強いられている企業も多いのではないでしょうか。出社していた際にはスムーズにおこなえていた業務も、テレワークだと難しくなってしまうということもあります。この記事では、ワークフローシステムのメリットや活用のポイントなどを解説しています。テレワークでスムーズに業務を遂行するための一施策として、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.テレワークとは
テレワークとは、情報通信技術を活用することで場所や時間にとらわれない働き方のことです。一般的には自宅での勤務を指すことが多く、リモートワークや在宅勤務と同様な意味合いで使用されています。新型コロナウイルスが流行する前にもリモートワークという言葉は使用されており、IT業界などのデジタル化が進んでいる企業では以前から推奨されている働き方でした。
2.ワークフローシステムとは
ワークフローシステムとは、企業の複雑な業務の流れなどをデジタル化したもののことを言います。企業内では、各種申請業務によく使用されており、ワークフローシステム一つで申請から承認、決済に対応することができます。
誰が申請して、誰が承認し、誰が決済をするのかを可視化することができ、組織全体の業務効率化を進めることができます。
3.テレワークにおける課題|紙の稟議書や申請書の存在
今まで紙の稟議書や申請書でやりとりをおこなっていた企業も、テレワークが導入されてからは出社する頻度が減り、なかなかスムーズに処理ができていないと悩んでいる人も多いでしょう。
また、承認の進捗も確認しづらく、承認者が出社するタイミングが悪いと、完了するまでに相当な時間がかかってしまいます。承認フローが複雑な稟議書や申請書は、早急にペーパーレス化を導入した方が良いでしょう。
4.テレワークでワークフローシステムを導入するメリット
ここからは、テレワークでワークフローシステムを導入するメリットについて紹介します。
導入を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
4-1.申請・承認作業のために出社する必要がなくなる
従来の紙で処理をおこなう場合、申請や承認作業のためだけに出社を余儀なくされます。各書類への押印や確認が必要となり、紛失や情報漏洩を防ぐために管理ややりとりも社内のみで進めることとなります。そのため、テレワークが導入されたとしても一部の人は出社をしなければならないでしょう。
ワークフローシステムを導入すれば、出社の必要がなくなるというメリットがあります。システム内で各種書類の申請や承認、決済ができ、上司やメンバーへの確認も簡単に共有することができます。さらに、交通費や移動時間などのコストを削減することができるので、生産性の上昇にもつながります。
また、場所や時間を問わずシステムで対応できるので、メンバーの不在によって承認作業が滞るといったこともなくなります。
4-2.進捗状況を見える化できる
紙での処理をおこなっていると、テレワークが導入されたときに、承認の進捗が確認しづらいというデメリットがあるでしょう。現在、どこまでの承認が完了しているのか、どの書類の申請が終わっているのか、書類の作成者や管理側は都度確認をしなければいけません。
そこでワークフローシステムを導入すれば、システム内で申請や承認などの進捗状況を見える化できます。見える化されることで各書類の承認作業が滞りにくくなり、スピーディーに作業を進めることができます。
5.テレワークだけではない、ワークフローシステムのメリット
ワークフローシステムを導入するメリットは、テレワークでの働き方の時だけではありません。その他でのメリットも確認していきましょう。
5-1.稟議や申請をスピードアップできる
紙の稟議や申請では、人の手で承認者に書類を回さなくてはならないので、時間がかかります。一方ワークフローシステムでは、まとめて承認を取ることができるのでスピーディーに処理ができるでしょう。
企業規模が大きいほど、稟議などの承認ルートが複雑になり、時間がかかる傾向にあります。多くの人を介すことになるので、その分時間もかかります。
ワークフローシステムを導入することで、現状どこまで承認が完了していて、どこで停滞してしまっているのかをシステム内で確認ができるので、複雑な承認ルートでも承認の催促がおこないやすくなっています。
5-2.内部統制の強化を図ることができる
ワークフローシステムを導入することにより、内部統制を強化することにもつながります。書類の稟議や承認については、曖昧なルールになっていることも多いです。そういった社内でのルールを明確にし、作業を洗い出してから整理をするとより内部統制を図ることができるでしょう。
導入をおこなう前には、各関係者に稟議や承認の際にどういった業務コストが発生しているのかをヒアリングして、システムにどう落とし込むかを考えておくと良いでしょう。また、作業の履歴が残ることも内部統制の強化につながります。
また、有料であればセキュリティの強固なシステムもあり、書類の紛失や改ざんなどの防止が可能です。
5-3.コスト削減につながる
ワークフローシステムを導入することにより、コスト削減にもつながります。今まで手作業でおこなっていた書類作成や、確認作業が自動化されるので、その分の人件費が削減できるでしょう。
また、従来の紙を用いての書類申請では、紙や印刷代などさまざまな費用が発生しています。それが積み重なると膨大な費用になるので、費用を抑えるためにもシステムを導入するのをおすすめします。
システム内で一括管理ができ、各部署への確認作業の手間も省けるのでぜひ検討してみてください。
6.テレワークでワークフローを活用するポイント
ここでは、テレワークでワークフローを活用するポイントについて解説していきます。テレワークでの働き方を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
6-1.誰でも使いやすいシステムを選ぶ
ワークフローシステムは稟議や申請書、契約書など会社のさまざまな人が利用するでしょう。会社全体で誰もが利用できるようなシンプルなシステムを導入しましょう。なかには、PCそのものや新しいシステムを利用するのが苦手という人もいるかもしれません。そのような人たちも今後利用していくことを踏まえてシステム選びをおこないましょう。
6-2.業務フローやルールを見直す
ワークフローシステムを導入する際は、検討段階で先に業務フローやルールの見直しをおこなっておきましょう。実際にワークフローシステムを導入することで、どのようなメリットがあるのかどれくらい業務を削減できるのか、事前に把握しておく必要があります。
業務フローやルールを見直すことにより、とくにワークフローシステムを取り入れなくてもコスト削減ができたり、無駄な業務を見つけたりすることができます。現在、何に時間を取られているのかなどを把握することによって業務効率化を図れるので、見直しの時間を把握するようにしましょう。
6-3.システムやルールの浸透を促す
会社全体でワークフローシステムを導入するとなると、社内に浸透させるのが重要となってきます。従来のやり方に慣れてしまっているがゆえに、なかなか新しいシステムの使い方やルールを浸透させられないということもあるでしょう。
できるだけ早くシステムを浸透させるには、各部署に対して使い方やルールを説明する時間を設けるようにしましょう。システム導入直後だけでなく、その後も複数回講習会をおこなったり、社員の利用状況などを確認したりすると良いでしょう。
6-4.外部ツールと連携させる
すでに社内で利用しているツールと連携ができると、ワークフローシステムがより利用しやすくなります。稟議や確認の連絡であれば、今までは直接本人に依頼することもありました。
そこで、ワークフローシステムをチャットツールに連携させると、承認依頼の通知を受け取ることができ、この直接依頼をする手間をなくすことができます。ワークフローシステムによってさまざまな外部ツールとの連携ができるので、導入検討の際に確認しておきましょう。
7.ワークフローシステムの導入でテレワークの課題を解決!
今回はテレワークにおけるワークフローシステムについて解説しました。テレワークなど働き方が多様になってきている昨今、システムを導入することによるメリットは限りなく大きいです。
従来の紙管理では、申請や承認をおこなうためにわざわざ出社したり、承認依頼の連絡をおこなったりなど、実際には相当なコストがかかっている場合があります。業務フローやルールの見直しを今一度おこなってから、ワークフローシステムの導入を検討してみると良いでしょう。
こちらの記事では、ワークフローシステムを選ぶ際に欠かせないポイントについてを紹介しています。導入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。







