
法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められており、これを超える労働時間数に対しては割増賃金の支給が必要です。ただし、近年導入が進むフレックス制度をはじめとする複数の労働制度では、上記の条件とは少し異なる場合もあります。
本記事では、法定労働時間の定義や賃金の計算方法、所定労働時間との違いなどを解説します。従業員の勤怠管理をおこなううえで、必ず理解しておかなければならないのが法定労働時間です。
労働時間は法律によって厳しく定められており、1日8時間以上、週40時間以上の労働をおこなうには36協定の締結が必要となります。法定労働時間について確認し、超えた場合の罰則や法定労働時間を超えないための対策を考えましょう。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 法定労働時間とは

法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間のことで、基本的に1日8時間、週40時間以内と決められています。この法定労働時間を超えて労働させる場合は残業代を支払わなければなりません。
しかし、企業や業務内容によっては、この法定労働時間内に労働時間を収められない場合もあるでしょう。そのような場合は、36協定と呼ばれる時間外及び休日労働に関する協定を労働組合と結び、行政に届け出る必要があります。
ただし、この36協定にも上限があり、無限に労働時間や出勤日を増やせるわけではありません。上限を超えて働かせると、労使間のトラブルが発生したり、法律によって罰則が科せられたりするため注意しましょう。
2. 法定労働時間の基本的な考え方

ここでは、法定労働時間の基本の考え方を解説します。
混合されがちな所定労働時間との違いや、法定労働時間における休憩時間の考え方、さらに見落とされがちな労働時間に入る時間について確認しておきましょう。
2-1. 法定労働時間と所定労働時間との違い
法律で定められた労働時間を法定労働時間といい、企業が定めた労働時間を所定労働時間といいます。この所定労働時間は、法定労働時間内に収める必要があります。反対に法定労働時間内であれば、それより短くても問題ありません。
所定労働時間が6時間の企業で2時間残業した場合、2時間の残業は法定労働時間内であるため割増賃金は発生しません。一方で3時間残業した場合、2時間分は法定労働時間内であるため割増賃金は発生しませんが、1時間分については割増賃金が発生します。
法定労働時間が短いと従業員のモチベーションを維持できる、業務効率化を図れるなどのメリットがありますが、一方で週の勤務日数が増える、残業が前提になってしまうなどのデメリットもあります。
2-2. 休憩時間に関するルール
法律では労働時間だけでなく、労働中の休憩時間についても細かく決められています。労働時間とは企業の指揮下にある時間のことで、この時間が一定を超える場合には休憩時間が必要です。
具体的には、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を付与しなければなりません。
従業員を丸一日働かせ続けることはできませんので、休憩時間も管理を徹底しておこなう必要があります。
2-3. 法定休日に関するルール
企業は従業員に対して、1週間で1日以上、または4週間で4日以上の休日を付与しなければなりません。この休日は法定休日と呼ばれ、労働基準法のルールであるため忘れずに付与しましょう。
土日の2日間を休みとしている企業も多く存在しますが、どちらかを法定休日、もう一方を法定外休日と設定するのが一般的です。また、法定休日に働かせる場合は、36協定の締結が必要となります。
2-4. 労働時間に含まれる時間
法律では、従業員が企業や使用者の指揮下に置かれる時間のことを労働時間と定めています。そのため、一見すると仕事をしていないような時間も労働時間としてカウントされるケースがあります。
たとえば、制服がある仕事での更衣の時間、自発的ではなく強制される清掃の時間、必ず参加しなければならない研修やセミナー、さらに業務に必要な資格取得にかかる学習の時間などです。
これらの時間も含めると法定労働時間を超えてしまう場合は、通常の業務の時間を短縮するなどして調整しなければなりません。
反対にこれらの時間を労働時間としてカウントしないことは法律違反にあたりますので注意してください。
3. 36協定の締結で認められる法定外労働時間の上限

従業員に法定労働時間を超えた労働をさせるには、36協定という労使協定の締結をおこなう必要があります。
ただし、36協定を結んだ場合でも、1カ月につき45時間、1年につき360時間以内が時間外労働の上限であり、それ以上の労働をさせてしまった場合は法律違反となります。また、この法定外労働が発生した場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
3-1. 特別条項においても月100時間未満、年720時間以内が限度
臨時的な特別な事情がある場合、36協定の1カ月に45時間、1年に360時間以内という上限を超えた労働をさせることが可能です。
しかし、あらかじめ特別条項について労働基準監督署に届出を提出し、受理される必要があります。上限は月100時間未満、年720時間以内であり、45時間の上限を超えられるのは年6回までなどの制限がついています。
4. 法定労働時間の上限を超えた場合の罰則

36協定を締結しないままに法定労働時間の上限を超過してしまった場合や、36協定を結んだうえでも時間外労働時間の規定を超過してしまった場合には、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
たとえ従業員が勝手に残業や休日出勤をしていた場合もこの支払いは免れません。そのため企業は、従業員の勤務時間をきちんと把握・管理し、上限を超過しそうな従業員へ注意を促す必要があります。
また、過度な長時間労働は従業員の心身の健康に悪影響を与えるため、できる限り避けたほうがよいでしょう。疲労が蓄積することで、モチベーションや集中力が低下するケースもあります。適度に休息を取れる労働環境を構築することで、従業員の健康と生活を守ることが大切です。
5. 法定労働時間を超える残業には割増賃金が発生

36協定や特別条項を締結した場合にも、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合、その時間数分だけ割増賃金が発生します。ただし、各企業が定めた所定労働時間を超えた場合には、8時間以内であれば割増賃金は発生しません。
5-1. 月平均所定労働時間とは
残業代を計算するには、まず1時間あたりの賃金(時給)を求める必要があります。その1時間あたりの賃金に、割増率と残業時間を掛けて、残業代を算出するためです。
1時間あたりの賃金を求める際、暦日数を分母にしてしまうと、1カ月にある日数は変動することから、同じ残業時間でも月によって金額に差が出てしまいます。このようなことを防ぐため、1時間あたりの賃金を求める際は当該月の暦日数ではなく、年間で換算する「月平均所定労働時間」を用いましょう。
月平均所定労働時間とは、下記の公式で求めることが可能です。
「月平均所定労働時間 =(365日 - 1年間の休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12カ月」
たとえば、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が105日ある企業の場合、下記のような計算式になります。
(365日 − 105日)× 8時間 ÷ 12カ月 = 173.333333時間
上記の企業の月平均所定労働時間は、約173時間となります。
5-2. 残業代の計算例
残業代の算出は下記の公式にあてはめて求めることができます。
「残業代 = 1時間あたりの賃金(時給)× 1.25(割増率)× 残業時間」
たとえば、月給が24万円、月平均所定労働時間が173.3時間である労働者が、1カ月間で合計15時間残業したとします。上記の公式にあてはめるには、まず1時間あたりの賃金(時給)を計算しなければなりません。
「1時間あたりの賃金(時給)= ⽉の所定賃⾦額(月給) ÷ ⽉平均所定労働時間数」
24万円 ÷ 173.3時間 = 1,384.61539円
1時間あたりの賃金(時給)が出たところで、残業代を算出する公式にあてはめて計算しましょう。
1,384.61539円 × 1.25(割増率)× 15時間 = 25,961.5385円
上記の数値が1カ月の残業代ですが、1円未満の端数は50銭以上の場合、切り上げが可能です。
そのため、支給される残業代は25,962円となります。
6. 法定労働時間の例外にあたる労働形態

法定労働時間は原則として「1日8時間・週40時間」と定められていますが、一部の特殊な労働形態を導入している場合は、条件が少し異なります。ひとつずつ確認していきましょう。
6-1. 特例措置対象事業場では「週44時間」
特例措置対象事業場とは、商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽などの業界で、かつ常時使用する労働者が10人未満である事業場が該当します。
これらの事業場に関しては、法定労働時間が「週44時間」へと延長されています。しかし「1日8時間」という規定は変わらないため、週6日の勤務形態を採用する企業も存在します。
6-2. 変形労働時間制
変形労働時間制とは、一定期間における平均労働時間が法定労働時間を超えない場合、特定の日や週において法定労働時間を超えて働かせてもよい制度です。季節によって需要が変動する、レジャー、旅館、スキー場などの企業にて導入することがあります。
6-3. フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、従業員が始業時間、終業時間を自由に決められる制度です。必ず勤務する必要のある「コアタイム」を設定して、その前後の時間の使い方は柔軟に決めることができます。
一定の期間(清算期間)のなかでの総労働時間が、法定労働時間を超えないよう調整するため、1日の法定労働時間はとくに設けられていません。
6-4.裁量労働制
裁量労働制とは、労働時間に関しては完全に従業員に任せる制度であり、法律で定められた特定の職種のみが適用可能です。
外回り営業をおこなう労働者などが該当する「事業場外みなし労働時間制」、研究職、開発職などに適用される「専門型裁量労働制」、マーケティングやデータ分析などをおこなう職種に適用される「企画型裁量労働制」の3種類が存在します。ただし企画型に関しては、労使協定以上に要件が厳しい「労使委員会決議」をおこなう必要があります。
6-5. アルバイトやパートの法定労働時間
アルバイトやパートといった雇用形態の従業員に対しても、もちろん労働基準法は適用されます。そのため1日8時間、週40時間以上の労働や、午後10時~午前5時の間の労働、法定休日の労働には割増手当が発生します。
これらの労働を指示する場合には36協定を締結しなければなりませんが、派遣社員に関しては派遣元で36協定を結ぶ必要があるため、注意が必要です。
6-6. 管理監督者の法定労働時間
管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある従業員のことです。一般の従業員とは異なり、業務の進め方に関して一定の裁量が与えられており、立場にふさわしい待遇を受けている場合は、管理監督者に該当します。
管理監督者は、経営的な判断などの重要な業務を随時おこなう必要があるため、法定労働時間のルールは適用されません。ただし、部長や課長という役職があっても、権限や待遇が一般の従業員と変わらない「名ばかり管理職」の場合は、通常通り、法定労働時間のルールが適用されます。
6-7. 高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度の対象となる従業員には、法定労働時間の規制が適用されません。高度プロフェッショナル制度の対象となるのは、以下のような職種です。
- 資産運用業務
- コンサルティング業務
- 金融商品の開発業務
- 有価証券の取引業務
上記のような職種は高い専門性が必要となり、労働時間と成果の関連性が薄いため、法定労働時間の規制を受けずに働くことができます。
7. 法定労働時間の上限を超過しないための対策

企業や業務内容によっては法定労働時間を超えてしまう、ギリギリになってしまうというケースも少なくありません。
しかし、違法行為が認められると罰則を受けるだけでなく、企業のイメージダウンにもつながります。法定労働時間を超過しないためにはどのような対策があるのかを紹介します。
7-1. 変形労働時間制を導入する
時期によって残業時間が変動する業務内容の場合には、変形労働時間制を採用することもおすすめです。変形労働時間制とは、1週間単位や1カ月単位などで労働時間を定められるというものです。
たとえば、月末のみ業務が増える仕事の場合、1カ月単位の変形労働時間制を採用していれば、1週目から3週目の所定労働時間を短くし、最後の週の所定労働時間を長くし、平均して1カ月の週の労働時間が40時間を超えないようにします。
7-2. 週の労働時間を調整する
1週間の所定労働時間を一律で固定している場合、無駄な労働時間が発生している可能性があります。
業務が少ない曜日は所定労働時間を短くし、業務が多い時間は所定時間を長くするといった方法で週の労働時間が40時間を超えないようにします。
このような取り組みは企業や使用者だけで管理しにくく、従業員一人ひとりの申告や意識の持ち方が重要です。
スケジュールにない仕事が入った場合どのように他の曜日で調整するか、残業してまで今日中に終える必要のある仕事なのかなどを判断する力も身につけさせましょう。
7-3. 業務効率を見直す
そもそもの業務効率が悪く、必要以上に労働時間が長くなる、残業時間が増えるといったケースもあります。法定労働時間に収めることばかりを考えるのではなく、今一度業務効率についてもチェックしてみてください。
アナログで時間のかかる書類作成を続けている、ごく少数の従業員にしかできない仕事がある、会計業務などを手作業でおこなっているなどの場合、不必要に労働時間が長くなっている可能性があります。
書類作成はデジタルでおこなう、使いまわせる文言やテンプレートを用意する、システムやプログラムを導入して会計業務を効率化させる、従業員の負担が大きくなる作業については分担するなどの方法があります。
業務を効率化させることで労働時間を大幅に短縮できるだけでなく、従業員のモチベーションの維持、スキルの向上にもつながり、よりクリアな労働環境を目指すことも可能です。
7-4. ノー残業デーを決める
ノー残業デーを決めることで、労働時間の短縮を図ることも可能です。会社や部署全体で、まったく残業をしない日を設定すれば、従業員全体の労働時間を短縮できます。その分、日中の業務効率や生産性が高まるでしょう。
ただし、ノー残業デー以外の日にしわ寄せがいき、全体の残業時間が変わらないようでは意味がありません。業務の効率化と一緒に進めることで、ノー残業デーの意義が高まると考えられます。
7-5. 残業の事前申請ルールを設定する
残業の事前申請ルールを設定することも重要です。従業員が自由に残業できる状態では、労働時間を把握しにくくなり、知らないうちに法定労働時間を超えてしまうケースもあります。また、急ぎではない仕事のために、無駄に残業をする従業員もいるかもしれません。
事前申請ルールを設定すれば、上司が残業の必要性を判断できます。無駄な残業を減らしつつ、法定労働時間の超過を防止できるでしょう。
7-6. 勤怠管理システムを用いて客観的な労働時間を記録する
法定労働時間を超えさせないためには、従業員に呼びかけを通して意識改革を図るほか、長時間労働を防ぐための仕組みをつくる必要があります。
勤怠管理システムは、管理者が従業員の労働時間をリアルタイムで把握できるため、呼びかけの材料にもなるほか、全従業員の労働時間が一目でわかることで、労働時間の上限を超えそうな従業員を確認して業務量を調整するなど、労働時間を超えないための対策をとることができます。
勤怠管理システムの導入は、法定外労働時間を削減するための有効な手段のひとつです。
8. 法定労働時間を超えないためには業務の見直しもポイント
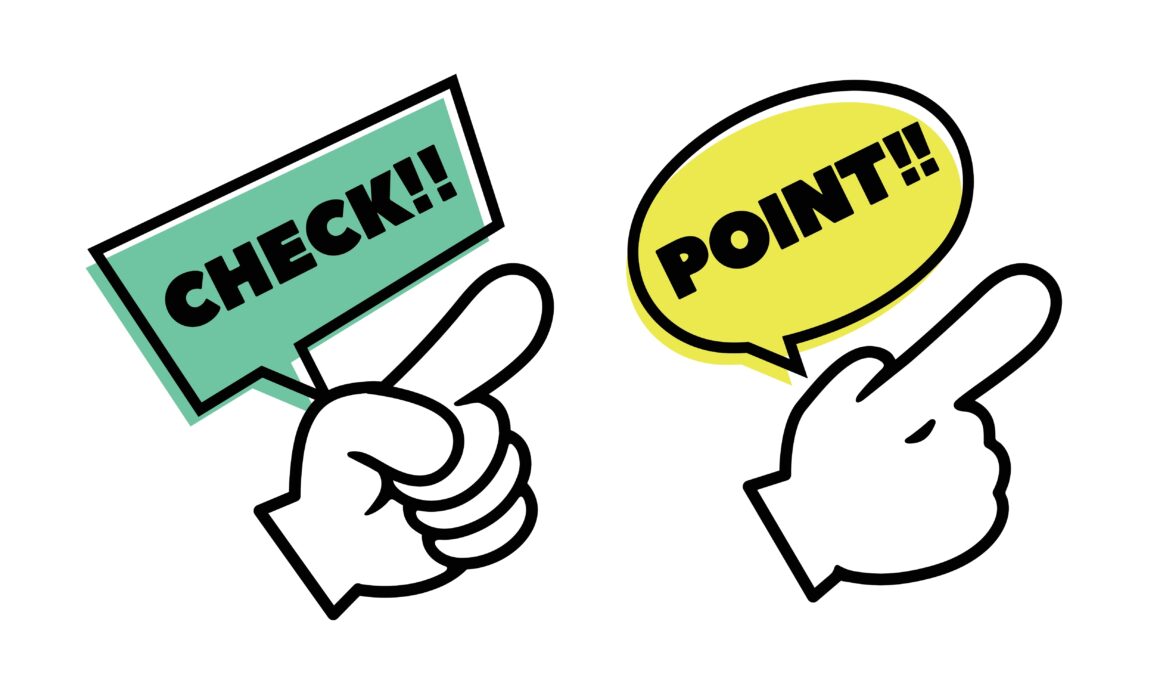
今回は、法定労働時間の意味や超過しないための対策について解説しました。法定労働時間を超える労働は基本的には認められておらず、残業代を支払う義務があります。休憩時間を取らせる、始業前後の清掃や更衣も労働時間に含めるなど、見落としがちなポイントは多いので注意してください。
また、残業時間の計算方法についてきちんと把握しておくことは大切ですが、同様に残業させない方法も理解し、実行しなければなりません。労働時間を臨機応変に変動させる、業務を効率化させて労働時間を短縮するなど、労働時間ばかりでなく業務そのものを見直すことも必要です。
従業員から不満が出ず、企業や使用者側も残業代の負担を少なくするためにどうすればいいのかを考えていきましょう。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。









