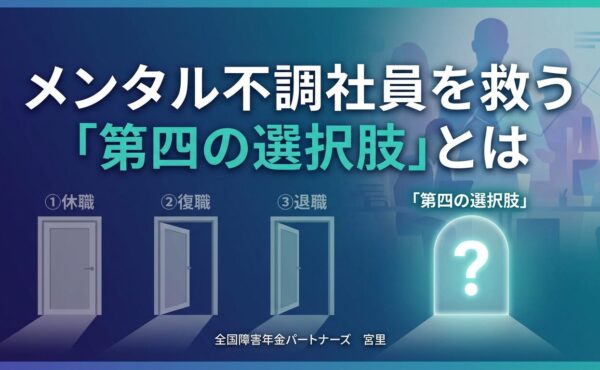アルバイトを雇用するときには、その働きぶりをチェックするために試用期間を設けることがあります。試用期間を設定することには、雇用する企業側と働くアルバイト側でミスマッチ防止にも効果的です。本記事では、アルバイトに試用期間を設ける適切な期間や、メリットやデメリット、注意点について解説します。
目次
1. アルバイトを採用する際に試用期間を設ける例は少なくない
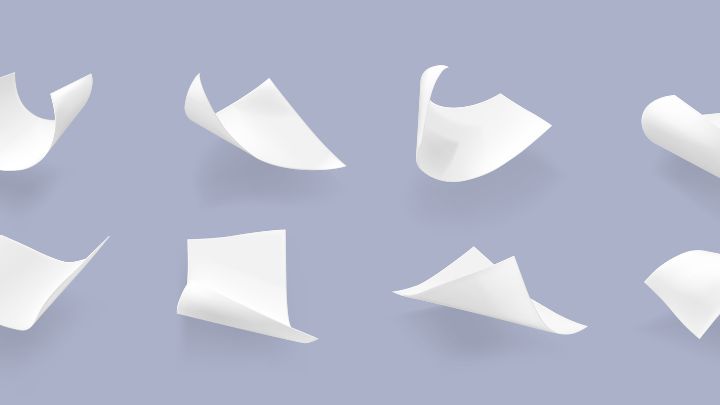
アルバイトの無期雇用契約をする際は、本採用に至る前段階で、労働者の働きぶりや適性を十分に確認したいものです。こういった目的から、アルバイトに対して試用期間を設ける企業や店舗は少なくありません。試用期間は、企業と労働者がお互いに見極めをおこなう有効な機会となります。
アルバイトの採用には大きく分けて、期間を定める有期雇用契約と、期間を定めず雇用する無期雇用契約があります。
「有期雇用契約」は最大で3年間と定められていますが、半年や1年などで契約することが多いです。契約期間満了までに契約更新か、雇止めの判断をおこないます。
一方で「無期雇用契約」は、契約更新をおこなうことなく長期的に雇用することになります。無期雇用は、より解雇できる条件が厳しくなることから、試用期間がミスマッチを防ぐための有効な方策になるのです。
1-1. 研修期間と試用期間の違いとは?
「研修期間」と「試用期間」の2つの用語は、似たような意味合いをもちますが、設ける目的が明確に異なります。目的は、以下の通りです。
ただし企業によっては、「研修期間」も「試用期間」も同様の定義でよんでいることもあるようです。ミスコミュニケーションを防ぐためにも、必要に応じて自社における用語の意味合いを最初に確認し、共通認識をもっておきましょう。
1-2. アルバイトの適切な試用期間はどれくらい?
一般的に、アルバイトの試用期間は3~6ヵ月程度に設定されます。試用期間は、長すぎず短すぎない期間にしておくのが無難です。
アルバイトに試用期間を設ける際の長さに、明確な決まりはありません。試用期間を数日から数週間程度という短期間に設定する企業もあれば、半年以上の試用期間を設ける企業もあるようです。
とはいえ、試用期間が短すぎると、アルバイトの能力や働きぶりを十分に把握できないまま本採用に進むことになってしまいます。
十分な見極めをおこなうためにも、できれば試用期間は最低でも1ヵ月程度確保するとよいとされています。
試用期間を半年から1年という長い期間に設定する例もごくまれにありますが、これはかなり高度な職務内容で能力の見極めに時間を要する場合となります。
ただし、試用期間を長く、さらに給与額や待遇を低く設定してしまうと、労働者が不満を抱きやすくなる点が懸念されるでしょう。待遇の悪さを理由に早期退職するケースも考えられるため、過度に長く設定しない点に留意しておくとよいでしょう。
2. アルバイトに試用期間を設けるメリット4つ

試用期間を設ける際には、目的を十分に理解した上で運用し、労働者の働きぶりや適性を見極めましょう。アルバイトの雇用時に試用期間を設けることには、以下のようにいくつものメリットがあります。
- 本採用すべきかの判断材料になる
- 本採用後のミスマッチを防げる
- 仕事内容をじっくり確認してもらえる
- 本採用後に比べて解雇がしやすい
ここから、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
2-1. 本採用すべきかの判断材料になる
企業がアルバイトを雇用する際には、応募の連絡や面接という限られた時間のみで相手の能力や人間性を判断しなければなりません。履歴書や面接のみでは、アルバイトの従業員の適性や能力を図ることは難しいケースもあるでしょう。
いざ採用してみると、遅刻や無断欠勤が多く、現場に大きな負担がかかってしまうこともあるかもしれません。
試用期間中の働きぶりをチェックすれば、今後継続的に働いてもらうかを冷静に判断できるでしょう。
2-2. 本採用後のミスマッチを防げる
アルバイトの応募者は、求人情報に記載されている限られた情報のみを見て応募することになります。もちろん不明点は面接の際に質問してもらうことも可能ですが、口頭でのやりとりで十分な理解を得るのは難しいものです。
試用期間なしで本採用してしまうと、労働者は自分に合っている仕事か否かを十分に判断できません。結果的に、労働者が早期退職してしまうこともあります。
アルバイトの場合、ミスマッチが起きると突然出社しなくなるケースもあるものです。試用期間を設けて仕事へのマッチ度を確認してもらえば、早期退職といった不測の事態をある程度防ぐことが可能となります。
2-3. 即戦力となる人材を確保しやすくなる
アルバイトの仕事内容は、口頭による説明よりも実践したほうが習得がはやいでしょう。試用期間を設けて実際の現場で働いてもらうことで、仕事内容への理解も深まりやすくなります。
試用期間を活用して十分に仕事内容を覚えてもらえば、本採用後には即戦力としての活躍が期待できるでしょう
2-4. 本採用後に比べて解雇がしやすい
労働基準法第20条には、雇用してから14日以内であれば解雇予告の手続きの対象とはされていませんので予告期間を設ける必要はないとされています。
アルバイトを雇用してから14日が経過した後には、労働基準法に定められた通りに解雇予告をすることで解雇が可能となります。
本採用後は試用期間中と比較すると、解雇が認められる条件がより厳しくなります。
とはいえ試用期間中であっても、解雇する場合には客観的かつ合理的ある理由で社会通念上相当性があることが必須となります。「会社や店舗の雰囲気に合わない」「仕事を覚えるのが遅い」などといった主観的で曖昧な理由では、解雇は認められないため気をつけましょう。
3. アルバイトの試用期間を設ける際の注意点

アルバイト雇用の際に試用期間を設ければ、ミスマッチを防いで会社や店舗に合う人材を見極められます。
ただし、試用期間の運用方法を間違えてしまうとトラブルに発展することもあるので気をつけましょう。試用期間を設定する際には、以下のようなポイントに注意して適切な運用方法を遵守したいものです。
3-1. 給与の規定を守り、しっかりと支払う
アルバイトの試用期間であっても、給与や割増賃金は正確に支払わなければなりません。
具体的な給与の規定としては、最低賃金を下回らないことが挙げられます。最低賃金を下回った給与を設定するには、都道府県労働局長に許可を得る必要があります。許可を得ずに、最低賃金以下の給与を支払うことは、違法となるためご注意ください。
また割増賃金においても、適切な額での支給が義務付けられています。
時間外労働(1日8時間もしくは週40時間を超える労働)、深夜労働(22時~5時の間の労働)には25%の割増手当、休日労働(法定休日の労働)には35%の割増手当の支給が必要となるため、留意しましょう。
3-2. 試用期間の長さやルールは事前に明示する
試用期間を設ける際には、雇用するアルバイトに対して具体的な内容をあらかじめ明示することが大切です。試用期間の条件に合意がないまま働かせた場合、違反とみなされることがあります。
試用期間の長さや待遇面、社会保険、解雇に至るケースなどについて、一つずつ細かく説明し、合意を得るようにしましょう。
3-3. 社会保険の加入条件を満たすか確認する
週の所定労働時間などがフルタイムの3/4未満のアルバイトの試用期間においても、加入条件を満たしている場合には、社会保険の加入が義務付けられています。
加入条件は、以下の通りです。
- 強制適用事業所・任意適用事業所に該当している
- 従業員が51名以上
- 2ヵ月を超えるの雇用の見込み
- 月給が88,000円以上
- 一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 学生でない
試用期間における社会保険の考え方について、詳しく確認したい方は以下の記事をご確認ください。
4. 試用期間とアルバイトに関連するよくある質問について

ここからは、試用期間とアルバイトに関する疑問について解説していきます。
正社員の試用期間中だけアルバイトとして雇用契約することの可否や、試用期間中のアルバイトの解雇の可否について、確認していきましょう。
4-1. 正社員の試用期間中のみ「アルバイト」として扱うことは可能?
正社員採用として雇入れ、試用期間中のみ「アルバイト」として雇用契約を結ぶことは可能なのでしょうか。結論からお伝えすると、法的には問題ないとされています。
アルバイトとして雇うと、給与は時給制となることが多いですが、そのほかの社会保険の加入や有給休暇は雇用形態に関わらず必要となるため、ご注意ください。
4-2. 試用期間中のアルバイトを解雇することは可能?
試用期間中にミスマッチを感じるときにはアルバイトを解雇することがあります。ただし試用期間であっても、合理的な理由なく一方的な解雇が出来るわけではありません。
試用期間中の解雇は、合理的な理由がある場合や社会通念上相当と認められる場合に限られます。例えば遅刻や欠勤が多いときや、申告した職務履歴などに虚偽があったときなどには解雇できる場合があります。
単に仕事の覚えが悪かったりミスが多かったりするだけでは、正当な解雇の理由として認められません。ただし、再三指導しても改善の余地が見受けられないときには解雇できることがあります。
不当な解雇は、大きなトラブルへと発展することもあります。試用期間中の解雇に関する判断は慎重におこなうことが大切です。
5. アルバイトに試用期間を設ける際には適切な運用を遵守することが大切

アルバイトを雇用する際の試用期間には、雇用する企業側と労働者側双方に大きなメリットをもたらします。
ただし、試用期間を設けたからといってアルバイトをすぐに解雇できるわけではありません。明確な理由なく解雇した場合には違反とされることもあるので気をつけましょう。
試用期間はあくまで、その後の長期雇用を前提とした制度なので、労働基準法に定められたルールを守って適切に運用することが大切です。