
多くの企業は、従業員の通勤にかかる費用を通勤手当として支給しています。通勤手当は電車やバスなどの公共交通機関だけでなく、マイカーで通勤する従業員にもガソリン代として支給されることがあり、どの範囲にどの程度の金額を支給するかは企業によって異なります。
では、この通勤手当に所得税が課税されるケースとされないケースがあることをご存知でしょうか。今回は通勤手当と交通費の違いや、通勤手当に所得税が課税されるケース・されないケースなどに関して詳しく紹介します。
関連記事:給与計算時の所得税の計算方法とは?源泉所得税や控除についても解説
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 所得税における通勤手当とは

通勤手当は、従業員が通勤する際にかかる費用のために支給される手当です。
企業に通勤手当を支給する義務はありませんが、福利厚生として通勤手当を支給する企業がほとんどです。厚生労働省による「令和2年就労条件総合調査の概況」によると、令和元年11月に「通勤手当など」を支給している企業は全体の92.3%であることがわかっています。
1-1. 所得税法9条における通勤手当の扱い
所得税法9条では「通勤手当」を非課税所得として扱っており、以下のように定義されています。
五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
このように、所得税法上は、通常必要であると認められた通勤手当に関しては、所得税はかからないことがわかります。
ただし、通勤手当が非課税となるのは、一定の範囲内に限られます。非課税の限度額は、交通機関を利用するケースと、マイカーや自転車を利用するケースで異なります。
限度額を超えた場合は、通勤手当にも所得税が課税されます。通勤手当が加わることで、所得税が発生する年収103万円のラインを超えてしまう場合もあるため注意が必要です。
交通手段別の通勤手当非課税限度額についは、のちほど解説します。
1-2. 通勤手当と交通費の違い
通勤手当と混同されやすい交通費ですが、それぞれには明確な違いがあります。
交通費とは、従業員が業務をおこなううえでかかる費用に対して支払われるものです。具体的には、営業の外回りやトラブル対応、研修などの参加や出張などで顧客先に向かう際にかかった費用などが「交通費」として支給されます。
また、通勤手当と交通費は支給のタイミングも異なります。
通勤手当は事前に申請をおこなって給与に上乗せして支給されますが、交通費は従業員が立て替えた金額を精算書などを提出し、それに対してあとから支払われるのが一般的です。ただ、企業によっては通勤手当も精算書を提出して後日支払うケースや、現物支給するケースなどもあるため、企業ごとに対応方法が異なります。
なお、交通費は全額非課税です。この点についても、正しく理解しておきましょう。
関連記事:所得税計算に交通費は含まれる?通勤手当との違い・ルールを解説!
2. 所得税に通勤手当を含むケース

基本的に給与と一緒に支給される手当は所得税が課税されますが、通勤手当の場合、一定額以下であれば所得税が課税されません。まずは、通勤手当を所得税に含むケースから見ていきましょう。
2-1. 公共交通機関の経済的かつ合理的な運賃が月15万円を超える場合
公共交通機関を利用していて、1カ月あたりの経済的かつ合理的な運賃が月15万円を超える場合は、通勤手当も課税対象です。2016年度に税制の改正が行われ、従来の月最大10万円から引き上げられました。
通勤用定期券を支給する場合も、15万円を超えると課税対象です。
2-2. グリーン車を利用して通勤する場合
新幹線のグリーン車など特別車両に該当する車両で通勤する場合は、「一カ月あたりの経済的かつ合理的な運賃の額」には該当しません。1カ月の通勤手当が15万円を超えていなくても、グリーン車などの特別車両料金などに該当する料金は課税対象です。
2-3. 通勤距離が片道2km未満の場合
マイカーやバイク、自転車などで通勤する場合でも、通勤距離の片道が2km以下の場合は支給される通勤手当の全額が課税対象です。
2-4. マイカー・バイク・自転車通勤で距離に応じた限度額を超える場合
マイカー・バイク・自転車通勤を行う場合、通勤にかかる距離に応じて1カ月あたりの非課税となる通勤手当の限度額が決まっています。この限度額を超えて交通費が支給される場合は所得税の課税対象です。
| 片道の通勤距離 | 1カ月あたりの限度額 |
| 2km未満 | 全額課税対象 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 |
2-5. 有料道路の利用料金月15万円を超える場合
有料道路を利用しての通勤が経済的かつ合理的として認められる場合でも、月15万円を超えた額は課税対象です。
2-6. 公共交通機関とマイカー・バイク・自転車を利用して月15万円を超える場合
遠方に住んでいる場合、自宅の最寄り駅までマイカー・バイク・自転車で移動したのち、会社の最寄り駅まで公共交通機関を利用して通勤することもあるでしょう。この場合、公共交通機関の1カ月あたりの経済的かつ合理的な運賃と、マイカー・バイク・自転車で通勤する距離に対して支給される額の合計が月15万円以上の場合、15万円を超過した額が課税対象です。
有料道路を使用してマイカー・バイク通勤をする場合も、有料道路の利用料金と距離に応じた額を合算した1カ月の合計が15万円を超えると、超過分が課税対象です。
3. 所得税に通勤手当を含まないケース

次に、公共交通機関を使う場合とマイカーなどを利用する場合で、課税されないケースを見ていきましょう。
3-1. 電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合
電車・バスなどの公共交通機関を利用して、通勤するためにかかる費用を通勤手当として支給する場合「一カ月あたりの経済的かつ合理的な運賃の額」は非課税となり、最大15万円までは課税対象外です。
①グリーン車も非課税になるケースがある
前述したとおり、新幹線のグリーン車など特別車両に該当する車両で通勤する場合、特別車両料金に該当する額は課税対象です。ただし、高齢者や病気を患っている人、障がいがある人などで、混雑する一般車両での通勤が難しいことが認められた場合は、グリーン車などの特別車両利用料も非課税となるケースがあります。
4. 所得税と通勤手当に関してよくある2つの質問
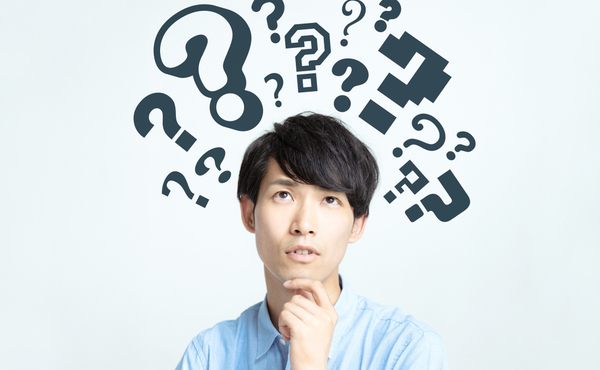 ここからは、所得税と通勤手当に関してよく生じる2つの疑問を紹介します。
ここからは、所得税と通勤手当に関してよく生じる2つの疑問を紹介します。
4-1. 通勤手当の課税・非課税を間違えた場合はどう対処すべき?
万が一、所得税が非課税である通勤手当を課税扱いしてしまうと、従業員の税負担額が増えてしまいます。
そのため間違いが発覚した際には、すみやかに事実を伝えて謝罪しましょう。
その後の対応としては、天引きしすぎた分を「翌月の給与の源泉徴収額で戻す方法」「年末調整で戻す方法」の2つが存在します。従業員の意向に沿った方法で誠実に対応し、再発を防ぐフローを整えましょう。
4-2. 通勤手当で定期代をまとめて支払う場合の対処法
企業の中には、3か月分・6か月分というように、数か月分の通勤手当をまとめて支給するケースも少なくありません。
通常、賃金は毎月1回以上、指定日に支払うよう労働基準法で定められています。しかし、通勤手当は賃金に準ずるものとして扱われるため、この規定に沿わなくても問題ありません。
公共交通機関を利用する従業員に通勤手当を支給する場合は、定期券を購入してもらい長期間分をまとめて支払うほうが割安です。企業にとって経費の削減につながるだけでなく、給与計算の手間も省けるなどのメリットもあります。
定期代をまとめて支払う場合は、就業規則などに支給基準を明記しておきましょう。従業員の負担を減らすため「先払い」で運用するケースが一般的なようです。
5. 通勤手当における事務処理上の注意点

通勤手当においては、事務処理の注意点も多くあります。
5-1. リモートワーク従業員への通勤手当の対処法
働き方改革や新型コロナウイルスの影響で、リモートワークが急速に拡大しています。従来のように通勤することがなくなると、これまで支給していた通勤手当をなくし、出社日分だけを支給したり、実際に出社した日数分をあとから経費精算したりといった方法で対処する企業も増えてきました。
このような方法で通勤手当を支給する場合は、就業規則などにその旨を記載しなければなりません。また、これまでのように通勤手当を定額支給しないため、計算ミスが生じやすくなるので注意が必要です。
また、企業の中には、出社日分の通勤手当しか支給しない代わりに、リモートワーク手当を支給するといった方法で対応するケースもあります。自社が推進する働き方に合わせて、通勤手当も見直すと良いでしょう。
5-2. 通勤手当が課税されている場合は年末調整での対応が必要
公共交通機関による通勤で、1か月あたり15万円を超える場合の通勤手当は、課税対象となります。この場合、年末調整にて給与に含める対応を忘れずにおこなう必要があります。
給与計算を電卓やエクセルでおこなっている場合は、通勤手当の課税・非課税をわけて把握できるよう、記録しておきましょう。給与計算システムであれば、課税・非課税を分けて自動計算ができるため、より業務の効率化を図りたい方におすすめです。
5-3. 通勤手当は標準月額報酬に含めて計算する
限度額内の通勤手当は、所得税の課税対象にはなりません。ただし、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額には含めて計算するため、覚えておきましょう。
6. 通勤手当で不正受給にあたるケース

従業員に悪意がなくても、通勤手当で不正受給になるケースがあります。従業員にしっかり周知できるよう、不正受給となるケースを把握しておきましょう。
6-1. 引越し後の申告漏れ
従業員の引越しによって通勤経路が変わった場合は、経路変更の申請を依頼し、引越し後の通勤経路で通勤手当を支給しなければなりません。この申請をおこなわず、引越し前の通勤経路に対する通勤手当を支給し続けた場合には、従業員に対する不正受給が疑われてしまうことがあります。
6-2. 申請経路・方法以外での通勤
通勤手当を支給するにあたって、通勤経路や通勤方法を申請することになりますが、申請した経路以外での通勤をしている場合は不正受給とみなされます。また、公共交通機関を使っての通勤を申請しているにもかかわらず、徒歩や自転車で通勤するといったケースも不正受給になるため注意しましょう。
6-3. 不正受給が発覚した場合の対処方法
引越しなどによって通勤経路が変わったものの申請をし忘れていた場合、引越し日に遡って超過分を全額返金させましょう。「公共交通機関での通勤申請をしているのに、徒歩で通勤していた」など故意に不正受給をしていた場合で、悪質と認められるケースには、懲戒処分などの罰則が適応されることもあります。
7. 非課税の通勤手当に所得税がかかるのはいつから?
最近、サラリーマン増税という言葉を耳にすることがあるかもしれません。これは、通勤手当などの非課税所得が課税対象となる可能性があることを意味する言葉です。
サラリーマン増税の背景には、会社員の税制制度の手厚さがあります。また、働き方が多様化する中で、通勤手当への課税だけでなく、給与所得控除の上限の引き下げなど、さまざまな増税の検討がおこなわれているようです。
しかし、2024年4月時点で、通勤手当への課税が決まっているわけではありません。今後改正される可能性があるため、注視していく必要があるでしょう。
8. 通勤手当の課税・非課税を正しくとなるケースに注意しよう

公共交通機関を利用する場合で、通勤手当が月15万円を超えるケースはそれほど多くありません。そのため、通勤手当に所得税がかかることも少ないでしょう。
しかし、新幹線通勤でグリーン車を利用する場合などは課税対象となるため注意が必要です。
また、マイカー・バイク・自転車などでの通勤の場合は距離ごとの限度額を把握し、課税対象となる額に対しては必ず所得税を課税するようにしましょう。









