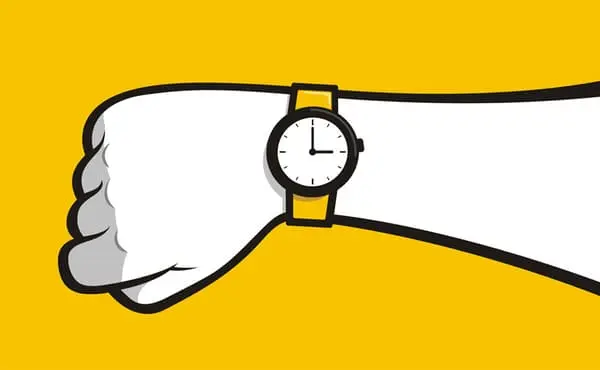
労働安全衛生法の改正により、企業は労働時間を客観的な記録によって把握するよう義務付けられました。過剰な長時間労働を是正し、従業員の健康を守るためにも、勤怠状況をしっかりと管理していきましょう。
今回は、労働時間の把握の義務化とは具体的にどのようなことなのか、対象や労働時間について解説します。また、適正な労働時間を把握する方法も紹介していますので、システム導入を考えている人は参考にしてみてください。
この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。
そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。
法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。
働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひ「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 労働時間の把握の義務化とは

従業員の労働時間を把握することは、給与を正しく計算するためだけでなく、長時間労働を防ぐためにも大切です。そのため、以前より労働時間の把握は重要視されていましたが、労働安全衛生法の改正で、2019年4月から企業は労働時間を客観的な方法で把握することが義務付けられました。
従業員の健康と安全を守るためにも、労働時間の把握は必要不可欠です。まずは、義務化の把握対象や労働時間について解説します。
参考:客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました|厚生労働省
1-1. 労働時間の把握が義務化された背景
労働時間の把握が義務付けられた理由としては、長時間労働により心身の健康を維持できなくなる従業員が多くいることが挙げられます。実は労働安全衛生法が改正される前から、労働時間の把握や従業員の健康維持は重要視されていたのですが、法律上の義務ではなかったため長時間労働が常態化していました。
そこで今回の法改正により、労働時間の把握を企業の義務として明確に定めたのです。各企業は法律に従って従業員ごとの労働時間を把握し、長時間労働を是正するために適切な対応を取らなければなりません。
1-2. 労働時間の把握の対象となる従業員
労働時間の把握は、労働基準法が適用される全ての企業が対象です。また、労働時間を把握する対象者には、一般従業員だけでなく管理監督者や裁量労働制、みなし労働時間制の従業員も含まれます。
管理監督者とは、以下の基準に当てはまる人物のことを指します。
- 経営者と一体的立場にあり責任の重い職務内容である
- 自己裁量で労働時間を管理している
- 地位にふさわしい報酬を受け取っている
- 会社経営に関与している
管理職と管理監督者は混同されがちですが、、立場や待遇が違うだけでなく、法律の適用範囲も異なります。自己の裁量で労働時間や業務量の調整ができ、それ相応の報酬も支払われているという理由から、管理監督者は残業代や休日出勤手当が発生しません。
ただし、時間外労働が80時間時間を超えた場合におこなわれる可能性のある「産業医の面接指導」や、深夜労働に対する割増賃金の支払は対象から除外されないため、管理監督者であっても労働時間の把握をおこなう必要があります。
1-3. 労働時間の定義とは
従業員の労働時間を正しく把握するためには勤怠管理をおこなう必要がありますが、そもそも労働時間とは何を指しているのでしょうか。
労働時間には「法定労働時間」と「所定労働時間」が存在します。法定労働時間とは、労働基準法が定めた労働時間の上限時間で、1日8時間、週40時間までと決められています。対して所定労働時間とは、企業ごとに異なる就業時間のことです。
法定労働時間を超えて働かせる場合は、労使間で36協定を締結しなければなりません。また、法定労働時間を超えた労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
2019年の働き方改革関連法案により、36協定を結んだ場合の時間外労働の上限は下記のようになりました。
- 原則として月45時間、年360時間
- 臨時的で特別な事情があり36協定を結んだ場合に限り年720時間
- 年720時間以内の規制においては、「2~6カ月の間で平均80時間以内」「月100時間未満」「月45時間を超えるのは年6回まで」
1-4. 労働時間と見なされる作業
企業が記録しなければならない労働時間の定義は「労働者が使用者の指揮命令下にある時間」です。
したがって、着用が義務付けられている制服への着替え時間や、強制でおこなわれる掃除なども「労働時間」として記録しなければなりません。
1分単位での管理と計算が求められるため、正しい労働時間を把握することが重要です。
2. 労働基準法で義務付けられている内容

労働時間を適切に把握するために、労働基準法ではいくつか規定が設けられています。各規定について順番に確認しておきましょう。
2-1. 客観的な勤務記録
2019年の働き方改革関連法案の施行により、労働時間を把握するための始業・終業時の打刻や勤務記録は、客観的方法によっておこなわれなければならないと決められました。
客観的方法の具体例としては、打刻システムによる記録、パソコンのログ記録などがあります。それぞれの打刻方法については、後の章で詳しく解説します。
2-2. 賃金台帳への記入
企業は、労働基準法108条及び労働基準法施行規則54条により、従業員の労働日数や労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数などの勤務記録を賃金台帳へ記入することが義務付けられています。
各種記録の未記入や記録の改ざんが発生した場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
2-3. 労働時間の記録書類の保管
労働基準法109条では、企業に対し、従業員の勤務記録を、賃金台帳等と同様に5年間保管することを義務付けています。保管をおこなわなかった場合にも30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、勤務記録は適切に保管しましょう。
2-4. 自己申告制の場合の対応
客観的な方法で労働時間を把握するのが困難な場合は、自己申告制を採用できます。自己申告制とは、従業員が手作業でエクセルや出勤簿などに時刻を入力する方法です。ただし、自己申告制が認められるのは限定的であるため、基本的には客観的な方法で労働時間管理をおこなえるよう環境を整えましょう。
また、自己申告制を採用する場合は、正しく自己申告するよう従業員へ指導する、実際の労働時間と合致しているか必要に応じて実態調査をおこなう、といった措置を講じなければなりません。
3. 適正な労働時間把握をするための対応

従業員の労働時間は、適正な方法で正しく把握されなければなりません。近年、テレワークの増加により「始業時間と終業時間は自己申告制で記録している」という企業も増えています。
前述の通り、厚生労働省は適正な運用を従業員に十分に説明することを条件に自己申告制を認めていますが、入力ミスや虚偽の入力などが起こる可能性も考えられます。
労働時間を客観的かつ効率的に把握するためには、以下のような方法を採用するとよいでしょう。
3-1. タイムカード・ICカード
紙のタイムカードでの勤怠管理は、最もシンプルで昔から使われてきた方法です。導入コストが抑えられ、誰でも簡単に使える特徴がありますが、紙媒体であることから集計の際のミスが発生しやすく、「他の人に打刻してもらう」などの不正が起こる可能性も考えられます。
そのため、最近では紙のタイムカードではなく、ICカードを用いた打刻を導入している企業が増えています。ICカードでの打刻は出勤と退勤時に、機械へかざすだけなのでタイムカードと似た側面がありますが、デジタルデータで記録される点はタイムカードと異なり、集計や計算も自動でおこなってくれる点が便利です。
3-2. 勤怠管理システム
ICカードも勤怠管理システムのひとつですが、さらに不正を防ぐための方法として指紋や顔認証を用いた打刻方法があります。
生体認証を活用すれば、他人が打刻するなどの不正を確実に防止することができ、会社の入り口などに設置しておけば、打刻忘れも防ぐことができるでしょう。
また、営業職など外回りが多い場合は、GPS機能が備わった打刻システムがおすすめです。スマートフォンの位置情報と打刻時刻を同時に記録してくれるため、どこでいつ打刻したのか正確に把握できます。不正の防止だけでなく、事業所に戻ったり連絡したりする手間も省けるなど、効率化を図るためにも有効的でしょう。
3-3. パソコンのログを利用する
テレワークで自己申告制を導入している企業におすすめな方法がパソコンのログを使った勤怠管理です。
パソコンは起動した時間がログとして保存されているため、そのデータを労働時間として記録できます。勤怠管理ソフトで申告している時刻よりも長く働く「隠れ残業」が見つかる可能性もあるため、正確な労働時間を把握する方法として活用できるでしょう。
ただし、パソコンをログアウトし忘れてしまった場合は、正しい時間が記録されません。また、ログの確認は従業員の数が多いほど手間がかかり、データの一元管理も難しいため、ログ管理システムの利用や、勤怠管理システムとの併用がおすすめです。
4. 労働時間の把握に違反したときの罰則

労働時間の把握は義務化されていますが、正確に把握されていなかったとしても現時点での罰則規定は存在しません。
しかし、先ほど説明した「時間外労働時間の上限」を超えた場合は、罰則があるため注意が必要です。この場合は「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
また、労働基準法108条及び109条では、賃金台帳の作成と記録の保存が義務付けられており、賃金台帳には従業員の労働日数や労働時間の記入が必要です。労働時間管理に用いたタイムカードや出勤簿は賃金台帳とともに、5年間保管しなければなりません。
決められた期間保管していなかった場合や、適切に記入されていなかった場合は、先述の通り「30万円以下の罰金」が科せられる恐れがあります。
労働時間の把握に関しては罰則がないにしても、把握や記録を怠ると労働基準法で定められた他の規定によって罰則が科せられるため、労働時間管理は必ずおこなうようにしましょう。
5. 労働時間の把握義務化へ対応するためのポイント

労働時間の把握義務化へ対応するためには、残業申請ルールを設定したり、従業員へ法改正について周知したりすることが重要です。以下、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
5-1. 残業申請ルールを設定する
労働時間を正確に把握するため、残業の事前申請ルールを設定するとよいでしょう。従業員が自由に残業できる状態では、知らないうちに労働時間の上限を超えてしまう可能性もあります。
また、急ぎではない業務をこなすために、無駄な残業が発生しているケースもあるでしょう。残業をするときは事前申請が必要なルールにすれば、上司が労働時間や作業の必要性を確認したうえで、残業を許可することが可能です。
5-2. 法律改正について周知する
法律改正について従業員へ周知することも大切です。労働時間の把握が義務化されたことや、従業員の健康維持が重要視されていることなどを従業員へ伝えておきましょう。朝礼や会議で伝えるほか、ポスターで掲示したり社内ホームページに掲載したりすると効率よく周知できます。
6. 労働時間は適正な方法で把握して管理しよう

今回は、労働時間の把握の義務化や、具体的な方法について解説しました。労働時間を管理することは、従業員の健康維持や正しい給与計算のためにとても重要な作業です。過剰な長時間労働は従業員の心身の健康に悪影響を与えるため、適正な管理をおこない、必要に応じて社内環境を改善していきましょう。
また、従業員ごとの労働時間は、客観的な方法で記録しなければなりません。手作業での申告や管理は、手間がかかるだけではなく、ミスや不正も起こりやすいため、勤怠管理に適したシステムを利用して客観的な労働時間の把握を実現しましょう。









