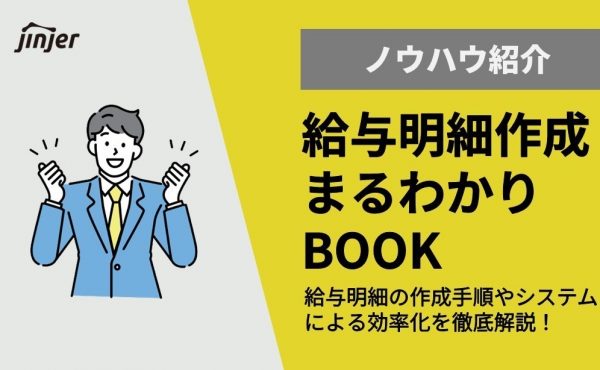給与明細の電子化とは、国税庁で定めた電子化方法で給与明細を発行することを指します。印刷の必要もなければ配布も容易になるなどのメリットから、導入する企業の数は増加中です。もちろんメリットがあればデメリットもあります。この記事では、給与明細の電子化を導入する方法や、同意書の必要性、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
毎月給料日近くになるとやってくる給与計算業務。
その中でも給与明細の発行と封入作業は、従業員の数が増えれば増えるだけ工数がかかり、根気が必要な業務になります。
また、給与明細の発行・交付が法律で決まっているにもかかわらず、従業員が持ち帰り忘れたり、出社しないため会社に残ったまま、というようなこともあるでしょう。
そこで本資料では、給与明細の複雑な作成ステップやその一連のフローをシステムの導入により、どのように効率化できるかなどを、実際の管理画面をお見せしながら解説しております。
「給与明細関連の業務を自動化したい」
「いつでも従業員が給与明細を見れるようにしたい」
このような悩みを抱えている担当者の方は、「給与明細作成まるわかりBOOK」をぜひご覧ください。
目次
1. 給与明細の電子化とは

給与明細の電子化とは「給与明細を電子ファイル化して交付すること」を指します。ペーパーレス化を推進するため、給与明細の電子化を導入する企業は増えています。国税庁により、給与明細の電子化の方法は以下の3つに定められています。
- 電子メールを利用する方法
- 社内LAN・WANやインターネットなどを利用して閲覧に供する方法
- フロッピーディスク、MO、CD-ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法
通常は電子メールかクラウド上で閲覧する方法が一般的です。給与明細の電子化の際には、定められた形で交付できるよう環境を整えることが大切です。
2. 給与明細を電子化するには従業員の同意が必要!

所得税法第231条により、給与明細を電子化するには、従業員の同意が必要になります。
退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
ここでは、給与明細を電子化するための同意の取り方と、同意書のテンプレートを紹介します。
2-1. 給与明細を電子化するための同意の取り方
給与明細を電子化するための同意の取り方に決まりはありません。そのため、口頭でも法律上は可能です。しかし、口頭の場合、証拠を残せないので、後にトラブルが生じる恐れがあります。
従業員から同意を得た証拠を残すため、紙や電子データの同意書を活用するのがおすすめです。紙媒体の同意書の場合、手続きに時間がかかる可能性もあります。また、紛失リスクもあります。一方、電子データであれば、メールやチャットなどで従業員に送付し、システム上で安全に保管することが可能です。
関連記事:給与明細の電子化には同意書がいる?必要性を詳しく解説
2-2. 給与明細の同意書内容の具体例
同意書について公的なテンプレートはなく、必要な項目が揃っていれば問題ありません。「どの書類を」「いつ」「どのように渡すのか」を記載しましょう。テンプレート例は以下のとおりです。
給与明細等電子交付同意書
私は、以下の内容による給与明細等の電子交付を受けることについて、同意します。
- 電子化して交付する書類の名称
- 電磁的方法の種類
- システムの利用方法
- 記録方法
- 交付予定日
毎月、給与(賞与)支給日の前日に交付
- 交付開始日
20 年 月 日( )
3. 給与明細を電子化するメリット(企業)
 給与明細を電子化することで、さまざまなメリットが得られます。ここでは、企業側の給与明細を電子化するメリットについて詳しく紹介します。
給与明細を電子化することで、さまざまなメリットが得られます。ここでは、企業側の給与明細を電子化するメリットについて詳しく紹介します。
3-1. コスト削減
給与明細を紙で発行する場合、紙代・印刷代・郵送代など、さまざまなコストがかかります。また、給与明細の写しを保管するためのコストもかかります。これらのコストは従業員数に比例して増えていくので、企業の規模が大きくなればなるほど負担も大きくなります。
給与明細を電子化すれば、ペーパーレス化を推進し、紙代や印刷代を削減することが可能です。また、メールやシステム上でやり取りできるので、郵送費用もかかりません。さらに、システム上で給与明細を管理できるため、保管コストを削減することができます。
3-2. 業務効率化
給与明細を紙で発行する場合、書類の作成・印刷・封入・郵送などの際に人的ミスが発生する可能性があります。人的ミスが生じると、給与明細を再度作成し直さなければならず、時間や手間がかかります。
給与明細を電子化することで、書類の作成から送付まで自動で処理することが可能です。そのため、きちんと運用方法を構築していれば、人的ミスの発生リスクを抑え、業務を効率化することができます。
3-3. 多様な働き方の推進
働き方改革の影響を受け、テレワークを推進している企業も少なくないでしょう。紙媒体の給与明細を発行するには、印刷や封入といった業務が必要になるので、オフィスに出社しなければ作業することができません。
給与明細を電子化すれば、PCとネット環境があれば、システム上で給与明細に関わるすべての業務をおこなえるため、リモートワークを推進することができます。このように、給与明細の電子化の導入は、多様な働き方を推進するための一歩となります。
4. 給与明細を電子化するメリット(従業員)

ここでは、従業員側の給与明細を電子化するメリットについて詳しく紹介します。
4-1. 時間や場所を問わず確認できる
紙の給与明細を自宅に保管している場合は「在宅時」、オフィスで管理している場合は「出社時」にだけ確認することができます。給与明細が電子化されれば、PCやスマホといった端末とネット環境があれば、時間や場所を問わず参照することが可能です。行政手続きなどで、給与明細が必要になるケースもあるので、いつでも閲覧できるようにしておくのがおすすめです。
4-2. 紛失リスク低下
紙の給与明細の場合、紛失リスクがあります。給与明細には企業名や個人名など、企業情報・個人情報が記載されています。そのため、紛失すると、社外秘の情報が漏洩し、企業の社会的信用を損なう恐れもあります。
給与明細を電子化すれば、システム上で管理できるので、紛失リスクを低減させることが可能です。また、封筒やファイルなどでまとめる必要もないため、管理の手間を減らすことができます。
5. 給与明細を電子化するデメリット(企業)

給与明細を電子化する場合、メリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、企業側の給与明細を電子化するデメリットについて詳しく紹介します。
5-1. システム導入コストがかかる
給与明細を電子化するには、専用のシステムの導入が必要です。システムを導入するには、初期費用や運用費用などのコストがかかります。そのため、自社の課題や目的にあったシステム選びが重要になります。
5-2. 情報が漏洩する恐れがある
給与明細を電子化したとしても、情報が漏洩するリスクはあります。
たとえば、電子メールで送付する場合、宛先や添付資料を間違えると、意図せず個人情報が漏れてしまう可能性があります。また、システムで交付する場合、パスワードやアクセス権限などを適切に付与していないと、社外の人間でも閲覧できてしまう恐れがあります。
給与明細を電子化する場合、セキュリティリスクについて洗い出し、あらかじめ対策を検討しておくことが大切です。
6. 給与明細を電子化するデメリット(従業員)
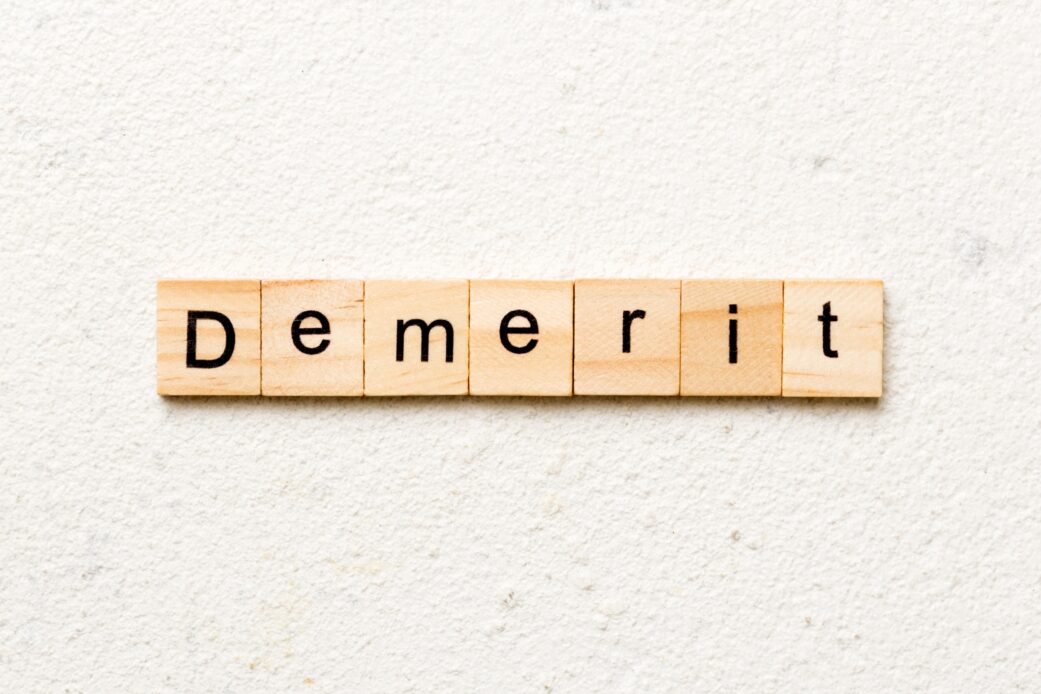
ここでは、従業員側の給与明細を電子化するデメリットについて詳しく紹介します。
6-1. メンテナンス時には閲覧できない
給与明細を電子化する場合、システムの改修・メンテナンスが必要になります。従業員は、システムメンテナンス時に給与明細を閲覧することができません。システムメンテナンスをおこなう場合は、事前に従業員にきちんと周知しておきましょう。
6-2. 長期間保管したい場合はデータ保存が必要
従業員は紙媒体の給与明細であれば、適切に保管しておくことで、いつの分でも確認することができます。しかし、電子データの場合、保管期間が無期限ではない可能性もあります。たとえば、退職すると、閲覧できなくなるケースもあります。
そのため、企業側はデータの保存期間やルールをきちんと従業員に周知しておくことが大切です。また、従業員側は長期間にわたって給与明細を保管したい場合、自分のサーバーなどに定期的に保存するようにしましょう。その際にセキュリティリスクがあることも忘れてはいけません。
7. 給与明細を電子化する方法と手順

給与明細の電子化には必ずおこなわなければならない手順もあります。ここでは、給与明細の電子化を導入する方法とその手順について詳しく紹介します。
7-1. 現時点での管理方法を見直す
まずは給与明細の電子化が必要かどうかをメリット・デメリットを踏まえて検討しましょう。従業員数が少ない場合、システム導入・運用コストの観点から、電子化しないほうがよい可能性もあります。
給与明細の電子化が必要だと判断されたら、電子化する書類の範囲を明確化します。たとえば、給与明細だけでなく、源泉徴収票も電子化するかどうかを検討しましょう。また、勤怠管理システムや給与計算システムなどを導入している場合、連携が必要かどうかもチェックしましょう。
7-2. 従業員の同意を得る
給与明細の電子化を導入するには、従業員の同意が不可欠です。すべての従業員から同意が得られば、紙での給与明細の交付を例外として位置づけ、コスト削減や業務効率化が期待できます。
まずは全従業員の給与明細へのアクセス環境を把握しましょう。PCやスマホなどの所有状況を確認し、従業員に配慮した給与明細電子化システムを選択することが大切です。また、従業員にシステムの内容や制度を説明し、理解を深めてもらうことも重要です。
7-3. 給与明細電子化システムを導入する
従業員の同意が得られたら、実際に給与明細電子化システムを導入します。管理担当者だけでなく、従業員から見ても使いやすいシステムを選定することが大切です。また、社内に定着させるために、十分なサポート体制が用意されているシステムを選ぶのがおすすめです。
このように、給与明細を電子化する際にはいくつかの確認しておくべき事項があります。まず、給与明細に必要な要件がそろっているか、電子化するための要件がそろっているかを確認しておきましょう。 当サイトでは、給与明細の作成をする上で確認しておくべき項目をまとめて解説した資料を無料でお配りしています。 法律に則った給与明細を作成できているのか確認したい方はこちらから「給与明細作成まるわかりBOOK」をダウンロードしてご活用ください。
8. 給与明細を電子化する際の注意点
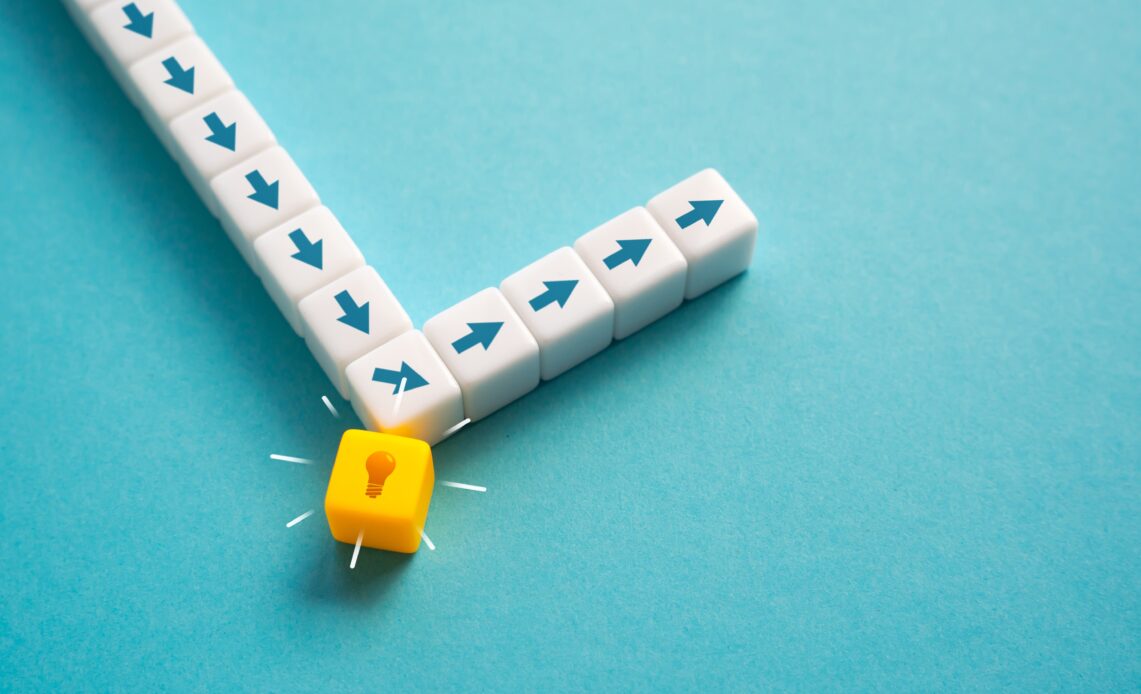
ここでは、給与明細を電子化する際の注意点について詳しく紹介します。
8-1. 紙で発行できる体制も残しておく
給与明細の電子化について従業員から同意が得られない可能性もあります。同意を得られなかった場合や、請求があった場合は、紙で給与明細を交付しなければなりません。
当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない
電子発行のシステムを用意していても、従業員からの同意がなければ使えません。また、金融機関のローンなどの審査用に紙での給与明細が必要となる場合もあります。従業員の希望に応じて、紙でも発行ができる体制を残しておくことも重要です。紙での給与明細の発行体制を残しておくことは、システム障害時の対策にもなります。
8-2. 給与明細の保管方法や保管期間に気を付ける
電子化された給与明細は、労働基準法や電子帳簿保存法などの法律に遵守したうえで、適切に保管する必要があります。
労働基準法第109条により、企業は従業員に交付する給与明細の写しを5年間保存しなければなりません。ただし、労働基準法第109条には経過措置が設けられており、当分の間の保管期間は3年で問題ありません。いつ経過措置が終了するかは未定なので、できる限り5年間保管しておくことが推奨されます。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
関連記事:電子帳簿保存法における要件は?具体的な保存方法も紹介
8-3. 自社のニーズにあう給与明細電子化システムを導入する
給与明細電子化システムには、さまざまな種類があります。自社のニーズにあわないシステムを導入すると、想定しているよりもコストがかかったり、機能を上手く使いこなせなかったりする可能性があります。
まずは給与明細電子化システムを導入する目的を明確にし、過不足のない機能を搭載したシステムを選ぶことが大切です。また、料金や使いやすさ、セキュリティ、サポートなど、あらゆる観点から複数のツールを比較することも重要です。既存の勤怠管理システムや給与計算ソフトと連携できるシステムを選べば、より業務を効率化させることができます。
関連記事:Web給与明細システムとは?タイプと選び方&導入メリットを解説
9. 給与明細の電子化を有効活用しよう
 給与明細の電子化は、企業側と従業員それぞれにメリットをもたらします。導入には従業員の同意を得ることも重要ですが、自社の事情にあったシステムを選ぶことも大切です。セキュリティなどにも気を配り、最適なシステムを見つけ出しましょう。
給与明細の電子化は、企業側と従業員それぞれにメリットをもたらします。導入には従業員の同意を得ることも重要ですが、自社の事情にあったシステムを選ぶことも大切です。セキュリティなどにも気を配り、最適なシステムを見つけ出しましょう。
毎月給料日近くになるとやってくる給与計算業務。
その中でも給与明細の発行と封入作業は、従業員の数が増えれば増えるだけ工数がかかり、根気が必要な業務になります。
また、給与明細の発行・交付が法律で決まっているにもかかわらず、従業員が持ち帰り忘れたり、出社しないため会社に残ったまま、というようなこともあるでしょう。
そこで本資料では、給与明細の複雑な作成ステップやその一連のフローをシステムの導入により、どのように効率化できるかなどを、実際の管理画面をお見せしながら解説しております。
「給与明細関連の業務を自動化したい」
「いつでも従業員が給与明細を見れるようにしたい」
このような悩みを抱えている担当者の方は、「給与明細作成まるわかりBOOK」をぜひご覧ください。