
雇用保険被保険者資格取得届の提出方法には、窓口での提出の他に郵送と電子申請があります。
窓口に向かう時間がない、近くにハローワークがない場合などに郵送は便利です。
郵送での提出方法や、郵送時の注意点を解説します。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届とは?作成方法をわかりやすく紹介
目次
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 雇用保険被保険者資格取得届は郵送できる?
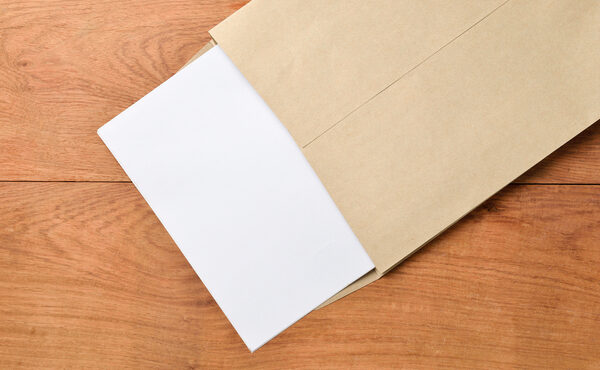
その一つが雇用保険被保険者資格取得届です。
雇用保険被保険者資格取得届は従業員を新たに雇用した月の翌月10日までの提出が義務付けられています。
窓口に行けばすぐに提出できますが、業務上窓口が開いている時間に会社を抜けられないこともあります。
ハローワークに行くまでの時間や受付で待たされる時間なども考えると、窓口での提出は効率的ではありません。
郵送であれば必要書類を送付するだけで提出が完了するので、時間が取れない場合などにおすすめです。
近年は新型コロナウイルスの影響によって、郵送や電子申請も推奨されています。
また、今後は電子申請の義務化が進むことも予想されています。
窓口以外の提出方法も抑えておく必要があります。
2. 雇用保険被保険者資格取得届の郵送方法

実際に雇用保険被保険者資格取得届を郵送する方法を解説します。
書類をダウンロードする段階で不備があると正式な書類として認められないので注意してください。
また、送付状の添付も推奨されています。
郵送方法にも注意して、正しく雇用保険被保険者資格取得届を提出ましょう。
2-1. 書類を正しくダウンロードする
まずは提出する雇用保険被保険者資格取得届をダウンロードし、印刷しなければなりません。
窓口に書類をもらいにいかなくても、ハローワークのホームページからダウンロードできます。
書類だけをダウンロードする方法と、あらかじめ必要事項を記入してからダウンロードする方法があります。
使いやすい方法を選びましょう。
ダウンロードした書類を印刷する際は、A4の白色用紙を使わなければなりません。
また、雇用保険被保険者資格取得届は機械で読み込みをおこなうため、基準マークまできちんと印刷する必要があります。
等倍で印刷し、ズレ、ボケ、かすれがないかよく確認してから提出しましょう。
どれか一つにでも不備があると正式な書類と認められず、再提出のためかえって時間がかかってしまいます。
2-2. 必要書類を揃える
基本的に雇用保険被保険者資格取得届の提出には別途添付資料は必要ありません。
ですが、事業者が初めて雇用保険被保険者資格取得届の申請をおこなう場合は提出期限が過ぎている場合、労働保険料の滞納がある場合などはそれぞれを証明するための書類の添付が義務付けられています。
必要書類が欠けていると郵送後再提出の連絡が来ます。
窓口での申請や電子申請よりも手間やコスト、時間がかかってしまう可能性があるので、必要書類は漏れのないようにしてください。
とはいえ、雇用保険手続きの対応で漏れが起きていないかか不安なご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、雇用保険手続きに必要な書類や手続きの流れを一冊にまとめた資料を無料でお配りしています。
社会保険手続きを漏れなく遅滞なくおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードして、ご活用ください。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の遅延理由書が必要なケースや書き方
2-3. 送付状を添える
必須ではありませんが、ハローワークへ書類を提出する際は送付状の添付が推奨されています。
何についての申請書類なのか、何枚の書類が同封されているのか、添付資料の詳細など、ハローワークの職員がスムーズに受け取りの作業ができるように考慮して送付状を作成しましょう。
2-4. 追跡できる方法で郵送する
雇用保険被保険者資格取得届はマイナンバーなどの個人情報を多く記入する書類です。
個人情報漏洩を防ぐためにも、一般郵便は使用しないようにしてください。
配達状況の追跡ができる特定記録や簡易書留が推奨されています。
3. 雇用保険被保険者資格取得届を郵送するときの注意点

雇用保険被保険者資格取得届を郵送する際にはさまざまな点に注意しなければなりません。
再提出になると余計な時間やコストがかかるため、一発で受理してもらえるよう下記の注意点を意識してください。
3-1. 返信用封筒の同封が必要
雇用保険被保険者資格取得届が受理されると、受理されたことを証明する書類が送られてきます。
書類を送付してもらうためにはあらかじめ返信用の封筒を同封する必要があります。
受理を証明する書類にも個人情報は記載されているため、一般郵便は避けるべきです。
返信用封筒も簡易書留やレターパックプラスなど、追跡、受け取り確認ができるものを選んでください。
3-2. 間違えた箇所を郵送で訂正する場合
雇用保険被保険者資格取得届の内容が間違っていたことに提出後気付いた場合、郵送で内容の訂正ができます。
訂正する場合は、ハローワークのホームページから雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届訂正(取消)願をダウンロードしてプリントアウトし、間違った内容と正しい内容をそれぞれ記入します。
さらに正しい情報を証明するための資料も添付しなければなりません。
必要資料はハローワークによっても指定が違うので、時間のロスを防ぐためにもあらかじめ確認しておきましょう。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届を書き間違えたときの処理方法
3-3. 前職の資格喪失手続きが済んでいない場合
前職の雇用保険の資格喪失手続きが済んでいない場合、現在雇用している企業が雇用保険被保険者資格取得届を提出しても正しい手続きができません。
この場合はハローワークから手続きができない旨の連絡が入ります。
企業で何か対策をする必要はありませんが、従業員の前の職場に資格喪失手続きをしてもらうよう連絡してもわなければなりません。
4. 雇用保険被保険者資格取得届の郵送以外の提出方法

雇用保険被保険者資格取得届は郵送以外にも、窓口、電子申請の方法があります。
それぞれの申請方法を簡単に解説します。
4-1. 窓口で提出する方法
窓口で提出する場合は管轄のハローワークの窓口に相談します。
書類などはハローワークで用意してくれます。
個人情報を入力するための書類を持参しなければならないので慎重に取り扱ってください。
適切な手続きを済ませ、不備がなければその場で受理を証明する書類を発行してもらえます。
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書などを受け取り、被保険者向けの書類は該当の従業員に渡してください。
4-2. 電子申請する方法
雇用保険被保険者資格取得届はe-Govというサイトから電子申請が可能です。
電子申請をするためにはe-Govのダウンロード、アカウントの取得を済ませておく必要がありますが、どれもすぐにできるので早めに用意しておきましょう。
電子申請で不備がなく書類を受理されると公文書を発行してもらえるので、各自ダウンロード、プリントアウトして保管しましょう。
e-Govは雇用保険被保険者資格取得届以外にもさまざまな書類の作成、電子申請ができます。
今後電子申請が義務化される可能性もあるため、早めに操作に慣れておくことをおすすめします。
5. 雇用保険被保険者資格取得届を郵送で提出しよう

雇用保険被保険者資格取得届を郵送で提出する方法を紹介しました。
郵送は窓口に行くよりも簡単にできますが、送付状や返信用封筒の用意、簡易書留やレターパックの手続きなどに手間取る可能性もあります。
また、書類に不備があると連絡が来て再度正しい書類を提出しなければなりません。
窓口よりも余計な時間がかかる可能性も考慮しておきましょう。
e-Govでは郵送よりもさらに簡単な電子申請ができます。
電子申請の方法にも慣れておくと、今後さまざまな書類の作成が楽になるでしょう。









