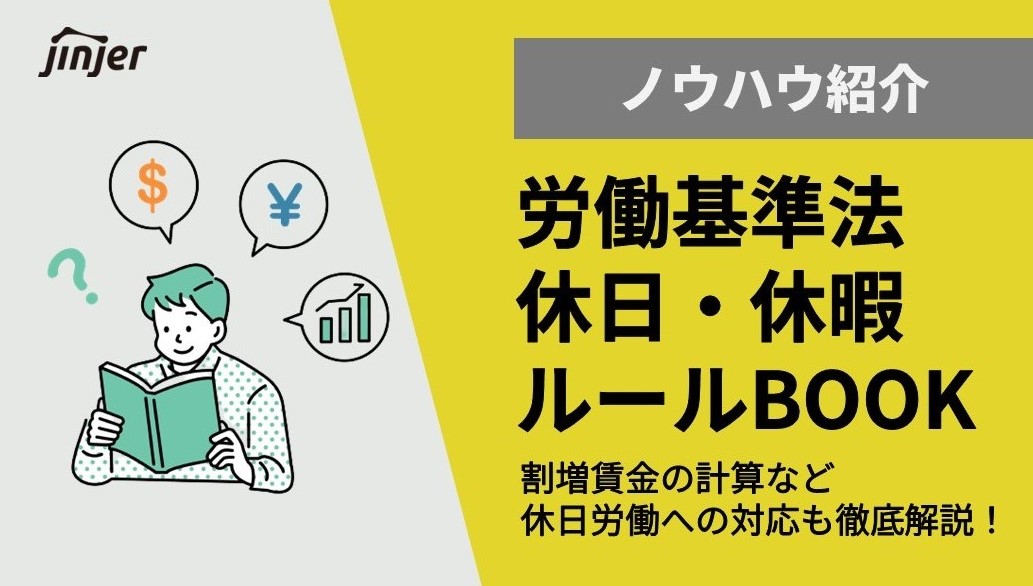会社が従業員に与える休日に公休があります。
公休は他の有給休暇や特別休暇などと意味合いや取り扱いが異なります。
他の休暇との違いをおさえておくことは、労務管理を正しくおこなう上でも非常に大切です。
今回は、労働基準法における公休の扱いやその他休暇との違いについて詳しく解説します。
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法における公休とは

公休とは、会社が定めている休日のことをいいます。休日には「所定休日」と「法定休日」がありますが、公休はその二つをあわせたよび方です。
例えば、就業規則などで「土曜と日曜を休みとし週休2日制とする」と定めているような場合は、土曜と日曜が公休にあたります。
公休を定める場合、会社が自社の都合に合わせて自由に決めて良いわけでなく、労働基準法の「法定休日」のルールに従って定めなくてはいけません。法定休日とは、週に1回以上または4週に4回以上の取得を義務付けた労働基準法上の休日のことです。[注1]
一方、法定休日とは別に、会社独自で決めた休日が「所定休日」になります。
前述の例で挙げた週休2日制は、法定休日に所定休日を組み合わせて設定していることになります。
なお、公休を含む休みについては就業規則に記載することが義務付けられています。
関連記事:法定休日をサクッと理解|法定外休日との違いや振替休日・代休との関係について解説
2. 公休とは?有給などそのほかの休暇・休みの違い

公休以外にも、従業員に与えられている休みに「有給休暇」や「特別休暇」があります。
公休とこれら休暇との違いを知っておくと、労務管理をおこなう上で役立ちますので、ここでしっかり押さえておきましょう。
2-1. 公休と法定休日の違い
公休と法定休日の違いは所定休日を含むかどうかです。法定休日は企業が最低限設定しなければならないと労働基準法で定められた休日です。一方、所定休日は企業が独自に設定している休日です。
そのため、所定休日がまったくない企業の場合、公休=法定休日となりますが、そうでないほとんどの場合、公休と法定休日は異なるものです。
2-2. 公休と欠勤の違い
公休と欠勤はまったくの別物です。公休とはそもそも企業が定めた所定休日と法定休日のことです。そして、休日とは、労働義務のない日を指します。
一方の欠勤は、労働義務のある日に休むことを指します。
また、企業側と労働者側どちらの都合で休んだかでも意味が異なります。
休みであることには変わりがないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、有給休暇の付与条件である出勤率を算出する場合や人事評価などにかかわってくるため、きちんとすみ分けをしておく必要があります。
2-3. 公休と有給の違い
有給休暇とは、賃金が支払われる休暇のことをいいます。
労働基準法では、6ヵ月以上勤続し、全労働日の8割以上出社した労働者に所定日数の休暇を与えることを雇用主へ義務付けています。[注2]雇用主は、労働者の希望する日に有給休暇を与えなくてはいけません。
一方で、公休は賃金支払い義務が伴わない休日です。
有給休暇との間には賃金発生の有無で大きな違いがあります。
また、有給休暇は原則労働者が自由に取得日を決められるのに対し、公休は事前に休日が決まっているといった違いもあります。
2-4. 公休と特別休暇の違い
特別休暇とは、会社が福利厚生の目的で独自に設定している休暇のことです。
例として、慶弔休暇やリフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇などが挙げられます。
特別休暇では、取得条件があらかじめ設けられていることが特徴としてあり、条件を満たした労働者の申請によって休暇を取得することができます。
一方、公休は事前に休日が定められているため、取得条件などに関係なく全ての労働者が休むことができます。従業員に休日休暇を取得させる際には、取得条件や賃金支払いの発生の有無などを確認しておく必要があります。当サイトでは、休日休暇の基本的なルールや休日休暇を取得させる際の対応についてまとめた資料を無料で配布しております。休日休暇の違いや種類を理解したい方は、こちらからダウンロードして、業務にお役立てください。
3. 公休の最低日数

会社が労働基準法に則って休日を設定していくにあたって、公休の最低日数を事前確認しておく必要があるでしょう。
前述した通り、労働基準法では「週に1回以上または4週に4回以上」の法定休日の設定を会社に義務付けています。
また、法定休日以外にも、労働時間の上限「1日8時間、週に40時間」についても考慮しなくてはいけません。
1年間は52週ありますので、週に40時間までの労働時間とすると、2,080時間が年間の労働時間の上限となります。
1日の労働時間の上限は8時間ですので、2,080時間を8時間で割ると年間の労働日数の上限は260日です。
365日から260日を引いた日数105日が公休の最低日数となります。
年間に最低105日は公休を確保しておかないと、労働基準法に抵触する可能性もありますので注意しましょう。
ただし、36協定を締結しており、36協定の範囲内で休日を与えている場合は除きます。
4. 公休に関するよくある疑問

最後に、公休に関して多く寄せられる疑問について回答します。
実務上での処理の仕方なども交えながら解説しますので、ぜひご参考にしてみてください。
4-1. 公休とは給料を支払う必要のあるもの?
公休については、賃金を支払う必要はありません。
これは、労務の提供の無い日は賃金の支払い義務はないとする「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用となるためです。
ただし、公休に勤務を命じた場合は、休日手当を支払う必要があります。
法定休日に勤務させた場合は、35%以上の割増率を乗じて計算しなくてはいけません。[注3]
所定休日に関しては、法定労働時間を超えている場合、25%以上の割増率を乗じて賃金計算する必要があります。
4-2. 公休に休日勤務させても問題ない?
公休に休日勤務をさせた場合は、別日に代わりの休みを付与するのが一般的です。
公休の代わりとなる休みを与えないことは、従業員の健康やメンタルヘルスを適切に管理する上でも望ましいことではありません。
休みを振り替える方法には、振替休日または代休を付与する方法があります。
事前に公休の代わりの休みを指定できる場合は、振替休日で公休の振替をしておきます。
この場合は、事前に公休の入れ替えをしていますので、休日労働に対する休日手当の支給は不要です。
事前に入れ替えが難しい場合は、代休で事後に休みを入れ替えします。
代休の場合は、事後に公休の入れ替えをするため、休日手当の支払いが必要となります。
いずれかの方法で、公休の代わりとなる休みを取得させるようにしましょう。
4-3. 公休とはパートやアルバイトなどシフト勤務でも関係はある?
公休の中でも、週に1回または4週に4回の法定休日に関しては、パートやアルバイトなど雇用形態に関係なく全労働者に与えなければならないとされています。
パートやアルバイトに法定休日を与えずに働かせた場合は、労働基準法の違反とされ、罰則が適用となりますので注意が必要です。
なお、所定休日に関しては会社が自由に定めることができるので、パートやアルバイトに与えなくても違法とはなりません。
ただし、就業規則でパートやアルバイトに与えることを規定しているにも関わらず、所定休日を与えなかった場合は、就業規則違反となりますので注意しましょう。
4-4. 自然災害時は公休として扱えるか?
地震や台風など自然災害が発生した場合、従業員の休みを公休として扱うかどうかは、会社側の判断によります。
自然災害の影響により公共交通機関が停止するようなケースでは、従業員に出社させるのは困難であると判断し、公休を従業員に与えるケースが多いようです。
一方で、会社ではなく従業員が判断して休みを取得する場合は、欠勤や有給消化として扱われるのがほとんどのようです。
いずれにしても、自然災害が起きた際にスムーズに対応ができるよう、あらかじめどのような対応をするか決めておいた方が良いでしょう。
4-5. 公休は繰り越しができる?
公休は年をまたいでの繰り越しをすることはできません。いくら多く公休出勤をしていても、年をまたぐと代休を取れなくなるため、その年のうちに消化するよう注意が必要です。
一方、有給は最大2年間まで繰り越しができます。公休と有給を混同しないように注意しましょう
4-6. 「公休扱い」とは何?
公休扱い」とは、欠勤にならない休日のことで、公休として定められていない日を公休として特別に処理することを指します。
例えば、親族に不幸があった際や、結婚式があるときなどに、本来勤務日だった日を公休扱いにすることで、従業員が欠勤になることが避けられます。また、欠勤扱いにならないため、昇給や賞与などに影響を与えることもありません。
公休扱いは不可抗力の欠勤の場合に利用でき、従業員にとってもメリットが多くあります。どのようなものを公休扱いにするかは、あらかじめ社内規定に設けておくとよいでしょう。
5. 公休に出勤した際の会社側の注意点
何らかの理由で従業員が公休に出勤することになった場合、会社側として注意しておきたい点があります。以下ではその注意点を解説します。
5-1. 割増賃金を支払うケースがある
従業員が公休に出勤する際には、会社側が従業員に割増賃金を支払わなければならなくなるケースがあります。割増賃金の支払が必要となるケースは以下の2つです。
- 法定休日に出勤する場合
- 所定休日に出勤する場合
法律で定められている法定休日に出勤する場合は、「労働時間の35%」の休日手当の支払が必要となります。
所定休日の場合は休日手当は不要となるものの、労働時間が1日8時間かつ週に40時間を超える場合は、週40時間を超えた分の労働時間に対して25%の割増賃金の支払が必要です。
公休には法定休日と所定休日の2種類があるため、混同しないように注意しましょう。
5-2. 代休や振替休日などを付与する
従業員を公休に出勤させた場合は、原則として代わりの休みを与えることとなっています。
そして、代休と振替休日では発生する休日割増賃金が異なるため注意が必要です。休日出勤後に「代休」として休日を与える場合には、割増賃金を支払わなければならず、休みで相殺しても、35%の割増賃金を支払います。
また、「振替休日」として前もって勤務日と休日を入れ替える場合は「振替休日」となり、休日手当の発生はありません。ただし、週の勤務時間が40時間を超える場合は、休みで相殺しても25%の割増賃金を支払います。
6. 公休の考え方を正しく理解し労務管理に活かそう

公休とは会社があらかじめ定めた休日のことを指します。
労働基準法における「法定休日」の他にも会社が独自に定める「所定休日」も公休に含まれます。
公休と有給休暇や特別休暇は、賃金や付与条件などで取扱いに違いがありますので、労務管理する際は注意が必要です。
また、会社が公休を設定する際には、労働基準法上で必要とされる最低日数105日を下回らないようにしなくてはいけません。
公休について正しく理解しておくことは、労務管理を適正におこなう上で必要です。
ぜひ、この機会にしっかりポイントをおさえておきましょう。
[注1]労働時間・休日|厚生労働省
[注2]年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています|厚生労働省
[注3]しっかりマスター労働基準法「割増賃金編」|厚生労働省
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK