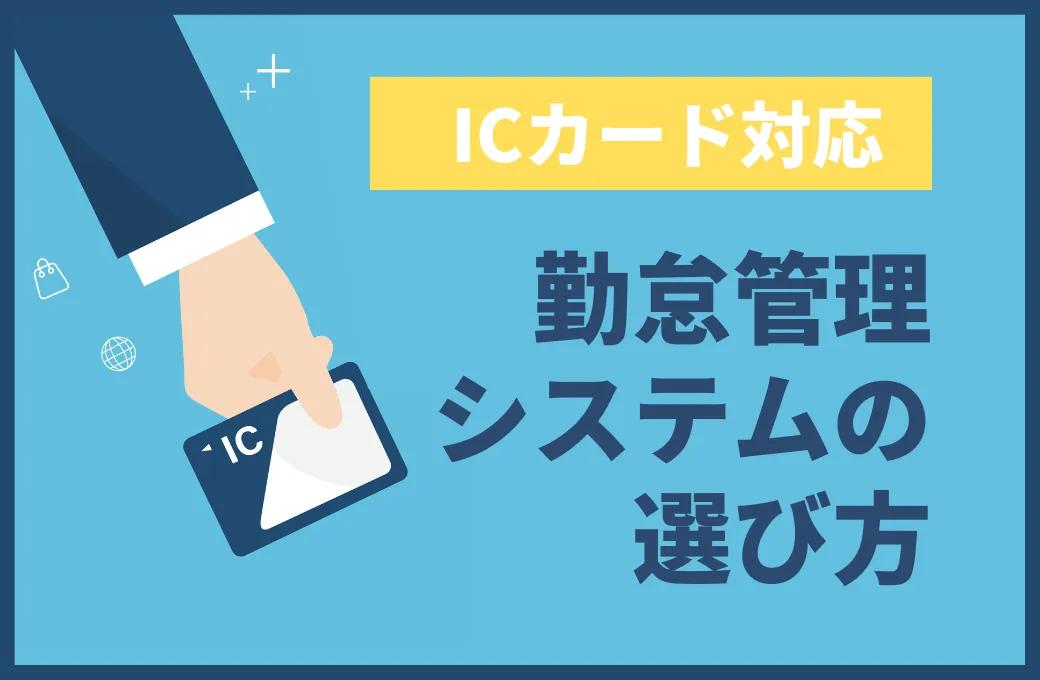
近年労働環境の改善などの重要性が増し、注目を浴びている勤怠管理システム。勤怠システムには多様な打刻の方法があります。そのなかでも今回は便利で導入しやすいICカードでの打刻について解説します。ICカードで打刻する勤怠管理システムのメリット・デメリットをご紹介します。
目次
1.ICカードで勤怠管理をするメリット
1-1.打刻がスムーズにできる
タイムカードで打刻をする場合、自分のタイムカードを取り出し、タイムレコーダーに差し込み、印字するという一連の動作があるため、始業時刻前・終業時刻後にタイムレコーダーの周辺で渋滞が起こるということがあります。それに対してICカードは、ICカードリーダーにかざすだけでスムーズに打刻をすることができるため、終業時刻前・終業時刻後の渋滞を緩和することができます。
1-2.集計作業が効率化できる
ICカードを活用して打刻することで勤怠のデータを自動で登録することができるため、集計にかかっていた時間を大幅に短縮することができます。これにより、人事部や経理部、総務部などの部署の月末・月初の負担を大幅に減らすことができます。また、勤怠データを自動集計することができるため、集計ミスを防ぐこともできます。
1-3.導入が容易
勤怠管理システムの打刻方法にはWeb打刻やアプリ打刻などさまざまな方法がありますが、これらの方法だと、PCやスマートフォンを使い慣れていない従業員がいる場合、操作に慣れるまでには時間がかかることもあるでしょう。その点、ICカードはICカードリーダーにかざすだけでよいため、タイムカードに近い感覚で打刻ができます。そのため、PCに不慣れな従業員でも簡単に打刻をすることができます。
2.ICカードで勤怠管理をするデメリット紛失の恐れがある
ICカードで勤怠管理をすることのデメリットとして、ICカード忘れや紛失の恐れが挙げられます。ICカードを新たに作って従業員に貸与する場合、持ち帰りのルールを定めたり、貸与しているカードの枚数などをチェックしたりする必要があります。
2-1.導入コストがかかる
ICカード打刻を導入する際には、ある程度の費用がかかります。かかるコストとしては、以下が挙げられます。
- 勤怠管理システムの導入費用
- ICカードリーダーの購入費用
- ICカードの購入費用
勤怠管理システムの利用料は、従業員の数に応じて月額料金を支払う従量課金型と、買取型があります。
少人数であれば従量課金型の方が利用する人数分だけ料金を払うことになるため、コストを抑えられます。一方、従業員規模が大きい場合には、買取型のほうが長期的にはコストを抑えることができるでしょう。
また、ICカードのICカードリーダーの購入費用も必要です。ICカードリーダーの価格は種類によって数千~数万円と幅広く、企業の規模や拠点の数によっても台数が異なるため一概には言えませんが、導入時にはそれなりの費用がかかります。
さらに、ICカードを新しく購入して使う場合には、ICカードの購入代金も必要です。ただし、カードは一度買えば長く使用することができます。また、すでに持っている交通系のICカードを使用すれば新しくICカードを購入する必要もないため、コストを抑えることもできます。
タイムカードを運用するうえで、紙のタイムカードやインクを買い続けることを考えれば、大きくかかるのは初期費用だけで、その後の運用費用はそれほど高くはないとも考えられます。
3.ICカードで打刻する勤怠管理システムの導入に必要なもの
3-1.ICカード
ICカードには、いくつかの規格があります。このうち勤怠管理システムで多く使われるのが「Mifare」と「FeliCa」です。
Mifareとは、世界で多く使われているカードです。日本ではtaspoなどに使われています。1枚300円程度と安価なのが特徴です。一方、日本で普及しているのがFeliCaで、交通系のICカードに多く使われています。1枚600円~900円程度とやや高価ですが、セキュリティの高さが特徴です。
このFeliCaには、ほかにも、セキュリティ機能が簡素化され、1枚300円程度と低価格に抑えられたFeliCa Lite-Sという種類のものもあります。また、MifareやFeliCaのほかに、EMカードというICカードも存在します。
3-2.ICカードリーダー
ICカードで打刻するには、ICカードリーダーを用意することが必要です。勤怠管理システムを提供する会社から購入したり、家電量販店やネットなどで自分で購入したりして入手できます。勤怠システムによっては専用のICカードリーダーでないと打刻できないという場合もあるので注意が必要です。
勤怠システムごとに対応している機器はさまざまですが、ICカードリーダーには次のものがあります。
PCに接続して使うICカードリーダー
USBでPCに接続して使うタイプのICカードリーダーは、価格は1台2,000円~4,000円とコストが低く抑えられ、ICカード打刻を手軽に導入することができるのが利点です。社内に共有で使用しているPCがあればそれにつないで打刻をするのが便利でしょう。勤怠管理システムでよく用いられている機器として、ソニー社のPaSoRiが挙げられます。
単独で使うICカードリーダー
単体で使うICカードリーダーは、シンプルなものは1台5万~6万円ほど、液晶画面や多様な機能が搭載されているものは1台8万~10万円ほどの費用がかかります。比較的高価ですが、PCにつなぐ必要がなくスペースを取らないのが利点です。
勤怠管理システムでよく用いられている機器として、スマート・ソリューション・テクノロジー社のPitTouchPro2やPitTouchBizが挙げられます。
これまでタイムカードを使ってきた場合、タイムレコーダーを置いていた場所にICカードリーダーを置けば打刻の習慣もつきやすいため、導入がスムーズです。
タブレット・スマホを読み取り機として使うICカードリーダー
NFC(※1)に対応しているAndoroid端末であれば、ICカードリーダーを購入しなくても、手持ちのタブレットやスマートフォンでICカードを使うことが可能です。iPhoneやiPadなどのiOS端末でICカードを読み取りたい場合は、Bluetooth対応のICカードリーダーを接続する必要があります。
※1:NFC
Near Field Communicationの略で、近距離無線通信技術の国際規格のことを指します。
4.ICカードで打刻ができる勤怠管理システムを選ぶときのポイント
ICカードに対応している勤怠管理システムは多く存在します。どのような観点でシステムを選べばよいのでしょうか。次に、ICカードで打刻ができる勤怠管理システムを選ぶときのポイントをご紹介します。
4-1.サポート体制が充実しているか
勤怠管理システムを導入する際には、自社の状況に合わせるためにシステムの初期設定が必要です。加えて、ICカードリーダーを導入する場合には機器の設定をおこなう必要もあります。設定などに不安がある場合は、サポートが充実しているサービスや設定代行のプランがある勤怠管理システムを選ぶとよいでしょう。
4-2.機能が充実しているか
ICカードでの打刻に対応している勤怠システムはたくさんありますが、その機能はさまざまです。集計機能は使いやすいか、シフト作成や休暇管理などといった、自社に必要な機能が揃っているかなどを把握しておく必要があります。
また、営業などで外出する社員が多い場合、スマートフォンでの打刻ができるかなど、ICカード以外の打刻方法があるかも重要なポイントです。
5.ICカードで楽に勤怠管理をしよう
いかがでしたか?勤怠管理システムは多数存在し、その機能や特徴はさまざまです。また、ICカード打刻にもさまざまな方法や機器があります。自社の状況や必要な機能なども見ながら、自社に合うシステムや打刻の方法を探してみてください。







