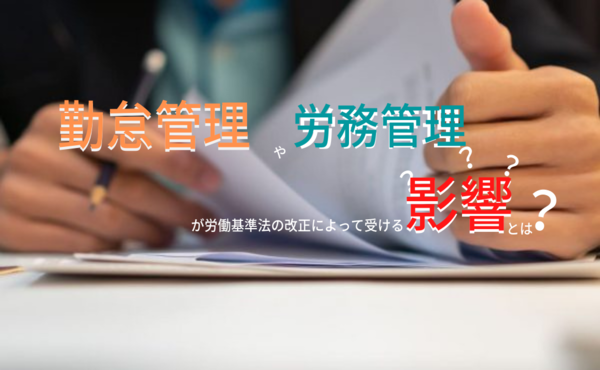
2019年の労働基準法の改正に合わせて、勤怠管理や労務管理などの方法を変えていかなければなりません。また、社会状況に応じて、今後も労働基準法は随時改正されていくでしょう。さらに、労働時間等設定改善法や労働安全衛生法なども改正されており、変更点を把握しておく必要があります。
今回は、現在までの法改正の内容と、勤怠管理や労務管理への影響について解説します。
働き方改革が始まり、法改正によって労働時間の客観的な管理や年次有給休暇の管理など、勤怠管理により正確さが求められることとなりました。
しかし、働き方改革とひとことで言っても「何から進めていけばいいのかわからない…」「そもそも、法改正にきちんと対応できているか心配…」とお悩みの人事担当者様も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、働き方改革の内容とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、法律にあった勤怠管理ができているか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。
目次
1. 2019年の法改正による勤怠管理への影響
 2019年施行の法令改正によって、ビジネスパーソンは「働き方改革関連法」に注目しているでしょう。働き方改革関連法は年次有給休暇や時間外労働などに関係して、働き方全般を改善するための法律です。
2019年施行の法令改正によって、ビジネスパーソンは「働き方改革関連法」に注目しているでしょう。働き方改革関連法は年次有給休暇や時間外労働などに関係して、働き方全般を改善するための法律です。
ここでは、2019年に施行された働き方改革関連法による影響について詳しく解説します。
1-1. 有給休暇の取得義務化
2019年の4月以降、年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、年5日は取得させることが義務付けられました。違反した場合、30万円以下の罰金が科されます。
なお、雇い入れの日から6カ月継続して雇われており、全労働日の8割以上出勤している従業員に対しては、原則として10日の年次有給休暇を与える必要があります。管理監督者や有期雇用労働者、パートタイム労働者も対象となるため忘れずに付与しましょう。
なお、パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない際には、その日数に応じた年次有給休暇日数が比例的に付与されることになっています。
1-2. 時間外労働の上限規制
以前から36協定の一般条項の限度時間として、月45時間・年360時間までと上限が設けられています。しかし、この制約に違反しても罰則はなく、特別条項を締結した際には上限規制がなく働けるというものでした。
しかし、2019年の労働基準法の法改正により、法律による上限規制ができました。特別条項においては、具体的に下記の限度時間となっています。
- 年720時間以内
- 2~6カ月平均80時間以内(休日労働含む)
- 単月100時間未満(休日労働を含む)
- 月45時間超は年6回まで
施行日としては2019年4月から大企業で、2020年4月から中小企業で施行となっています。違反した際には、6カ月以内の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
1-3. フレックスタイム制の清算期間延長
清算期間で定められた所定労働時間の枠内で、従業員が始業・終業時刻を自由に選択できる制度をフレックスタイム制といいます。フレックスタイム制は、本人が始業・終業時刻を自身の裁量で決定し、定められた清算期間内の労働時間に合わせて働くことが可能です。
従来のフレックスタイム制の清算期間は1カ月となっていました。そのため、月の前半と後半で労働時間の配分調整は可能でも、月をまたいでの調整が困難でした。
法改正にともない、この清算期間の上限が3カ月に延長され、月をまたいだ調整が可能になりました。この場合、3カ月の平均で、週あたりの労働時間が法定労働時間内に納まっていれば問題ありません。
ただし、1カ月を超える清算期間を定める際には、労使協定の届け出と月の労働時間の上限設定が必須となるため、把握しておきましょう。
1-4. 高度プロフェッショナル制度の創設
年収1075万円以上の一部の専門職に対して、労働時間規制や時間外労働の割増賃金の支払い規定の対象外とする制度を、高度プロフェッショナル制度といいます。書面の本人同意と、労使委員会での決議があり、企業が申請することで導入可能です。
注意点として、高度プロフェッショナル制度を適用された従業員は勤怠管理の対象外となります。一定の成果を出せば早く帰宅できますが、実際には残業制限がないため、長時間労働になりやすいです。その結果、賃金以上の労働が発生する可能性もあるため注意しましょう。
また、高度プロフェッショナル制度の対象者には「健康確保措置」が義務化されます。年104日の休日取得に加えて以下の4つのなかからいずれかを選択する必要があります。
- 働く時間の上限設定
- 終業から翌始業まで一定の休憩時間の確保(勤務間インターバル制度)
- 連続2週間の休日取得
- 残業80時間以上での健康診断
企業は成果を求めることと並行して、心身の健康管理に配慮する必要があります。
高度プロフェッショナル制度のもと働く従業員は、始業・終業時刻も他の従業員と同一ではありません。そのため、働きすぎにならないように勤怠状況を把握しておくことが求められます。
2. 2020〜2022年の法改正による勤怠管理への影響
 続いて、2020年~2022年の改正労働基準法について、2つのポイントを解説します。
続いて、2020年~2022年の改正労働基準法について、2つのポイントを解説します。
2-1. 同一労働同一賃金
同じ仕事に就いている限りは、正社員であるか、非正社員であるかを問わずに同一の賃金を支給するという考え方を、同一労働同一賃金とよびます。正社員と非正社員の間の不条理な待遇差を解消して、さまざまな働き方を選択できる社会の実現を目指しています。
同一労働同一賃金の考え方は、2020年4月の法改正によって導入されました。この考え方は、もともとは海外で浸透していたものです。たとえばEU諸国においては、人権保障に関する差別的取り扱い禁止原則の一つとして位置づけられています。性別や障害の有無、宗教や信条などを理由として賃金差別を禁じるためのものです。
同一労働同一賃金を実現することで、さまざまな社員が活躍の機会を得られます。また、キャリアアップにつながることで非正規社員の仕事へのやりがいも増えていくでしょう。同一労働同一賃金への対応は、大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から求められています。
企業がするべき対応として、まず労働者の雇用形態や待遇状況を確認しましょう。雇用形態によって待遇は異なるため、整理する必要があります。そして、待遇の違いが異なる場合は、不合理ではないのか確認しましょう。その待遇ごとに違いがある理由を明確にして、説明できる状態にすることが理想的です。この確認を徹底することで、法違反が疑われることはなくなります。もし、改善が必要な場合は、社内の状況を鑑みて対応するべきでしょう。
2-2. 子の看護・介護休暇の時間単位の取得
育児・介護休業法などの改正により、2021年1月1日から育児や介護をおこなう労働者は、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになりました。対象者は、企業で働きながら育児や介護をおこなう労働者です。
この休暇は、病気やけがをした子どもを看護する場合や、予防摂取や健康診断を受けさせる際に利用できます。また、高齢などの理由で「要介護状態になった家族」の介護をする従業員も利用可能です。
法改正前は半日単位での子の看護休暇・介護休暇の取得は可能でしたが、1日の所定労働時間が4時間以下の場合は取得不可能でした。法改正によって時間単位での取得ができるようになったため、より柔軟な働き方が可能となりました。この他にも、育児・介護休業法は2022年4月1日、2022年10月1日、2023年4月1日に法改正が施行されたため、内容を把握しておきましょう。
①2022年4月1日
2022年4月1日からは、本人または配偶者の妊娠・出産などを申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度などに関する以下の項目の周知と、休業取得の意向確認を実施する必要があります。
育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度(制度の内容など)
育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申出先(例:人事部など)
育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき社会保険料の取扱い
引用:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説|厚生労働省
加えて、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和も実施されます。
育児休業
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上
⑵ 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない介護休業
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上
⑵ 介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない
引用:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説|厚生労働省
②2022年10月1日
2022年10月からは、出生時育児休業(産後パパ育休)制度の創設と育児休業の分割取得が施行されています。
出産する女性以外の男性・養子を迎える女性が、子の出生後8週間以内に、最長4週間まで取得可能です。通常の育児制度とは別物として利用できる制度となっています。
③2023年4月1日
育児休業取得率の公表が義務化されました。
従業員数が常時1000人を超える会社は、育児休業の取得状況を年1回公表することが義務付けられています。公表方法は、自社ホームページ、厚生労働省運営のWebサイトである「両立支援のひろば」などです。育児休業と育児目的休暇の取得率、もしくは男性の育児休業等の取得率などを公表しなくてはなりません。
3. 2023年の法改正による勤怠管理への影響

2023年以降は中小企業においても、時間外労働が60時間を越えた場合、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。中小企業については猶予期間が設けられていましたが、2023年4月にこの猶予措置が終了し、大企業と同様、50%の割増率が適用されます。なお、月60時間超の時間外労働が発生した際、割増賃金の代わりに代替休暇を付与することも可能です。
ここまで法改正の経緯について解説しましたが、内容をまだ完全に理解できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?当サイトでは、法改正の内容や企業が罰則を受けないための対策をまとめた資料を無料配布しております。法改正で企業がすべき勤怠管理について理解を深められる内容となっておりますので、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
4. 2024年以降の法改正による勤怠管理への影響

前述の通り、2019年の法改正により時間外労働に対する罰則付きの上限規制が設けられましたが、以下の業種については仕事の特殊性や取引慣行の課題があることから、5年の猶予期間が設けられていました。
- 工作物の建設の事業(建築業)
- 自動車運転の業務(運送業)
- 医業に従事する医師(医療業)
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
しかし、2024年4月に猶予期間が終了したため、他の業種と同様、時間外労働の上限規制を遵守しなければなりません。長時間労働が発生しやすい業種であるため、従業員の健康を守るためにも、適切な方法で勤怠状況を正確に把握することが大切です。
5. 労働基準法とともに改正される法律
 労働基準法の改正とともに、他の法律も改正されました。ここでは、勤怠管理をするうえで重要となる、労働時間等設定改善法と労働安全衛生法について解説します。
労働基準法の改正とともに、他の法律も改正されました。ここでは、勤怠管理をするうえで重要となる、労働時間等設定改善法と労働安全衛生法について解説します。
5-1. 労働時間等設定改善法の改正
この法改正により、従来は勤務管理の適用外とされていた管理監督者や、専門型裁量労働制、企画型裁量労働制、事業外労働に関するみなし労働時間制が適用される従業員の勤怠管理が義務化されました。そのため、一般従業員と同様に勤怠記録を取る必要があります。
また、その際にはタイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な方法で勤怠管理をおこなうことが、2019年4月以降に義務付けられています。
5-2. 労働安全衛生法の改正
この法改正により、勤務間インターバル制度が促進されています。これは1日の最終的な勤務終了時から翌日の始業時刻までの間に、一定時間の休憩を確保する制度のことです。従業員が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、健康維持、長時間労働の防止を目的としています。
しかし、インターバルの時間に法的な拘束力はないため、現状の時間設定は企業の采配に委ねられています。採用済みの企業では、概ね8〜11時間で設定している場合が多いです。
6. 法改正に対応した勤怠管理のポイント

法改正に正しく対応するためには、以下のようなポイントに注意して勤怠管理をおこないましょう。
6-1. 代替休暇の付与を検討する
代替休暇制度とは、月60時間を超える時間外労働が発生した際に、50%以上の割増賃金を支給する代わりに有給休暇を付与する制度です。代替休暇制度を導入するためには、労使協定を結ばなければなりません。
ただし、代替休暇を取得するか、割増賃金の支給を受けるかは、従業員が自由に選択できます。会社側が強制することはできないため注意が必要です。また、代替休暇を取得する場合でも通常の割増賃金は発生するため、25%以上の割増賃金は忘れずに支給しましょう。
6-2. 労働時間を客観的に把握する
法改正に対応するためには、従業員ごとの労働時間を客観的に把握することが大切です。過重な長時間労働や割増賃金の未払いなどの問題が発生しやすいことから、自己申告制による労働時間管理は原則として認められません。
タイムカードやICカード、勤怠管理システムなどを活用して、客観的な方法で勤怠管理を進めましょう。
6-3. 管理監督者の勤怠管理を徹底する
一般の従業員だけではなく、管理監督者の勤怠管理も徹底しなければなりません。管理監督者には労働時間の上限規制など、一部のルールは適用されませんが、深夜労働や休日出勤に対する割増賃金の支給、有給休暇の取得義務化といったルールは一般の従業員と同様に適用されます。
管理監督者の勤怠管理を怠ると、正しい給与計算ができなくなったり、有給休暇の付与日数を間違えたりするため、しっかりと管理しましょう。
6-4. 勤怠管理システムを導入する
改正された法律に違反しないよう、企業は従業員ごとの労働時間を正確に把握しなければなりません。しかし、従来のようなタイムカードやエクセルなどで勤怠管理をしていると、不正打刻や打刻漏れ、入力ミスや不正な書き換えなどが発生するケースもあるでしょう。
従業員による不正やヒューマンエラーを防止しつつ、管理業務を効率化するためには勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。勤怠管理システムを活用すれば、労働時間の管理を効率化できるのはもちろん、給与計算や休暇申請などをシステム上でおこなえます。クラウド型のシステムであれば、法改正があった際に自動でアップデートされるため、手作業で設定を変更する必要もありません。
7. 法改正に合わせて勤怠管理の方法を見直そう!
 この記事では、2019年から現在までの法改正について概要を解説しました。社会の状況や課題に合わせて、労働関連の法律は随時改正されています。「働き方改革」を推進していくためにも、企業は適切な勤怠管理や労務管理をしていくことが大切です。
この記事では、2019年から現在までの法改正について概要を解説しました。社会の状況や課題に合わせて、労働関連の法律は随時改正されています。「働き方改革」を推進していくためにも、企業は適切な勤怠管理や労務管理をしていくことが大切です。
また、従業員の健康を守り、ルールを遵守していくためにも、法改正の内容をしっかりと理解したうえで適切な方法で勤怠管理を実施しなければなりません。さらに、労働時間等設定改善法や労働安全衛生法等も改正されているため、変更点を確実に理解して、勤怠管理や労務管理をしていくようにしましょう。








