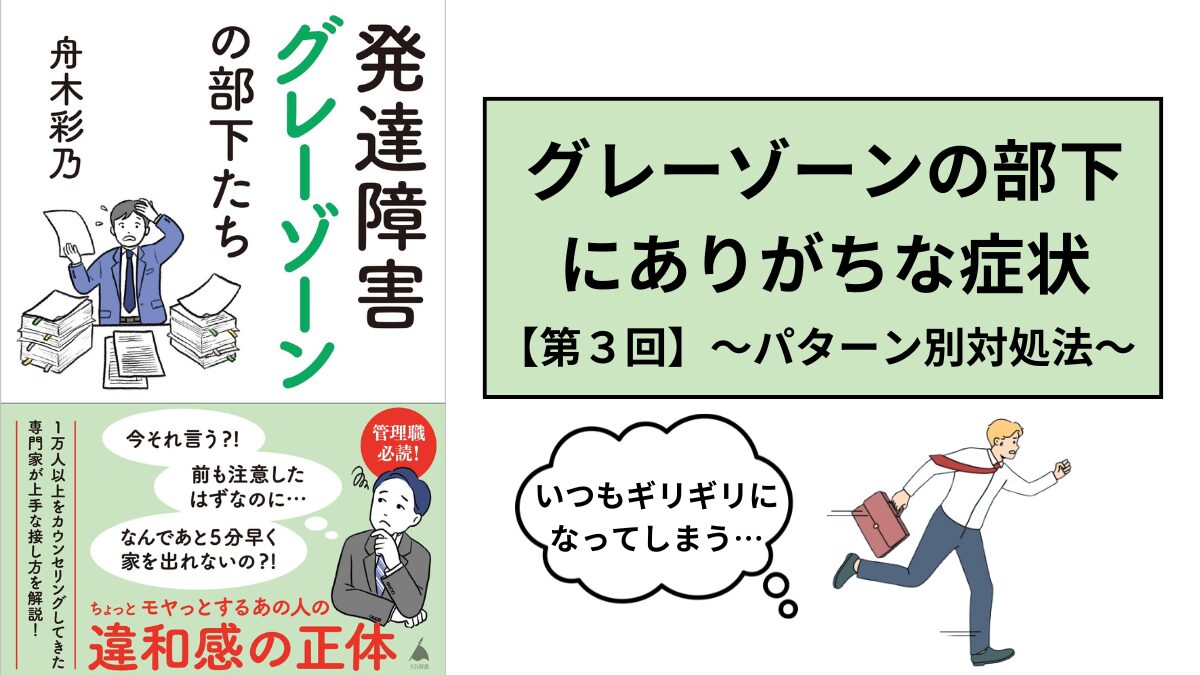
発達障害という言葉は、近年さまざまなメディアで取り上げられ、解説書などもたくさん出ているので、世間に広く知れ渡っています。しかし、発達障害と健常者の中間にあるグレーゾーンに対しては、まだそれほど理解が進んでいない印象があります。職場でも、グレーゾーンの人に配慮していることは、それほど多くないように思います。
グレーゾーンという言葉そのものを病名だと思っている人もいますし、そもそもの発達障害自体が、正しく理解されていないと感じることがよくあります。発達障害にASDやADHDなどの分類があることを知らないまま、たとえば「こだわり」が強い人がいると、その部分だけに着目して「あの人は発達障害だ」と決めつけていることもあります。
しかし、最近になって、多くの企業で「発達障害」や「グレーゾーン」を正しく理解しようという動きが出てきています。メンタルヘルス対策のセミナーやコンサルティングでも、発達障害やグレーゾーンもテーマや対策の1つに入れてほしいという要望が増えています。
また、これまでは発達障害やグレーゾーンの本人に対するカウンセリング、あるいは人事担当者へのコンサルティングがほとんどでしたが、同じ職場の上司や先輩を対象としたセミナーなどの依頼も増えています。さらには、グレーゾーンだけを対象とした仕事の依頼も出てくるようになりました。
これは、企業が発達障害やグレーゾーンについて正しく理解しようとしていることの表れだと感じています。本人だけではなく、指導的立場にある人が彼らへの適切な対応法を学ぶことが、良質なラインケアやセルフケアにつながるという視点が大切です。
ここでは、グレーゾーンの人によくあるパターン別に、対処法をみていきましょう。
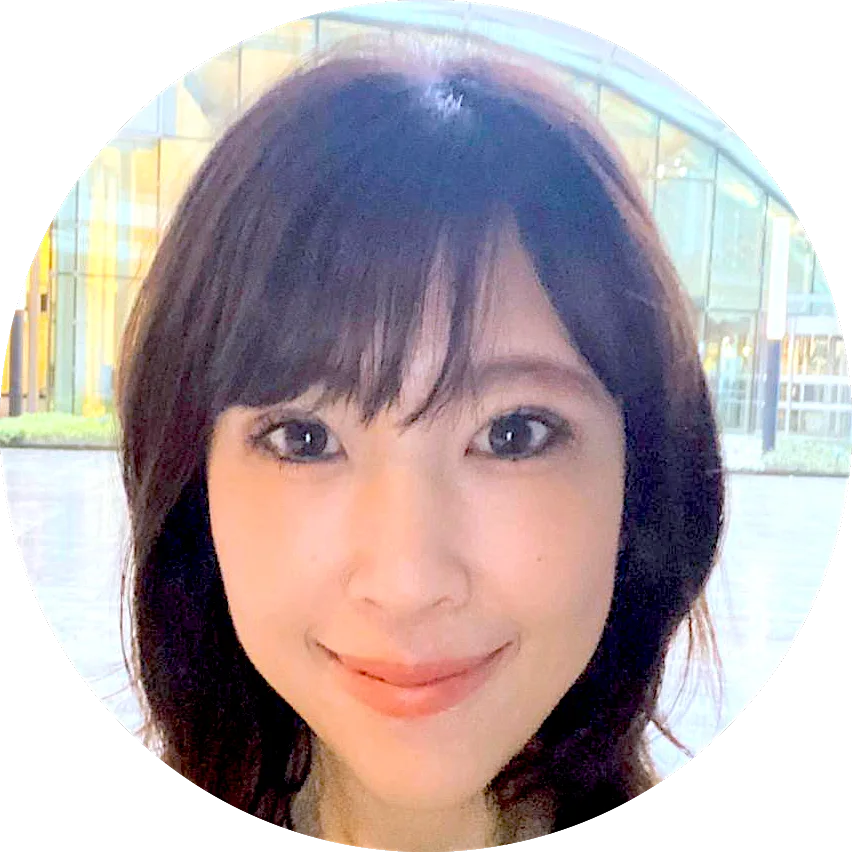
執筆者舟木 彩乃氏心理カウンセラー/ストレスマネジメント専門家/株式会社メンタルシンクタンク副社長
Yahoo!ニュースエキスパートオーサ-として「職場の心理学」をテーマにした記事、コメントを発信中。AIカウンセリング「ストレスマネジメント支援システム」発明(特許取得済み)。国家資格として公認心理師や精神保健福祉士などを保有。カウンセラーとして約1万人の相談に対応し、中央官庁や自治体のメンタルヘルス対策にも携わる。博士論文の研究テーマは「国会議員秘書のストレスに関する研究」。ストレスフルな職業とされる国会議員秘書のストレスに関する研究で知った「首尾一貫感覚」(別名:ストレス対処力)に有用性を感じ、カウンセリングに取り入れている。著書に『「首尾一貫感覚」で心を強くする』(小学館)、近著に『過酷な環境でもなお「強い心」を保てた人たちに学ぶ「首尾一貫感覚」で逆境に強い自分をつくる方法』(河出書房新社)がある。
目次
よくあるパターン別の指示・指導方法

発達障害者への対処と似ているところがありますが、グレーゾーンの場合は、以下のようなパターンが見られれば、まずはそれぞれの対処法で様子を見ると良いでしょう。
診断が出ている発達障害者の場合は、医師やカウンセラーなどの専門職や人事と密に連携し、さらに手厚いケアや環境・業務内容を変えるなどの対応が必要になる場合もあります。
[パターン1:会議などに開始ギリギリにくる、小さな遅刻を繰り返す]
「数分であっても遅刻はしないよう注意しましょう」と伝えたうえで、遅刻の原因をヒアリングします。本人も遅刻を気にしながら、なぜか間に合わないということが多いようです。
こういったケースへの対策案としては、スケジュールを可視化し、会議の開始前の時刻にアラームをセットしてもらう、周囲に声がけをお願いするなどが考えられます。
会議に必要な準備に手間取って遅刻しているケースもあるため、準備にどれくらい時間がかかるかを確認し、余裕を持って声がけをすることも必要です。
[パターン2:指示が理解できていない(通じない)]
「手が空いているときに簡潔にまとめておいて」などという曖昧な指示はNGです。このような指示では、急ぎ具合、あるいは簡潔とはどの程度なのかといった抽象的なことが、本人に伝わりません。
「〇時までに△を、こんな感じで(完成形の資料などを見せながら)やっておいてもらえますか?」というように、指示は具体的に出します。そのうえで、本人の認識している「完成形」が、示した完成形と合致しているかどうか、相手がどのような理解をしたかを答えてもらいます。
[パターン3:会議などで話が止まらない]
会議前に、話す内容をまとめたものを、あらかじめメモなどで確認しておきます。
普段の時間があるときに、1つの項目についてどれくらい話しているのかを自覚してもらうために、ストップウォッチなどで計ります。または、許可を得られたら会議中の発言などを録音しておくことも1つの方法です。
そのうえで、〇分以内など適度な時間を決め、その時間内に収める練習をしておくと良いでしょう。
[パターン4:こだわりが強くコミュニケーションに問題がある]
グレーゾーンはマイルールや規則にこだわる人、仕事でもマニアックな細部にこだわる人が多いです。コミュニケーションにおいては、自分の思い通りの展開にならない場合でも、過剰に反応しないようにするスキルなどを伝えられると良いでしょう。
過剰反応には、内的な過剰反応と外的な過剰反応の2種類があります。
前者はその出来事に囚とらわれて落ち込むことなどを指します。コミュニケーションで特に問題になるのは、後者の外的な過剰反応のほうです。思い通りにならないと、物に当たったり、怒鳴ったりするなどが挙げられます。過剰反応をコントロールするには、自分はどのような場面で「怒り」や「恥」などの感情を揺さぶられることが多いのかを知ることが重要です。
自分をコントロールできなくなるかもしれないと感じたら、深呼吸をして神経を落ち着かせ、思慮深く生産的な対応を選び取ります。もちろん人格を否定されたりした場面では、感情を抑えて我慢する必要はありませんが、単に客観的な指摘を受けているだけのケースもあり、どちらか見極めることも必要です。以上のようなことを指導できると良いでしょう。
仕事でマニアックな細部にこだわってしまう場合は、全体像を見せたうえで、1つひとつの仕事にかけられる時間を提示し、どの部分にフォーカスしてほしいかについて説明して、時間配分などを共有します。
[パターン5:音などの刺激に敏感な場合]
発達障害は知覚過敏の人が多いといわれますが、グレーゾーンも同じです。五感全部というよりは、特に音に過敏な人が多い印象があります。コピー機の音が気になったり、よく話す人の声が気になったりして、仕事に集中できないことがあります。
まずは、1対1での面談の機会を持ち、職場の環境面で困りごとがあれば話してほしいと伝えましょう。差し支つかえない範囲で、席替えや耳栓の使用なども検討します。その際に、部署全体に理由を伝えるなど、周りに事情を説明しておくとスムーズであることを、本人にも伝えておけると良いです。
[パターン6:仕事の優先順位がつけられない]
グレーゾーンは、優先順位をつけることが苦手なケースが多いです。全体と部分の把握が難しいため、今後の展開を予測しにくい、なにか途中で別の仕事が入ると今していることを忘れてしまう、などといったことが起こりがちです。
1週間や1日のはじめに一緒にToDoリストを作成し、チェックすると良いでしょう。重要度が高い順にメモし、終わったら削除するなどとすると達成感も得られます。
[パターン7:仕事のクオリティにムラがある]
グレーゾーンは、得意な業務とそうでないものが明確な場合が多く、これは好き嫌いが明確であることにも通じています。できている部分にフォーカスして褒めたうえで、不得意なことについてはどのようなフォローがあればできそうかを、一緒に考えましょう。
得意と不得意のギャップがあまりにも大きい場合は、得意なことに集中できる環境をつくれるかどうか、人事などに相談するという考え方もあります。
[パターン8:メタメッセージやニュアンスが伝わらない]
グレーゾーンの場合は、コミュニケーションの際に言葉以外によってもたらされるメタメッセージが上手く伝わっていないことが多いようです。そのため、空気が読めず余計なことを言ったり、取引相手に平然と失礼なことを質問したりします。また、相手がやんわり否定していることに気づかないこともあります。
経験を積むことで得られるスキルもありますが、タイミングを見ながら「どういうことを相手に伝えようと思いましたか?」「そのとき相手はどう思ったか想像できますか?」などと聞き、相手の立場になって考える訓練をすることも有効です。
グレーゾーンの人に具体的な指示をするときに念頭に置くべきポイントとしては以下の3点があります。
①ハラスメントにならない注意の仕方
②モチベーションを維持してもらう褒め方
③コミュニケーション能力を高める声がけ
グレーゾーンの人たちは発達障害の診断を受けた人たちとは違う独特の悩みを持っています。そのため、彼らの指導役である上司や先輩もまた、同じように悩んでいるのです。







