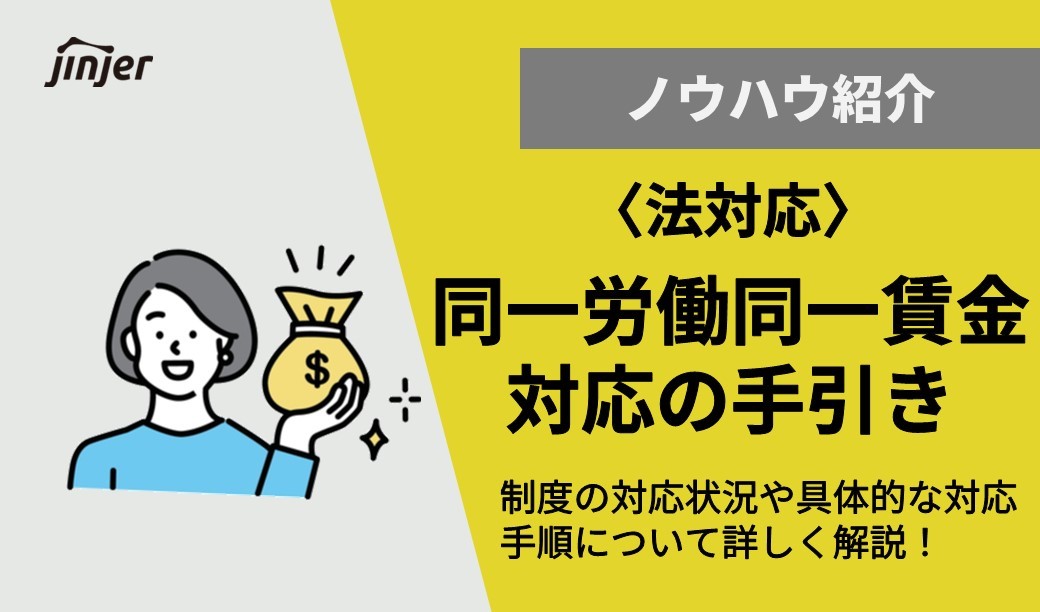2021年4月より、すべての企業に適用された「同一労働同一賃金」。正社員や契約社員といった雇用形態を問わず、同じ仕事をする労働者には同じ賃金を支払うという内容です。また賃金にかぎらず、福利厚生や教育制度なども公平に機会を与える必要があります。
同じ仕事をするにもかかわらず、なんらかの理由で「正規雇用者と非正規雇用者との待遇が異なる」場合には、きちんと説明できなければいけません。そこで今回の記事では、同一労働同一賃金の説明義務にフォーカスし、会社がすべき説明内容や対象者をはじめ、説明できない場合のリスクなどを解説します。
目次
同一労働同一賃金の手引書を無料配布中!
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。
自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 同一労働同一賃金の説明義務とは?

同一労働同一賃金の説明義務とは、「同じ条件で働いているのに、なぜ給与や福利厚生の待遇が違うのか?」と質問された際に、合理的な説明をしなければいけない義務のことです。
「上層部がそう言っているから」や「昔からの決まりだから」などの一言で片づけると、説明義務に反してしまいます。本人はもとより、第三者が聞いても納得できるような「明確な理由」が必要です。
1-1. 説明義務の背景
以前は「正規雇用者」と「非正規雇用者」が同じ仕事をするにもかかわらず、待遇が異なるのは当たり前の光景でした。従業員に不満があったとしても、企業に格差を解消する義務は課せられておらず、「正社員だから」「パートだから」と不合理な格差が野放しになっていた実情があります。
しかし働き方の多様化が進むにつれ、正規雇用者と非正規雇用者の待遇格差が問題視されはじめます。その後「同一労働同一賃金」に反すると違法とされるようになりました。昨今では、同条件で同じ仕事をする場合には、正規雇用者も非正規雇用者も同じ賃金や待遇を受けさせるのが当然という考えが浸透しています。とはいえ、合理的な理由があれば、賃金や待遇に差をつけられます。
同条件で賃金や待遇で差をつける場合には、従業員から説明を求められた際に、納得できるような合理的な説明が不可欠です。
1-2. 説明を受ける対象者
説明を受ける対象者は、正規雇用ではない以下のような働きをする人です。
・パートタイマー
・有期契約社員
・派遣社員
パート、アルバイト、嘱託、臨時社員、準社員など、呼称はまちまちですが、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べてて短い場合は、「パートタイマー」に該当します。
1-3. 説明義務が発生するタイミング
同一労働同一賃金の説明義務が発生するタイミングは、主に以下の2場面です。
▼雇用したとき
非正規雇用者を雇用したタイミングで、必ず賃金や待遇の説明をします。その際に、非正規雇用者と待遇が異なる場合には、理由を含めて詳細を説明しましょう。
雇用時の説明について、タイミングに規定はないものの、速やかに実施するよう決められています。そのため、入社した当日に説明するのが妥当でしょう。
▼労働者から説明を求められたとき
非正規雇用者から「(正規雇用者との)待遇差を説明してください」と求められたときにも、説明義務が発生します。特に説明を求められなければ、会社からの説明は不要です。
2. 労働者が“格差”を感じるのはこのようなケース

労働者が正規雇用者との格差を感じる場面について、いくつか例を挙げます。
2-1.ボーナス(賞与)の支給
A社では、正社員と契約社員に「同じ営業の仕事」を任せています。しかし、正社員のみにボーナスが支給され、契約社員にはボーナスが支給されていません。
契約社員には営業ノルマが課せられておらず、転勤もありません。一方正社員には営業ノルマが課されており、転勤も日常茶飯事であるなどの妥当な理由があれば、合理的だと認められる可能性が高いでしょう。
2-2. ケース2:交通費の支給
B社では、正社員には交通費を支給するものの、契約社員やパート社員には支給していません。
同じように勤務先まで来て働いているのであれば、契約社員・パート社員のみに交通費を支給しない状況は認められないでしょう。また、正社員には交通費の上限を3万円とし、契約社員やパート社員は上限を1万とするなど、条件に差をつけるのも違反です。
2-3. ケース3:設備の使用
C社では、正社員には社員食堂の使用が許可されているものの、派遣社員は使用できない決まりがあります。
「昔からの決まり」などの理由では、合理的だと認められません。明確な理由がなければ、派遣社員も社員食堂を利用できるように調整しましょう。ただし、正社員からは食堂の利用料(固定)を毎月徴収し、派遣社員からは徴収していないといった理由があれば、合理的だと認められる可能性があります
2-4. ケース4:教育訓練の機会
D社では、正社員にはキャリアアップに向けた教育訓練の機会が与えられているものの、パート社員には機会が与えられていません。
明確な理由がない場合には、格差づけは認められないでしょう。パート社員に「キャリアアップコース」を設け、コースを選んでいない人は「教育訓練の対象外」とする場合には、合理的と認められる可能性が高いといえます。
3. 労働者への合理的な説明方法とは?

労働者について、待遇差の合理的な説明をする際には、以下のポイントを押さえましょう。
3-1. 比較対象者の選定
まずは、比較対象者となる「正規雇用者」を選定します。ポイントは、職務内容が最も近い人を選ぶことです。
ベストな比較対象者は「職務内容が同じであり、配置変更の範囲も一緒」な人です。条件に合致する人がいなければ、「配置変更の範囲は異なるものの、職務内容が同じ人」や「配置変更の範囲は同じである一方、職務内容が一部異なる人」などを選定しましょう。
3-2. 待遇差の内容と待遇差を決定した根拠
つづいて、「待遇差の内容」と「待遇差を決定した根拠」を説明できる状態にします。
待遇差の内容とは、説明が必要な非正規雇用者と、比較対象者に選定された正規雇用者の間にある「格差の詳細」です。賃金テーブルや待遇の基準リストなどを使用し、格差の根拠を整理します。
3-3. 口頭だけではなく「書面」を用意
説明をする際には口頭だけではなく、書面も交えることが大切です。口頭だけだと、双方の認識にズレが生じる可能性があるからです。
書面には、職務内容や配置変更の差はもちろんのこと、経験や今までの成果といった「合理的な説明の根拠となり得る要素」をすべて記載します。あわせて、企業が用意している就業規則内容や賃金テーブルの情報を記載しても良いでしょう。
ここまでとるべき合理的な説明方法をご紹介しましたが、具体的にどのような説明をすればいいかイメージがつかないなど、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。本サイトでは、同一労働同一賃金の対象者の条件や確認方法、待遇が不合理ではないことを説明する観点をまとめた資料を無料で配布しています。ぜひこちらから資料をダウンロードして、具体的な説明文の検討材料としてお役立てください。
4. 同一労働同一賃金の説明ができない場合のリスク

同一労働同一賃金の説明ができない場合でも、法的な効力をもった罰則はありません。しかし、説明義務に反するため、格差を不満に思う従業員から訴訟を起こされる可能性は大いにあります。敗訴すれば、賠償金を支払う可能性があるでしょう。
訴訟を起こされなかった場合にも、格差を不公平に思う従業員たちのモチベーション低下が懸念されます。会社に対する不信感はもとより、正規雇用者への妬みなどから、人間関係の悪化につながる恐れもあるでしょう。モチベーションダウンは生産性低下に直結します。
また「同一労働同一賃金に反する企業」だと、外部へのうわさが広がれば、企業のイメージダウンは免れません。
5. 人事担当者は「給与の根拠」を理解し、説明できる状態にしよう

同一労働同一賃金がすべての企業に適用されたため、その存在を知らない従業員はまだ少ないと言えます。格差を感じた非正規雇用者は、企業に対し「格差の詳細」について説明を求めてくるでしょう。
そのとき、合理的な説明ができなければ、同一労働同一賃金の説明義務違反になってしまいます。
トラブルを回避するために、人事担当者や管理職は「給与の根拠」を理解し、いつでも説明できる状態を維持することが大切です。
同一労働同一賃金の手引書を無料配布中!
同一労働同一賃金に罰則はありませんが、放置すると損害賠償のリスクが高くなります。
同一労働同一賃金とは、「正社員と非正規社員を平等に扱う概念」のように認識されていても、具体的にどのような対策が必要かわからない方も多いのではないでしょうか?
本資料では、どのような状態が「不平等」とみなされうるのかや、企業が対応すべきことを4つの手順に分けて解説しております。
自社でどのような対応が必要か確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。