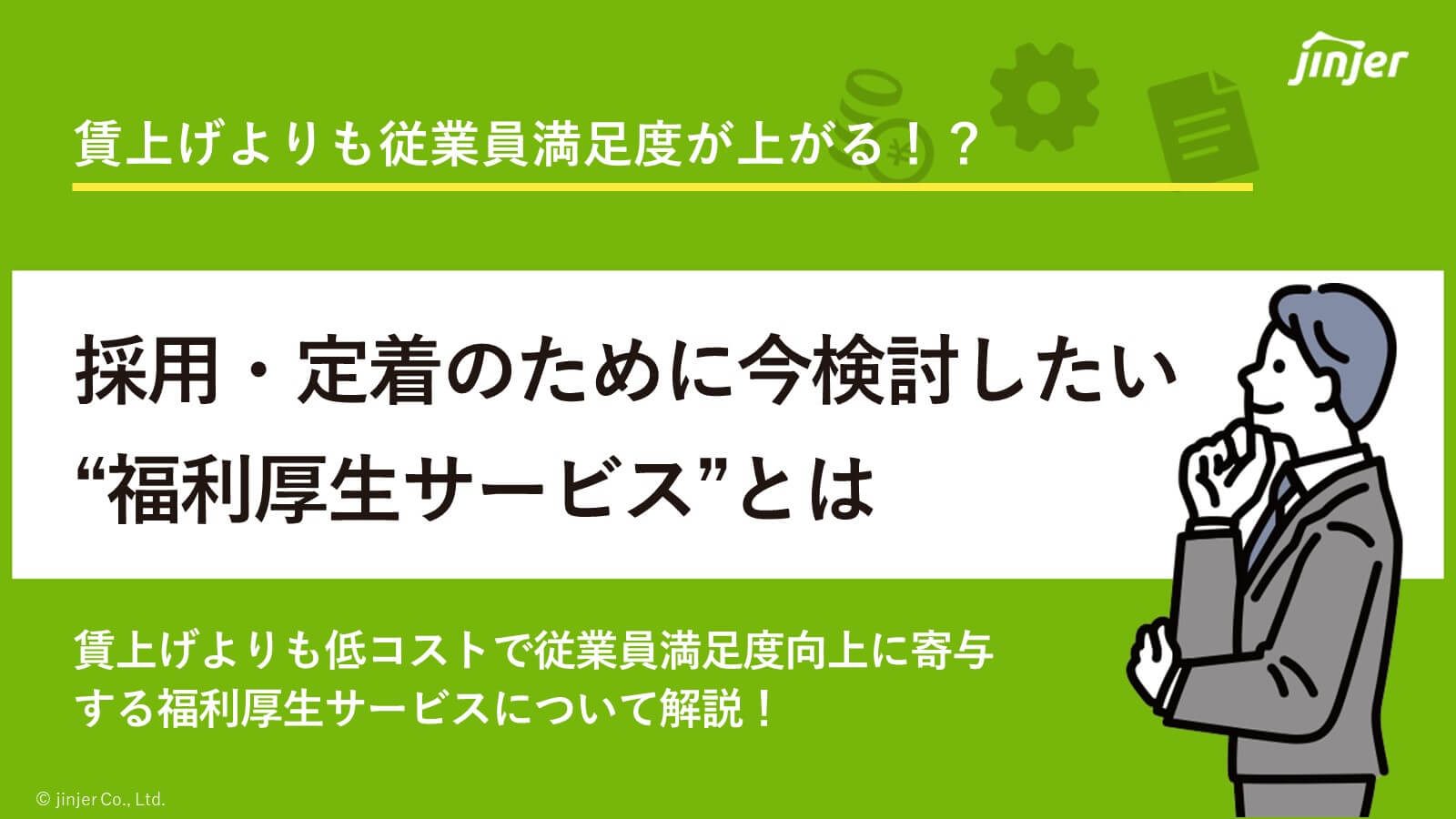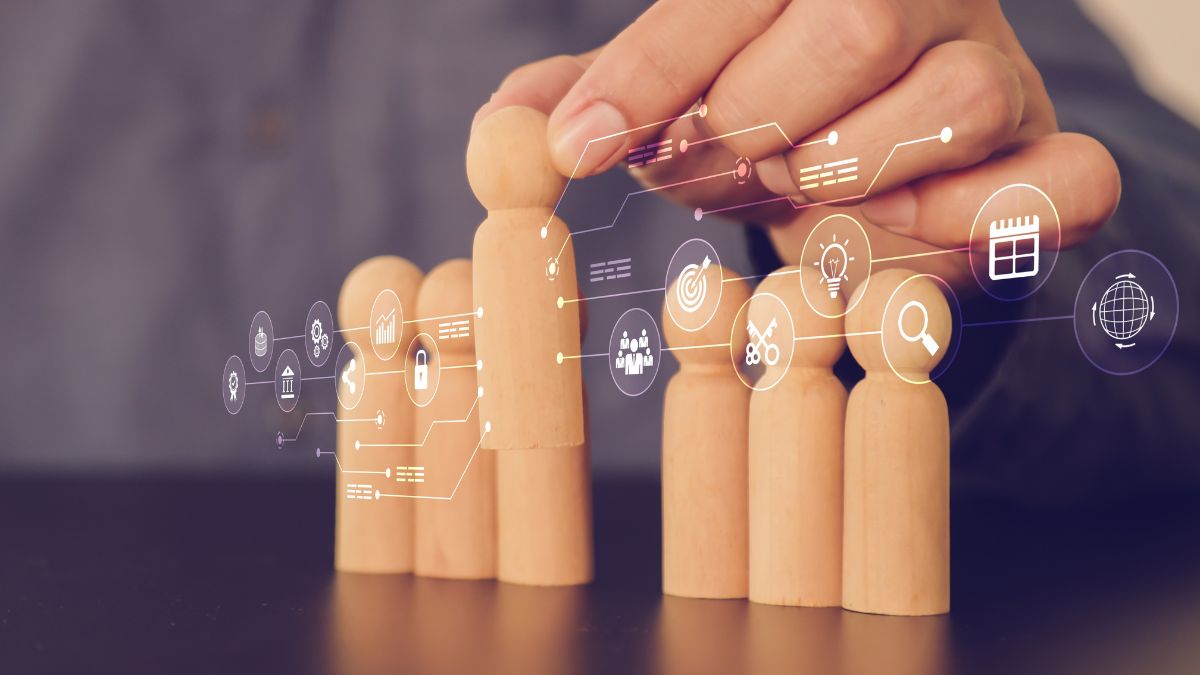
「福利厚生に節税効果があるって本当?」
「節税対策ができる制度は?」
上記のような悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。福利厚生には節税効果がありますが、利用する制度によって非課税にするための条件があります。
今回は、福利厚生の節税効果や節税対策できる制度、注意点を解説します。福利厚生の節税を理解し、企業のコストを抑えましょう。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 福利厚生には節税効果がある!仕組みを解説

福利厚生に節税効果があるのは、損金に算入できるためです。損金とは、企業の持つ資産が減る原因となる損失額や費用を指します。
会計上では収益から費用を差し引いた額を利益とする一方で、税法上では次のように置き換えて算出するのが特徴です。
- 収益→益金
- 費用→損金
- 利益→課税所得
税法上では損金算入額が高くなるほど利益が圧縮されるため、納税額も少なくなります。
福利厚生は損金に算入できることで利益が圧縮されやすくなり、納税額が減るため節税効果があるのです。
2. 福利厚生費を経費にする条件

福利厚生費を経費にする条件は、次のとおりです。
- 現物支給を避ける
- 金額に妥当性を持たせる
- 機会を平等にする
それぞれ詳しく解説します。
2-1. 現物支給を避ける
福利厚生費を経費にするには、現物支給を避ける必要があります。現物支給は給与と見なされ、所得税や住民税などの算定基礎に含まれるためです。
現物支給の例としては、換金性の高い金券や株式の有価証券などが挙げられます。
ただし、社員に仕出し弁当や社員食堂などの形で食事を現物支給する場合は、次のような条件で経費に計上可能です。
- 社員が半額以上の食事代金を負担する
- 企業の負担額が1人あたり月額3,500円以内である
通勤手当や家賃補助なども現金支給に該当しますが、一定の範囲内であれば経費として計上できます。
2-2. 金額に妥当性を持たせる
福利厚生を経費にする条件として、金額に妥当性を持たせることがあります。金額の妥当性があるとは、社会通念上で妥当な範囲に収まっているかを確認する項目です。
金額に妥当性がない例として、以下が挙げられます。
- 1食あたり10,000円の食事補助を支給する
- 通勤費として毎日の往復飛行機代を支給する
- 数十万円の高額な人間ドック代を健康診断補助として支給する
福利厚生を経費にする上では、支給上限額や支給頻度に制限をかけ、社会通念上妥当な範囲に抑える工夫が大切です。
2-3. 機会を平等にする
福利厚生を経費にする条件の一つは、機会を平等にすることです。機会の平等とは、すべての社員に対し平等に支給されることを意味します。
機会が平等ではない例は、次のとおりです。
- 本社にいる社員のみが利用できる社員食堂
- 一部の役職者のみが利用できる保有地
通勤手当や健康診断補助などは全社員が平等に利用できるため、機会が平等であるとみなされます。
3. 節税効果がある福利厚生

節税効果がある福利厚生は、次のとおりです。
- 社宅制度
- 通勤手当
- 出張手当
- 食事補助
- 健康診断
- 法人保険
それぞれ詳しく解説します。
3-1. 社宅制度
社宅制度とは、企業が社員に住宅を貸与する制度です。法人が所有している賃貸物件に役員や社員が住むなどのケースで、家賃を福利厚生として計上できます。
社宅制度を計上するには、社員から1ヵ月にかかる賃貸料相当額の50%以上を徴収しなければいけません。
50%未満の徴収や無償での貸与では賃貸料相当額が給与として扱われ、福利厚生としての計上が不可になります。
3-2. 通勤手当
通勤手当とは、社員が通勤するために必要な費用を企業が支給する手当です。所得税が原則として非課税の手当でもあります。
無制限な支給は認められず、非課税となる金額には上限が設けられているのが特徴です。電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合は月に15万円が非課税枠の上限になります。
マイカー通勤の距離による非課税枠の上限は、次のとおりです。
|
片道通勤距離 |
1ヵ月の上限額 |
|
2km未満 |
全額課税 |
|
2~10km |
4,200円 |
|
10~15km |
7,100円 |
|
15~25km |
12,900円 |
|
25~35km |
18,700円 |
|
35~45km |
24,400円 |
|
45~55km |
28,000円 |
|
55km以上 |
31,600円 |
上限の超過分は給与所得として課税対象となり、支給を受ける社員の税負担が増える可能性があります。
3-3. 出張手当
出張手当とは、遠方へ出張する際に旅費や交通費などの費用を社員に支給する手当です。出張手当は給与として扱われず、所得税は非課税となります。
必要以上の支給をおこなった場合は、課税対象になるため注意しましょう。税務調査などで指摘されないよう、出張旅費規程を作成し適切な金額を支給する必要があります。
3-4. 食事補助
食事補助とは、社員の食事代の一部を企業が負担する制度です。弁当を支給したり、社員食堂を利用させたりすることも食事補助に該当します。
食事補助を非課税にする条件は、次のとおりです。
- 社食や弁当の提供などを1人あたり月3,500円以下にする
- 社員が食事代の半分以上を負担する
深夜勤務者については、現金で1食あたり300円までの支給でも認められます。
3-5. 健康診断
健康診断の福利厚生は、企業が社員の健康診断費用を負担する制度です。健康診断は法律によって実施が義務づけられているため、健康診断の費用を計上できます。
健康診断を福利厚生にする条件は、以下を参考にしてください。
- 社員全員が受診する
- 法人名義で支払う
- 人間ドックの高額なオプションなどを実施しない
現金を社員に支給する形で診療機関に支払う場合は、給与として扱われます。非課税対象にするため、会社が診療機関に直接支払うことが重要です。
3-6. 法人保険
法人保険とは、法人が契約者となって経営者や社員などを被保険者として加入する保険の総称です。
契約者の法人が社員などを被保険者として保険料を支払うと、一部を福利厚生として計上できます。
解約がある定期型の法人保険であれば、解約時に返戻金を受け取ることが可能です。
保険の種類によっては掛金を資産計上する必要があるため、詳細を事前に確認することが大切といえます。
4. 福利厚生で節税する際の注意点

福利厚生で節税する際の注意点は、次のとおりです。
- 一般的な控除や減税制度とは異なる
- 節税が認められない福利厚生もある
- 給与所得にならないよう注意する
それぞれ詳しく解説します。
4-1. 一般的な控除や減税制度とは異なる
福利厚生は、一般的な控除や減税制度とは異なるものです。企業側の損金も含まれるため、社員への利点を考えながら必要なものを選ぶ必要があります。
社員へどのような影響を与えるのかを考慮しつつ、企業の負担が大きくなりすぎないものを選ぶことが大切です。
4-2. 節税が認められない福利厚生もある
福利厚生に含まれる制度でも、一定の基準を満たさなければ節税効果を得られないこともあります。以下は一部制度の基準です。
|
制度 |
課税対象になる基準 |
|
健康診断費 |
法人から医療機関へ費用を直接支払わない |
|
慶弔見舞金 |
金額が常識的な範囲を超える |
|
社員旅行費 |
役員だけで実施する旅行や接待を目的とした旅行である |
|
社宅制度 |
社員の家賃負担額が50%未満 |
福利厚生を導入する際は、基準を満たす内容にしましょう。
4-3. 給与所得にならないよう注意する
福利厚生で節税する際は、給与所得にならないよう注意しましょう。福利厚生であっても、給与として認められる場合は課税対象です。
例えば、税務調査によって現物支給が発覚した場合は課税対象になります。給与所得にならない支給を意識しつつ、節税効果を得るための条件をすべて満たすことが大切です。
5. 福利厚生をうまく活用して節税効果を得よう

福利厚生は損金に算入できるため、節税効果が期待できます。しかし、すべてが節税になるわけではありません。
現物支給を避けたり金額に妥当性を持たせたりするなど、福利厚生を非課税対象にするには条件があります。
条件をすべて満たした上で給与所得にならない支給を実現させ、節税効果を得ましょう。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。