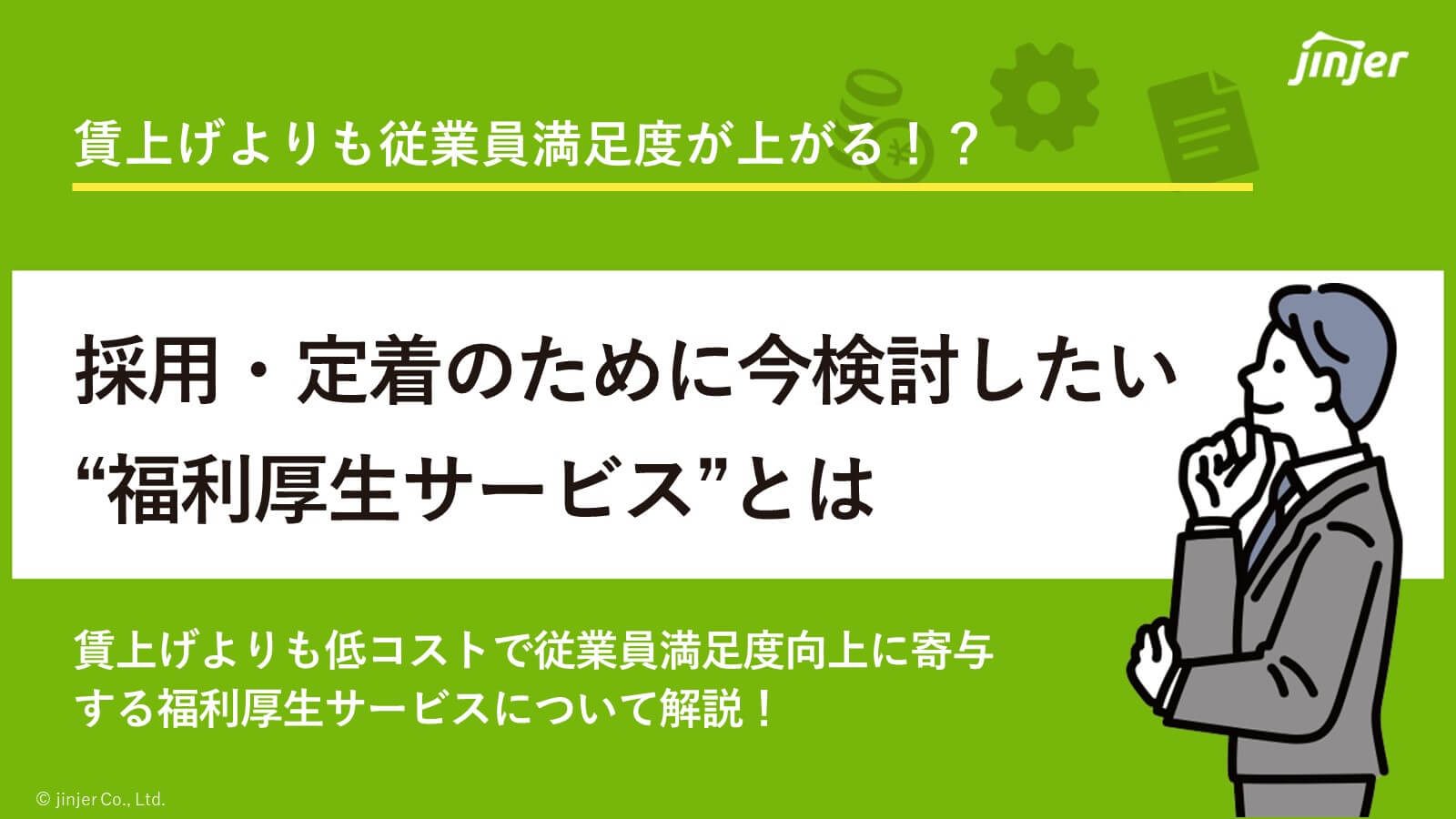「福利厚生を導入するメリットとデメリットは?」
「福利厚生を導入する際に注意点はある?」
上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
福利厚生とは、企業が従業員とその家族に提供する給与以外の報酬やサービスのことです。従業員が働きやすい環境を作るうえで重要な制度であるため、導入のメリットや注意点を把握しておきましょう。
本記事では、福利厚生を導入するメリット・デメリットや導入する際の注意点を解説します。独自の福利厚生を導入した企業事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 福利厚生を導入する際のメリット

福利厚生を導入する際のメリットは、以下の6つが挙げられます。
- 従業員の満足度が向上する
- 採用力が向上する
- 生産性が向上する
- 従業員の健康を維持できる
- 企業の社会的信頼性が向上する
- 節税効果がある
1-1. 従業員の満足度が向上する
福利厚生を導入することで、従業員の満足度向上につながります。従業員が休暇を取りやすくなり、ワークライフバランスを実現できるためです。
自由に有給休暇を取得できるようにすれば、働く意欲が向上し仕事と生活にメリハリを付けられます。働きやすい職場環境になるため、従業員の離職率低下にもつながるでしょう。
1-2. 採用力が向上する
福利厚生の導入により、採用力の向上が期待できます。求職者が企業を探す際、福利厚生が充実しているかが判断基準の一つであるためです。
企業のアピールポイントになるような独自の福利厚生を導入すれば、ほかの企業と差別化を図れます。
獲得したい人材が魅力的に感じる福利厚生を用意することで、優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。
1-3. 生産性が向上する
生産性が向上することも、福利厚生を導入するメリットです。ライフワークバランスの実現により、従業員が良好なコンディションで業務を進められます。
心身の疲労回復を目的とした特別休暇やスポーツクラブの割引制度を導入すると、従業員の気力低下の抑制に効果的です。
従業員が集中して仕事に取り組めるようになるため、業務の効率化が図れるでしょう。
1-4. 従業員の健康を維持できる
福利厚生を導入すると、従業員の健康維持をサポートできます。人間ドックの費用やマッサージ費用の補助制度を設ければ、従業員が体のケアをしやすくなるでしょう。
休暇を取得しやすくしたり社内にカウンセリング窓口を作ったりすると、従業員のストレス軽減に効果的です。
従業員の健康を維持することで、心身の不調による離職の防止にもつながります。
1-5. 企業の社会的信頼性が向上する
福利厚生の導入により、企業の社会的信頼性が向上する可能性があります。福利厚生が充実していることで、人材への投資に積極的な企業として社会に評価されるためです。
休暇が取得しやすく補助も充実している企業は、従業員を大切にしている印象を与えられます。
働きやすい職場環境であるとアピールできれば、企業のイメージアップにも貢献するでしょう。
1-6. 節税効果がある
福利厚生を導入することで、節税効果も期待できます。一定の条件を満たして福利厚生費と認められれば、経費として計上可能です。
経費として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 賃金に該当しない
- 全従業員が対象になっている
- 社会通念上妥当な範囲の金額である
上記を満たすものは福利厚生費として経費になり、法人税の節税につながります。
2. 福利厚生を導入する際のデメリット

福利厚生を導入する際のデメリットは、以下の2つが挙げられます。
- 費用負担と管理負担が大きい
- 全従業員のニーズを満たすのが難しい
2-1. 費用負担と管理負担が大きい
福利厚生を導入すると、費用負担と管理負担が大きくなることがデメリットの一つです。節税効果は得られますが、運営や管理に費用がかかります。
福利厚生の申請書類の作成や受付、処理などの業務量が増え、業務担当者の負担も大きくなるでしょう。
導入前に、費用や業務にどの程度の負担がかかるのかを確認しておく必要があります。
2-2. 全従業員のニーズを満たすのが難しい
全従業員のニーズを満たすのが難しいことも、福利厚生を導入する際のデメリットです。個々のライフスタイルや年齢などによって、欲しい福利厚生は変わってきます。
従業員数が多くなるほどさまざまなニーズが生まれるため、対応が困難になるでしょう。制度を利用する人に偏りがでないように、福利厚生の内容を調整する必要があります。
3. 福利厚生の種類

福利厚生の種類は、以下の2つに分けられます。
- 法定福利厚生
- 法定外福利厚生
3-1. 法定福利厚生
法定福利厚生とは、法律で企業に導入が義務付けられている福利厚生のことを指します。
法定福利厚生の種類と会社の負担額は、以下のとおりです。
|
種類 |
会社の負担額 |
|
健康保険 |
半額 |
|
厚生年金保険 |
半額 |
|
雇用保険(失業保険) |
2分の3 |
|
介護保険 |
半額 |
|
労災保険 |
全額 |
|
子ども・子育て拠出金 |
全額 |
企業はすべての法定福利厚生を導入して、費用の全部または一部を負担しなくてはなりません。
3-2. 法定外福利厚生
法定外福利厚生とは、企業が自由に導入できる福利厚生のことです。企業に法的な導入義務はありません。
法定外福利厚生の例としては、以下のような制度が挙げられます。
|
制度の例 |
内容 |
|
通勤手当 |
従業員の通勤や出張にかかる費用を支給する制度 |
|
住宅手当 |
従業員が支払っている家賃の一部または全部を負担する制度 |
|
リフレッシュ休暇 |
年齢や勤続年数に応じて長期休暇を取得できる制度 |
|
人間ドックの費用補助 |
人間ドックにかかる費用を支給する制度 |
|
資格取得費用の補助 |
資格取得の際に必要な受験料や教材費を支給する制度 |
上記の制度をすべて導入しても問題ありません。企業は従業員のニーズや社会情勢に合わせて、独自の法定外福利厚生を提供できます。
4. 福利厚生を充実させる際の注意点

福利厚生を充実させる際は、以下の点に注意しましょう。
- 導入目的を明確にする
- 従業員のニーズを把握する
- 従業員へ周知する
- 定期的に制度を再検討する
4-1. 導入目的を明確にする
福利厚生を充実させる際は、導入目的を明確にしましょう。目的が定まっていない状態で取り入れても、得られる効果が低くなります。
「ワークライフバランスを実現するために、休暇制度を充実させる」のように、目的を明確化することが重要です。
4-2. 従業員のニーズを把握する
福利厚生を充実させる際は、従業員のニーズや意見を確認することが大切です。ほかの企業で人気がある制度でも、自社の従業員には人気が出ない場合があります。
事前にアンケートやヒアリングを実施して、従業員が必要としている制度を把握しましょう。企業の目的と従業員のニーズがミスマッチするのを防止できます。
4-3. 従業員へ周知する
福利厚生を充実させる際は、事前に従業員へ周知しましょう。周知が不十分だと、従業員に利用されない可能性があるからです。
そのため、メールやチャットツールなどを使って、制度の周知と利用促進を図る必要があります。説明会を開いたり、管理職に周知を依頼したりすることも効果的です。
4-4. 定期的に制度を再検討する
福利厚生の導入後は、定期的に制度を再検討しましょう。従業員に利用されていない制度や満足度の低い制度を改善する必要があります。
改善が見込めない場合は制度の廃止も検討しなくてはなりません。福利厚生の導入効果を高めるためには、定期的な見直しをおこなうことが重要です。
5. 独自の福利厚生を導入した企業事例

独自の福利厚生を導入した企業事例として、以下の3つを紹介します。
- Know Me
- 推しメン休暇
- 幸せは歩いてこない
5-1. Know Me
A社は独自の福利厚生として「Know Me」を導入しています。「Know Me」とは、他部署の社員と飲みに行く際に、一人あたり最大3,000円が支給される制度です。
この制度の名称は「飲ーみー」が由来となっています。A社では2022年6月〜2023年5月の間に1,419回使用されました。
「Know Me」の導入により、部署を超えたコミュニケーションの活性化につながっています。
5-2. 推しメン休暇
B社は独自の福利厚生として「推しメン休暇」を導入しています。「推しメン休暇」とは、アニメや漫画、ゲームのキャラクターなど自分の推しメンバーの記念日に休暇が取得できる制度です。
また、年1回までお祝いを支援する活動費が最大5,000円まで支給されます。プライベートを充実させられるため、従業員の満足度向上に効果的です。
5-3. 幸せは歩いてこない
C社は独自の福利厚生として「幸せは歩いてこない」を導入しています。「幸せは歩いてこない」とは、月間平均10,000歩を達成すると報奨金3,200円が受け取れる制度です。
目標達成のために従業員が歩く習慣を身につければ、健康の維持にもつながります。
C社はほかにも、以下のようなユニークな制度を複数用意している企業です。
- 毎月平均7時間以上の睡眠をとった従業員に3,200円を支給する「寝る子は育つ」制度
- TKG(たまごかけごはん)がセントラルキッチンで食べ放題になる「TKG」制度
独自の福利厚生を多数導入しているため、採用力の向上が期待できるでしょう。
6. 福利厚生のメリットを活かして働きやすい職場環境にしよう

福利厚生を導入することで、従業員の満足度向上や生産性の向上などのメリットが期待できます。企業のイメージアップにも効果的です。
費用負担と管理負担が大きくなるため、導入の目的を明確化して、従業員のニーズに合った制度を検討する必要があります。
導入後には制度の再検討をして、福利厚生の導入効果を高めることが重要です。福利厚生のメリットを活かして、働きやすい職場環境にしましょう。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。