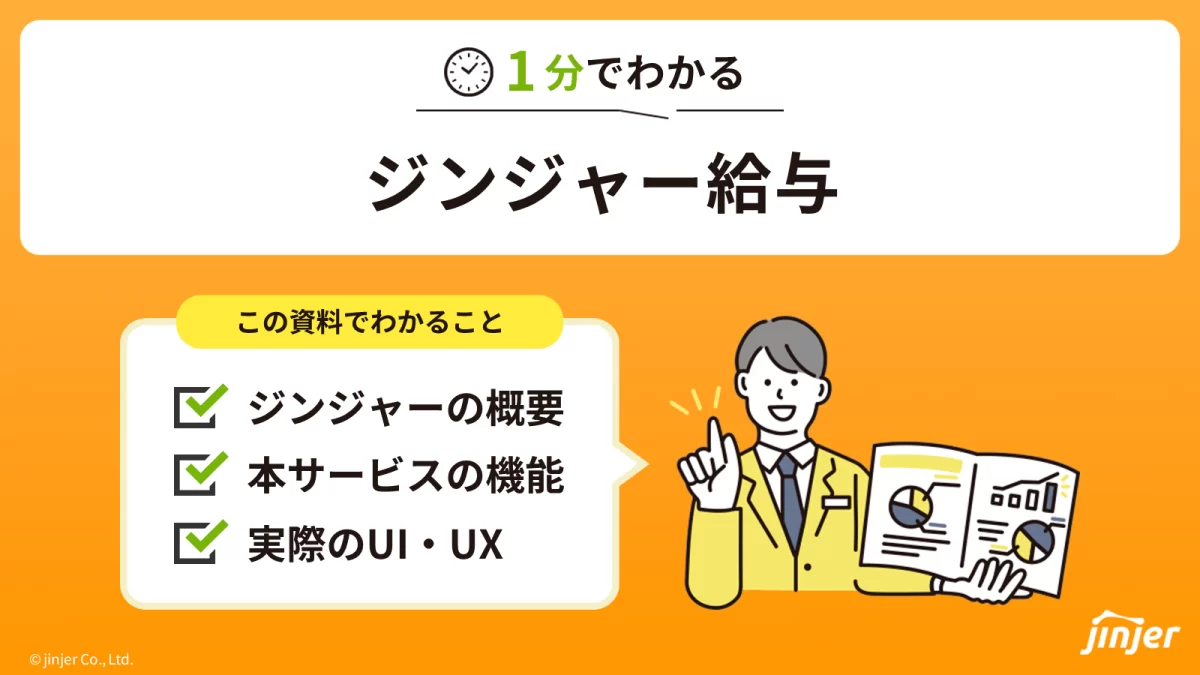「企業年金の受け取り方にはどのようなものがある?」
「企業年金の受け取り方ごとの利点は?」
「従業員にとって、企業年金は一時金と年金のどちらがお得?」
企業年金の受け取り方について、このような疑問をもつ人事労務の担当者もいるのではないでしょうか。
企業年金とは、退職後の従業員をサポートする趣旨で、企業が従業員に対して支給する年金です。退職金を分割払いしたものが企業年金の起源ですが、年金制度のいわゆる3階部分に該当し、福利厚生の一環として人気があります。
本記事では、企業年金の受け取り方や、受け取り方ごとの利点を解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
給与計算はシステムを使って工数削減!
給与計算を手計算しているとミスが発生しやすいほか、従業員の人数が増えてくると対応しきれないという課題が発生します。 システムによって給与計算の内製化には、以下のメリットがあります。
・勤怠情報から給与を自動計算
・標準報酬月額の算定や月変にも対応しており、計算ミスを減らせる
・Web給与明細の発行で封入や郵送の工数を削減し、確実に明細を従業員へ渡せる
システムを利用した給与計算についてさらに詳しく知りたい方は、こちらからクラウド型給与計算システム「ジンジャー給与」の紹介ページをご覧ください。
1. 企業年金のもらい方

企業年金の受け取り方は、年金と一時金の2種類です。
年金の場合、定められた年間の支給回数に基づき、一定額を従業員へ支給し続けます。一方の一時金は、退職時に退職金として一括で支給するものです。
企業年金は法で定められた制度ではありません。そのため、どちらの方法で受け取れるかや支給額については、企業ごとに異なります。企業によっては、従業員が好みの支給方法を選べたり、併用できたりも可能です。
また、企業年金がない企業もあります。大企業ほど企業年金制度を導入しており、中小企業では導入率が低いのが一般的です。
2. 企業年金は一時金と年金のどちらがお得?

従業員が企業年金を受け取る際、一時金と年金のどちらがお得かについてはケースバイケースです。
年金として長期間受け取った方が、総合的な受取金額はアップする傾向が見られます。これは、年金の場合には所定の利回りで運用することで、年金の元手が増やせるためです。
ただし税制上の観点から見ると、退職時に一括で一時金を受け取った方が負担が少なくなります。これは、退職一時金は退職所得となり、税制上の優遇措置を受けやすいためです。
退職金には、退職所得控除額が設けられています。勤続年数が長いほど大きな控除が受けられ、特に20年を超えて勤務していたケースでは有利です。
例えば勤続30年で退職一時金2,000万円の場合には1,500万円が退職所得控除額に設定されます。この退職所得控除額以下であれば、受け取った退職一時金には課税されません。
年金は、公的年金と同様に雑所得扱いとなり、課税の対象です。厚生年金と合算したり、退職後にアルバイトしたりすれば控除額を超えた受給額となりやすく、手取り額が減額するケースも少なくありません。
退職後のライフスタイルを見据えた受け取り方法の選択が肝要です。併用可能な企業であれば、非課税ギリギリの額を退職一時金として受け取り、残りを年金として受け取る方法もあります。
3. 企業における企業年金制度のメリット

企業における企業年金制度の大きなメリットは、従業員の離職防止や採用力のアップにつながる点です。
企業年金制度の整備された企業は、退職後に受け取れる年金が増えることから、労働者にとって魅力的に映ります。優秀な社員を集めやすいことから、結果的に企業の競争力アップに貢献可能です。
また企業年金は、税制上の優遇措置を受けられるメリットもあります。年金の掛け金は全額損金扱いになるため、節税対策として有効です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の場合には、掛け金を拠出した時点で企業側の負担額は確定されます。その後に年金の積立不足は発生しないため、事業計画が練りやすいでしょう。
確定給付企業年金の場合、法に則った範囲内で柔軟な年金設計が可能なメリットがあります。企業型DCやiDeCo、中小企業退職金共済との併用も可能です。
また選択制の確定給付企業年金であれば、給与の一部を年金原資として減額できます。標準報酬月額の等級が低下すれば、企業側が負担する社会保険料が軽減可能です。
4. 企業年金の支給月

企業年金を一時金ではなく、年金として受給する際の支給月は、一般的に年金額や従業員の誕生月によって異なります。
企業年金連合会においては、27万円以上の支給であれば、誕生月に無関係で年6回、偶数月に年金を支給する決まりです。6万円未満の場合、誕生月の2~3ヵ月後に年1回支給します。
年金は基本的に後払い方式です。そのため、支払月の前月分までの年金を、支払月の1日付けで支払います。
企業年金連合会の年金は、公的年金と同様に終身年金となっており、対象者が死亡するまで受給可能です。
5. 企業年金受取の手続き方法

企業年金を一時金ではなく、年金として受給する際には、年金の種類によって手続き方法が異なります。
例えば確定拠出年金の場合、窓口は運営管理機関です。一般的には、60~70歳未満の任意の時期に受給申請します。
確定給付企業年金については、企業年金基金(※基金型の場合)もしくは所属していた企業(※規約型の場合)が窓口です。基本的に、規約で定めた60~65歳の時期に受給申請します。
なお、現在新規加入の取り扱いがない厚生年金基金については、各厚生年金基金が申請窓口です。公的年金の支給開始年齢、もしくは60歳が受給開始時期ですが、基金独自のルールがあればそちらが優先されます。
企業年金を受け取るための案内や請求書類は、それぞれの企業年金で定められた時期に、登録されている住所宛に送付するのが一般的です。
ただし、受給者側で請求手続きをおこなわない限り、基本的には支給が受けられません。長年企業に貢献した従業員の利益を守るためにも、企業の担当者は注意喚起しておきましょう。
参考:第3章 企業年金を受け取る場合の手続き|金融広報中央委員会
6. 企業年金の受け取りに関する注意点

企業年金の受け取りには、以下の点に注意が必要です。
- 企業ごとに制度が異なる
- 中途退職時にも企業年金を受給可能な場合がある
- ルールが変更される可能性がある
それぞれ具体的に解説していきます。
6-1. 企業ごとに制度が異なる
企業年金を受け取る際には、企業ごとに制度が異なる点に注意しましょう。
年金と一時金のどちらに対応しているのかや、併用が可能かどうかは、企業ごとに設定します。年金の場合、受取開始の時期は一般的には退職した1~2ヵ月後であることが多いですが、企業ごとにさまざまです。
従業員が企業年金制度を把握していれば、退職後のライフプランを立てる際に役立ちます。企業側の対応としては、就業規則の退職金規則を確認するよう社員にうながしたり、企業の担当部門から直接説明する機会を設けたりしましょう。
6-2. 中途退職時にも企業年金を受給可能な場合がある
中途退職時にも、場合によっては企業年金を受給可能です。
例えば、加入していた企業年金を脱退後、加入期間分の年金原資を企業年金連合会に移した人は、そこから年金が受け取れます。
また、企業年金は通算が可能です。ポータビリティ制度を使い、退職前の企業における年金資金を、転職先の企業年金に移して継続がおこなえます。
ただし、すべての企業年金が通算できるわけではありません。企業の担当者は、中途採用者や中途退職者があった際の対応に注意しましょう。
参考:企業年金連合会から給付を受けられる方とは?|企業年金連合会
6-3. ルールが変更される可能性がある
企業年金制度やその受け取り方は、時勢に合わせて変更される可能性があります。法改正などがあれば、それに合わせて企業年金制度を見直すこともあるでしょう。
従業員にとって、企業年金はリタイヤ後の生活を支える大切な資金源です。変更が決まった際には、すみやかに従業員へ周知するよう配慮しましょう。
7. 企業年金制度を活用し企業と従業員の利益を獲得しよう

企業年金の受け取り方には、年金と一時金の2種類があり、どちらが得かはケースバイケースです。
企業年金は、退職後の従業員の生活を支えるのみならず、企業側にも社員の離職防止や採用力のアップ、税制上のメリットなどをもたらします。上手に活用し、企業と従業員の双方が利益を獲得できる体制づくりに努めましょう。
給与計算はシステムを使って工数削減!
給与計算を手計算しているとミスが発生しやすいほか、従業員の人数が増えてくると対応しきれないという課題が発生します。 システムによって給与計算の内製化には、以下のメリットがあります。
・勤怠情報から給与を自動計算
・標準報酬月額の算定や月変にも対応しており、計算ミスを減らせる
・Web給与明細の発行で封入や郵送の工数を削減し、確実に明細を従業員へ渡せる
システムを利用した給与計算についてさらに詳しく知りたい方は、こちらからクラウド型給与計算システム「ジンジャー給与」の紹介ページをご覧ください。