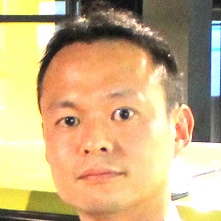“テクノロジーの進化”を洞察することで、ヒトの働き方が今後どのように変わっていくかを検証する「ヒト×テクノロジー研究所」。
記念すべき第一回目のレポートとして、所長の村山とヒトテク戦略部門パートナーの高橋が、タクシー業界を代表する経営者、“タクシー王子”こと日本交通・川鍋一朗会長を直撃しました。
モノづくりニッポンを代表する主要産業のひとつである自動車。日本の叡智と技術の結晶ともいえるクルマを最大限に活用したサービス産業が「タクシー業界」であることは、みなさんもご承知のとおり。
今回は、シリコンバレーで誕生したタクシー配車サービス「Uber」(ウーバー)がスマートフォンの進化と共に世界中を席巻する中で、日本のタクシー業界の風雲児が見通す未来を聞き出し、労働市場に与えるインパクトを考察しました。
この言葉が黄金期を迎える近未来を、ちょっとだけご紹介いたします!
※今回は、前編・後編の二部構成でご紹介いたします。

川鍋 一朗(カワナベ イチロウ)| 日本交通株式会社 代表取締役会長
テクノロジーの進化で<高まる安全性>と長距離移動の快適さが<変える東京生活>
村山:まず、僕が聞きたいのは、川鍋さんがこの先どんな世界を想像しているのかということです。車の自動運転化が見えてきている今、どこにビジネスチャンスを見出しているのか気になります。
高橋:そうですね。超高齢化社会が約束されている日本を、テクノロジーの力で乗り越える未来を思い描いた時に、川鍋さんはどんなビジョンをお持ちですか?

川鍋:まずは、自動運転化へのチャレンジを考えています。タクシー業界はその約7割が人件費なので、自動運転化に移行した場合、運賃は相当下がると考えています。
というのも人件費は、乗務員の二種免許取得や研修など、安全性を高めるためのコストも含まれるからです。もちろん最終責任は会社が負いますが、たとえば「衝突防止ブレーキの全車導入」など、テクノロジーによって安全性が担保されることで乗務員の必要スペックが下がり、結果的にはコスト負担が減ります。
また、駐車場などで、アクセルとブレーキの踏み間違えによる痛ましい事故が起こっていますが、こういった問題も「センサー」と「自動停止システムの向上」で防ぐことができます。
人間の視認性の限界や、睡眠不足・体調不良で起こるような不幸な事故は、この世からなくなるでしょう。

川鍋:それから、車が完全に自動運転化されないうちから、ものすごく生活は良くなると考えています。
いま、地方の過疎地にある道の駅を利用して、道の駅間を自動運転で移動するといった実験をしているところですが、本格的な自動運転化のファーストステップは、高速道路からの導入になるはずです。
決まった「自動運転レーン」を作るなど、閉域でテストをおこない実績を積み上げることで、BRT(Bus Rapid Transit:バス高速輸送システム)の導入も現実味を帯びてくるでしょう。

川鍋:こうなると、長距離移動の利便性が格段に上がります!
タクシーの未来としては、例えば、高速道路までは乗務員が運転し、インターで乗務員は降りて「どうぞ行ってらっしゃいませ」とボタンをピッと押して車を送り出してしまう。そのままスーッと自動運転で進んで行きます。行き先の高速道路出口まで来ると、そこには地元の乗務員が待機していて「ようこそいらっしゃいませ」と乗り込み、機械から手動での運転を引き継ぐのです。
自分の車でも、高速に乗ってしまえば最寄りのICまで運転せず運んでもらえるなら、相当ラクですよね。
そうなれば、東京の人間であれば“週末のデュアルライフ”が気軽に楽しめるようになります。金曜午後からのプレミアムフライデーも、会社が終わってビール一杯ひっかけてから高速に乗り、週末は海や山で遊んで過ごす。
東京に求めるものを“職住接近”の利便性とすれば、何千万もの家を買う必要はありません。その代わりに、自然豊かな地方でもう一軒「別宅」を持てば、すごくリッチな生活ができます。
実際のところ、私は子どもが3人いてサーフィンもやりますが、千葉県鴨川では数百万で目の前に海が広がるマンションが買えますからね。
東京での暮らしはスペックを抑えておいて、その分週末のリッチな地方ライフで子育てを楽しむ。そういった、総合的な暮らしの価値を上げられる世界が間違いなく来ると考えています。
高速が自動化されるだけで実現するのなら、そう遠い話ではありません。いま、地方の過疎化が叫ばれていますが、むしろ高速道路にアクセスの良い土地の価格は上がるかもしれませんよ!

「自動運転技術」の進化で「人の温かみのあるサービス」の価値が向上する
村山:とはいえ、まだこの先10年では完全自動運転の時代にはならないですよね。しかし、その時が来たら、運転手の仕事はどう変わるのでしょうか。
川鍋:たしかに変化のスピード感は読めないところがありますね。ただ、「完全自動運転」の時代が来たとしても、少なくとも今タクシー業界で運転しているプロドライバーたちの仕事はなくならないと考えています。
というのも日本交通では現在、お子さまだけ、またはご高齢のお客さまだけの移動の際にご利用いただける「キッズタクシー」と「サポートタクシー」、それに妊婦さんが事前登録する「陣痛タクシー」といったコミュニケーション重視のタクシーサービスを展開しています。

川鍋:この分野に関して、新卒採用の若い乗務員が非常に高いスキルを持っていて、育成の段階から“見守り”や“声がけ”といった、ヘルパーとしてのサービスレベルは確実に向上しています。
こうしたサポートを必要とするお客様に対して、何かあればすぐ察知して即対応できる「介護事業者」や「保育士」のようなスキルを持つ乗務員が運転するタクシーやモビリティは、自動運転の時代においても、今の乗務員人口の2割ぐらいは生き残るはずです。
高橋:なるほど。テクノロジーが人を代替えするのではなく、テクノロジーが進化すればするほど逆に“人にしかできない仕事”が浮き彫りになる。つまりは人と人との“触れ合い”や“温かみ”といった付加価値が求められるのかもしれませんね。
川鍋:そこを見据えての準備とも言えます。
高橋:実際に日本交通さんはドライバーのみなさんがすごく良いので、僕自身毎日気持ちよく使わせていただいています。みてください、この桜カード。僕3枚持っていて、実は妻も1枚持っています。

川鍋:おお!これ3枚も持っている人初めて会いました。都内約4,000台のうち4台で配布しているものなのに・・・!!本当に毎日使ってくださっているのですね。ありがとうございます!
村山:たしかに、僕も海外だと便利なので「Uber」を利用しますが、日本では日本交通さんです。「Uber」は時間が遅れると有無を言わさず課金されますが、日本交通のドライバーさんは待っていてくれたり、車が変わる場合はきちんと知らせてくれたりなど、アプリからしてホスピタリティを感じますよね。
高橋:システムで運営されている印象の「Uber」と、人の温かみがあるサービスを提供する日本交通さんの違いはこんなに大きい。われわれが一番大事だと考えているのはそこで、「人の温かみを残す技術革新」を探していきたいと思っているのです。