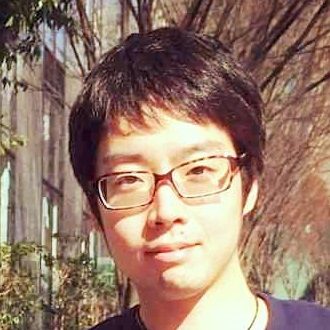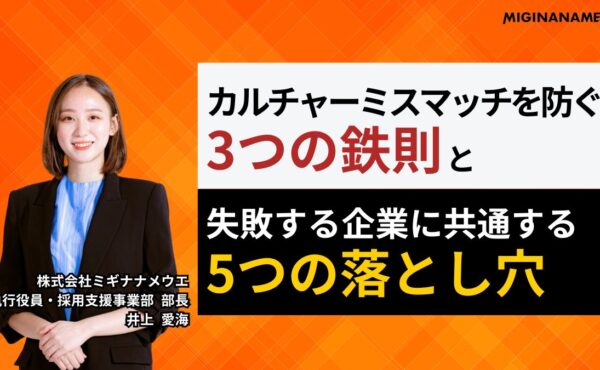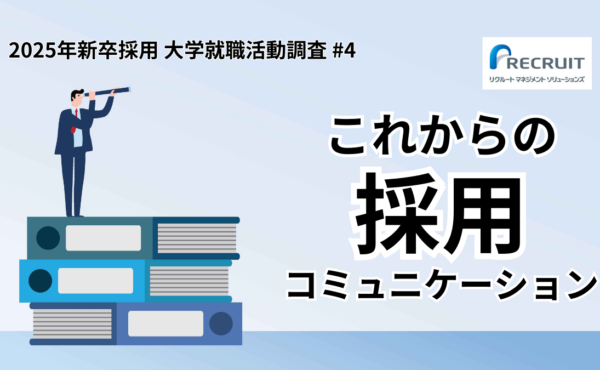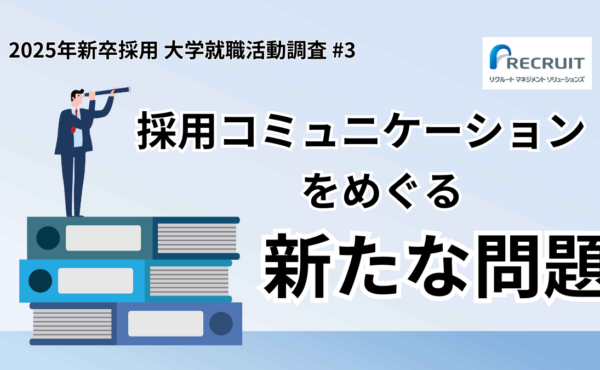ここ数年で、毎日のように技術進化に関する記事を目にするようになってきました。
「10年後にはロボットに取って代わられる職業」のようなランキングが発表されるなど、今後の働き方において「人とロボット」は密接に関係してきます。
その中でも注目したいキーワードがあります。それが「RPA」です。
導入している企業が増えているものの、その意味をきちんと理解している人は多くないのではないでしょうか。
そこで今回は、RPAについてそもそもの定義から事例、導入のステップまで詳しくご紹介していきます。
目次
1. RPAとは
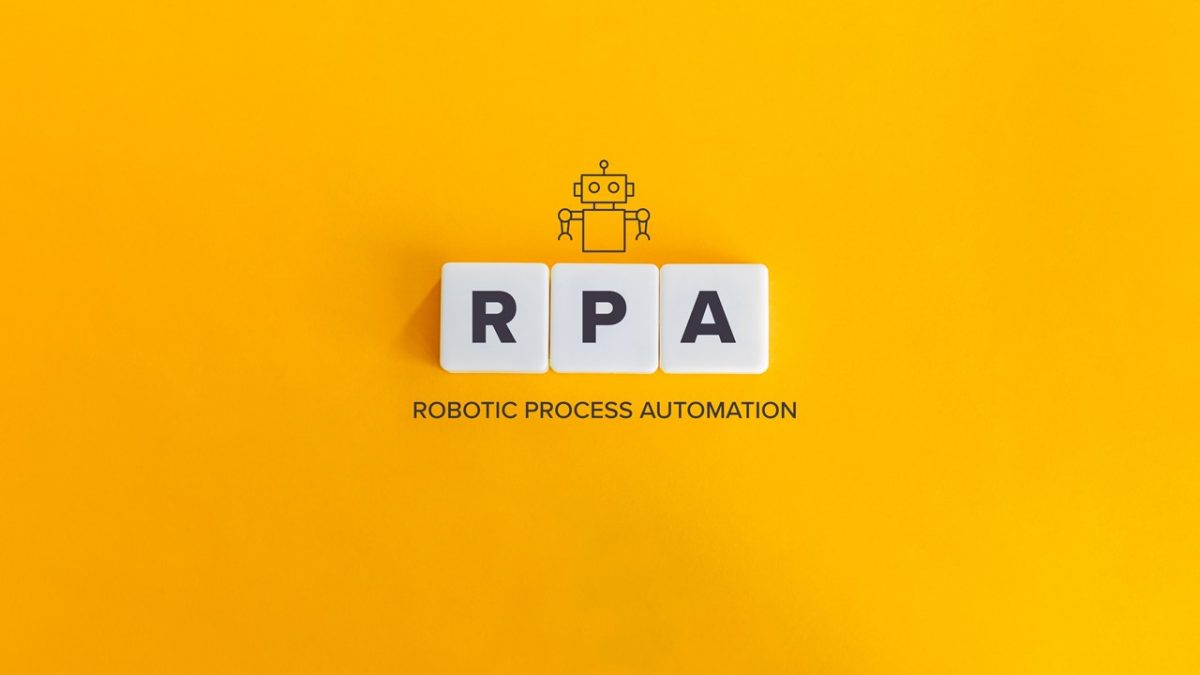
RPAとは「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略語です。日本RPA協会は、RPAは以下のように定義しています。
「これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしくはより高度な作業を人間に代わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用して業務を代行・代替する取り組み」
RPAの主な利用事例としては、事務作業のようなルーティンワークが挙げられます。
たとえば、2014年からRPAを利用している日本生命では、人からRPAが業務を担当するようになって5倍速で仕事を遂行出来るようになったと報告されています。
※参考:事務作業5倍速で手応え、日本生命がRPAの範囲拡大へ/日経コンピュータ
これまでは人が作業を遂行してきましたが、RPAが導入されるとデジタル上における”仮想知的労働者(デジタルレイバー)”が人の代わりに作業を遂行することになります。
24時間365日稼働が可能であり、業務も正確なためルーティン業務においては、人間よりも圧倒的にパフォーマンスを発揮します。
2016年が「RPA元年」と言われていますが、2017年にかけて導入が進み、2018年以降はより多くの企業が活用していくであろう取り組みとなっています。
MM総研の調査によると、2020年度末の時点で、民間企業への普及率は39%、自治体への導入は61%となっています。
1-1. RPAが普及し始めた背景
では、なぜRPAが日本で普及し始めているのでしょうか?
その背景には、RPAが「日本の課題である”人手不足”を解決出来るソリューションになり得る」という期待が存在します。
日本における重要課題の一つに「生産年齢人口の確保」が挙げられます。少子高齢化が叫ばれ始めて久しいですが、経済成長以前に現在の経済を維持するためには、減少していく労働力をいかにして担保するかが求められます。
最近では、少ない労働力でも同じアウトプットが保てるように「生産性」というキーワードの元に働き方改革が推進されていますが、人間の労働力には限界があります。
そのため、24時間365日いつでも稼働可能な仮想知的労働者(デジタルレイバー)が新たな労働力として期待されているのです。
1-2. RPAを導入するメリット
RPAを導入するメリットを、さらに掘り下げて見ていきましょう。
①業務の効率化
単純作業をRPAに任せることで、人間の何百倍ものスピードで情報を処理することができます。そのうえ、エラーが起きない限り人間よりも正確に仕事をしてくれるため、効率的に業務を進めることができます。
②コストの削減
今まで多くの人数を要していた業務も、RPAを導入したらパソコン1台で解決します。これまで5人でおこなっていた仕事が1人で十分になることや、場合によってはそれ以上の効果を得られるでしょう。
これにより、人件費が大幅にカットできます。
③業務品質の向上
正確に膨大な量の作業をおこなうRPAを導入することで、労働者の業務時間に余裕が生まれ、それまで事務処理に割いていた時間をクリエイティブな仕事に充てることができます。
これにより、より良いアイディアが生まれたり、ミーティングの時間を増やして意見交換の機会が増えたりするでしょう。
1-3. RPAとAI、VBAの違い
RPAと混同されがちなキーワードとして、AIやVBAが挙げられます。実際にどのように異なるのかを知ることで、RPAについてさらに理解を深めましょう。
①AI(Artificial Inteligence)との違い
RPAは指示された業務を正しくおこなうのが得意ですが、反対に自分で考える業務には適していません。
一方、AIの最大の特徴は「学習能力」なので、AIは指示された業務を自分で判断しておこなうことができます。
RPAが「作業」に特化しているとすると、AIは「思考と作業」を両立していると言えます。
しかし、RPAにAIを搭載し自律的に判断できる、高度なRPAも存在します。
その発達段階に応じて、3種類、RPAのほかに、EPA(Enhanced Process Automation)、CA(Cognitive Automation)も存在します。最も高度なCAでは、自身が考え判断をするため、業務の全工程を自動化することができます。
②VBA(Visual Basic for Applications)との違い
VBAとRPAの大きな違いは2つあります。
一つ目は、RPAはパソコン内でおこなわれる作業全般に対して自動化が実装できるのに対し、VBAは原則としてOfficeアプリケーションでしか作動しない点です。
二つ目は、RPAは基本的にノンプログラミングなのに対し、VBAはプログラミングが必要な点です。そのため、RPAの方が実装のハードルが低いと言えます。
2. RPAの導入に向いている企業の特徴

先述したように、仮想知的労働者(デジタルレイバー)は労働力を担保する新しいリソースとして注目を集めていますが、現在のRPAは全ての業務に適用可能なものではありません。
実際には”新しい思想を生み出すこと”は現状の技術では難しく、基本的には”作業”に向いています。具体的には、作業時間が長い業務、作業が多い業務に適していると言えます。
1回の作業時間が長い業務や、毎日おこなうような作業頻度の高い業務、そして多人数でおこなっている場合であれば、RPAに移行した際のコスト削減量は大きくなります。
「人の能力差で、結果の差異が出ない作業」においても、適用しやすいのが特徴です。
これらの作業の代表例として、以下の業務が当てはまります。
- データの登録、転記
- システムの管理
- 社内アプリの操作
- データの同一性チェック
- 大量のファイルのダウンロード、アップロード
- メールの一斉送信
また人事・労務の観点から考えると、以下のような業務にも積極的に導入を検討すべきです。
- 業務をおこなう時間が就業時間外となってしまう業務
- 業務をおこなう時間が決まっており、かつ他の業務を止めて対応しなければならない業務
- 業務難易度や負荷がかかる業務
現在、こういった業務が多くなっている企業は、RPAを活用することで大きな効果を得られると考えられます。
RPAを活用することで、これまでどうしても発生していた残業や長時間労働の原因となっていた業務の削減につながるため、人事・労務の観点からRPAは積極的に活用してくべきです。
ただし、RPAは非定型業務が苦手で、都度判断や変更が必要な業務には適用することはできないため、注意が必要です。
3.RPAの活用事例

ここまで、RPAとは何か、そしてRPA導入に適している企業の特徴を解説してきました。
それでは、実際にRPAを活用するとどのような効果があるのか、活用事例をご紹介します。
3-1.人事・総務部門でのRPA活用|株式会社シーエーシー
過重労働管理業務(対象社員の絞り込み~アラートメールの通知)や、人事考課業務(考課表の配布・回収)などを自動化することが可能です。
月次報告書作成業務などシステム連携が必要な業務についても自動化が目指せます。
また、タイムカードの打刻漏れをチェックし、該当者に一斉に注意喚起メールを送ることも、RPAを導入すれば自動でおこなうことができます。
株式会社シーエーシーでは、70本のソフトウェアロボットが稼働しています。その結果月間で約15時間、83%の工数削減効果が生まれました。
さらに社員からは、速さだけではなく、いつも同じ処理を手動で繰り返す精神的な負担ををなくす、ストレス軽減の効果もあったという声も挙がりました。
参考:RPAを人事部に導入し、生産性が向上|株式会社シーエーシー
3-2.経理部門でのRPA活用|株式会社マルエツ
具体的には売掛・買掛処理や資産管理業務、交通費確認業務といった業務を自動化可能です。また人が介入しないことで記入漏れといった人為的なミスを防ぐ効果もあります。
マルエツでは、社員が申請した交通費を確認する業務や、会計システムへ登録する際におこなう金融機関との照合などの作業を自動化しました。
2018年4月から6月に実施した実証実験では、月間200時間かかっていた作業時間を20時間に削減できました。
参考:RPA導入事例まとめ7例|sweep magazime
3-3.営業・販売部門でのRPA活用|カゴメ株式会社
見積作成業務やメール受注業務などを自動化することが可能です。特に営業部門については、直接利益を生み出さない作業時間を減らすことで、生産性の向上が見込めます。
カゴメ株式会社では、EC企業からの受注業務を半自動化、各商品の納品予約や販促申請の作業を自動化しています。
その結果、一人あたりの残業時間が年間で約100時間カットできました。
参考:受注業務や納品予約・販促申請業務を簡易化|BizteX cobit
4.RPA導入の手順

それでは、実際にRPAを導入する時にどのような手順を踏めば良いのでしょうか。5つのステップをご紹介します。
①自動化したい業務を洗い出し、決定する
まず、社内でおこなわれている業務のうち、ルーティン作業と化しているものを洗い出し、自動化する業務を決定します。
最も時間を要しているものや、人間による判断がほとんど不要なものをピックアップするのが良いでしょう。その際、現状どれくらいのコストがかかっているのかも計算しておきましょう。
②要件に合わせてRPAツールを選定する
RPAツールは様々な種類があります。
- Webブラウザ上で操作をする「クラウド型」か、自社にサーバーを設置する「オンプレミス型」か
- 「特化型」なのか「汎用型」なのか
- 欲しい機能は備わっているのか
- サポートは充実しているか
などを基準に検討するのが良いでしょう。
③RPAツールをテスト導入する
初めて導入する際は、無料トライアル期間があるツールを用いてRPAを試してみるのが良いでしょう。
例えば、WinActorやBizRobo!には、無料トライアル期間があります。
フリーソフトもありますが、セキュリティの安全性や機能の種類、サポートの手厚さなどから、有料ツールの無料期間をまず使用してみることをおすすめします。
④導入効果を検証する
テスト導入したツールの使い勝手や、自動化した業務の成果などを踏まえて、改めて自動化すべき業務やツールの検討をおこないます。
その際、①で計算した業務当たりの所要時間と導入後の所要時間とを比べて、効果を数字で測れるようにしましょう。
⑤RPAツールを本格導入する
④までで決定した内容を元にRPAツールを選定し、実際に会社に導入していきます。
その際、業務内容が変更になる部署に関して、ワークフローや就業マニュアルの改訂もおこないます。
先述した通り、RPAは自分で判断する場面になると作業が停滞してしまうおそれがあります。自動化する業務を完全にRPAに任せるのではなく、エラーの対応役として従業員を1人は配置するようにしましょう。
経営者から人事に求められることは単に「RPAを導入によるコストや労働時間を削減する」ことだけではありません。実際には「RPA導入後の労働リソースを如何に活用するか」ということまで経営者は考える必要があり、人事としてもこの目線を忘れないことが大切です。また働く側の視点から考えると、優秀な人材ほど「リソースをどこに割り当てるのか」を重視します。単純なルーティン業務から解放された後に、業務難易度が高く個人としても成長が見込める業務に比重を多く割けるかどうかによって、個人の成長度合いは大きく左右されます。これは人材の採用や定着において、一定の影響力を持つ要素になります。少なくとも、誰がやっても成果に差異が出ず、個人の成長にも寄与しにくいルーティン業務をどのように減らすかが事業の成長にも組織の成長にも大きな影響を与えるのではないでしょうか?
5.まとめ
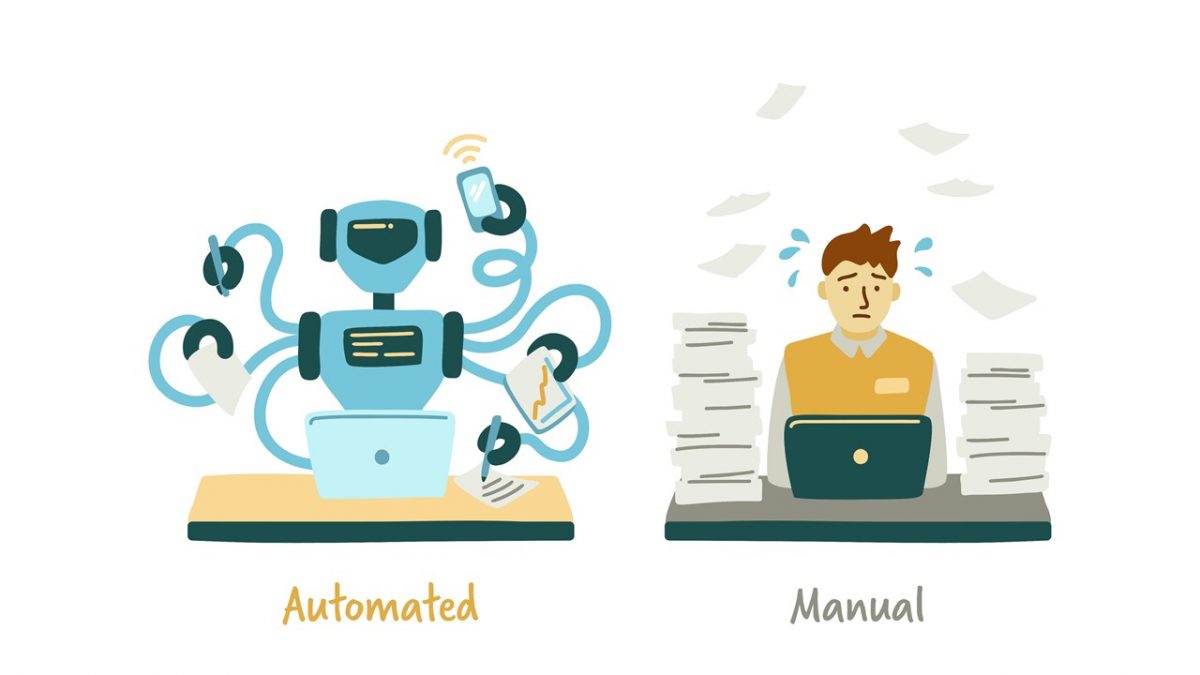
RPAについての理解は深まったでしょうか?
人件費を削減したい、残業時間を減らしたい、、このような課題を抱えている企業にとって、RPAはひとつの解決策となり得ます。
ルーティン化した仕事を効率化することによって、クリエイティブな仕事をはじめとする「人間にしかできない」仕事にリソースを割くことができ、生産性の向上や品質アップ、さらに、残業時間削減による社員の働き方改善も期待できます。
ぜひ、迷っている方も、はじめてRPAを知った方も、この記事を参考にして導入を検討してみてください。