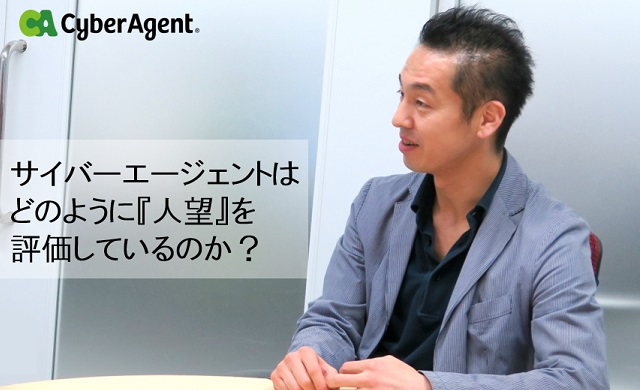 社員を評価する際に、売上といった『成果』に注目している企業は非常に多いと思います。その一方で「人徳がある」「信頼がある」といった『人望』の部分に注目して評価する企業もあります。
社員を評価する際に、売上といった『成果』に注目している企業は非常に多いと思います。その一方で「人徳がある」「信頼がある」といった『人望』の部分に注目して評価する企業もあります。サイバーエージェントでも、表彰や管理職登用の際に『人望』を重視しているとのこと。しかし、この『人望』の部分をどう評価していくのか。人望がある社員、人望がない社員をどのように見極めて評価していけばいいのでしょうか。
今回は、サイバーエージェントが実施している人望の評価方法や、そもそもなぜ人望を重視しているのかについてご紹介します。

曽山 哲人(そやま てつひと)|株式会社サイバーエージェント 取締役 人事統括
目次
サイバーエージェントは、なぜ人望を評価するのか?
―曽山さんが考える人望とはどのようなものでしょうか?
曽山氏:人望とは、第三者から「あの人は良い人だ」と言われることです。本人の評価軸は全く関係ありません。第三者から見て「良い人だと思われている度合いが高い」ことが、人望があるということです。
成果を出せることも、もちろん一つの人望なのですが、結局その人自体の魅力は、周囲の人たちに対して敬意を持って接しているか、気配りができているか、そういったところから生まれてきます。
逆に人望が得られないパターンはデリカシーのない人です。繊細な部分に気がつかない、周囲に対する配慮が足りない人は人望がないと言われてしまいます。
1年目の社員でまだ結果を出していなくても、周囲に対する気配りがしっかりでき一生懸命頑張っていく姿を見せていくことで、人望を集めていくことができます。
―そもそもサイバーエージェントでは、なぜ人望を評価するのでしょうか。
曽山氏:サイバーエージェントの上場直後にマネジメントがうまくいかなかった時期があったことがきっかけですね。
弊社は1998年に創業して、2000年に上場をしているのですが、上場前は社員数もそこまで多くなく、仕組みが整っていなくてもある程度うまくいっていたんです。
そこから上場したタイミングで、幹部となる人材を採用するために、中途採用に力を入れていきました。けれど、まだマネジメントの仕組みができていなかったことと、採用した方々がネットのビジネスに慣れていなかったこと。この掛け算が悪い方に働いてしまいました。
採用した方々にマネージャーを任せ、本当に必死にやってくれていたのですが、すごく厳しいマネジメントをされる方が多かったんです。その結果、組織内でさまざまな不協和音が生まれていきました。
また、突き抜けた結果を出すのですが、その評価が割れてしまう人もいました。「あの人はすごい」というリスペクトと、「あの人の仕事のやり方にはついていけない」という不満の両方が出るんです。
たとえば営業だと分かりやすく、売上はつくるけれど、その後の書類対応やオペレーションが雑なため、サポートスタッフのメンバーからは信頼されないケースなどがありますね。こういったケースが増えると、一枚岩の組織をつくることが難しくなります。
当時を振り返ると、その人たちが悪いというわけではなく、明らかに経営サイドの採用ミス、マネジメントミスが引き起こしたものだと感じています。このような経験から、人望がある人材をリーダーに登用することの重要性に至りました。
「表彰は経営メッセージである」人望の重要性を社員に伝える方法

―人望の重要性を社員に伝えるためにどのようなことをされているのでしょうか。
曽山氏:できるだけ、人望がある方を表彰するようにしています。
表彰とは経営メッセージなんです。表彰されて壇上に上がる人を見て「私たちはこのような人を評価するので、みなさんもそのようになってくださいね」というメッセージを送っています。
もし、人望がない人を表彰で壇上へ上げた際、社員はどう見るか。「表彰されるってことは、会社にとってあの人のやり方が評価されるということなんだ。自分さえ成果を出せばいいんだな」と、組織にとって悪影響を与えることにつながるかもしれません。
もちろん、徹底的に結果だけを見て評価していくやり方でも問題ないと思います。それを否定するつもりはありません。あくまでも、会社のポリシーが明確で、そこに則っているかどうかが重要だと思います。
また、人望が高い人を表彰すると、共通して周囲に対する数多くの感謝の言葉を発信するんです。人望のある人は表彰のコメントで周囲へ感謝をし、人望が少ない人は感謝よりも、自分に対しての褒め言葉を増やすんです。
―売上などのわかりやすい成果と、評価が見えにくい人望。誰を表彰すべきか、そのバランスが難しそうですが、どのようにしているのでしょうか?
曽山氏:まず大前提としてあるのは、成果をあげた人を表彰の対象にすることです。そして、成果をあげた人の中で人望のある人を選んでいくというイメージです。なので、人望はあるけれども成果の上がってない人が表彰されて壇上に上がれることはありません。
―なるほど。そこで成果をあげたけれども表彰されなかった人は、何が足りなかったのか気づくわけですね。
曽山氏:そうです。そこで足りないことに気づいてもらい、意識してもらい、実行に移してもらうようにしています。私は、人はやれば変われるはずだと思っています。
人望を評価するために見ている3つの視点
―人望を評価するために実施していることはどのようなものでしょうか。
曽山氏:大きく3つあります。
1つ目は、社員総会に向けて誰を表彰すべきか推薦を募ることです。新人賞、マネージャー賞などさまざまな賞があるのですが、全社員が「誰を表彰するべきか、表彰させたいか」推薦することができるんです。
そして、「推薦は強制ではなく任意である」という点がポイントです。任意なので、推薦したくなければしなくていいんですよ。その上で「あの人を壇上に立たせたい」と推薦してくるということは、かなり意味のある一票になります。
推薦は、毎年3000件くらい集まります。1つの賞につき200人分くらいの推薦があります。また、その推薦の中に、推薦コメントもついていて、「こういう点でお世話になった」といった感謝の言葉が入っているんですよ。
2つ目は、役員と社員の定期的な食事です。役員が普段から社員と食事に行くようにしているのですが、そこでの会話の内容が重要です。「どこの部署が評判が良いのか」「誰が最近イケてるのか」という内容が会話の中で自然と出てくるのです。そうすると「この人の名前が挙がってくるんだ」と、人望のある人材が誰なのかインプットすることができます。
3つ目は、特に私になりますが、人事本部長として将来の幹部候補になり得る社員と折を見て面談をさせてもらっていて、そこでどのような思想を持っているのか、よく聞いているんですね。
具体的には、その人の周りのメンバーにはどういう人がいて、自分の近くにいる有望な人材は誰か聞くんです。有望な人材をたくさん言える人は、人望があるというケースが多いですね。
「あの人すごい良いですよ」とか、「1年目の彼、超イイですよ」というように、自分より下のレイヤーの人を褒めることができる人材は、自分の長所と短所を見極めることができていて、周囲を活かせる人だと思います。
管理職には人望のある人材を必ず登用するようしている

―経営メッセージとして、「人望がある人を評価していく」ということは伝えているのでしょうか?
曽山氏:明確に全社メッセージとしては伝えていませんが、弊社社長の藤田がいつもメディアの取材やブログなどで公言しています。
一方で、管理職の登用においては、人望を評価することは明確に伝えています。必ず人望のある人を管理職にするように決めていて、そういった人であれば、周囲に感謝したり配慮したりできるので、協力や応援が集まりやすいんですよ。結局ひとりよがりでは、管理職は務まりませんから。
―管理職登用の際は、どのように人望を評価しているのですか?
曽山氏:そうですね。私たちの場合は『GEPPO』を用いています。GEPPOには、社員一人ひとりが毎月のアンケートで回答した内容とともに、人事との面談で話していた内容などが紐づいているんです。ネガティブ情報というよりは加点情報をとにかく入れるようにしています。
また、管理職への昇格は、役員会で決議しています。役員全員で、昇格候補者の顔写真つきのプロフィールを見ながら議論しているんです。それくらい私たちの中ではすごく重要な意思決定にしています。
―ただ成果を出すことだけにガムシャラになっていてもいけませんね。
曽山氏:若いうちはそれでも良いかもしれません。人望を意識し過ぎて、周りへの配慮に終始し結果を出さないよりは、まずは1回結果を出すことが重要だと思います。
ただ、人望がない人はそこから結果を出し続けるのが難しくなるんですよ。人望がなくても、すぐに結果を出すことはできます。しかし、続かないんです。
人望があって結果を出している人は永続性があります。なぜかというとピンチのときに助けてくれるサポーターが多いからです。私たちは自社の永続的な成長(ゴーイングコンサーン)を目指しています。そういった観点でも、本当に人望が必要になってくるんです。







