
突然ですが、「GRIT(グリット)」という言葉を聞いたことはありますか?
起業家、ビジネスマン、アスリート、アーティスト、学者など、さまざまな分野で多大な成果を上げた「成功者に共通する力」として、今非常に注目を集めています。
本記事では、「GRIT」を発揮するためにはどうすればよいか、その具体的な手法と事例について解説します。
GRIT(グリット)とは

GRIT(グリット)とは「やり抜く力」のことで、アメリカの心理学者であり、ペンシルヴァニア大学のアンジェラ・リー・ダックワース教授が提唱した言葉です。
- Guts(ガッツ):困難に立ち向かう「闘志」
- Resilience(レジリエンス):失敗してもあきらめずに続ける「粘り強さ」
- Initiative(イニシアチブ):自らが目標を定め取り組む「自発」
- Tenacity(テナシティ):最後までやり遂げる「執念」
以上の4つの頭文字を取って、GRIT(グリット)と言われています。
アンジェラ教授は、世界有数のコンサルティング会社マッキンゼーで勤務した後、ニューヨークの公立中学の数学教師をしていた際に、成績が優秀な学生の共通した特徴は、頭の良さや生活環境ではないことに気づきました。
そこから大学に戻り研究を続けた結果、『成功する人に共通する特徴は「情熱」と「粘り強さ」、すなわち「やり抜く力(GRIT)」である』と結論付けます。
2016年に発売された書籍「Grit: The Power of Passion and Perseverance」はベストセラーとなり、日本でも「やり抜く力――人生のあらゆる成功を決める『究極の能力』を身につける」というタイトルで発売されています。
また、TEDに登壇した際の動画は900万回以上も再生されています。
才能や知性がある人のGRITが強いわけではない
この研究の面白い点は、「才能や知性」と「GRIT」には、全く関係が無いと定義付けたことでしょう。(「才能が重要ではない」という話ではなく、「才能があったとしてもそれを生かせるどうかは別の問題である」ということです。)
「成功に才能や知性が関係していない」とするこの理論は、さまざまな人種や学歴の人が存在するアメリカで広く受け入れられました。
研究では「高い才能をもちながら途中で挫折してしまった人」や「周囲と比較して際立った才能を持っていなくても成功を収めた人」などが実際に存在することを例に挙げながら、そのことを詳しく説明しています。
FacebookのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏がビジネスで成功した要因もGRITであるとされています。
GRITは伸ばすことができる
そしてGRITは、大人になってからでもトレーニングを実施すれば、後天的に伸ばすことができます。
これまでに成果を出すことができなかった人でも、GRITを高めることで成果の出せる人材になることができれば、個人としても企業としても喜ばしいことでしょう。
人事ご担当者の方は、社員研修や目標設定面談の際にGRITを取り入れて評価・フィードバックをおこなってみてはいかがでしょうか。
GRITを伸ばすための方法
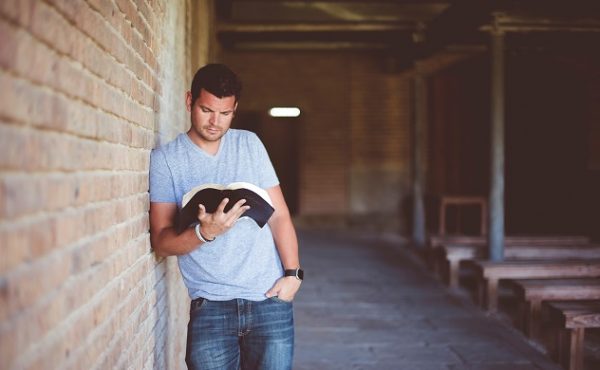
GRITは、「ただ何かをやり抜けば良い」というわけではありません。
正しい目標設定をおこない、他人のアドバイスを謙虚に受け止めながら、周囲の人に認められるような行動を起こすことが大事です。
GRITを伸ばすための方法としては、次のようなことが挙げられます。
- 興味があることに打ち込む
- 失敗を恐れずチャレンジし続ける(挑戦せざるをえない環境を作る)
- 小さな成功体験を積み重ねる
- GRITがある人のいる環境に身を置く
まずは、学生時代の部活動や課外活動のように、自分が本気で打ち込めるものを探してみましょう。
これは、本業に直結していなくても構いません。その活動を粘り強くおこなうことでGRITが育まれ、それが本業にも活きてくるからです。
また、その際には何事も最初から無理だと決めつけずに、新しいことにチャレンジしてみることも大事です。
「もしかしたら、できるんじゃないか」「どうやったらできるだろうか」と物事を前向きに捉えるクセをつけることから始めてみましょう。
自分の意識や習慣を変えるのはなかなかハードルが高いと思いますので、GRITが高い人がそばにいる環境に自ら飛び込み、そうせざるをえない状況に追い込むことも時には必要かもしれません。
アンジェラ教授も、実際にルールとして「ハードなことに挑戦する」というルールを家族で共有し、やらざるをえない環境を作っていたとのことです。
人は周囲の環境にどうしても依存してしまうものですので、もし人事担当者として社員のGRITを高めたいと考えるなら、GRITの高い人材をメンターとして配置したり、中長期的にはGRITを会社の文化として根付かせていくというような施策を打つことも大事でしょう。
そして、最後に、GRITが高い人は常に自分に自信を持ち、自分ならやれるという信念を持っています。その信念を支えている要素の1つが過去の成功体験でしょう。
まずは自分でもできるところから少しずつ始め、徐々に自分のスキルより少し上の目標を設定しそれをクリアするという経験を積むことも大事です。
その上で果敢に挑戦し、失敗したとしてもチャレンジし続けましょう。GRITが高いとされている人たちも数え切れないほどの失敗を経て大きな成果を残すに至っています。
GRITの具体的な測定方法
自分にGRITがあるのかどうか測定する方法として、アンジェラ教授がアメリカ陸軍士官学校で実施した調査の中で開発した「グリット・スケール」という方法について解説します。

グリット・スケールは、以上の10個の各項目について、自分が当てはまると思うスケールの数字をチェックしていき、その数字の合計を10で割った数字(グリット・スコア)によりGRITの高さを測定します。
最高点は5点で、グリット・スコアが高いほどGRITが高い状態となります。
このグリット・スコアは、現在の自分がどのような状態にあるか測定するものであり、気持ちや状況によって変化します。
常に高い数値を取ることができるように、自分のGRITを高めることが大事です。
「GRIT が高い日本人」とは
①イチロー(プロ野球選手)
「特別なことをするために特別なことをするのではない、特別なことをするために普段どおりの当たり前のことをする。」
「努力せずに何かできるようになる人のことを天才というのなら僕はそうじゃない。努力した結果何かができるようになる人のことを天才というのなら僕はそうだと思う。」
やり抜く力と聞いて、イチロー選手のことを想像する方も多いのではないでしょうか?
もはや説明の必要性はないかもしれませんが、当たり前のことを毎日積み重ね続けるまさに職人。
1つ1つは地味に見えることを、ひたすら継続するというのはGRITが高い人に共通している部分です。
②本田宗一郎(本田技研工業・創業者)
「私の最大の光栄は、一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起きるところにある。」
「得手に帆を揚げて」とはよく言ったもので、得意な道を一生懸命に打ち込んでおりさえすれば、チャンスは必ずある。」
今もなお起業家精神に満ち溢れた経営者として崇拝され続けている本田宗一郎氏。
創業当初から世界を目指して高い目標のもと突き進んでいた同氏ですが、「倒れるごとに起きる」という精神はまさにGRITそのものだと言えるでしょう。
③山中伸弥(京都大学iPS細胞研究所所長・教授)
「9回失敗しないと、なかなか1回の成功が手に入らない」
「ここで研究をやめたら、臨床医の世界から逃げ出して以来、二回目の挫折になる。それはあまりにも情けない。研究をつづけるべきか迷っているうちに、朝も起きられなくなっていきました。」
2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞された、山中教授もやり抜く力に長けた方です。
前人未到の領域に長年取り組み、特許戦争や資金難など度重なる困難にも立ち向かい続けた上でのノーベル賞受賞。感銘を受けた方も多いでしょう。
④伊能忠敬(江戸時代の測量家)
「歩け、歩け。続ける事の大切さ。」
急に歴史上の人物になってしまいしたが、私個人はGRITと聞いて伊能忠敬を最初にイメージしました。
50歳で天文学を学び、そこから17年という膨大な年月をかけて全国各地を測量し、『大日本沿海輿地全図』を完成させた、まさに凄まじいGRITの持ち主です。
今からでも遅くはない。GRITを高めよう。
今回はGRIT(グリット)についてご紹介しました。
「やり抜く力」「情熱」「粘り強さ」といった価値観は新しい概念というわけではないため、中には「当たり前じゃないか?」 と思われた方もいるかもしれません。
しかし、当たり前のことを持続してやり続けることはとても大変で、わかっていても実践できないという人も多くいることと思います。
環境の激しい現代社会において、これからは目の前のことに集中してやり抜く力がとても大切です。
GRITは今からでも伸ばすことができるので、少しずつ育んでいってはいかがでしょうか。







