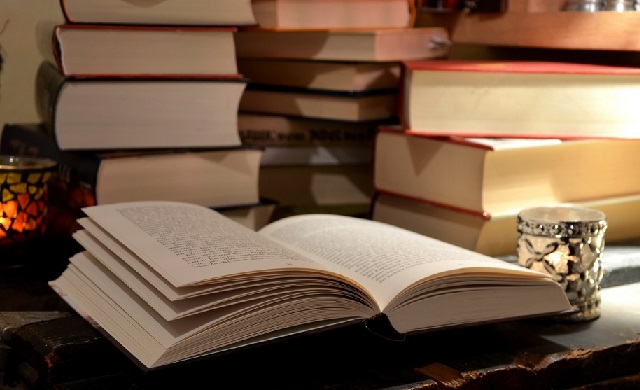
人事担当者が目指す資格試験として真っ先に思い浮かぶものの1つに社会保険労務士(社労士)試験があります。
ただ、社労士試験は毎年数万人が受験し、合格率1ケタの「難関資格」であるため、受験を躊躇している人事担当者や人事への転職希望者が数多くいらっしゃると思います。
そこで、今回の記事では社労士試験の合格者である筆者が社労士試験を合格することで得られる3つのメリットについてお伝えしていきたいと思います。
そもそも社労士試験って?

社労士試験とは人事労務や社会保険のプロである社会保険労務士になるための「国家試験」で、毎年1回実施されています。国家試験というからには合格するための難易度もそれなりのもので、合格率はおおよそ7〜9%で毎年推移しています。
他の国家資格では行政書士や公認会計士の合格率が10%前後なので、合格率だけで考えればこれらと同等の難易度であるということができます。
社労士試験を合格することで得られる3つのメリット

1.人事(特に「労務」)の体系的な知識が身に付く
社労士試験の試験範囲は労働法や社会保険制度など企業の人事担当者であれば知っておいて損はないものばかりで構成されています。
そのため、社労士試験の学習を通して人事業務(特に人事領域のうち労務)に関する体系的な知識を身に付けることができます。勉強した知識は決してムダにはならないため、仮に試験には落ちてしまったとしても、人事としてスキルアップできることは間違いありません。
2.人事の就職・転職に非常に有利
これは筆者の経験ベースですが、社労士の資格を有していれば、人事担当者の就職・転職には非常に有利に働きます。
有利になる度合いは人事のポジションや職種により多少異なりますが、担当者レベルの求人募集において社労士合格者が書類選考で落とされることはほとんどないといってもいいでしょう。(事実筆者は以前転職活動をしたとき約20社に応募して書類で不合格になったのは1社だけでした。)
3.フリーランスや独立を目指せる
これは受験するメリットというより合格後のメリットですが、社労士のスキルを持っていれば企業に属さずともフリーランスとして活動したり、社労士事務所を個人で立ち上げたりといったことが可能になります。
筆者は社労士として資格登録や開業はしていませんが、フリーランスとして人事コンサルティングやライター、講師など社労士のスキルを活かしながら、少なくとも会社員をしていた頃以上の収入を得ることができています。
最後に
このように、得られるメリットは決して少なくないため、人事の道に進む方であれば社労士試験は是非ともチャレンジしていただきたいものです。試験は毎年8月に実施されており、6~7か月程度集中して学習すれば充分合格は狙えるため、今から(2016年11月現在)学習をスタートしてみてはいかがでしょうか?







