目次
1. 日本における勤怠管理は江戸時代から
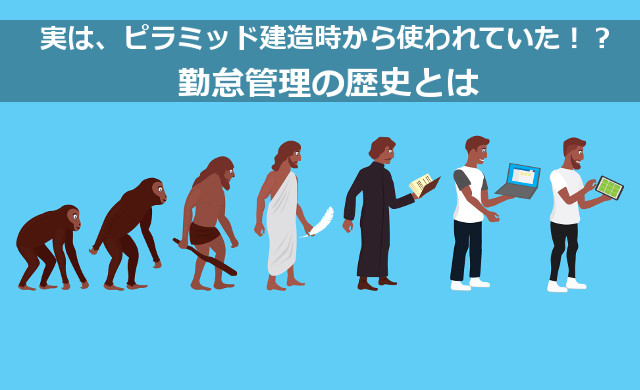
日本では江戸時代にはすでに、時代劇などでおなじみの「三井越後屋」において「改勤帳」「批言帳」という帳簿を用いた勤怠管理がおこなわれていたという記録があります。
「三井財閥」の前身となった三井越後屋は、江戸時代の都市部において「大店」と呼ばれる大規模な店舗を構えていました。奉公人と呼ばれた従業員数は1店舗で100人を超えるほどの大所帯であったため、その勤怠を管理する必要がありました。
さらに、奉公人たちはその働きによって役割が与えられ、有能なものは昇進する仕組みが存在していたようです。彼らが決められた勤務をこなしているかを責任者が把握・管理・評価するためには勤怠管理の仕組みが必要不可欠でした。
このように、日本では18世紀にはすでに人事組織とそれに付随する勤怠管理を含む各種人事規定の明文化と運用の実績がありました。
2. 世界的に見る勤怠管理の歴史とタイムレコーダーの発明

世界的にみると、労働者の勤怠管理の運用はすでに古代エジプトのピラミッド建造時からあったとされています。その勤怠管理の概念と方法が広まるのは産業革命を迎えたころからです。
そんな中、19世紀にアメリカでタイムレコーダーが発明されます。タイムレコーダーには時計が内蔵され、タイムカードに出勤日、出勤時刻、退勤時刻を記録する機能があります。
明治時代に入っていた日本にもこのタイムレコーダーは輸入され、多くの工場で使用されました。その後、昭和初期には国産のタイムレコーダーも開発されるほど、タイムレコーダーは勤怠管理に不可欠の道具となりました。
3. 勤怠管理における客観的指標の必要性

戦後、日本の高度経済成長・バブル期が終わり、経済の停滞が長く続く中で、企業における残業代などの賃金未払いが問題になるようになりました。
そんな中、厚生労働省は2001(平成13)年に労働基準法における「基発339号―労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」を発令します。
当時、自己申告で労働時間を把握していた事業所は労働時間の適正な把握のために対策をたてる必要がでてきました。そこには「タイムカード、ICカードなどの客観的な記録をその根拠とすること」と明記されていたので、タイムレコーダーなどを利用した勤怠管理システムの導入が一気に普及することになりました。
4. 勤怠管理システムの登場

タイムレコーダーによってタイムカードに打刻された時刻をもとに、従業員ごとに勤務時間から給与を計算するという業務は長い期間に渡って担当者の手作業でおこなわれていました。
しかし、時代を経て企業の雇用・給与体系はどんどん複雑化し、一律に出退勤時間だけで給与計算をすることが難しくなってきたため、勤怠管理には膨大な労力がかかるようになりました。
そこで時計をデジタル化した電子タイムレコーダーが発明されました。この勤怠管理システムの登場により打刻内容がデータ化が可能になったため、作業にかかる時間は大幅に削減されただけでなく、給与計算や転記ミスなども激減し、人事担当者の業務が効率化されました。
5. タイムレコーダーによる勤怠管理の問題点と今後の進化について

そもそもタイムカードをはじめとする勤怠管理システムには、なりすましや改ざんなどの不正打刻が発生してしまうリスクがあります。また、昨今は超過勤務による過労死などが問題になっていることもあり、これからの勤怠管理はますます正確性・客観性を高めることが要求されます。
6. まとめ
現在もタイムカードへの打刻というタイムレコーダーよる勤怠管理方式を続けているところも多いですが、近年は働き方の多様化と賃金体系の複雑化もあり、ますます手作業での管理は困難になっています。
テクノロジーの進歩に伴い、このような管理業務については今後も効率化・システム化が進んでいくことでしょう。最終的なコスト削減のためにも、勤怠管理における最新システムの導入は不可欠になってくるのではないでしょうか。







