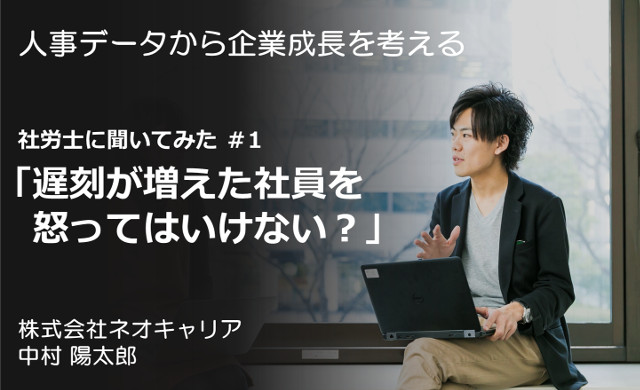
はじめまして、jinjer株式会社で『ジンジャー』というHRTechサービスのマーケティング担当をしている中村 陽太郎です。
この度私は、ジンジャーの目指す世界観『人事を経営のセンターピンに』を実現するために、マーケティング活動と平行して、人事データを駆使して経営に最適な打ち手を提案する『戦略人事』という考え方を世の中に広める活動を開始することにしました。
そもそも「人事データを活用するとはどういうことなのか?」「人事データを活用してアクションを起こすことで企業経営にどのような影響を与えることができるのか?」「またそれに際してHRTechサービスをどう活かすことができるのか?」などを調査していき、その結果見えてきた情報をHR NOTEにて定期的に共有させていただきます。
従業員の勤怠管理を担当されている人事の方であれば、勤怠データを見るとなんとなくこの人「コンディションが悪そう」「退職してしまいそう」というのを肌感覚でお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は経験から「なんとなく感じている」人事データと従業員の行動の相関関係を知ろうということで、実際のデータに紐付いた話ではないことを前提に、「退職する人の傾向は、勤怠データから読み取ることができるのか」をテーマに多くの企業の勤怠データを見てこられた社会保険労務士(以下社労士)の先生にお話をうかがってきました。
今回から3記事にわたって、社労士の先生にお聞きしたお話の内容をご紹介させていただきます。
退職する人がどういう動きをするかは、正直経験からはわからない
今回お会いした社労士の先生は、業種業態はもちろん、規模もバラバラの企業を見てこられた方でしたが、退職する人の勤怠データから「一概にこれだ」と呼べるものは見て取れなかったようです。インタビューをする前に私は下記のような仮説を考えていました。
もちろん退職日に差し迫った時には、上の傾向が読み取れるとのことでしたが、退職する可能性がある人を経験則から導き出すことは難しいとのことでした。企業、業種、規模ごとにセグメントして考えれば具体的な答えがあるかもしれませんが、全体を通して回答することは難しいとのことでした。
しかしながら、一部分の退職者にしか当てはまらないかもしれませんが、勤怠データから「遅刻が増えている人」「欠席が以前よりも増えている人」は、退職する傾向が少なからず読み取れるようです。
遅刻・欠勤が増えた社員が退職していく傾向は間違いではない

社労士の先生にその理由を聞いてみると、遅刻が増えている社員は「精神疾患の可能性がある」とおっしゃっていました。日経BPが提供するうつ病治療と復職支援を考える「メンタルヘルスとリワーク」では、下記のように書かれています。
意欲が低下すると、仕事に対する関心が薄れてくるので、作業能率が低下し、仕事は遅くなり、期限が守れないなどの支障が生じる。仮に、こなせたとしてもかなりの時間がかかるようになる。集中も出来ないので、ミスが多発する。当然の結果として、成績は低下する。 周囲に対する関心も薄れてくるので、一見ぼんやりしているように見えることも多い。また、出社意欲も低下するので、遅刻・欠勤なども増えてくるだろう。仕事が遅く、ぼんやりしているようにみえるので、“サボっている”と間違えてしまうこともあるので注意したい。
あくまで社労士の先生の経験則との前置きではありますが、遅刻が増えたり、欠勤が増えたりしている従業員がいる場合「そこで注意や追い詰められた人が心を痛め、退職していく結果につながっているのでは」と精神疾患になるアラートだと考えられるとのことでした。また遅刻する理由も体調不良をはじめ、他にも複数回答を持ち合わせている人が多いため「本人の話だけではなく、遅刻が増えた事実を見て会社としてどう対応していくのかを考えてもいいのでは」との回答もいただきました。
怒るのではなく、まずは状況を把握する
必ずしも遅刻や欠勤が増えている社員が精神疾患かというと、そういうことではありません。ただし、遅刻や欠勤が増えてきた社員に「怒る」「叱る」マネジメントは通用しない、なぜなら本人の心を痛めつける可能性があるからです。
まずは勤怠データから遅刻や欠勤が増えている社員がいるという事実に目を向けて、「何が起きているのか」を把握することが求められます。社労士の先生は「過去の傾向からみると、まずはしっかりと対象の社員と話をし、本人が把握できていない場合でも病院で診察を受けることをすすめています」とおっしゃっていました。
今後の社員のマネジメントには「まず勤怠データから事実をきちんと把握し、その事実にどう対応していくのかを冷静に考えていくこと」が今後求められそうです。







