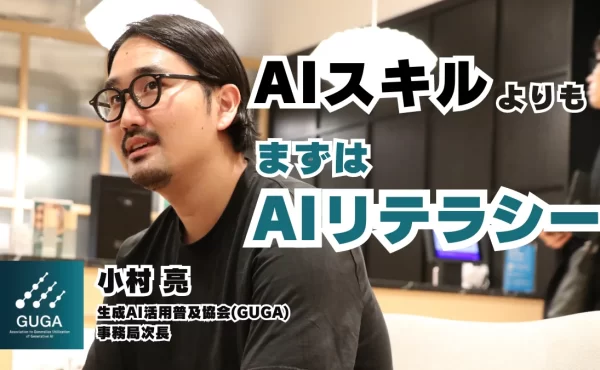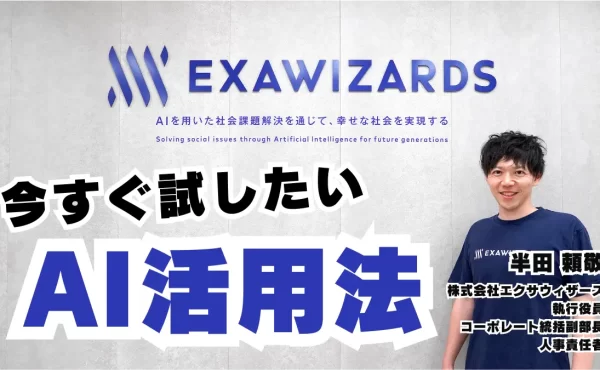タイの人事領域に特化した非営利団体PMATは、国内最大規模の人事イベント「HR DAY」や人事向けのワークショップ「HR Forum」などを開催しています。
PMATは創立50年以上の歴史があり、現在では2000社以上の企業を会員として抱えており、多くの企業の人事課題を支援しています。
今回はPMATの代表を務めるBoyさんに、「激変の時代におけるタイ企業の未来」や「タイ企業がグローバルで戦うために必要な要素」について語っていただきました。

Bowornnan Thongkalya | MITR PHOL GROUP 人事部長兼PMAT理事長
20年間ほどはサイアム・セメントグループ(SCG)の人事を担当し、その後は人事コンサルタントとして5年間活動。現在では製糖会社のMITR PHOLの副社長に就任。PMATには6年前に代表取締役に就任し、現在は理事長を務める。
目次
『人事の成長が組織の成長に』タイの人事領域の活性化を担うPMAT

人事として30年。数々の人事経験を経て、PMATの代表に就任。
Boyさん:私自身、人事を30年以上経験しています。
長年人事として働いてきましたが、昔と変わらず今でも人事は組織において重要なポジションだと認識しております。
また人事は「禅」の教えと共通する部分があると考えるようになりました。
禅には「ヒトのために尽くす」という教えがあります。
過去に禅について勉強していた時期あり、この禅の考え方に感銘を受けましたが、同時に「これは禅に限ったことではない」と思いました。
人事の仕事でも禅の考えは常に求められます。
「従業員がシアワセに働くためにどうすればいいか」「彼らはどのような価値観や目標を持っているのか」など、常に従業員について考えることが重要です。
その結果として、彼らがやりがいを感じて働く環境を作り出せるのは、人事の一番の醍醐味ではないでしょうか。
創立50年以上の歴史を持つPMAT。「人事の重要性」を認識したメンバーが集まる。
Boyさん:PMATはタイで創業して53年ほど経っており、人事領域では一番古い組織になります。
PMATは毎年人事向けに組織開発やマネジメントに関するセミナーを人事向けに開催しています。
他にも年に1回、大規模な人事イベント『HR DAY』を開催し、そのイベントには数千人もの参加者が来場されました。
このようなイベントを人事向けに多数開催していますが、PMATは非営利団体のため、活動する目的は利潤ではありません。
また活動するメンバーは、仕事外の時間を活用してミーティングなどに自主的に参加しているんですね。
しかし、PMATのメンバーは「組織の目的達成においてヒトが大きな成功因子だ」と組織における人事の重要性を認識しており、それが彼らの大きなモチベーションへとつながっています。
ヒトが組織のパフォーマンスを変えることができる唯一の存在であって、我々はヒトが充実したキャリアを実現するための方法を模索し続けています。
「今が時代の境目」Boyさんが語る”新しいパラダイム”

「この数年で人事領域は大きく変化した」
Boyさん:30年間、人事として仕事をしてきましたが、ここ数年で人事業界は著しく変化したと感じています。
特にテクノロジーの進歩により、人事そのものに対して大きな変化を求められる時代になりました。
煩雑な事務作業が自動化されるだけでなく、人事のワークフロー全体に変化が求められるでしょう。
AIやチャットボット、ブロックチェーンなどが今後人事業務にも導入され、今の仕事の形を大きく変えていきます。
例えばマネジメントにおいては、個人データをもとに正確な能力を把握することができ、マネジメントをおこなう際のバイアス軽減にもつながります。
また教育の分野では、実際にリアルで体験しなければならない研修も、VRが活用され、実際にその場にいるような感覚で研修をおこなうことができます。
人事の仕事の多くは、テクノロジーが代替する時代になるのではないでしょうか。
「アジャイルな組織」が求められる時代に。
Boyさん:先ほど言ったように、いま凄まじいスピードでテクノロジーが進歩しており、そのスピードに企業は追いつく必要があります。
ここで重要なのは、個人のスピードを引き上げるのではなく、チーム全体のスピードを上げていく必要があるということです。
「アジャイルなチーム」が組織において重要になり、組織内でスピード感のあるチームをつくることが、今後タイ企業の直面する課題です。
そのため官僚体制にあるトップダウン体質な組織は今後、厳しい局面を迎えるでしょう。
今後はスタートアップのようなビジネスの進め方が、大企業でも適用されるようになります。
長期的な目標だけでなく短期的な目標も同時にかかげ、そのサイクルをすばやく回していく。
今後、人事は機敏に時代に対応するためにも、「アジャイルな組織」をつくりだす必要があります。
「大企業は傲慢になってはいけない」
Boyさん:ビジネスのスピードが早い組織ほど競争優位になっている時代です。
かつては「大きい魚が小さい魚を食べる時代」でしたが、いまは「素早い魚が大きい魚を食べる時代」です。
つまり、大企業が競争社会では優位という時代は終わろうとしています。
先ほど申したようにアジャイルな組織が優位に立つ時代です。
しかし、大企業は過去の成功体験から「変化しなくてもいい」という考えが根強く残っているのではないでしょうか。
新しい方法に挑戦せず、いまだに既存の戦略でやり続けています。
このような変化の激しい時代に、大企業の「傲慢さ」がビジネスの発展を阻害し、結果として成果を出し続けることに苦労する企業が増えてくると思います。
タイ企業がグローバルで戦うためには

労働人口の減少が進行。「生産性」が求められる時代に
Boyさん:日本をはじめ他の国でも少子化、労働人口の減少が進行していますが、タイでも同様の現象が起きています。
そのため、今後はより生産性を高めていく必要があり、人事そのものの考え方を変えて、既存から新しい方法にチャレンジしていくことが重要になります。
また同時に人事のワークフローは大きく変わっていくでしょう。
たとえば採用では正社員の比率が減り、フリーランスとして仕事をする方が増えていきます。
それに伴いどのような人材を採用するのか、採用の定義そのものを変えていく必要があります。
また従業員の評価においても、役職などで評価する等級評価から、個人の数字や業績などパフォーマンスに基づいて評価する時代になります。
労働人口減少に備えて生産性を上げる必要があるいま、人事は新しい取り組みを積極的に取り入れていく必要があります。
ASEANの中でもタイの生産性は低い
Boyさん:少しグローバルな視点でタイを捉えてみると、ASEANの中でもタイは生産性が低く、それは政府も認識している課題になります。
特にタイでは個人の能力において、シンガポール、マレーシア、ベトナムなどをベンチマークとして捉えていますが、それらの国と比べてまだ追いついていないのが現状です。
我々はこの状況を「緊急事態」として認識するべきでしょう。
「グローバルで見るといま危険な状態だ」という認識をもっていれば、おのずとビジネスのスピードを加速することが期待できます。
そろそろタイもコンフォートゾーンを抜け出す必要があり、それをサポートするのは我々人事のミッションだと思っています。
タイが世界で戦うために必要な「5つの教養」
Boyさん:生産性を引上げ、タイのビジネスを加速していくためには5つの教養が重要だと思っています。
この考えはPeter Sengeという方が提唱している考え方ですが、今のタイのビジネスマンにとって重要な要素だと思っています。
1.システム思考(System thinking)
ビジネスにおける構造的相互作用を把握する能力
2.自己マスタリー(Personal mastery)
個人が明確な目標・目的を持ち、それを更に高いレベルまで導いていく
3.メンタル・モデルの克服(Mental models)
個々人がそれぞれに抱えている固定的なイメージや考え方を必要に応じて変えていく
4.共有できるビジョンの構築(Shared vision)
個人と組織のビジョンに整合性を持たせ、誰もが共感・共有されるビジョンを構築する
5.チーム単位での学習(Team learning)
基本的な単位はチームとなるので、チームで学習が出来るようなスキルと場を養う
これは人の能力を伸ばす上で必要な教養スキルです。
2年前のPMATのイベントにて、こちらの5つの教養を提唱するPeter Sengeさんを招待し、タイの人事の方に向けて講演をおこなってもらいました。
このような「5つの教養」がグローバルで戦っていく上で重要で、これらを習得した人材を育てる必要があります。
「コンフォートゾーン」から抜け出す時が来た
Boyさん:今後は新しいことを考え、挑戦し続ける人材が求められる時代になりました。
もし自分自身の可能性を信じていて、成長したいというマインドがあるのならば、既存の価値観にとらわれず、どんどん挑戦していくべきだと思います。
しかし、まだまだ挑戦に対して苦手意識を感じる人が多くいるのが現状です。
これは教育方式にも影響していると思います。
タイの教育方式は答えが常に用意されている暗記型が導入されており、結果として「答えのない問いへの挑戦」に抵抗を感じるのでしょう。
政府もそれを問題として認識しており、暗記型から思考型の教育システムにシフトしようとしています。
新しい変革を起こすことは簡単ではありませんが、いまはどの国の組織も改革の必要性を感じています。
特にタイではそれが深刻な状況であり、新しい物事に挑戦できる人材育成が急務となっています。
組織自体に命はない。「個人」が組織に命を与える。

Boyさん:今後人事は自分の仕事や考え方自体にフォーカスするべきだと思っています。
人事としてのスキル、考え方をアップデートしていく必要があり、また同時に従業員のスキルを引き上げていくことが重要になります。
従業員の成長が組織の成長につながり、それが組織の目的達成につながります。
継続して組織が目標を達成しつづけるためには、従業員の可能性を引き出し、変化し続けられるようになるべきですね。
しかし、それは個人の考え方が重要になるでしょう。
私は組織自体には「命」がないと思っていて、そこで働く一人ひとりが「命」を組織に与えていると思うんです。
だからその「命」自体を強くするためには、働く人の個人の能力を最大限に引きだしていく必要があります。
人事はこの激しい変化の時代だからこそ、組織の中でもますます重要な存在になっていくと思います。