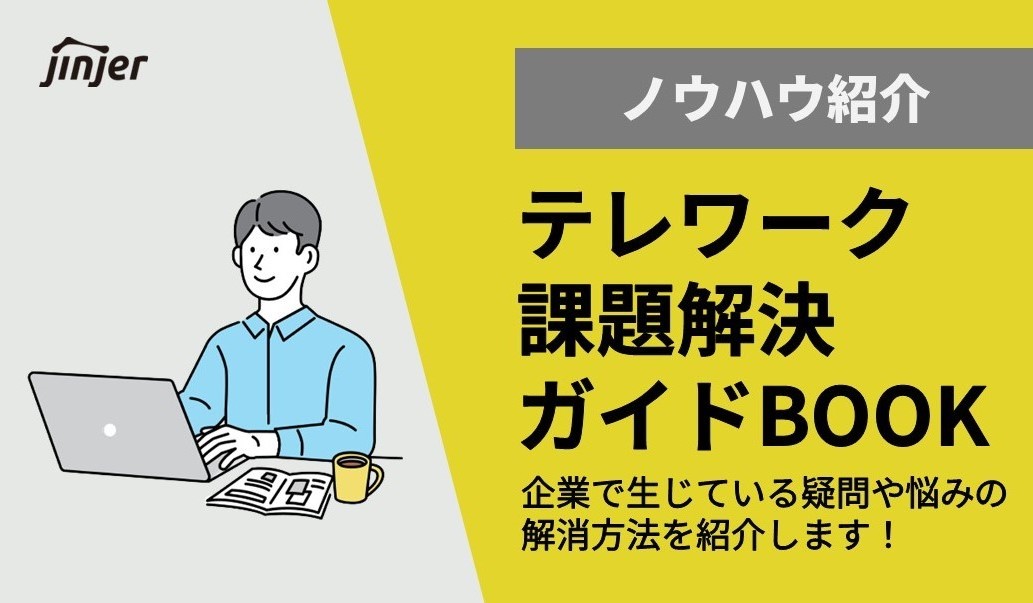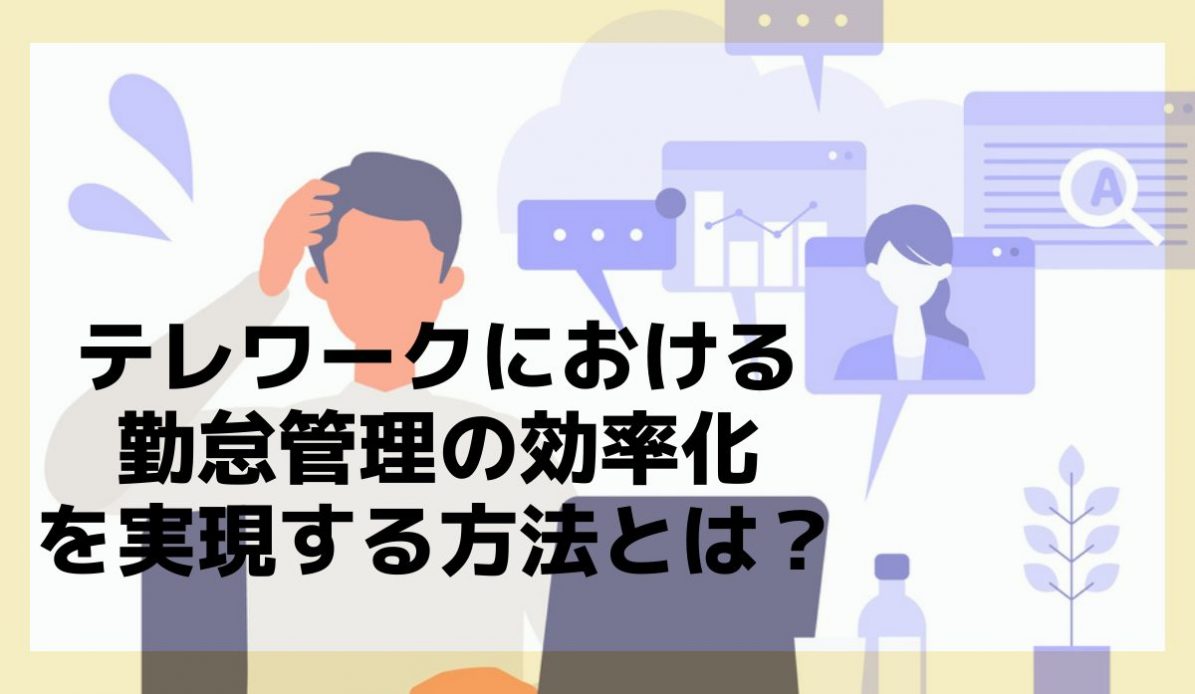
通勤のストレスを減らし、自分らしく働けるテレワークは、企業・従業員ともにメリットが大きい制度です。しかし、テレワークの勤怠管理には、多くの課題があります。この記事では、テレワークの勤怠管理の課題に対する解決方法を解説します。また、テレワーク対応の勤怠管理システムの選び方も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
コロナの蔓延によって急激に普及したテレワーク。
今後も続けていこうと考えていても、「本当に労働しているか分からず、勤怠管理が難しい」「サービス残業が発生しているのではないか」など困りの場合もあることでしょう。
そのようなお悩みをお持ちの人事担当者様に向け、労働時間管理や残業管理の課題をどのように解決すべきかをまとめた資料を無料で配布しております。
テレワーク時の労働時間管理でお困りの方は、ぜひ資料ををダウンロードしてご覧ください。
目次
1. テレワークの勤怠管理におけるよくある課題

昨今の働き方改革の影響もあり、多様な働き方を推進するため、テレワークを導入する企業は多いです。テレワークと言っても、在宅勤務やモバイルワーク、サテライトオフィス勤務、ワーケーションなどのさまざまな種類があります。
実際に出社する場合、上司や管理職の人が直接目でみて労働時間を管理できます。しかし、リモートで働く場合、直接目でみて働いている様子を確認できないため、課題が生じやすいです。ここでは、テレワークの勤怠管理におけるよくある課題について詳しく紹介します。
1-1. 正確な労働時間の把握が難しい
通常のオフィスワークであれば、従業員の出社・退社を目視で確認できるため、労働時間の把握はそこまで難しくありません。一方、テレワークの場合、従業員の働いている様子を目でみてチェックできないため、いつからいつまで働いていたのかが曖昧になりやすいです。
また、仕事とプライベートの境界線がわかりにくく、中抜けが生じた場合の労働時間の管理も困難です。正確に労働時間を管理できなければ、正しく給与計算ができないだけでなく、従業員の健康に悪影響を及ぼしたり、労働基準法違反となり罰則が課せられたりする恐れもあります。
1-2. 長時間労働につながりやすい
オフィスに出社して働く場合、仕事とプライベートのスイッチの切り替えがしやすいです。また、遅くまで残っている従業員に対しては、上司や管理職の人が直接声を掛けて、タスク量などを調整し、労働時間を管理できます。
一方、在宅勤務などのテレワークを採用する場合、仕事とプライベートの切り分けが難しく、気づいたら終業時刻を超えて働いていたというケースもよくあります。また、直接目でみえないことから、管理者はその事実に気づきにくいため、無意識に放置してしまっている可能性もあります。
1-3. セキュリティ面の課題もある
テレワークでも正確に、かつ効率よく労働時間を管理するため、インターネット環境を利用して勤怠管理をおこなっている企業もあるかもしれません。その場合、セキュリティ対策をきちんとしていなければ、不正アクセスなどのセキュリティ攻撃を受けやすく、勤怠に関する情報が盗み取られる恐れがあります。勤怠情報は重要な個人情報を含むため、外部に流出すれば、大きなニュースとなり、社会的信用を失うリスクもあります。
1-4. 正しく人事評価ができない
勤怠データを人事評価の対象にしている企業もあるかもしれません。この場合、テレワーク中の勤怠管理制度がきちんと整備されていなければ、テレワーク社員の人事評価も正しくおこなえなくなります。人事評価が曖昧になれば、会社への不満につながり、従業員のモチベーションが低下し、労働生産性が低下する恐れもあります。
1-5. 人間関係に悪影響を及ぼす
テレワークを採用すると、コミュニケーションが希薄化しやすいです。そのため、上司や管理職の人は、テレワーク中の従業員が正しく仕事できているか不安になりやすくもあります。頻繁に部下の進捗状況を確認している場合、自分の業務に集中できていない可能性があります。
また、テレワーク社員にとっても、常に監視されていると感じれば、ストレスにつながり、スムーズに仕事を進められない恐れがあります。結果として、社内の人間関係が悪化し、離職率の上昇などにつながるリスクもあります。
当サイトでは、テレワークの運用がうまくいかない時の対処法について解説した資料を無料で配布しております。テレワーク時の対応や勤怠管理方法でお困りのご担当者様は、こちらから「テレワーク課題解決方法ガイドBOOK」をダウンロードしてご確認ください。
2. テレワークの勤怠管理における課題を解決するための方法

テレワークの勤怠管理における課題を解決できれば、より多様な働き方を推進し、人材確保や業務効率化などにつなげることができます。ここでは、テレワークの勤怠管理における課題を解決するための方法について詳しく紹介します。
2-1. メールやチャットで報告・連絡する
テレワークで正確な労働時間を管理するため、メールやチャットなどを使って、始業時刻や終業時刻、中抜け時間などを報告・連絡する方法があります。メールやチャットにより記録を残すことで、勤怠に関するトラブルを未然に防止することが可能です。また、既に使用しているツールを活用すれば、コストも抑えられます。ただし、メールの確認や申告情報の転記など、管理者の負担が大きくなりやすいことにも注意しましょう。
2-2. エクセルなどの電子上の出勤簿に記録する
管理者の負担を減らす観点から、エクセルやスプレッドシートといった電子上の出勤簿にテレワーク社員が自ら記録してもらう方法もあります。上司や管理職の人は、必要なタイミングで出勤簿を確認すればよいため、勤怠管理の業務を効率化できます。
ただし、この方法を採用する場合、従業員との信頼関係が重要です。出勤簿の記載漏れが発生すれば、正確に勤怠管理ができません。また、テレワーク社員の申告に基づき、勤怠管理するため、仕事していない時間を業務時間とするなど、虚偽申告が生じやすくなる点にも気を付ける必要があります。
2-3. 勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システムを導入することでも、テレワークに対応した勤怠管理ができます。勤怠管理システムであれば、PC・スマホ・ICカード・生体認証などのなかから、自社のテレワークにあった打刻方法を選ぶことが可能です。また、PCログを活用すれば、不正打刻の防止にもつながります。さらに、テレワーク中の過重労働の課題に対しても、アラート機能により、抑制を促すことが可能です。
ただし、勤怠管理システムには、さまざまな種類があります。料金や機能、使いやすさ、サポート、セキュリティなどの観点から、複数のツールを比較し、自社のニーズにあったテレワーク対応の勤怠管理システムを導入することが大切です。
3. テレワークの勤怠管理におけるポイント

テレワークの勤怠管理における課題は、勤怠管理システムを導入することで解決できる可能性があります。しかし、勤怠管理システムを導入するだけで、社内ルールを見直さなければ、テレワークの勤怠管理の課題解決につながらない恐れもあります。ここでは、テレワークの勤怠管理におけるポイントについて詳しく紹介します。
3-1. 厚生労働省が提供するガイドラインをよく確認する
正確に従業員の労働時間を把握することは、法律で定められた使用者の義務です。正しく労働時間を管理していない場合、知らぬ間に労働者の労働時間が労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)や、36協定の上限時間をオーバーするなど、違法となる可能性があります。
このような事態を防止するため、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を提供しています。たとえば、使用者が始業・終業時刻を確認・記録する方法として、ガイドラインでは原則次の方法を認めています。
- 使用者が自ら確認・記録をする
- タイムカードやICカード、パソコンの使用時間など客観的な記録を用いる
テレワークの場合、紙のタイムカードを使用したり、使用者が自ら確認したりするのは難しいでしょう。そのため、勤怠管理システムを導入するなどの対策が必要です。このほかにも、労働時間の考え方などのルールが細かく定められているのでよく確認しておきましょう。
3-2. テレワークの勤怠ルールを明確化する
テレワークの勤怠ルールは、法律の要件を満たしていれば、会社が自由に決められます。しかし、従業員によって違う勤怠管理の方法を採用する場合、内部統制が取れず、不正も横行しやすくなります。
テレワークの勤怠ルールを明確にしたら、就業規則などに記載したうえで、従業員に正しく周知することが大切です。テレワークの勤怠ルールがきちんと遵守されることで、勤怠管理の質も高まります。
3-3. コミュニケーションの取り方も見直す
勤怠管理システムを導入して客観的に労働時間を把握することは重要ですが、テレワーク社員が気持ちよく仕事できているかチェックするため、コミュニケーションの取り方を見直すことも大切です。
たとえば、勤怠管理システムでテレワーク社員の労働時間が長いことを把握できたら、Web会議システムやチャットツールなどのコミュニケーションツールを使って、何かテレワークにおける悩みや問題がないか当該従業員にヒアリングしてみましょう。「情報共有に時間がかかる」「仕事とプライベートの切り替えが難しい」など新たな課題が見つかったら、それに対する解決策を探ることで、従業員の労働環境の改善につなげることができます。
4. テレワーク対応の勤怠管理システムの選び方

テレワークの勤怠管理における課題を解決するためには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。ここでは、テレワーク対応の勤怠管理システムの選び方について詳しく紹介します。
4-1. コストは適正か
勤怠管理システムを導入・運用するには、コストがかかります。まずは勤怠管理システムでどのようなことを実現したいのか目的を明確にしましょう。また、費用対効果を検証することで、勤怠管理システムを導入すべきかどうかがみえてきます。
一つの勤怠管理システムに、複数の料金プランが用意されているものもあります。自社の目的や従業員規模にあわせて料金プランを選ぶことで、コストを最適化することが可能です。
4-2. 機能は過不足ないか
勤怠管理システムには、さまざまな機能が搭載されています。テレワークに対応した機能が搭載されているか事前にチェックしましょう。フレックスタイム制や裁量労働制など、自社の働き方すべてに対応できるか確認することも大切です。また、後からでも機能を追加できるか、拡張性も考慮してシステム選びをおこないましょう。
4-3. 従業員が使いやすいか
勤怠管理システムは、人事労務担当者だけでなく、現場の従業員も使用します。勤怠管理システムの操作が難しい場合、勤怠管理の業務に時間がとられて、コア業務の生産性が低下する恐れもあります。勤怠管理システムを導入する際は、自社の従業員のITリテラシーを考慮し、直感的に操作できるツールを導入するのがおすすめです。
4-4. サポート体制
勤怠管理システムを導入する際、初期設定に時間や手間がかかることもあります。また、運用中にエラーやトラブルが発生することも少なくありません。
このような場合、サポート体制が手厚いツールを選んでいれば、素早く問題を解決することができます。また、テレワーク制度により、リモートで働く従業員が多いのであれば、オンラインサポートが充実している勤怠管理システムがおすすめです。
4-5. 他のシステムと連携できるか
導入する勤怠管理システムが、既存の給与計算ソフトや人事管理システムと連携できるかどうかも重要なポイントの一つです。勤怠管理システムと他のツールを連携すれば、データ入力・出力などの作業を自動化し、業務を効率化することができます。
4-6. ペーパーレスのシステムか
勤怠管理システムを導入する場合、ワークフローのチェックも必要です。テレワークを導入できても、申請・承認手続きを電子化できない場合、わざわざ紙の手続きをするため出社しなければならず、従業員は気持ちよくテレワークで働けません。そのため、勤怠管理システムを使って、オンライン上で書類などの提出もできるか確認しておきましょう。
4-7. 法改正への対応の速さ
労働基準法などの働き方に関連した法律は、時代が進むにつれて繰り返し改正されます。法改正に自動で対応できる勤怠管理システムを選べば、法令・コンプライアンス違反を未然に防止することが可能です。
5. テレワークにおすすめの勤怠管理システム3選
ここでは、テレワークにおすすめの勤怠管理システムを比較しながら紹介します。自社のテレワーク制度にあった勤怠管理システムをぜひ探してみてください。
5-1. ジンジャー勤怠
jinjer(ジンジャー)勤怠は、jinjer社が提供するテレワークに対応した勤怠管理システムです。シフト制・時差出勤やフレックスタイム制、みなし労働制など、多様な働き方にも対応できます。使いやすい操作画面となっているので、操作が不安な人でも利用することが可能です。また、チャットやオンラインなど、充実したサポートも提供しています。
jinjer株式会社 (jinjer Co., Ltd.)
東京本社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿
5-2. 勤次郎
勤次郎とは、勤次郎社が提供する勤怠管理と健康管理を一元化したシステムです。パソコン・スマホ、タイムレコーダー、生体認証など、多様な打刻方法が搭載されているため、テレワークにも対応することができます。また、定期健康診断やストレスチェックといった健康管理の機能も豊富に搭載されています。
勤次郎株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田4丁目14番1号秋葉原UDXビル北8階
5-3. KING OF TIME(キングオブタイム)
KING OF TIME (キングオブタイム)とは、ヒューマンテクノロジーズ社が提供するテレワークにも対応できる勤怠管理システムです。豊富な機能が搭載されているため、複雑な勤怠管理制度を導入している場合でも、柔軟に対応できます。また、ハードウェア・ソフトウェアの両面からセキュリティ対策がおこなわれているのも特徴です。
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6
6. 勤怠管理システムを導入してテレワーク中の労働時間を適切に把握しよう!

テレワークの勤怠管理には、労働時間を把握しにくい、長時間労働が発生しやすいといった課題があります。勤怠管理システムを導入すれば、自社のニーズにあった打刻方法を用いて、正確な労働時間を管理することが可能です。また、アラート機能で過重労働になりそうなテレワーク社員に自動で通知を出すことができます。
勤怠管理システムには、さまざまな種類があります。テレワークの勤怠管理における課題を解決するためにも、複数のツールを比較して、自社のテレワーク制度にあった勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。
コロナの蔓延によって急激に普及したテレワーク。
今後も続けていこうと考えていても、「本当に労働しているか分からず、勤怠管理が難しい」「サービス残業が発生しているのではないか」など困りの場合もあることでしょう。
そのようなお悩みをお持ちの人事担当者様に向け、労働時間管理や残業管理の課題をどのように解決すべきかをまとめた資料を無料で配布しております。
テレワーク時の労働時間管理でお困りの方は、ぜひ資料ををダウンロードしてご覧ください。