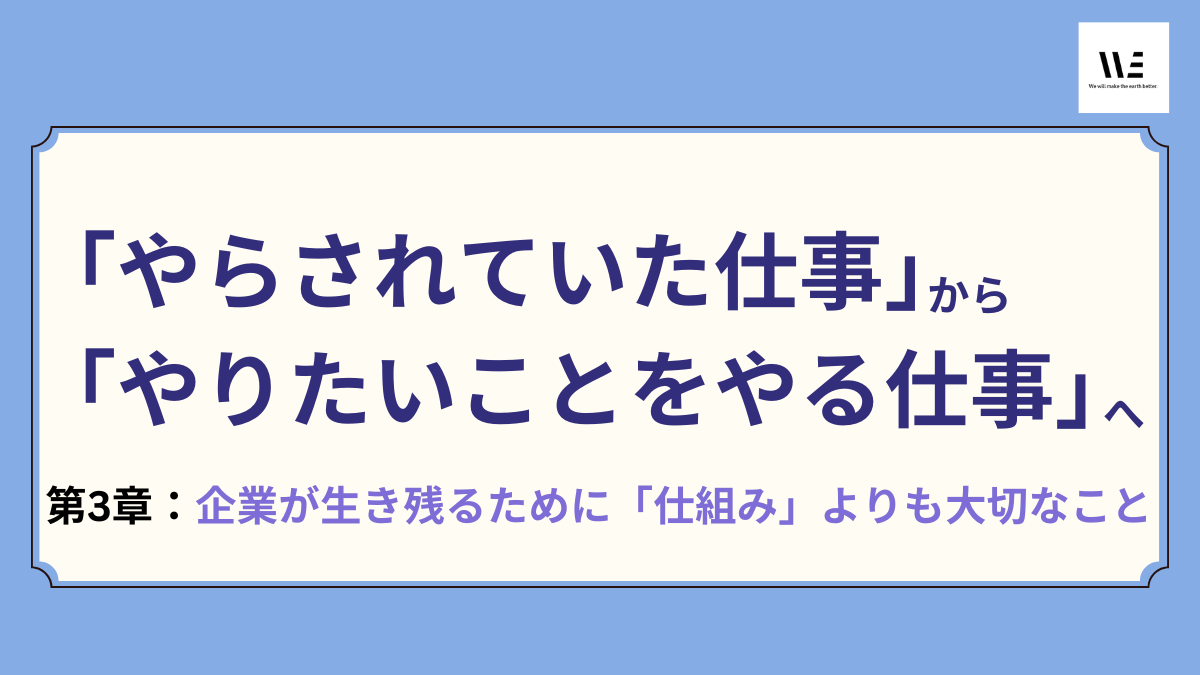 皆様ご無沙汰しております。株式会社WEの戸田です。
皆様ご無沙汰しております。株式会社WEの戸田です。
従業員の「やりたい」を引き出すにはどうしたら良いかについて、第3回目の記事となります。
第2回では「どうやって個人の”やりたい”を引き出すか?」について書かせていただきました。実際に研修で使用しているワークシートは活用いただけたでしょうか?感想や質問等があれば、ぜひご連絡いただければと思います。
さて、今回は「仕組み」について考えることを書いていきます!

執筆者戸田 裕昭氏株式会社WE 代表取締役 / 総務省地域力創造アドバイザー
大学卒業後、オフィス家具メーカーにて新規事業創出・地域活性化に携わる。総務省地域力創造アドバイザーや国土交通省スマートアイランド推進実証事業コーディネーターなどを担い、全国各地の地域における事業振興のアドバイスを行なっている。 また、個々人のやりたいことが起点となる事業創出を目的とした伴走型教育プログラムを開発・構築。小学校から大学までの教育機関や自治体、民間企業と連携し、人材育成を軸とした「組織変革」「事業創造」「地方創生」を行う。
1. 「今までの仕事」から「これからの仕事」へ
 第1回・第2回で書かせていただきましたが、これからは「小さな『やりたい!』」を起点に仕事を作っていく時代になります。
第1回・第2回で書かせていただきましたが、これからは「小さな『やりたい!』」を起点に仕事を作っていく時代になります。
ビジネス界隈を中心に「0→1をつくる」といった言葉がよく使われていますが、「1」になるよりも前の段階がさらに重要になってくると思います。
では、何かを達成することを「1」と定義しましょう。その「1」はどのように生み出せるでしょうか?
最近、「何かの課題をビジネスで解決する」「ビジネスで不を解消する」といった大義名分ばかりが重視されているように思います。もちろん課題解決や不の解消は大事でわかりやすいですが、それを推進する人間がワクワクしていないように思えます。
推進者が本当にその課題を解決したいのか、本当にその不を解消したいのか、この部分が大事です。しかし、どうしても置きにいってしまうような企画も多いのではないかと感じます。
社会課題は簡単に解決できないからこそ存在しています。解決のための行動を続ける方には、強い覚悟が必要です。
2. 「やりたいこと」が結果に繋がる
 第2章のワークシートに取り組んでいただいた方はわかると思いますが、まずは個人のやりたいことから始めていけばいいと思います。その行動の結果、誰かの役に立ったり、社会課題を解決したり、何かの不を解消できるようになったりすると思います。
第2章のワークシートに取り組んでいただいた方はわかると思いますが、まずは個人のやりたいことから始めていけばいいと思います。その行動の結果、誰かの役に立ったり、社会課題を解決したり、何かの不を解消できるようになったりすると思います。
どんなに綺麗なビジネスモデルを描いても、どんなに儲かりそうな事業計画を描いても、それは机上の空論です。実際にやってみるとすぐに失敗したり壁にぶつかったりします。世の中、簡単に思い描いた通りにはならないものです。
それでも、やり続けることで、いつか綺麗な形に落ち着いていくものだと思います。
3. 企業が生き残るために「仕組み」よりも大切なこと
 おそらく本記事を読んでくださっている人事の方はご自身が所属している組織の人材育成に取り組み、企業を成長させ、これからも生き残る企業を作っていくことが仕事だと思います。
おそらく本記事を読んでくださっている人事の方はご自身が所属している組織の人材育成に取り組み、企業を成長させ、これからも生き残る企業を作っていくことが仕事だと思います。
これまでの事業も簡単に成功させてきたわけではないと思いますし、これからの事業も簡単には成功しないでしょう。事業を維持するだけでも努力が必要です。
その事業を運営する人材を育成することで組織貢献していくのは、人事の皆さんのお仕事です。これまでにお伝えさせていただいているように、一人ひとりの育ってきた環境や得意分野、価値観は異なりますので、「仕組み」を考えることよりも先に「一人ひとりに向き合う覚悟」が大事だと思います。
手間はかかるかもしれませんが、やはりそれが一番やらなければならないことだと思います。
4. 人が変わること
 私は教育者でもあるので「人は変わる」と信じています。変わらないと諦めた時点で、教育者失格だと思います。人事の皆さんも人を育てることが仕事ですので、ぜひ「人は成長する」と信じて行動し続けていただきたいです。
私は教育者でもあるので「人は変わる」と信じています。変わらないと諦めた時点で、教育者失格だと思います。人事の皆さんも人を育てることが仕事ですので、ぜひ「人は成長する」と信じて行動し続けていただきたいです。
過去に「人が変わるためには、非日常と衝撃が必要で、戸田さんの研修では、その2つを同時に行ってくれる」と伝えられたことがあります。
私の「見た目がチャラい(非日常)」「意外と普通のことを言う(衝撃)」という点が評価されたというのは半分冗談ですが(笑)。やはり非日常と衝撃は本当に重要な要素だと思います。
では、どのようにその非日常と衝撃を与えることができるのか。人によって異なると思いますが、これまでの組織が作ってきた文化や風土、ルール(仕組み)が日常だとするならば、そこから少し外れることを許す(非日常)のは、ありなのかもしれません。
「うちの仕組みのここなら変えてもいいかな」と思うところがあれば、そこを一人ひとりに好きに変えさせてみる。こんなやり方も非日常を作ることかもしれません。
衝撃は「僕を呼んでください!」なんて冗談(本気)ですが、人事の皆さんが従業員一人ひとりに本気で向き合い接することが衝撃に繋がると思います。「自分のことをこんなに見てくれている」と思う従業員もいるかもしれません。その人にとっては、向き合ってくれたこと自体が衝撃です。
5. AIの発展とこれから
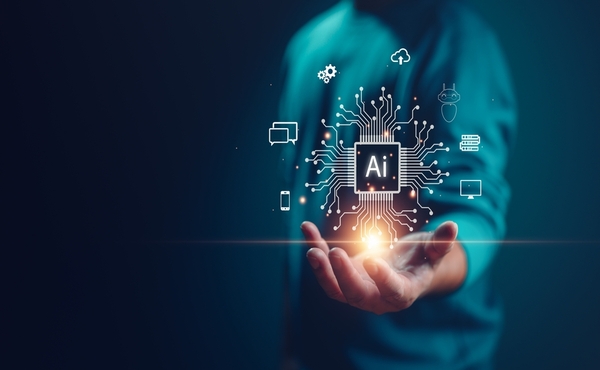 今回、このような話をしてきた背景には、今の時代に大きな変化があるからです。生成AIはとても便利で、私自身も「流石に使わないとまずいな」と思い、使うようにしています。
今回、このような話をしてきた背景には、今の時代に大きな変化があるからです。生成AIはとても便利で、私自身も「流石に使わないとまずいな」と思い、使うようにしています。
AIツールを活用すれば、これまで多くかかっていた作業時間を大幅に短縮できます。また、これからもツールはどんどん使いやすくなっていくでしょう。
すなわち、これから時間はどんどん余っていきます。その余った時間で、今まで面倒だと思っていたことができるようになるのです。
今までは何をやるにも人がやらなければいけませんでした。だから、仕組みを作って少しでも効率的になるような工夫をする必要がありました。
これからは、テクノロジーが効率的にやってくれる。だからこそ人間は今まで効率的にやってうまくいかなかったことに時間を使えるようになるはずです。ということは・・・人事の皆さんは従業員の皆さん一人ひとりに向き合う時間ができます。
人を成長させたり、人の行動を変えたりすることは、正直大変なことも多いです。しかし、人は絶対に成長し変わります。一人ひとりに真剣に向き合っていくことで、その瞬間を見た時に感動することができると思います。
人事の仕事は、とても素敵な瞬間をたくさん見られる素敵な仕事です。ぜひ「仕組み」ではなく「一人ひとりに真剣に向き合う」ことに取り組んでいってください。
今年もありがとうございました。ぜひ良いお年をお迎えください。







