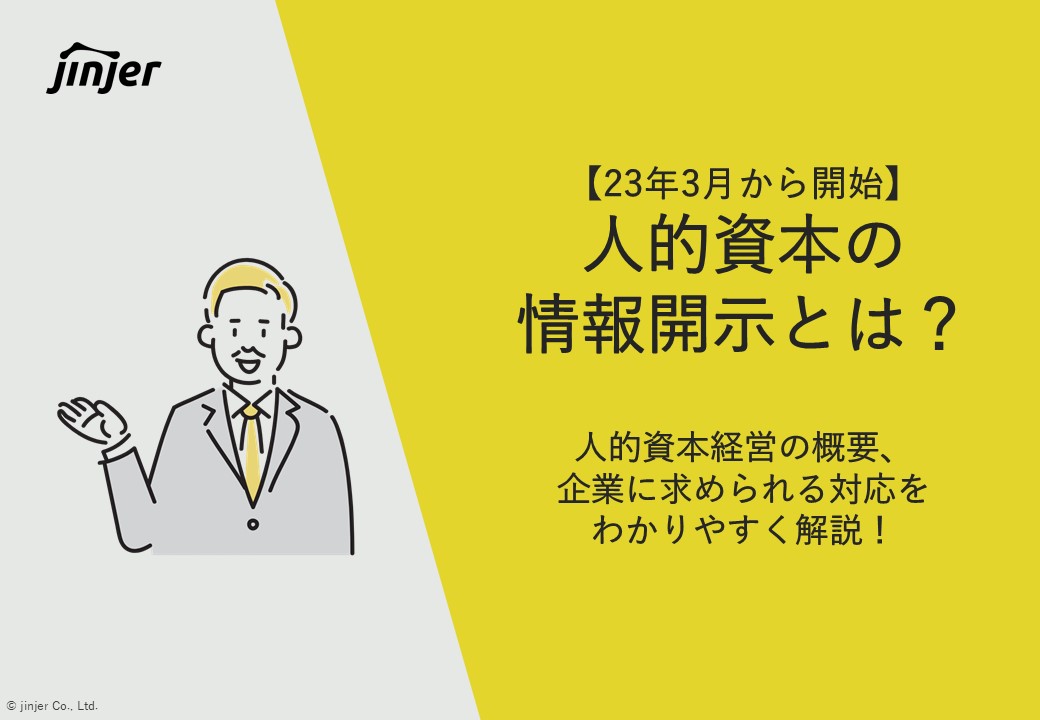「低コストで実施できる効果的なチームビルディングの方法を知りたい」
「チームビルディングの具体的な進め方を知りたい」
人事労務担当の中には、上記のようにお悩みのケースもあるのではないでしょうか。
チームビルディングは、チーム力を向上させるための方法として導入する企業が増えています。しかし、チームビルディング活動を実施するのみで、効果を実務に活かせないこともある状況です。
本記事は、チームビルディングとは何かの基本概念ややり方、具体例を簡単に解説します。進め方がわかれば、自社に合ったチームビルディングの方法を検討しやすくなるため、ぜひ参考にしてください。
目次
2023年から人的資本の情報開示が義務化されたことにより、人的資本経営に注目が高まっています。今後はより一層、
人的資本への投資が必要になるでしょう。
こういった背景の一方で、「具体的な開示内容がわからない」「実際に人的資本経営を取り入れるために何をしたらいいの?」と不安をお持ちの人事担当者の方はいらっしゃいませんか?
そのような方に向けて、当サイトでは人的資本の情報開示について解説したガイドBOOKを無料配布しています。
資料では、人的資本経営の基本や注目されるようになった背景から、開示が望ましいとされる7分野19項目の内容までわかりやすく解説しています。
「人的資本の情報開示について、詳しく知りたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
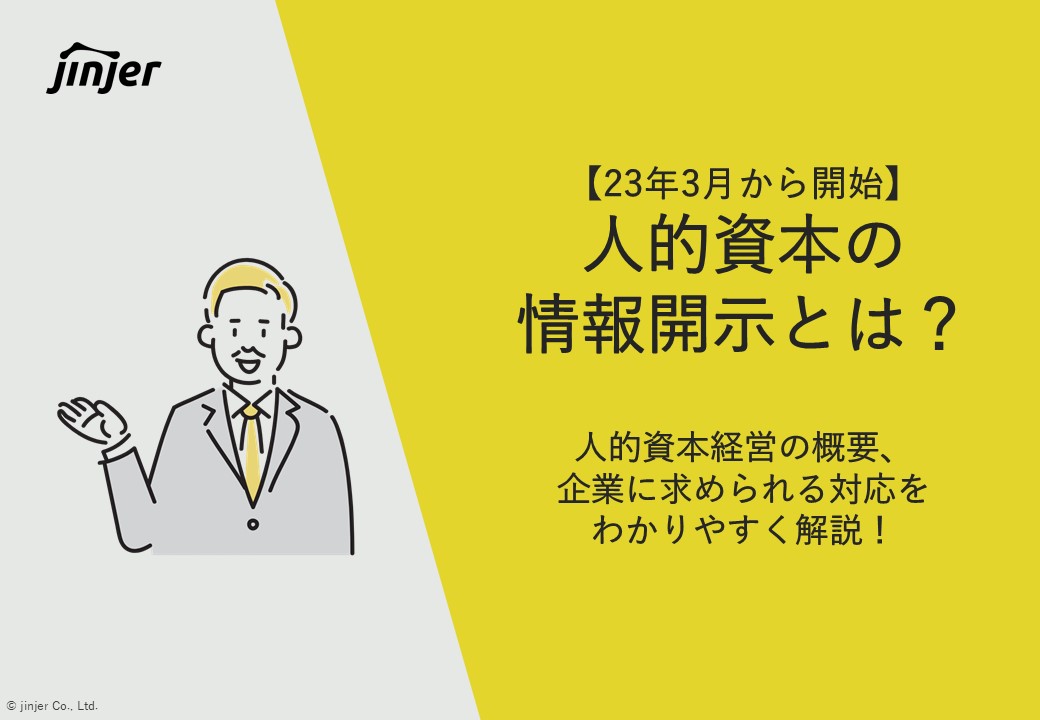
1. チームビルディングとは?簡単に解説

チームビルディングとは、従業員の本来の力を引き出すことでチームワークを向上させ、目標達成できる組織構成のための取り組みです。新たなチームを立ち上げる際など、組織開発の方法として導入する企業が増えています。
さまざまな演習で訓練し、チームに主体性を持たせたり成長を促進したりして、目標達成を目指すことが特徴です。
一度の教育訓練で劇的な変化が現れることはないため、定期的または数日間の合宿などで長時間かけて実施されます。
2. チームビルディングに取り組む目的

企業がチームビルディングに取り組む目的は、以下のとおりです。
- 組織の経営方針を共有するため
- 円滑なコミュニケーションで結束力を高めるため
- 的確な判断で人員配置するため
- 個々の段階に応じた人材育成のため
なぜチームビルディングが必要なのか、具体的に説明します。
2-1. 組織の経営方針を共有するため
組織が掲げている経営方針を従業員に共有することが、チームビルディングに取り組む目的の一つです。
チームとして成果を出すためには、何を目標とするべきかメンバー全員が共通の認識を持つ必要があります。メンバーが違う方向を向いていれば、チームとして結果を出すことはできません。
経営層が持っているビジョンを従業員にも浸透させ、認識を揃えてマインドセットを形成していくことが重要です。
2-2. 円滑なコミュニケーションで結束力を高めるため
コミュニケーションが円滑になるようにすることも、チームビルディングを実施する目的です。
チームの結束力を高めるには、心理的安全性が確保された職場環境が欠かせません。心理的安全性とはだれがどのように発言しても、だれも否定したり拒絶したりしないと安心感を持てる状態です。
円滑なコミュニケーションができていれば、従業員が意見を出しやすく、新たなアイディアが生まれやすくなります。また、チームで意思疎通できていれば、ささいなことも相談できて、課題解決やトラブル回避につながるでしょう。
2-3. 的確な判断で人員配置するため
チームビルディングに取り組むのには、適切に人員配置できるようにする目的もあります。
コミュニケーションが円滑になれば相互理解が進み、従業員の能力やスキルを把握するのが容易です。チームが結果を出すためには、的確な人員配置も重要な要素といえます。
人事労務で従業員のスキルを把握していても、実務で発揮できる能力は現場で見ていないと正しく把握できません。的確な人選で人員配置するためには、チームビルディングの取り組みが必要不可欠です。
2-4. 個々の段階に応じた人材育成のため
人材育成も、企業がチームビルディングに取り組む目的の一つです。
対象が若手や中途入社の社員の場合、自社の業務に必要なスキルや能力の獲得がメインとなります。また、中堅社員にはチームのリーダーを任せられるよう、メンバーの管理やまとめ役など管理する役割の経験を積ませる教育が必要です。
チームビルディングを通した人材育成でスキルや能力が向上し、結果が出れば従業員のモチベーション維持につながるでしょう。
3. 効果的なチームビルディングのやり方

チームビルディングのやり方には、以下のような方法があります。
- ゲームで交流を深める
- アクティビティで結束力を高める
- イベントで互いへの理解を深める
- ワークショップで主体的な行動を促す
- 1on1で信頼関係を構築する
どのようにしてチームビルディングを進めるのか、順に見ていきましょう。
3-1. ゲームで交流を深める
効果的なチームビルディングの進め方の一つに、ゲームの実施があります。チームの立ち上げ段階など、メンバーがまだ打ち解けていない段階では、ゲームでの交流が有効なためです。
配属になったばかりでメンバー同士の交流が進んでいないと、相談しにくいなど業務への支障が懸念されます。ゲームならだれもが気軽に取り組めるほか、チームで戦うために協力し合うため自然に交流を深められるでしょう。
3-2. アクティビティで結束力を高める
アクティビティの実施でも、チームビルディングを進められます。
チームで一つの目標を達成するためには、結束力の高さが必要です。結束力を強くするには、以下のように身体を動かす運動をチームで実践することが有効といわれています。
- スポーツ
- ダンス
自社で運動会を主催し、チーム対抗戦で競えば部署ごとに結束力を深められるでしょう。
3-3. イベントで互いへの理解を深める
業務を離れた場所でのコミュニケーションにより、お互いへの理解を深めることもチームビルディングのやり方の一つとなります。相互理解を促進するためには、以下のようなイベントの開催が有効です。
- 懇親会
- 社員旅行
- バーベキュー
業務中はコミュニケーションの時間が取れなくても、イベントがきっかけで相互理解が進み、業務を進めやすくなることが期待できます。
3-4. ワークショップで主体的な行動を促す
体験型の講座やグループ学習などワークショップの開催は、チームに主体性を引き出すためのチームビルディングになります。
ワークショップでは実践を見据えた課題を用意し、グループで相談して解決方法を見つける流れが一般的です。課題解決のためにはメンバー間で意見を出し合い、協力する必要があります。
ワークショップを通じ、協力して成果を出す体験を積むことで、実践でもメンバーが自主的に協力し合う体制を構築できるでしょう。
3-5. 1on1で信頼関係を構築する
信頼関係を構築するための1on1も、チームビルディングを進める方法の一つです。1on1は、上司と部下が1対1で定期的に実施する面談を指します。
面談では部下が現状や業務についての悩みを話し、上司は聞き役に徹する決まりです。部下は抱えている悩みを上司に話すことで状況を整理し、客観的に捉えられるようになります。
悩みを客観視できれば自然に解決策が見つけやすくなり、部下の成長促進が期待できるでしょう。
4. チームビルディングを進めるステップ

チームの発展段階を5つのステップで表す、タックマンモデルを紹介します。各段階とチームビルディングで実施する内容は、以下の表のとおりです。
|
形成期(Forming) |
・自己紹介 ・目的や目標の明確化 ・緊張をほぐすためのゲーム |
|
混乱期(Storming) |
・心理的安全性を確保した上でのディスカッション ・ワークショップで協力的な課題解決方法の練習 ・1on1で信頼関係の構築 |
|
統一期(Norming) |
・チームの共通目標を再確認し、全員で合意 ・効果的な意思決定プロセスを確立 ・チーム内の役割と責任を明確化 |
|
機能期(Performing) |
・定期的なフィードバックを実施 ・より高い目標を設定し、チームの成長を促進 |
|
散会期(Adjourning) |
・プロジェクトの振り返り ・チームの成果と学びを文書化 ・次のプロジェクトや新しいチームへの移行をサポート |
これらの活動を各段階に応じて実施することで、チームの発展を効果的に促進できます。
5. チームビルディングに会社が取り組む際の注意点

会社としてチームビルディングに取り組む際、注意するべき事項は以下のとおりです。
- ゲームやイベントなどを実施する際は意図を共有し、自発的に参加する空気を作る
- チームビルディングでの取り組みを実務に活かせるようにする
- 意見や考え方の違いをお互いに認め合う
- 定期的に効果測定をおこない、効果が見られない取り組みは見直す
これらの点に注意を払うことで、より効果的なチームビルディングが可能になるでしょう。
6. 効果的なチームビルディングで相乗効果を生み出そう

チームビルディングの目的は、チーム力を向上させて目標を達成できる組織づくりです。新規事業のチームなどで、メンバーが交流を深めたり結束力を高めたりできるよう、さまざまなことに取り組みます。
効果的なチームビルディングの方法は、以下のとおりです。
- ゲームで交流を深める
- アクティビティで結束力を高める
- イベントで互いへの理解を深める
- ワークショップで主体的な行動を促す
- 1on1で信頼関係を構築する
チームの状況に応じて適切な方法を取り入れられれば、相乗効果で効率良く目標達成に近づけるでしょう。
2023年から人的資本の情報開示が義務化されたことにより、人的資本経営に注目が高まっています。今後はより一層、
人的資本への投資が必要になるでしょう。
こういった背景の一方で、「具体的な開示内容がわからない」「実際に人的資本経営を取り入れるために何をしたらいいの?」と不安をお持ちの人事担当者の方はいらっしゃいませんか?
そのような方に向けて、当サイトでは人的資本の情報開示について解説したガイドBOOKを無料配布しています。
資料では、人的資本経営の基本や注目されるようになった背景から、開示が望ましいとされる7分野19項目の内容までわかりやすく解説しています。
「人的資本の情報開示について、詳しく知りたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。